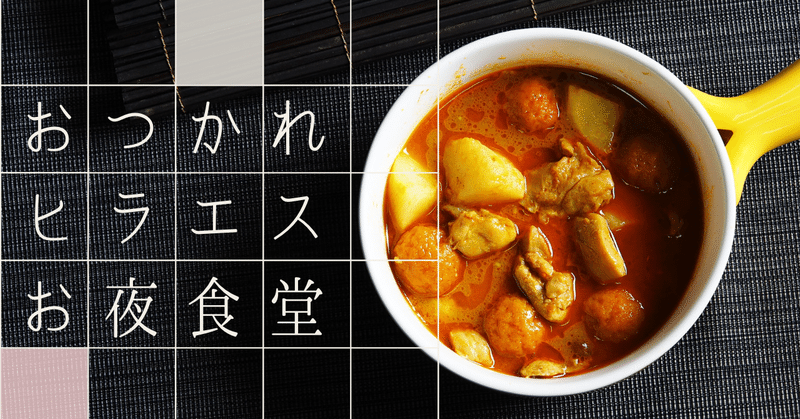
『おつかれヒラエスお夜食堂ーあやかしマスターは『思い出の味』であなたを癒しますー』第1話
【あらすじ】
ほっこりグルメ×銀髪霊狐の美形店長×黒髪女中風ウエイトレス
女性会社員の水城は多忙な日々の中で働く意味を忘れかけていた。終電で眠り込んだ彼女が辿り着いたのは廃墟の駅。怖がる彼女は駅前商店街にポツンと灯りが見えることに気づく。そこは『おつかれヒラエスお夜食堂』。『思い出』をメニューとして出す店だった。入店した彼女に出されたのは、兼業主婦だった母の作った懐かしいカレー。カレーを食べて過去を思い出す中で、水城は今の仕事を選んだ理由、出世したいと頑張るようになったきっかけを思い出し、再び前向きに現実に向き合えるようになる。
店の店長の正体は、人々の『思い出』を糧とする農耕神の霊狐だった。
第一話
切電した後も耳の奥までガンガンと、クレーマーの怒鳴り声が染み付いて離れない。怒鳴るだけのクレーマーはとにかく平謝りをし続ければ治るので、まだ対応が楽な部類だ。
私はヘッドセットを外して溜息をつき、暗いオフィスで顔を上げる。
時計は午後23時を示している。今日も終電だ。げんなりとした心を奮い立たせ、私は肩を回して業務日報を打ち込んでいく。
そして、オペレーターさんたちの成果を一括ダウンロード。その間に私は、すっかり冷めてしまったコーヒーを捨てるために給湯室に向かった。
ーー健康食品の通販会社、そのコールセンター部門のCV。
いわゆるいわゆる電話口に出るオペレーターの向こうにいる「上の人」が私だ。今日は私の管理する架電チームの新人パートさんが、退勤寸前の20時45分に大クレームを起こした。ただのフォローアップコールに対して一時間も延々と罵倒され続けたパートさんも可哀想だが、彼女が電話口で泣きながら客に言い返してしまったのだから、たまったもんじゃない。その後はただただ、私が平謝りして今に至る。
給湯室を片付けて、データと日報を社内チャットで支店長に送信。
個人情報をクライアントから預かっている都合上、原則仕事は持ち帰れない。今夜は泊まり込みをしたくないので、私は明日の自分に委ねるため、机の上に付箋がいっぱいついたクリアファイルが積み重ねた。
「はー……ようやく帰れる……」
私は伸びをした。新卒正社員入社も厳しい地方都市で、私はなんとか東京本社の正社員職に滑り込んで数年。大人になればなるほど身に染みる正社員という肩書はありがたいけれど、定額使い放題の働き方は心身を蝕む。
美容室に行く気力もなくて、服を楽しむ余裕もなくて、最低限社会人としてのまともな服装を整えて、日々押し流すように生きている。
ーーSVは体力勝負の仕事だ。
自分より一回り以上年上のパート女性たちの管理と指導。指示書の作成に売上データ報告、営業報告に卸売業者とのやりとり。悪い意味でフレックスタイム、みなし残業、土日休みなんてもってのほかーーその代わり給料だけはまともなのが救いだ。
その給料も病気やストレス解消の散財で消える人が多いのが実情だけど。
女性社員はそこそこ入社してくるし、全社で見れば管理職にだっている。けれど当支店には今のところ、正社員の女性は私しかいない。
事務業務は契約社員の人ばかりで、男性社員は時々そこで彼女を捕まえて結婚している。私は、学生時代以来彼氏なんて一人もいない。作る暇なんてないまま、あっという間に二十代を浪費している。
ワーカホリックな支店長は、私が送信して20分ほどで本日の業務成績をまとめたものを社内チャットにアップロードする。
今日も最も売り上げを上げたのは私のチームだ。
ほっとして、私はざっと他のSVのチーム売上成績もチェックする。
そしてざらりとした心地になった。
ーー二番手は、やっぱり常盤か。
私より2歳年下のイケメン。専門学校卒で元美容師の中途採用だ。だからかいつも小綺麗で、声が大きくていかにも体育会系。日焼けマッチョの支店長のお気に入りだ。
多少客にタメ口を使っても許されるような明るい調子と体育会系育ちのパワーで、私よりも成績が下でも妙に気に入られて、ガリガリと仕事をする私よりずっと社内の評価が高い気がする。
よく遊び、よく働く! そんなことできるか。ばーか。
成績では勝てているはずなのに、背中をちりちりと焼かれるような心地が取れない。
ーー常盤、私より先に出世するんだろうな。
私は、出世をしたいと思っている訳ではないはずだ。
でもなんとなく、負けるのだと思うと嫌な気持ちが心を蝕む。
27歳。
結婚する友達も増えてきて、メッセージアプリのアイコンが子供や結婚式の写真になる人も少なくない。仕事で出世した人もいるし、ライフワークバランスが整った会社でのんびり趣味を楽しんでる人もいる。少なくとも独身で彼氏のいない人は婚活や恋活に勤しんでいる状態だ。
それに比べて、私は。
出世できるかもわからない、会社のハイペースな業務についてくのも必死で、毎日罵倒されながら、ネイルもしないで深夜帰宅、休みはシフト制だから土日もなし。
確かにお給料だけはマシだけど。
でも成果給の割合が多いから、走り続けないとすぐにドボン、だ。
終電に滑り込もうとする人の波に乗って歩いていると、ふと、電車に乗る途中で、駅前の映画館の上映告知ポスターが目に入る。
人生を、生き方を問いかけてくるシンプルかつ力強いポスター。
ーー私は、どう生きたいんだろうなあ。
ーーはー……私も転職しようかな……ううんそれ以前にライフプラン……。
最終電車に滑り込んだところ、たまたま空いたすみっこの席を確保できた。連休前日の終電は、浮かれた飲み会帰りの酒臭い息の人ばかりだ。
くたびれたオフィスカジュアルを隠すようにバッグを大手目を閉じて、私は電車の揺れに身を委ねた。
ーーなんでこんなに努力してるんだろう。
ーーなんでこんな会社、こんな人生を、選んだんだっけ?
◇◇◇
気がつけば熟睡していたらしい。
電車が止まったので目を覚ますと、知らない駅で電車が止まっていた。
「うそ、終点……?」
もちろん自宅の最寄駅は終点ではない。
呆然と電車を降りると、そこは真っ暗だった。
駅員さんすら、誰もいない。照明も私がいる場所と、改札しか灯っていない。蛾の一匹すらいない無音の空間に、私は怖くて一気に目が覚めた。
「こ、この路線に無人駅なんてあったっけ……」
肩にかけたビジネスバッグの持ち手をギュッと握り締め、防犯ブザーを指にかけ、そろりそろりと駅の階段をおりる。
駅はほぼ廃墟だった。
壁に貼られたポスターも妙に古くて見覚えのないものばかり。改札には誰もいない。自動改札すらない。出る時に音が鳴ったり、駅員さんが呼び止めてくれることを祈ったけれど、響くのはパンプスが床を踏みしめる音だけだった。
駅の外も当然真っ暗で、目の前には廃墟の商店街が広がっていた。
降りたこともない駅で、三百六十度どこにも灯りがない、深夜。
ーー怖い。
震える膝を踏ん張り、なんとかへたり込むのを堪える。
草がぼうぼうに生えていて、アーケード街らしきものはボロボロ。真っ暗なゲームセンターの壊れたネオンが、月明かりを反射し、死んだ魚の目のような濁った色で鈍く浮かび上がっている。
「あ、そうよ、どこ……うそ……」
スマートフォンは充電が切れている。
「う、嘘でしょ? こんなことって……待ってよ」
野宿しかないのだろうか。ただただ怖い。
見上げると空が妙に明るくて、星がいっぱいに輝いているのがますます不気味だ。空が華やかだからこそそ廃墟の真っ暗が余計に墨で塗りつぶした大きな化け物のようだ。
「だ、誰かいますか……?」
泣きたい気持ちを抑えて一歩一歩、私は商店街の方へと向かう。
頭の隅に、ネットで流布した都市伝説が過ぎる。
ーーある女性が日常的に乗っている電車で、見知らぬ異界の駅に迷い込んだ話。
どこまで行っても人がいなくて、不思議な駅で迷子になったまま連絡が途絶えて。
私もついにあの都市伝説の仲間入りをしたのだろうか。
冗談じゃない。もう27歳で、社会人で、アラサーで。
都市伝説なんて信じてきゃあきゃあ言えるような歳でもないのに。
私はむしろ自分の正気を疑い始めた。疲れて幻覚が見えるようになったのかもしれないーー
その時。
廃墟のアーケード街の奥の方に、あたたかな明るい店の明かりが覗いているのに気づいた。飲み屋だろうか、食堂だろうか。暖色の明るい光に思わず駆け寄る。
表には『食堂』の大きな二文字が描かれたサイン看板が淡い光を放っている。
第二話
第三話
第四話
第五話
第六話
第七話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
