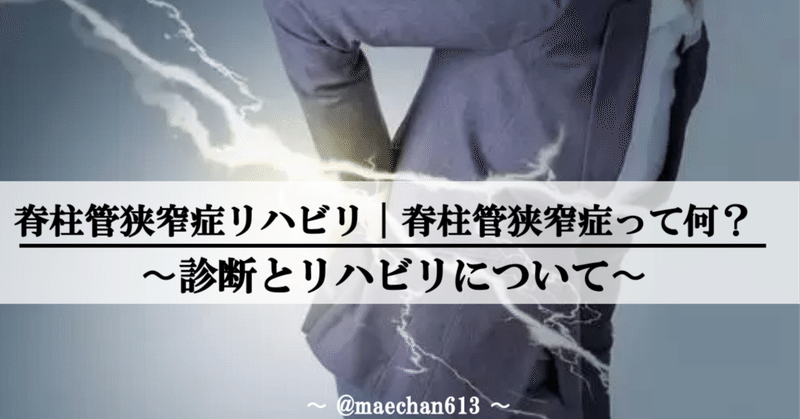
脊柱管狭窄症リハビリ|診断とリハビリについて
皆さんこんにちは!
理学療法士の前田です🤗
前回は脊柱管狭窄症の症状や分類に関して投稿させていただきました。
今回は脊柱管狭窄症の診察やリハビリ内容の情報をご紹介します。
1.はじめに
腰部脊柱管狭窄症は加齢による変形などで腰椎の脊柱管が狭くなり、神経や血行の障害が起き、下肢の痛みやしびれが現れ、長時間の歩行が困難になる病気です。リハビリは、痛みを軽くするとともに腰痛予防のためにも非常に大切な治療法です。そこで脊柱管狭窄症の診断からリハビリについて書いて行こうと思います。
2.脊柱管狭窄症の診察って何やるの?

脊柱管狭窄症には、明確な定義はありませんが 「腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン」にて個々の疾患にこだわることなく、実際の臨床所見をもとにした診断基準が提唱されました。

腰部脊柱管狭窄症では、下半身の痛みや痺れに加えて立ち止まっては歩き、立ち止まってはまた歩くような『間欠性跛行』と呼ばれる特徴的な歩行が診られますが、末梢動脈疾患などの血管性間欠跛行でも同じような歩き方をします。これら類似疾患との鑑別、および治療方針の検討が重要となるため診察では、以下のような項目が実施されます。
🔶問診
年齢や既往歴を詳しく問診します。特にどのような姿勢、どの程度の歩行により症状が出るのか、どのように休むと改善が得られるのかなどを確認します。
🔶身体所見

脊柱管狭窄症では、狭窄が起こる部位によって症状の出る部位や障害される筋肉が異なります。そのため腰痛の有無、痛みやしびれのある部位を確認し、感覚障害・運動障害(筋力低下)・反射異常などの神経学的所見をチェックます。閉塞性動脈硬化症とまぎらわしい場合には、下肢の動脈硬化の状態も確認します。
🔶レントゲン検査
腰椎のレントゲン検査を行い、背骨の状態を確認します。レントゲンでは変形性腰椎症の程度、腰椎すべり症の有無、などから脊柱管の状態を推定することができます。
🔶MRI検査

レントゲンには骨しかうつらないため、詳しく検査を行う場合にはMRIを使用します。MRI検査により、実際にどの程度脊柱管が狭くなっているのか、椎間板や関節・靭帯の状態はどうなのか、神経への圧迫状態はどうなのか、その他の合併異常がないか、を確認できます。
🔶CT検査、脊髄造影検査
MRIを撮影できない患者さんや、MRIのみでは診断がつかない場合、手術に備えてより詳細に検査したい場合には、CT撮影や脊髄造影検査を行うこともあります。脊髄造影検査では、神経の狭窄度を、実際に目で見て確認することができます。
3.腰部脊柱管狭窄症のリハビリとは?

脊柱管狭窄症は慢性進行性のため進行していくと、歩行困難や尿漏れなどの運動機能の低下につながります。そのため、運動機能を維持・向上させるためには、リハビリテーションなどの保存療法を実施することが推奨されています。
脊柱管狭窄症に対するリハビリの分類として、
①理学療法(歩行・バランス練習、姿勢練習、身体運動、生活指導など)
②運動訓練(筋力増強訓練、バランス運動、歩行訓練、持久性運動など)
③ストレッチ(体幹、股関節周囲、肩甲骨周囲など)
④トレッドミル歩行(速度や傾斜を調整したトレッドミル歩行、部分免荷でのトレッドミル歩行)
⑤ノルディック歩行 などがあります。
腰椎の牽引や、温熱治療などの物理療法、および歩行やストレッチ、マッサージなどの運動療法を行う場合もあります。これらを組み合わせて行うことで、腰臀部痛や下肢痛を改善する効果が報告されています。
脊柱管狭窄症は筋力の低下や同じ姿勢などで進行しやすい疾患ですので、筋力の維持・向上を目的としたリハビリや自主トレは有効です。痛みがある部位の筋肉がほぐれると、症状の改善にもつながり、症状が出ない範囲で適度に運動を行うことがとても大事になります。ただし、痛みがあるのに我慢して長時間歩くと神経にダメージが加わるためなど、症状を悪化させてしまう可能性もあるため無理な運動はしないようにしましょう。
※脊柱管狭窄症のセルフケア内容に関しては徐々に投稿させていただきます。
下記ストレッチも参考までに✨
〜セルフエクササイズ〜
【お尻ストレッチ】
殿筋群は股関節の安定性や動きに関与する筋肉です。しかし柔軟性が低下することで骨盤の動きを制限したり、下半身に伸びている神経や血管を圧迫することで痺れや痛みを助長してしまいます。骨盤の動きを意識しながら伸ばしてみましょう!

【腸腰筋ストレッチ】
腸腰筋は腰椎の安定性や股関節の動きに関与している筋肉です。柔軟性が低下することで腰の動きが制限され、腰部への負担が増大することで症状を悪化させてしまうこともあります。腰の反り過ぎに注意しながらストレッチを実施しましょう。


【もも裏ストレッチ】
もも裏にはハムストリングスという大きな筋肉が坐骨から膝裏に付着しており、様々な動作に対して骨盤から下半身の安定性に関与しています。柔軟性が低下することで骨盤の動きを制限し、姿勢の乱れや痛みの要因となってしまうため、こまめなストレッチをオススメします。

【ヒップリフト】
ヒップリフトは殿筋のトレーニングです。腹部や殿筋群の筋力低下することで腰や骨盤が不安定な状態となるため、関節に負担がかかってしまいます。ストレッチで
筋肉を緩めた後に適切な刺激を与えることで筋肉の質を高めることが出来ます。

4.おわりに
脊柱管狭窄症は、様々な要因によって脊柱管内で神経が圧迫されることで症状が出現し、身体所見とレントゲンやM R I検査などの検査を踏まえて診断されます。しかし、身体の柔軟性が低下したり、筋力が低下することで同じような症状が出現することもあるため、必ずしも画像所見と症状が一致するとは限りません。脊柱管狭窄症の疑いのある方や診断されている方は、ご自身の身体の状態を確認することの大切な行動のひとつかと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
徐々に投稿していきますのでまた読んでいただけると嬉しいです(^ ^)
〜参考文献〜
1)日本整形外科学会,日本脊椎脊髄病学会.腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2011,南江堂
2)日本整形外科学会ホームページ「腰部脊柱管狭窄症」(2019年8月参照)
3) 紺野慎一,日本腰痛会誌 15(1):32-38,2009.
4)菊池臣一:プライマリケアのための腰部脊柱管狭窄ー外来マネジメントー改訂版,医薬ジャーナル社:22,2015.
5)Kasukawa,Y,et.:Lumbar spinal stenosis associated with progression of locomotive syndrome and lower extremity muscle weakness.Clin Interv Aging14:1399-1405,2019.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
