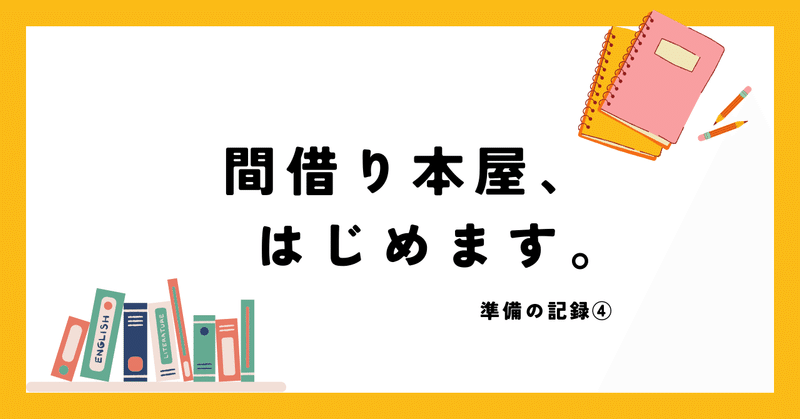
どんな本屋にしたいか
昨日はハリ書房さんにお邪魔して今後のスケジュールを共有(先日、鏡開きをされたとのことで切り餅をおすそ分けしてもらいました)。
その後、神田小川町にある「本の問屋」、八木書店さんを紹介いただき一緒にご挨拶へ。本来、個人経営や小規模の本屋は新刊を仕入れるハードルが高いのだそう。しかし、八木書店さんはそうした小さな本屋でも新刊の仕入れができる場所となっています。
カレンダーを見ると、本屋オープンまであっという間に残り半月。最初の計画では年始頃までにnoteの記事を10本くらいは公開したいなと考えていたのですが、生来のさぼり癖も出てしまい前回更新時から1週間を過ぎてしまいました。さすがに焦って、ようやくまた書き始めています。
実は更新が滞ってしまったのにはもう一つ理由がありました。言葉を発信することの無責任さについて、ふと考えることがあったのです。
年始に実家へ帰り、いりえで扱う本を整理していたとき。途中で何度かTwitterを更新したのですが、作業終了のつぶやきをする際、最初に書いた文面を一度消して、下のような内容にしたのです。
途中、おしるこで一休みしてひとまず整理を終えました。文庫本129冊、漫画20冊、その他すべての一般書178冊、計327冊。後日ハリ書房さんの店舗内へ郵送し、順次値付けを。全体的にお求めやすい価格にしてポイントカードなども作りたいな。オープンまで3週間と少し。一つひとつ準備を頑張っていきます! pic.twitter.com/jFxlgG2JqU
— 間借り書房 いりえ (@magarishoboIRIe) January 7, 2024
私の地元は北海道。真冬だと-15℃くらいまで気温が下がる地域です。大量の本を置くスペースには暖房がなく、作業を終えた頃には身体が冷え切っていました。なので、はじめは「凍えた身体をあたたかい湯船で癒します!」と書こうと思ったんですね。
そこでふと、元旦の大地震によって被災した地域の方々のニュースが頭に浮かびました。避難所でどうにか日々をしのぎ、決して心穏やかにはいられない状況。フォロワーも少ない私のアカウントですが、当事者の方が目にしないとしても、なんだか「あたたかい湯船」という言葉は書きたくなかった。
いやいや、家でのんきに好きなことしてるじゃないか、おしるこ食べてるじゃないか、それは書いてもいいのかよという自問もありました。
まだまだ配慮に欠けている部分はあるかもしれないと自覚しつつも、発信を続ける上では目の前の生活すべてを検閲・自粛することは難しいので、違和感のあるものはよく見つめて少し横に置いておく。せめてそれくらいの心がけは持とうと思いました。
さらに実際に本屋をオープンしたら、訪れる方がいろいろな場所、属性、境遇、構造について知れるような本も多少ならず置いていきたいなという考えに発展。
たまたまタイムラインで見かけた下のツイートも、そうした思考への流れを作ってくれたような気がします(映画「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を観ていない方はもしかしたら少し分かりにくいかもしれませんが…)。
ダンジョンズ&ドラゴンズ、脚本のバランスが素晴らしいとよく褒められてるけど、脱獄したあと馬を盗むシーンについては「遊牧民にとって大事な財産なのに」という批判を見かけたことがあり、こういう細かい箇所にどれだけ配慮できるかは、異なる文化や価値観をどれだけ知っているかで決まるんだろうな
— 泉谷めい (@izmyaya) January 6, 2024
この脚本を書いた人なら、知っていたら「主人公が遊牧民から馬を盗む場面」は入れなかったと思う(観客への配慮だけでなく、ストーリー上もあそこでエドガンの好感度を無駄に下げる必要はない)
— 泉谷めい (@izmyaya) January 6, 2024
だから多様な文化を知ることは大事だし、多様な価値観を持つ人々と作品を作ることも大事なんだよね
なにかしら言葉を発するとき、自分とは異なるけれども考慮できる立場や価値観というものが、1日に一つずつでも増えていけばいい。
いりえは「ひと休み/交じり合う/外へ」をコンセプトにしていますし、当面は古本をメインにしつつ、そういった本も地道にしっかり取り揃えていきたいなと、また少し方向性が見えた近頃でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
