
富山県「高校再編」市町村長ら、県教委に不信感
次期高校再編に向け、県内15市町村が18日、新田八朗知事や荻布佳子教育長と意見を交わす初の会合がオンライン形式で開かれた。再編議論を進める県教育員会に対し、首長からは「規模ありきだ」と不信感をあらわにする意見が相次ぎ、再編の目的やメリットを明確にするよう求めた。過去の再編や毎年の募集定員の決め方に対する不満が浮き彫りとなり、県立高校がある13市町村全てで存続を求める声も上がった。
再編議論会議と市町村の意見の乖離が明らかに
富山県の高校再編に関する会議は、大きく3つになります。
・教育委員会会議(県議会を除けば最高意思決定機関)
・県立高校教育振興検討会議(校長など教育関係者、保護者、経済界の代表者で構成。現時点で第4回まで開催。委員長・副委員長は互選)
・総合教育会議(県知事主催の会議)
注目されるのは、これらの再編検討会議では、「再編やむなし」が前提条件のように議論されている一方、今回の記事では、各市町村長がこぞって「再編に反対」つまり、「地元の高校をつぶすな」と強く求めている点です。
矢継ぎ早に行われる再編検討会議と、当事者である自治体の意見に大きな隔たりがあることを示しています。
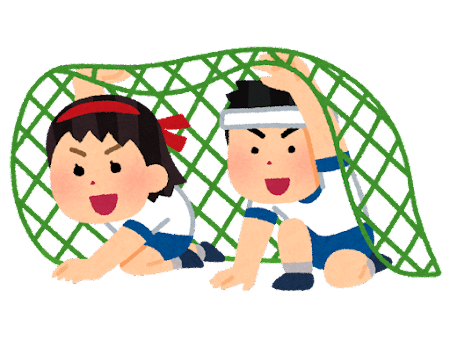
「再編」に賛成と反対があるのはなぜ?
そもそも公立高校再編の議論が行われているのは、急激に進む少子化が背景になっています。
「再編」に賛成の意見は?
少子化がすすむと学校規模が縮小していく。子どもたちの数が少ないと、学校の教育活動(部活動も含む)も縮小していくしかない。
再編・統合により、学校規模を維持または大きくすれば、教育活動が充実するとともに、子どもたちも「切磋琢磨」することができる。
財源(主に人件費)の問題。高校標準法により、クラス規模(1クラス当たりの人数)および学級数に応じて教員の定数が決まります。これを前提とする以上、生徒数が減るにしたがって学級数が減り、国からの補助が縮小。手厚い教育を維持するためには、各地方自治体が独自に教育予算(人件費)を確保しなければならない。しかし、厳しい財政状況のなか、それだけの余裕はない。(長くてすみません)
「再編」に反対の意見は?
生徒数の減少に伴い、教員数を維持するだけで少人数学級が段階的に実現する。
日本の1クラス当たりの生徒数の基準(小学校は35人、中高は40人)は、国際標準(20~30人)と比べて多すぎる。少人数学級が実現すれば手厚い指導が可能。
高校の無くなった自治体は、子育て世代から選ばれなくなり、地域の衰退につながる。職業系の高校などが定員割れを起こしやすいが、地元の産業の担い手づくりに貢献しており、産業振興の面でも存続させるべき。
最後に みなさんの自治体はどうなっている?
この高校再編問題は、各地で起きているはずです。
最近再編が行われたよ! という自治体もあるでしょう。
「知らないうちに、子どもを通わせる学校が近くに無くなった」というようなことのないように参照すべきソースは次の通りです。
地方新聞
都道府県のHPに公開される議事録
教職員限定で、教職員組合(日本国憲法によって保障された労働組合。大きく分けて日教組、全教の2系統があり、地域で所属団体が異なる)が都道府県教委と行う交渉に参加する。または、発行する交渉詳報や資料を参照する。
地方新聞は可能なら複数紙を参照してください。
HPは各種再編関係会議や県議会の議論、決定が比較的早く公開されます。
可能ならば、「傍聴」をしてください。県民、市民に開かれた会議ですので、とくに申し込みもなく、当日受付で傍聴が可能の会議が多いはずです。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
よかったらスキとコメントお願いします! あなたの反応があるから、「けい先生」はこのネット世界でかろうじて存在することができます!
