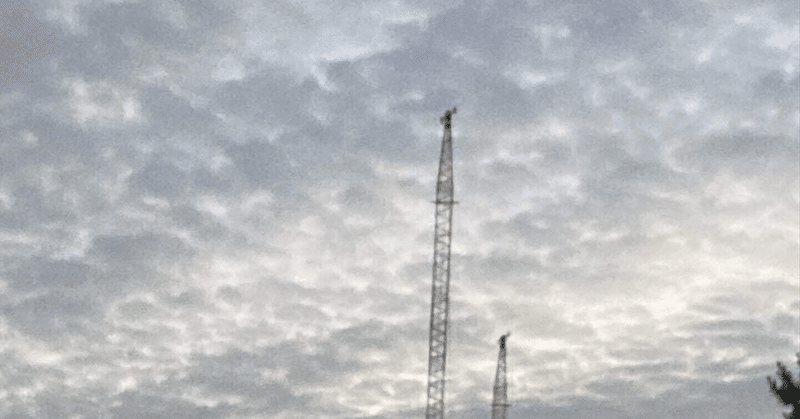
2024年度年間テーマ評論「時事詠を考える」⑤
後ろめたさ、外から 染野太朗
時事詠と言えば、もうずっと考えていることがあり、しかし考えるたびにその考えが変化し、結局どのような立場で時事詠を詠み、読めばいいのかわからなくなり、自分では詠まなくなってしまった、あるいは、詠んだとしても発表しない、もしくは通常よりもずっと慎重になって取捨選択し、結局それが時事詠なのかわからないような歌を提示する、というようなことをくりかえしている。
正直なところ、時事を詠むことが怖ろしい、あるいは後ろめたいという気持ちがある。いや、怖ろしい、のほうはまったく個人の、作者としての態度や資質の問題だからここで話題にしてもほとんど意味はないのかもしれない。対象とする社会的事件・出来事に対しての無知や思考の浅さが歌に表れてはいまいか、という点での怖ろしさは、ひとりの表現者としてはあまりにも情けない心情であろう。これは実は、歌会などにおいて、その歌からはどうにも読み取ることのできない個人的な物語を嬉々として、あるいは苛立ちながら説明するのとほとんど変わらない態度でもある気がする。歌を作者個人の所有物として矮小化し、オープンソースとしての〈表現〉から切り離す態度。もちろんこれも偏った考え方で、個人の所有物でありオープンソースでないことには価値がないとか、それらがゼロであることが理想だ、などと言いたいわけではない。
後ろめたさについて。ごく個人的な感覚だが、社会的事件等を詠むときの後ろめたさが、自分のなかで年々大きくなっているような気がする。題詠化する後ろめたさ。東日本大震災直後から大量に震災詠が発表され、そしてほどなくして、テレビ等の情報だけをもとに、ときにさも当事者・経験者であるかのような、あるいは当事者・経験者なのか判別がつかないような内容と口ぶりで詠むことへの批判の声が上がった。あの災害において当事者とは誰を指すのか、当事者とそうでない者の境界は曖昧であるし、いずれにせよそれが詠まれることの意義はあるという結論に私自身は落ち着いていた。想像力と論理を駆使し、多面的な視点で考え抜き、オープンソースとして提示された歌には意義がある、いや、そもそも意義などというものを前提とすることは、表現そのものや読者に対する傲慢な態度だと思っていた。それに、これほどまでに広範囲の、大量の情報が露わになり、だからこそそのぶん大量の隠蔽や視点の偏り、真偽の不明さも広範囲に渡り、しかもそれがほとんど画面や紙で隔てられた向こう側で起こっていて、そのような情報環境にさらされながら何かしらを詠もうとするとき、真にその当事者であることはおそらく不可能であり、しかもその向こう側のできごとから私たちは必ず何らかの影響を受けているのだ、ということまでも情報として与えられ自覚させられるこの状況では、無自覚なままだとしても、誰もが「当事者」でいることしかできないようにも思う。
それでもなのか、だからこそなのか、時事を詠もうとするときの、あるいは読むときの、拭えないこの後ろめたさはなんなのだろう。それらは間接的にであれ自分の生活に影響を与えているものであり、しかし同時に画面や紙の向こう側の出来事でもあるということ、そのどちらもが以前より強く感じられ(るような環境を生きており)、だからこそもっと真正面から時事詠に取り組まなければという思いと、しかしそれをすることは結局、自分の歌のためにそれらを歌の題として消費しているに過ぎないのではないかという思いが、強く摩擦を起こす。この後ろめたさも、作者としての個人的な心情・資質の問題として乗り越える、あるいは無視すればよいのか。
縦の空に黒き煙はのぼりゆくスマホに撮りしをスマホに見たり 吉川宏志『雪の偶然』
治りそうな負傷ばかりが映されて横たわる人にぼかしのかかる
焼け焦げしビルのあいだをピンク色に着膨れしたる子が逃げてゆく
雪の上に遺体散らばりいるならむ地図の縁(ふち)から赤く抉(えぐ)らる
命捨てて自由を護るは正しきか 崩れたビルの鉄芯が立つ
焼け跡を歩きて溶ける靴底の臭いは想像できる できるか
ロシアによるウクライナ侵攻を詠んだ歌。吉川は慎重だと思う。自分はあくまでもスマホによって爆撃による「黒い煙」を見ているのだと明らかにする。しかも、スマホで撮った映像を、である。そこには物理的なもの以外にも、幾重もの隔たりがある。二首目、映されているのは何らかの常識や規制、規則の範囲内のものなのだ、と示す。それ以外はたとえ映されたとしても「ぼかし」を入れられる。スマホの画面に切り取られた「縦の空」のその外側に何があるのか、見ることはできない。ごくごく一部しか見ることができない。つまりこの二首は、実は戦争を詠んでいるのではない。現代における情報のあり方を詠んでいる。三首目に感じる慎重さは、感情を交えずに見えたものを見えたままに詠もうという感覚。言語化する以上「見えたまま」はありえない。けれどもこれはそのような印象をもたらす歌だと思う。四首目、地図を赤く塗りつぶすことによって侵攻の度合いを可視化したニュースの映像だと思う。ここに現れたのは見えないものを見ようとする想像力と、画面をぼんやりと見ているだけでは感じ得ない痛み。「抉らる」という一語が、負傷した、あるいは殺された人間の肉体を想起させる。この歌がなければ想像しえなかった生々しさかもしれない。五、六首目において注目すべきは「正しきか」「できるか」であろう。自らの判断や想像力への疑いである。例えば、特に一、二首目や五、六首目のような、対象となる事柄そのものというより、それと向き合う際の自分自身や自分が置かれた状況を描くことは、あるいは後ろめたさに対するひとつの回答になるのかもしれない―いや、なるのだろうか。それは、後ろめたさを根本的に解消する方法ではなく、題詠化(つまり作者の言葉と修辞に対象を従属あるいは矮小化させる)を避ける方法ではなく、後ろめたさを覆い隠すための方法、免罪符にも見えないか。そして肝心なのは、そのように見たのは吉川ではなく、これをそのように読んだ私であるということ。たとえ仮に吉川本人にとっての免罪符であったとして、それは読者にはかかわりのないことではないのか―私はなぜそこまで後ろめたさにこだわるのだろう。
やらされるエイサーだった秋空に子どもの俺は写真のなかで 平安まだら「パキパキの海」(「短歌研究」2023.7)
不発弾処理のチラシを不発弾処理のチラシの円内で見る
軍払い下げ品店にやってきた高校生がナイキにしゃがむ
金網に囚われている軟球を取り返そうと網ごと掴む
明け方の街に倒れている人の酔っ払いではない可能性
第六十六回短歌研究新人賞受賞作。沖縄を詠む。作者は沖縄県出身であるが、当事者の歌だから安心して読めるというわけでなく、当事者の言葉だから心して読むべきだというわけでもなく、テキストとしてそもそも批評力があると思う。例えば選考委員の黒瀬珂瀾は「(「沖縄」を詠むということにおいて)本作は現代におけるひとつの成果だと思う。沖縄という場における生活の中に見え隠れする条理不条理を丁寧にたどることで、その多重文化性や産業と戦争との関係性、生死の明暗を浮き彫りにしている」と述べる。ただ、ここで一度立ち止まっておきたいのは、同じく選考委員の斉藤斎藤が「ちょっと外からの目線に配慮し過ぎな気がしてしまって」「いや、実際よくできているんです。ただ、新しい沖縄の歌として、外のわれわれが受容しやすいところに落とし込まれてる気がしてしまって」と述べている点である。米川千嘉子は「沖縄の中の人だったらこうは見ないだろうというのが、それこそが先入観なんじゃないかなと思いますけどね」と述べる。それもまったく肯けるところなのだが、しかし私は斉藤のこの発言をどうしても退けることができない。平安の作品が本当に「外のわれわれが受容しやすいところに落とし込まれている」かどうかももちろん大切なのだろうが、「外からの目線に配慮し過ぎ」「受容しやすいところに」という観点が提示されること自体に、時事詠の(あるいは現代短歌の)難しさがあらわれているように思う。作品の修辞や内容そのものだけでなく、「外からの目線」への意識の有無ということへの、メタ的な視点も持ち合わせながら作品と向き合うこと。そのような視点をより強く持たなければならないような現在であるように思うのだ。
もういいかい もういいやあ と呼応して 戦争が起こっていること知っている 花山周子「気流」(「短歌研究」2023.7)
子の貯金箱の硬貨に昭和と平成と令和があり時の巡りに
川の面の誰(た)が感情に添わせつつチャイコフスキーは聴けなくなるか
生きることの特典のように死を思う春雷、透視図法の窓に
友だちと鬼ごっこして夕暮れに子は帰りくる明日のために
ロシアによるウクライナ侵攻が「戦争」と大枠で捉えられ、そこに「知ってる」という最低限の認識のみが示されたときの、「もういいやあ」に読みうる疲労感や諦念はいったいどこからくるのだろう。それでもおそらくその「戦争」が、時代を俯瞰さえ、抑圧されうる芸術への眼差しを予め喚起し、遠かったはずの死を意識させ、「明日」を享受すべき「子」への思いを新たにさせる。主観ははっきりとし、一方で「外からの目線」もすでに内面化されているように思う。時代状況と〈今ここ〉にいる人間が、摩擦を起こしながらそこにある。苦しい歌だと思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
