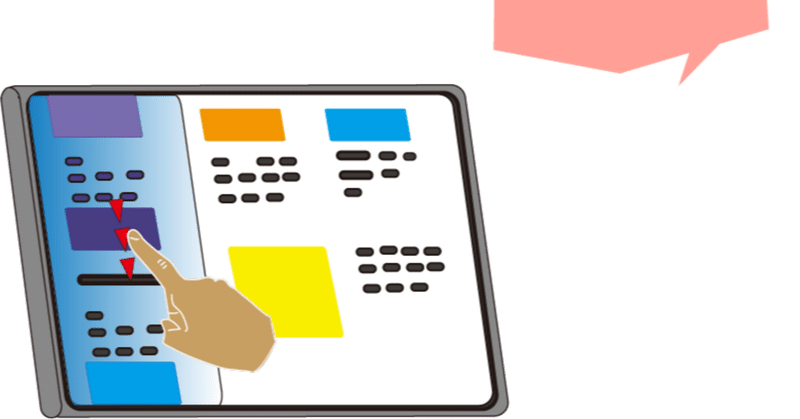
2024年年間テーマ「時事詠を考える」④
〈生き物としての人間〉という視点 柴田典昭
東日本大震災のあった年、二〇一一年の七月に金子兜太、半藤一利の対談集『今、日本人に知ってもらいたいこと』が刊行されている。金子は二〇一八年、半藤は二〇二一年に亡くなっているから、肉声で語り合った、二人の遺言集のような趣のある一冊となった。
金子は俳人、半藤はノンフィクション作家と表現方法に相違はあるが、第二次大戦に拘り、終生、表現し続けたことで共通する。その表現行為は、金子の言葉を借りれば、「悲壮とか悲劇」が「出発点」、「『殺戮死』というものへの嫌悪感」を「原点」とする思いから発している。半藤はそのことを「骨身にしみて自分の心の中にそれが入った人たちだけが戦争を語れるのだな」などと語っている。
金子は出征前から俳句を作っており、半藤には長い編集者時代があった。従って表現手段の相違は当然の帰結なのだが、金子は俳句に「臨場感」と「相対的思考」を注ぎ込むことに心掛け、半藤は取材、聞き書きの体験を通して「人間というのは嘘をつくのだ」ということを痛感して、「勉強」と「研究」へとひた走ったのだと言う。
さて、この対談は時事詠ということを考えるとき、一つの手がかりを与えてくれるように思う。勿論、「骨身にしみ」る体験は頻繁にあるわけでもなく、出来ればあって欲しくはない。また、短歌一首ではノンフィクションのような効果は挙げにくい。ここではまず時事詠の大前提として、「生き物としての人間」(金子)という視点、他人を共感を以て捉える視点の必要性については確認しておきたい。それは孟子の所謂「惻隠の情」のようなものであろうか。
その上で表現方法としては、「臨場感」の方へ向かうのか、或いは事実、真実を掘り下げる方向を目指すのか、が各自に問われるだろう。両者が共に立ち上がって来ることもあるだろう。そのときに留意したいのは、「大泣きに泣く」(金子)短歌の特質は時事詠の方向とは相容れず、避けるべき姿勢であるということだ。
昨年刊行された歌集で一冊がそのまま時事詠集といった趣を持つものに出会った。渡辺幸一の『プロパガンダ史』と太田美和の『とどまれ』の二冊である。渡辺はすでにイギリスに移住し、太田は英文学者としてイギリスへの留学を繰り返している。そうした生活環境に在ることが、日本、そして世界の現状に対して捉われのない視点、すなわち「相対的思考」で見ることを可能にさせている。まず、渡辺幸一『プロパガンダ史』より引く。
弱きものが圧殺される戦争を憎む障害者の親なるわれは
疫病の街を見おろし中世と変はらぬ空を雲動く見ゆ
原爆の語り部年々減りゆくを危ぶむ記事が英字紙に載る
杖をつき公務を果たし二日後にこの世を去りぬ老いし女王は
「身を挺しなぜ守らぬか」警察を責むる日本の世論の異常
集中に「平成二年(一九九〇年)思い悩んだ末。」という詞書持つ作品、「障害を持つ吾子のためイギリスへ移り住まむと心定まる」
があり、渡辺の移住の理由が知られる。第一首はそうした痛みを背景に「戦争」の本質が捉えられている。第二首はイギリスで体験するコロナ禍を長い歴史と時空感覚の中で捉えている。第三首からは被爆という事実が国内問題に止まらないことを知らされる。第四首はエリザベス女王を歌い、指導的立場にあるものの姿勢を問い掛ける。第五首では海外移住者の視点から見える日本の現状を憂う。
イギリスのトピックを追い、イギリスの日常を捉え、日本に居ては分からない世界の実情を知らされる。『プロパガンダ史』にはまるでノンフィクションのような面白さがある。しかし、この歌集で特に目を引くのはやはり作者の心の動きが垣間見える作品である。
次にイギリスと日本を行き来する中で生まれた作品を収めた、大田美和の『とどまれ』を見てみたい。
ニホンはもう終わったんだから帰るなと欧米人は親切だった
ギリシャからドイツをめざす国境は羊が越える木の柵のよう
嫌いな奴にも嫌われたくないって何なんだLine世代のああ面倒くさ
歴史知らず芸術知らずの人たちに後ろから刺されたりするのかな
ブラックではなくてグレーと慎ましく青年は呼ぶやめた会社を
第一首は東日本大震災、第二首はギリシャの財政破綻を背景とした作品。同じ「国境」の連作にあるので二〇一一年のものと見てよいかと思われる。そこには「欧米」の眼から見て「終わった」当時の日本の姿、同じEUに在りながら「木の柵」という「国境」に阻まれる当時のギリシャの姿が捉えられている。第三首から第五首は閉塞する日本社会の中で飼い馴らされ、従順と言うよりは人間としての矜持や心の豊かささえ失った若い世代が捉えられている。
『とどまれ』も『プロパガンダ史』と同様に日本国内に逼塞してしては分からない、日本や世界の実情に溢れている。その中で惹かれるのはやはり「生き物としての人間」を鋭くかつ柔軟に捉えた作品である。渡辺の場合とまったく変わりはないように思われる。
さて、時事詠と言えそうな作品はそれほど多くはないものの、日本の現実に肉薄しているように思われる歌集にも触れてみたい。一冊目は川野里子の『ウォーターリリー』である。
ブレーキとアクセル踏みまちがへたといふ日本(につぽん)がそしてある老人が
昨夜見し強行採決群がりて奇怪なる巨人造られゆきぬ
石鹼箱に音するやうにイ・カ・タかたかた音してイ・カ・タ
大ヤドカリひとつかみ砂を摑むまま持ち上げられたり辺野古の浜に
アメンボが水面圧(お)さふる力もて保険を買へりタッチパネルに
第一首で採り上げられるのは高齢者の運転ミスによる事故である。運転免許証の自主返納奨励へと問題は発展して行ったが、それ以上に問題なのは劣化して行くばかりの日本の現状である。どちらがより重大なのかということを、「日本」を先、「老人」を後に置く構成で伝えているのだ。第二首で歌われる「奇怪なる巨人」とは集団防衛を可能にした新たな法制度のことを言うのだろう。
第三首の「イ・カ・タ」は言うまでもなく伊方原発のことである。「伊方」は「井方」で、「水」すなわち「海」に囲われた地域といことではないかと思われる。「伊方」の対岸には作者の故郷、大分がある。作者はこの歌集の「あとがき」で、「耳を澄ますと遠く聞こえてくる見知らぬ誰かの声」と「私自身の声」を「擦り合わせたい」と記している。もはや殆ど見ることもない「石鹸箱」のカタカタ鳴る音に故郷にほど近い地の「誰かの声」を聞き取っているのである。被曝の不安に怯えて来た人々の声であろう。
第四首の「大ヤドカリ」には「辺野古」への米軍基地の移設を反対する人の姿を重ね、第五首では「タッチパネル」ひとつで「保険」への加入手続きが済む危うさを「アメンボ」の姿に重ねている。
『ウォーターリリー』には現在の日本の危うさを総体で捉える視点があり、作者の視野の広がりを感じさせる。そしてその中から危うさの核心部分を取り出し、比喩を駆使して表現している。その多くは視覚に拠るものだが、「あとがき」でも記すように「声」、或いは音を意識させることで、我々が忘れそうになっている何かを想起させるものもある。今を生きる人、かつて生きた人に寄り添う感覚が読者にも自ずと生じているのである。
川野に通じる視点を感じる市川正子の『風越』を採り上げたい。
ニッポンハスゴイデスネと言わせいるテレビを消してひとり鍋する
鉛筆を押しつけ書いた十歳の「先生どうにかできませんか」
頤マスクに炎天二キロを帰りくるランドセルの群れ涙ぐましも
ミサイルの落ちし黒土の大穴をつけっぱなしのテレビに覗く
ウクライナに送ってやりたきホカロンを背中や腰に貼る冬が来た
子供・孫自慢、故郷自慢に通じる日本自慢を外国人に強要するマスコミの劣化を歌う第一首。第二首は虐待死した「心(み)愛(あ)ちゃん」の遺書が新聞に掲載され、それに基づいた一首。第三首はコロナ禍の自粛、自粛の毎日を健気に生きる小学生を捉える。第二首、第三首では幼き者、弱き者に対する作者の温かな眼差しが感じられる。
第四首では「つけっぱなしのテレビ」で見かけた戦場のリアルな映像にたじろいでいる。「大穴」ばかりでなく、戦争の悲惨さを伝える映像が日々に報じられる現実の闇を「覗く」のである。第五首では日常の側から見た戦争の異常さ、「冬」の戦場の厳しさを思い遣り、せめてもの思いを諧謔的に伝えているのである。
作者は「あとがき」で「深みゆく老いの日常と社会」と「きな臭い今の時代」を「見つめ歌い続けること」で、「自分を確認していく」決意を述べる。『風越』の時事詠も「生き物としての人間」という視点で貫かれ、「日常」の場にあって「社会」や「時代」を歌うことが出来る、歌うべきなのだということを思わせてくれる。
さて、時事詠が対象になった事象に直接働きかけることは殆どなく、対象者に声が届くこともまずあり得ない。しかし、時事詠ほど社会と時代の中で、他者との関わりの中で我々が生きている事実を自覚させるものは多くはない。如何に時事詠を歌い、読むのかということは、自身の生き方と短歌の根幹に関わっているのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
