
#109 南米の仇をインドで打つ-3
※この文章は2013年〜2015年の770日間の旅の記憶を綴ったものです
23時少し前に目が覚めた時、昨晩あんなにも激しくテントを叩きつけていた雨の音は、耳をすましても聞こえてこなかった。寒さへの抵抗と体力の節約から23時にセットしたアラームが鳴るまでしばらくぐずぐずとテントの中で粘っていたけれど、とうとう我慢できなくなってトイレに飛び出した。
今夜わたし達と一緒に出発するグループが何組も居るはずなのに、不思議と他のテントもホテル(中央の大きなテント)の周りも静まり返っている。訝しく思いながらトイレから戻ってくると、わたしの横にテントを張っていた件のスイス人がちょうどテントから出てきて驚くべきことを言い出した。
「僕らは今夜の出発を取りやめて明日に延期した。他のグループもみんな同じはずだ」
そんなことわたしは聞いてない!と急いでホテルに駆け込むと、テントの奥でミンマが淡々と準備を進めている姿がすぐに目に入った。彼を見つけたことにホッとして近づいて行こうとするわたしに、あのスイス人と同じグループで来ていたインド人の男が寄ってきて「Are you going to summit? 」「Are you sure??」「Wow, you are so brave!」とニヤニヤしながら矢継ぎ早にまくし立ててきた。
その言い方にかなりムッとしたけれど、この男を相手にしていてもしょうがないと割り切って、ミンマのところへ駆け寄って行き「他の人達は出発を延期したらしいけど、わたし達はどうするの??」とわたしも彼に掴みかからんばかりに勢い込んで尋ねた。
「今夜、出発する」
期待していたミンマの言葉に安堵しつつも「本当に大丈夫なの??」という疑問の言葉を飲み込めず、さらにまくし立てるわたしに、ミンマは困ったような笑顔を見せながらも「まずは氷河の始まる所まで行ってみよう。」「もし天気が悪くなったらここへ戻って来て明日もう一度チャレンジしよう」となだめるように言ってくれた。
「今日チャレンジしてダメだったら、明日またチャンスがあるんだ」。この時のわたしにとってはそれがとても大きな励みになった。
行くと決まればあとは予定通りの準備を進めるのみ。寝る前に用意しておいた持ち物を確認し、必要なものを身につけて手早く身仕度を整えた。
今晩出発するのはわたし達だけだったけれど、ホテルで働くラダッキーの若者は、出発前の朝食のヌードルを準備してくれたり(その朝食を食べたのは23時半)、ほんのり甘いチャイを入れてくれたり、持って行くパック・ランチを用意してくれたりと、甲斐甲斐しく世話をしてくれて「Good luck!」と見送ってくれた。
アッパー・キャプを出発したのが0時15分。
雨は完全にあがっていて、頭上には淡く瞬く星空が広がっていた。
「どうか、この天気が続いてくれますように…」祈るような気持ち。
と同時に、初日のロウアー・キャンプで迎えた夜の土砂降りが翌日にはあがっていたことや(その日アッパー・キャンプに到着してひと息着いた頃にまた降り出した)、ここアッパー・キャンプでの昨夜の激しい雨も出発を決めた今は過ぎ去っていたことから、何か不思議な力が私たちに味方していて、頂上までの道をきっと拓いてくれている…そんな根拠の全く無い自信にも支えられていた。
登山靴を履くのはエクアドルでコトパクシに登った時以来だから約一年ぶり。そのガッチリと足を包み込んでくれる重みを頼もしく思いながら、一歩一歩を踏みしめて歩いた。
そのうち斜面を雪が覆いはじめたけれど、フカフカの新雪。アイゼンを付けるようにとの指示はまだ無い。3時間ほど歩き続けたところで、我慢できなくなって「氷河はどこから始まるの?」とミンマに尋ねた。
前日のうちに大まかな道のりと時間配分を聞いた時に、ミンマが「出発から2時間ほどで氷河が始まる。そこからアイゼンを着けることになる」と言っていたのがずっと頭にあったからだ。それほど悪いペースじゃなくここまで来ているはずなのに、まだ氷河にたどり着けていないことが気がかりだった。
ところが「ここが氷河だ。新雪が積もってるからアイゼンは必要ない」というミンマの答え。そして笑顔で「Good walk!」という言葉を付け加えてくれたことに励まされた。
そう、出発から4時間くらいまでは全てがうまく進んでいるように思えた。
「これなら旅行会社で聞いていた平均の7時間で十分登れるかもしれない」
「いや、もしかするともっと早く頂上へ行けるかもしれない」その期待で胸が膨らんだ。
けれど、そんな甘い考えを自ら否定し始めたのは出発から6時間を過ぎたあたりからだった。脚が思うように前に進まず、ストックとピッケルを杖がわりに立ち止まっては息を整えるために首を突き出し頭を垂れてしまうのだ。
もうその頃にはアイゼンを着けてザイルでミンマと繋がっていたので、後ろの私が突然動かなくなることでようやくミンマが気付いて少しの休憩をとってくれた。
これまでに登ったワイナ・ポトシやピスコの時はいつも適当なところでガイドが休みをとってくれたけれど、驚いたことにこの夜のミンマは自ら休憩を宣言したことは一度も無かった。
ストックにもたれかかって立ち止まった何度目かの時、突然ミンマから怒鳴られてハッとした。
「Don’t sleep!」
恐ろしいことにその時のわたしは瞼を垂れて意識がどこか遠くへ行きかけていた。出発する前「途中で天気が崩れたら戻って来てまた明日チャレンジすればいい」というミンマの言葉にホッとした自分を小突きたい気分だった。
今のわたしに「明日」なんて無い。ここから戻って明日また下からスタートできるなんて到底思えなかった。
今しか無い。
再び気をとりなおし重たい脚を引きずり上げる。
苦しい時にいつも必ずつぶやく言葉。もうこの世には居ない三人のわたしの守り神にまた今回も身勝手なお願いをする。ポケットに忍ばせてきたお守りのありかを確かめながら。
もうだいぶ前から手はかじかんで痛みさえも通り越していたけれど「心が温かくなることを思い浮かべれば体温も戻ってくるはずだ…」と信じて心の中で唱え続けたある人の名前。
けれども遂に耐えきれず「手が冷たすぎて感覚がないの…」とミンマに訴えた。すると彼は立ち止まって自分の手袋を脱ぎ、わたしの手袋も脱がせて強く何度も何度もさすってくれた。
ミンマの固くゴワっとした手のひらから伝わってくる体温と、わたしの紫色の指先に少しずつ感覚が戻ってくるのを感じながら、自分の不甲斐なさが情けなくて涙が滲んだ。



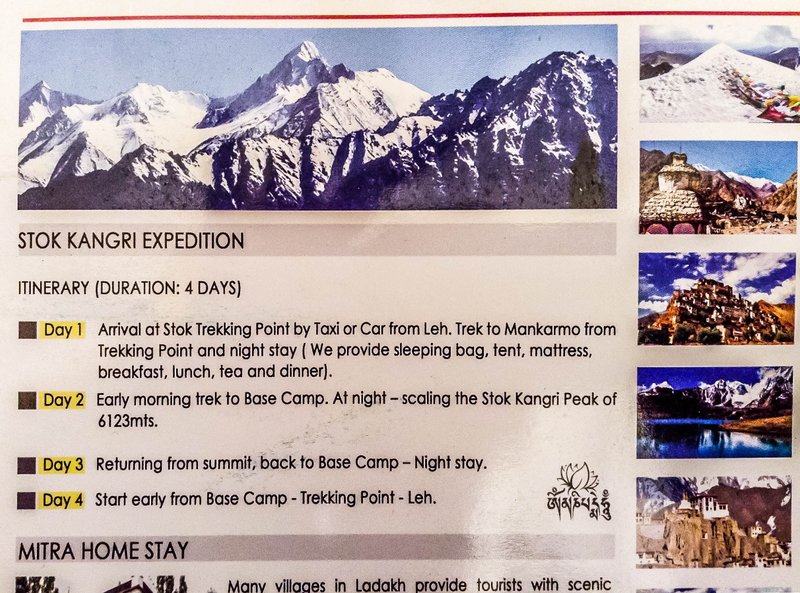
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
