
「歴史の終わり」の先にあるアイデンティティという問題――フランシス・フクヤマ『アイデンティティ』レビュー①
(※この記事は2020/05/18に公開されたものを再編集しています。)
フランシス・フクヤマという思想家
フランシス・フクヤマの『アイデンティティ:尊厳の欲求と憤りの政治』は、2018年に出版され、その翌年たる2019年には日本語版の翻訳が刊行された。つまり、原書が出されたのは、トランプ政権の誕生からちょうど2年目のときのことであり、翻訳本が流通したのは、彼の出世作「歴史の終わり?(“The End of the History?”)」という論文が表に出てから、ちょうど30年の節目にあたる。
何やらメモリアルな雰囲気を醸し出したのは、『アイデンティティ』が、その論文を押し広げる形で著された『歴史の終わり』の正統な続編とでも言うべき著作にほかならず、しかも同時に、2020年秋にアメリカ大統領選挙が待っている私たちとしては、アメリカだけでなく世界を席巻するポピュリズムについて、彼がなにがしかのことを述べているのだとすれば、傾聴に値すると思われるからだ。
意図したものではないだろうが、彼には、主張すべきタイミングを見極める才能があるのかもしれない。今回もまた、『歴史の終わり』と同様にタイミングのいい議論だった。
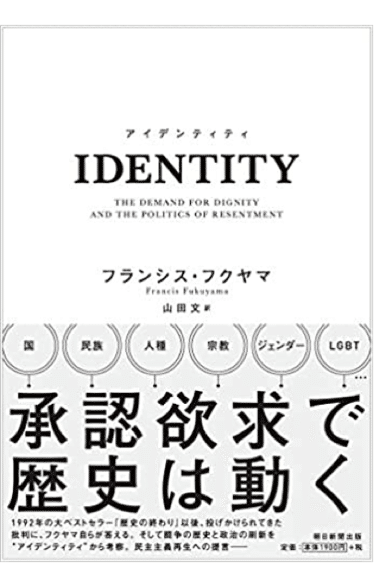
「歴史の終わり」は何の「終わり」?
そもそも、今日の読者に、「フランシス・フクヤマ」という響きがどのような含みを持つのか、私にはよくわからない。ただ、一応断っておくと、彼の「歴史の終わり」論は、ちょうどベルリンの壁崩壊やソ連崩壊の直前だったこともあり、一種の予言的なテクストとしてセンセーショナルに扱われた。
その種の本にありがちなように、手頃な要約と教科書的な理解が出来上がった後は、ほとんど読まれることがなく、彼の「歴史の終わり」論をひとまず批判しておくことが、なにかもっともらしい議論の導入になると思われているほどだ。
「歴史の終わり」とは言っても、「話は聞かせてもらった、人類は滅亡する!」という話ではない。ある特殊なニュアンスが込められている。簡潔に言えば、G. W. F. ヘーゲルの歴史哲学に倣い、世界史を自由が展開していくものと捉え、その到達点=目的(end)を描くというのがフクヤマの「歴史の終わり」論の眼目だった。
彼自身の言葉をかりるなら、教科書的な理解におけるカール・マルクスは「共産主義のユートピアが歴史の終わり(目的地)になると示唆した」けれども、むしろ、「発展の行きつく先は市場経済と結びついた自由主義国家だという考えがより妥当と思われる」というものだ(p.13)。
歴史が終わっても残る問題
このような理念的な到達を歴史が仮に得たとしても、そこで万事解決すると考えていたわけではない。対立や闘争がこの世から消え去ると彼は主張していないし、ナショナリズムや宗教がなくなる、あるいは、自由をめぐる具体的な政治的アクションが行われないと述べたわけでもない。
フクヤマは明確にそのことを認識しており、近代の到達点たる「資本主義+自由民主主義」というカップリングが実装された大衆社会においては、フリードリヒ・ニーチェが「末人(last man; Letzter Mensch)」が決定的な問題として前景化すると考え、『歴史の終わり』の終盤で重点的に検討していた。

テューモス(気概)という鍵概念
『アイデンティティ』では、末人よりも、「テューモス(thymos)」という概念がキーとなっている。これは、末人同様に、『歴史の終わり』でキータームとして登場した言葉で、「気概」とも訳される。
「気概」とはいっても、「この人は、なかなか気骨があってね……」というような強気で戦士的な語感を読み取る必要はない(そういうニュアンスは確かにあるが、フクヤマの議論を理解する上では、少しミスリーディングに思える)。むしろ、人として尊厳を認めてもらいたいという感覚として、素朴に理解しておいた方がよい。
人は、他者と並び、他者を越えたがる
「尊厳の承認」は、市場経済・自由主義・民主主義を組み合わせ、人々を等しく承認するかに見える社会にあっても難題であり続ける。
フクヤマは、二つの視角からそのことを論じている。すなわち、①他者と対等な承認を求める方向と、②他者より優れた存在としての承認を求める方向である(それぞれ「アイソサミア」と「メガロサミア」と呼ばれる)。
①「現代の自由民主主義諸国は、最低限の尊厳を平等に認めると約束し、おおむねその約束に従って行動しており、それは個人の権利、法の支配、参政権として具体化されている。しかし、民主主義国に暮らす人が実際に平等な尊敬を得られる保証はない」(p.14)。その典型が、「社会の周縁に追いやられてきた歴史を持つ集団の人々」(Ibid.)である。
②自由民主主義諸国は、それなりの繁栄と平和をもたらしてきたように見えるが、しかし大衆消費社会に生きる人間たちは、「消費することで得られる満足感を飽くことなく追い続け」ているだけであり、「自分の核に何かある」わけでも、「自分が目指したり、そのために自分を犠牲にしたりする高い次元の目標や理想」を持つわけでもない(p.14)。これが「末人」である。代わりに、他者との比較において優越し、賞賛を受けることを求める自己宣伝と承認欲求の終わりなき競争へと身を落とす。そして、このような生き方は、すべての人間を満足させるわけではない。

なぜ尊厳の問題は消えないのか
やや抽象的な物言いだった。具体例を挙げながらまとめ直そう。
①は、制度上や理念上の平等は常に不完全であり、最低限の尊厳を実質的なものとして確保することが決して容易いものではないことを言っている。本書で例として挙がるのは、警官の黒人への暴力への怒りを端緒とするブラック・ライヴス・マター運動、各種ハラスメントや見た目や性的魅力で女性を評価する文化を告発したMeToo運動などである。
②は、他者への優越に基づく「尊厳」の感覚である以上、勝ち負けが、優劣が存在している。学校の成績、誰かとの仲の良さ、恋愛、パートナーの容姿、出身大学、学歴、年収、社会的名声、結婚、出産、居住地、キャリアパスなど、ライフステージの様々なところで、そうした(唾棄すべき)「競争」や「心理戦」が存在することは、誰しも知っていることだ。もし、そのゲームに乗るか、そのゲームの存在を意識してしまえば、私たちは自分の生活を、他者との勝ち負けのように理解してしまう。
テューモスを刺激される現代社会
これら二つは、根本的に解消しえないものである以上、尊厳の感覚をめぐる問題は未だに積み残されており、フクヤマは「テューモス」の問題を検討し続ける必要があると示唆した。その課題を、2020年を間近に臨むタイミングでフクヤマ自身が引き受け直した。そうして書かれたのが『アイデンティティ』という本だ。
「様々な場面で政治指導者たちは、集団の尊厳が傷つけられたり、ないがしろにされたり、無視されたりしているというイメージを使って支持者を集めてきた」(p.24)という言葉が象徴するように、現代の政治は、尊厳の感覚を刺激し、私たちの情念を煽られることで駆動している側面がある。そして、現実において尊厳の感覚を維持することが難しい以上、私たちはそうして煽られることを心のどこかで望んですらいるのだ。
フランシス・フクヤマ『アイデンティティ:尊厳の欲求と憤りの政治』朝日新聞出版
https://amzn.to/3aTQNl9
先月の書評でもアイデンティティの問題を扱った。こちらも参照されたい。
市場経済はアイデンティティを利用する――アミン・マアルーフ『アイデンティティが人を殺す』レビュー①
誰もが疎外を感じる時代のアイデンティ――アミン・マアルーフ『アイデンティティが人を殺す』レビュー②
フランシス・フクヤマ(Francis Yoshihiro Fukuyama, 1952-)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%AF%E3%83%A4%E3%83%9E
歴史の終わりhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AE%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%8A
②に続く
2020/05/18
著者紹介

博士(人間・環境学)。1990年生まれ、京都市在住の哲学者。
京都大学大学院人文学連携研究員、京都市立芸術大学特任講師などを経て、現在、京都市立芸術大学デザイン科講師、近畿大学非常勤講師など。 著作に、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(Discover 21)、『鶴見俊輔の言葉と倫理:想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)など多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
