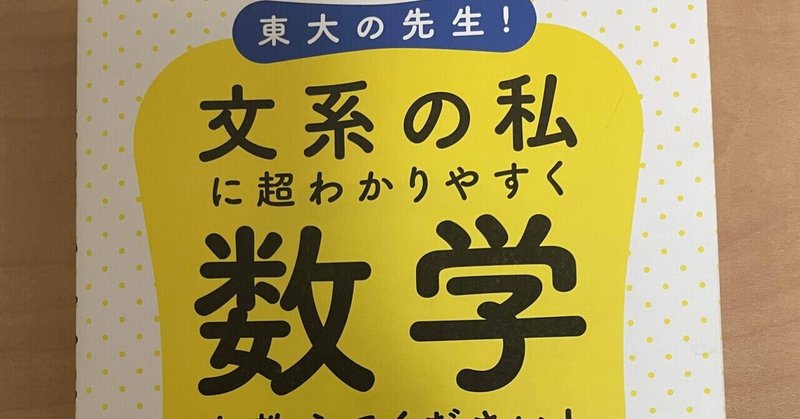
東大の先生!

素直な感想としては、字も大きいしスペースも多いし絵も多いしサクサク読め、読み物としては面白いけど、この本の表紙に書いてあるように5~6時間で中学数学が終わってしまうとは思えないし、(相似には触れて合同には触れないなど、足りない部分も多い)誰かに教えられるほど理解できるとも思えない。
あと、この本の読者層にはどれくらいの数学出来レベルの人を想定したのか?
全くできない人にとってはあの数行の数式だけでいっぱいいっぱいだし、少しでもできる人にとってはわかりきっていて読み飛ばすレベルだし、ターゲットがいまいちわからない。この本に何を求めるかで評価は変わると思う。
マイナス×マイナス=プラスになる理屈などはワタクシが教えるときはもっと理屈を付けられはするけど理屈を理解する方がめんどいので“こういうルールだから覚えてね”って教えている。
この本だとそのあたりをもっと詳しく書いているのかな・・・って思ったのだが、この本でも“決まりごとだから覚えてね”で解決するという。
まあ、それがわかりやすいってことかな。
ワタクシも曲がりなりに数学教えててわかることだけど、“やり方がわかること”と“点数が取れること”って違う。
入塾希望者と面談しているとき、数学に関して話を聞くと数学が本当にできないという人はもちろんいるけど、別に学校の授業がわからないわけじゃないのになぜかテストではいい点数が取れないという人が多い。
たいがい後者は、問題演習が足りていないのである。
たとえば、方程式とか因数分解とか、たいして難しいことも言ってないし理解もしやすいと思うけど、じゃあいざ問題といてみよう!ってなるとルールはわかっているものの移項したときに符号が変わっていないとかカッコほどくときに足し算とかけ算まちがえたとか小さなミスを積み重ね、正解できないというパターンが多い。
こういう症状は問題演習することによって自分のミスりやすい箇所を見つけてそれを意識して改善していけば解決することが多い。
話を聞いて、理解し(たつもりになって)、演習をせず、その結果点数に結びつかないし、なぜ点数が取れないかもわからない。
問題が解けるかどうかは“演習量”と“出会った回数”だと思う。
最短経路でゴールを目指すためには問題演習や延々と練習問題を解くことがムダというこの本の意見とは真反対。
“練習しない、でもできる”のは一握りの賢い人なんだろうけど、そんな人、ほとんどいない。
ちなみに著者は東大の教授。
凡人なワタクシに比べて数倍賢いしそもそも本書いてるしすごいんだろうけど賢いが故に凡人の立場になりきれていない気がする。
長々と書いてしまったが、結論としては・・・
読み物としては面白いが、タイトルが誇張しすぎ。
多くを求める人にとっては物足りない内容。
続編もあるが、もちろん購入しない。
#東大の先生 ! #数学 #読書感想文
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
