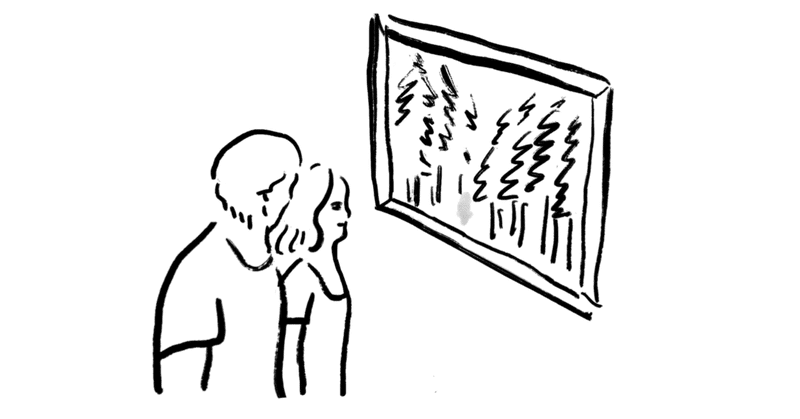
不確かな夏の記憶 中
月曜日になると、彼女の行きつけの無料のギャラリーで絵を見ながら、僕たちは作品に対して評価したり皮肉を言ったりしていた。
すると彼女は突然
「私本当はね、絵描きになりたかったの。」
と言いいだした。
「僕も絵描きみたいな人生には憧れるな」
「あなたも?どうして?」
「絵描きには世の中の常識とかはきっと関係ないからさ。自由気ままに生きて、たまにスキャンダルなんか起こしても時間が経てばまた先生とか言われてさ。しかもそれらを全部作品にしてしまったって絵描きなら許されるだろ。君はどうして?」
「私はね、自分の口から出る言葉が嫌いなの。
でも絵だったら曖昧に優しく伝えられるでしょ。
そしたらもう私はしゃべる必要がなくなるのよ。」
彼女の口から出る言葉はいつも僕の予想を一回りも二回りも超えてくるので、僕はすぐに言葉が返せない。
「なるほど、でも僕は君の言葉が好きだな。」
「ありがとう。」
彼女は気難しい話をした後も必ず最後は笑顔を見せてくれる。それは、まるでそれまでの話を無かった事にするみたいに。僕はそんな彼女の笑顔が好きだった。

彼女は音楽が好きで、木曜日には大きなスピーカーのあるジャズ喫茶に行っていた。
僕はもともとロックが好きだったし、ジャズなんてスカしたやつの聴くものだと思っていたけど、彼女に付き会うためだったら話は別だった。
ジャズ喫茶は古いビルの3階にあったけど、窓はしっかり閉じられていて、まるで地下室の様だった。密閉された空間の中で大音量で鳴り響く音楽に僕たちは包まれていた。
僕はブレンドコーヒーを彼女はウィンナーコーヒーを頼んだ。
「君はよくここにくるの」
「最近からよ。私はエラ・フィッツジェラルドが好きで木曜日になるとこの喫茶店ではエラの曲がよくかかるの。」
「ふうん、実を言うとね、僕はロックの方が好きなんだ。ジャズには全く知識がなくてね。」
「そう、私もロックは好きよ。でもロックの喫茶店ってなかなかないし、あったとしてもそんなに落ち着かないと思うの。」
「たしかに言えてる。」
「まぁジャズもたまにむせ返っちゃうくらい情熱的なものもあるけどね。」
喫茶店を出るとちょうど日が沈む時間だった。
「少しそこの川沿いを歩かないかい?あの橋から夕日がすごくよく見えるんだ。」
「いいわね」
夏の夕日は情熱的な濃いオレンジ色で、僕たちにその存在をこれでもかと主張している様だった。
「きれいだね」
「ええとっても」
それから数分で日はすっかり落ちて、空はうっすらしたピンク色と水色のグラデーションに落ち着いた。
僕たちの間には長く沈黙が続いていたが、
とうとう彼女が口を開いて、
「さっきの夕日も綺麗だったけど、私は今の空が好き。いつだってこのくらい落ち着いた心でいたいもの」と言った。
「君は落ち着いていたい。って事をよく言うよね」
「情熱的なのももちろん好きよ。でも私わかりやすい美しさってなんか飽きちゃうのよね。」
「そうかな、僕はわかりやすいのは結構好きかな」
「それが1番いいわ。でも私はもっともっと複雑な方がずっと見ていたくなるのよ。」
そう言って彼女は少し静かになったのち、
「私、いつもこやって色々とめんどくさいことばっかり考えているのよ、変でしょ」っと僕の方を振り返って明るく無邪気な笑顔をみせてくれた。
彼女が決まって最後に笑顔を見せてくれた時、僕は心から彼女を好きでいられるのだった。
そんなふうにして僕たちは夏の間この毎週のルーティンを繰り返していた。
僕は周りの誰よりも彼女の事を知っていた。
僕たちは付き合うわけでもなく一定の距離を保っていたが、僕たちの会話には他の人が理解できない深みがあったし、それが居心地がよくて、お互いが特別な存在だって僕はそう思っていた。

夏も終わりに近づいた月曜日、僕たちはいつものギャラリーでいつものように作品を見ていた。彼女がある写真の前で立ち止まっていて、そこには記憶というタイトルがあった。
美しい自然の中に人が立っている写真だったが、景色は鮮明に写っているのに"人"だけが表情も見えなければ男性か女性かも判断が難しいくらいにボケているのだ。
「この作品が気に入った?」と尋ねると。
「記憶ってこのくらい曖昧なものよね」と彼女はつぶやいた。
「そういう曖昧なものもあるけど、はっきり覚えてる事だってあるよ。」
「たとえば?」
「少なくとも君のことははっきり記憶に残るはずだよ。」
「本当にそう思う?」
「だってこんなに毎週あっているし、僕たちはもうこんなにたくさんの話をしているだろう。忘れるはずがないよ」
「じゃあ、この夏に私があなたの隣にこうしていた事を忘れないって約束してくれる?」
「もちろん忘れるわけがないよ。永遠にね」
この日の彼女は一日中何か考え込んでいるようだった。でもギャラリーを出て僕が彼女にカフェラテを買ってやった時にはもうあの無邪気で屈託のない笑顔を浮かべていたし、彼女はいつも通りだった。
夏も終わりに向かっていた、よく晴れた木曜日、彼女はいつものジャズ喫茶に現れなかった。こんなことははじめてだった。僕は好きでもないエラのジャズを聴きながら夕方まで彼女を待った。僕は不安といらいらで、彼女が嫌いだからと数ヶ月前に辞めたタバコを2本吸ってしまった。

日の沈む時間になると僕は川沿いの橋に移動した。ここで彼女と夕日を見なかったのは夏の間の木曜日に2度あった雨の日だけだ。今日はこんなにも晴れている。
けれども彼女は見に来なかった。この日はすごく透き通った空で、日が沈んだ後には彼女が好きそうな薄いピンクとブルーが空いっぱいに埋め尽くされていた。

そういえば僕は彼女の連絡先も知らなければ住んでいる街も分からない。でも僕たちには今までそんなものは必要ないくらいお互いの事をよく分かっていたし、お互いを裏切った事なんて一度も無かった。
来週も、再来週も彼女は現れなかった。
そしてそれは僕だけではなくて、あの夏何となく出来上がったグループのみんなも最近は彼女を見ていないみたいだった。
最初は現れない彼女に僕は腹を立てていたが、次第に僕の記憶から彼女がだんだんと曖昧な存在になっていったのを感じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
