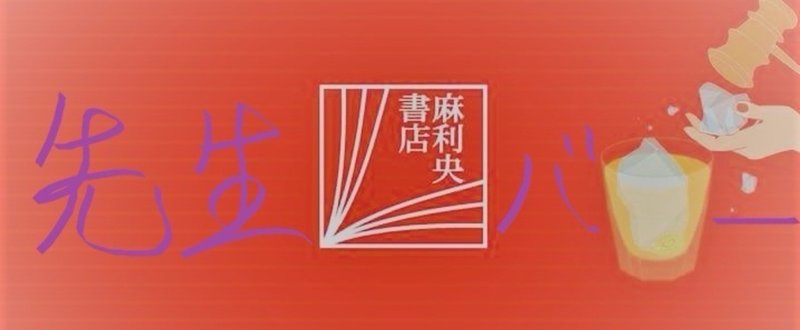
先生バー③(終)
先生バー①
先生バー②
それはベストに着いた光るバッチだった。男は海外に長いこといたが、それが何かは知っていた。弁護士バッチだ。ただ、このバーテンダーは少しインチキくさいと感じていたので、本物かどうか疑ってもいた。
「あなたは弁護士なんですか」
「あ、気付きました?だけどこれはもう何の価値もありませんよ。過去の勲章とでも言いましょうか。私、本橋と言います」と胸元のバッチを見たあと、そう自己紹介した。
「セージです」バーテンダーが名前を言ったので、男も返した。
「セージ、さん」本橋は曖昧に繰り返した。
「…あ、セイジって言うのは名前で、名字は…加賀です」
海外にいると名字よりも名前をよく使う。欧米人にとって『カガ』は認識しにくいようだったし、あるアーティストとごっちゃにされてしまうことが多かったので、積極的に『誠二』と名乗っていたのだ。しかし自ら名乗ったことが少し恥ずかしくなった加賀は誤魔化すために
「弁護士、もう辞めたんですか?」と聞いた。
すると、待ってましたとばかりに本橋は語り出した。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
まぁ、そのかつては弁護士でした。このバッチ、もらいものじゃないですからね。僕が小さい頃、母親がいつもDVDでドラマを見ていましてねぇ、2000年代にブームだったHEROっていうドラマです。それに影響されて、弁護士になりたいなぁと小学生の頃から思っていました。
でもね、中学生の時にHEROの新シーズンが始まって気づいたんです。って、検事の話だったんですよ、検事!どっちかと言うと弁護士のライバル。幼かったんでよく分かっていなかったんですねぇ。まぁでも、そのまま弁護士を目指しました。だって弁護士になれば、将来は安泰、そう考えられている職業でしたから。運良く浪人せずに志望大学の法学部に入って、法科大学院に行って、司法試験もストレートで合格、勧められた弁護士事務所で働き出しました。はい、まさに順風満帆。もう何年も司法試験落ち続けている仲間、たくさんいましたから。
でもね、実際はドラマのネタになるような刑事事件はほとんどありません。離婚、相続、借金・破産という自分の人生においては関わりたくない事例と毎日のように向き合っていました。
でもね、これだけは言わせてください。間違ってはいたんですけど、昔見たそのドラマの主人公、えっと、あぁ演じていたのは木村拓哉です、あ、お客さん知らないかな?あ、知ってます?その人柄というか仕事への姿勢っていうのはすごく印象に残っていましてね。納得いくまで調べ上げる、事件の大小に関係なく取り組む姿は僕もモットーにしていたんです。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
と、少し胸を張って言ったかと思うと、本橋は急に顎に手を当てて、考え事を始めたのか黙った。次の言葉をハイボールとチェイサーをゆっくり交互に飲みながら加賀は待った。
「くりゅー!!」本橋は叫んだ。
「くりゅう?」
「くりゅうです、久利生!その木村拓哉が演じている検事は、久利生って名前なんですよ。」とスッキリした表情で再び語り出した。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
久利生検事はね、その破天荒な行動から最初は煙たがられちゃうんですけど、仕事に対する熱意を次第に同僚が認めて、信頼され始めるんです。僕もそんなモットーを貫く弁護士になろうと一生懸命事件と向き合ったんです。そしたらね、噂が噂を呼んで、事務所に僕宛の仕事の依頼が増えまして。まだキャリアは浅かったんですけど、独立することにしました。新しく事務所を立ち上げてからも、「本橋先生だけが頼りです」と過去の依頼者やその紹介を受けた方が僕を頼って訪ねてきてくれる。嬉しかったですねぇ。
忙しいながらも事件の大小問わず取り組んでいましたが、どうしても大きい事件に割かれる時間が多くなるでしょう。ある時、小さめの案件を処理するのをすっかり忘れちゃいましてね、それがクレームに繋がってしまいました。依頼人が必要以上に騒ぎ立てましてね、すぐに熱は冷めるだろうから大丈夫だと思って、一旦事務所を休むことにしました。
忙しい毎日だったので、旅行したり、体を動かしたり、仕事から少し離れました。そろそろ仕事を再開しようと思ったとき、友人から連絡があったんです。「お前ヤバいぞ」って。ネットを見てみろって言うから僕の事務所のホームページを開いてみたら、そこにはあることないこと、ものすごい量の誹謗中傷の書き込みがされていたんです。僕個人の批判もありました。「インチキくさい」とか「メガネが気に入らない」とか、ほっとけって感じですよね。それを見ていたら、すべてが面倒くさくなって、戦う気も失せちゃって。
その時です。ある人物がコンタクトを取ってきたのは。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
本橋はここからが本番だと言わんばかりにニヤっと笑いながら、人差し指を立てて「1」作り、加賀の顔の前に突き出した。その手をゆっくりと自分の目に持って行って
「このコンタクトじゃあ、ないですよ、ハッハー!」
とくだらないダジャレを言い放った。加賀は肩の力が抜けて、少し話を聞く気が失せた。そんな加賀の様子に気付かない本橋は話を続けた。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
ま、冗談はこのくらいにして、その人物は国、つまり政府の人間でしてね、裁判に「あるシステム」を導入する話が進んでいるので協力しないかと言われました。人が人を裁くのはリスクが大きい、大きく法律は変わっていないのだから、過去の事例をデータベースに落とし込んで、コンピュータで裁判を行えるようにしたい、どうしても発生してしまう誤審を無くしたい、とそんな話でしたね。弁護士や検事、裁判官の考えや経験によって左右されることのない平等な裁判を行うために必要なんだと言っていました。
実際、死刑については今も執行を容認する派と反対派と議論が絶えません。
加えて、2009年から実施されていた裁判員制度も問題が多くありました。三十年前くらいに残忍な事件の裁判員をされた方がストレス障害を起こし、今も苦しんでいると聞いたことがあります。
そんな話を聞いて、確かに人が人を裁くこと自体が無理なのかもしれない、とも思い始めましてね。だから、その裁判のシステム導入に協力することにしたんですよ。それに弁護士としての立場は守ると言っていましたから。
指定の日に、指定の場所に行ったら、周りが全く見えないバスに乗せられてある施設へ連れて行かれましてね、そこには知り合いの弁護士や、テレビにも出ている有名な弁護士も乗っていました。政府の人間は、協力を要請してきた時の丁重な姿勢と打って変わって、急に上からものを言うようになりました。
弁護士なんて今の時代には必要のない仕事だとか、「先生」と呼ばれ、頼りにされていい気になってたんじゃないかとか、そんなことでしたね。改めて周りを見回してみると、最近大なり小なり裁判で負けていたり、依頼者とトラブルを起こしたりした弁護士が集められていると気付きました。
僕たちがやらされたのは、自分の携わった判例全てをデータベースに落とし込む作業です。僕は弁護士になってそこまで長くありませんが、それでもかなりの量でした。最初は依頼人のことなんかも思い出しながらやってましたけど、それすら面倒になってきましてね。それに慣れない環境で疲れも出て、置かれている状況に反抗する気力もなく、ひたすら作業に没頭していました。
1ヶ月ほどで解放され、十分すぎる謝礼を渡されましたが、僕はもう弁護士ではありませんでした。それから1年ほどして裁判に無人システムが導入されたことがニュースになりました。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
加賀は何も飲まずに話をじっと聞いていた。話が一旦ブレイクすると喉の渇きを覚えてチェイサーを一気飲みした。そして、こう聞いた。
「じゃあ……今は、裁判はコンピュータが行っているんですか」
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
そうですよ。弁護士なんて職業はなくなりましたし、今も裁判は何の問題もなく行われています、表向きにはね。学校も、病院も、裁判も、もしかしたら、政治もすでにコンピュータが行っているのかもしれません。
僕はね、日本の組織が「先生」っていう立場の人間を全部排除しようとしていると思うんです。先生はかつて聖職とされて、崇められた。でもね、教師だって、医者だって、弁護士だって、人間だから過ちを犯すでしょ。でも許されない社会になってしまったんですよ。だからね、無くしてしまったら早いと考えたんじゃないかなって。テクノロジーが進歩したのをいいことにね。
普通、コンピュータの中枢はマザーと呼ばれます、つまり「母」って意味ですよね。だけどね、日本はそれを「センセイ」って呼んでいるらしいですよ。先生は一つ、いや一人と言っていいのかな、それだけでいいってことですね。
今はこうやってバーで働いていますけど、実は僕、漫画家になりたいんです。昔から漫画オタクでね、ドラえもんが好きです。あ、知っています?海外でも流行っていると聞いたことがあります。さすがだなぁ。
僕はドラえもんの道具がいつか出来ると信じていました。昔ドローンってあったんですけどね、遠隔操作できる小さい飛行機みたいなのです。それを見たときタケコプターはもう少しで出来るぞ!と子供ながらに喜びましたが、今も出来ていません。あんなに素敵な道具は一向に出来ないのに、世の中はコンピュータやロボットが支配する味気ない時代になってしまいました。せめて、今の子供たちが目を輝かせて未来を想像できる漫画が描けたら、とこっそり書き溜めているんです。
✽ ✽ ✽ ✽ ✽
「今度、読ませてくださいよ」加賀は思わず言っていた。
「僕の漫画なんて、まだお見せできないですよ、OKが出ないと」本橋は探るような表情で加賀の後ろに視線をやった。
加賀が後ろを振り返ると、くたびれたジャケットを着た男がチラッとこちらを見て、すぐに視線を手元に戻した。男は何か書いている最中のようだった。
「あの人に、描き方、教えてもらってるんです」小声で本橋は言った。
「描き方?」
「はい、漫画家なんです」
「漫画家?」
「はい、そして、ここのオーナーです」
「オーナー?」
「僕たちみたいな不要になった先生を雇ってくれています」
「先生を?」
加賀の反応に満足そうな本橋は、男の様子を窺ってから、大きな声で男に話しかけた。
「僕、いつになったら漫画見せてもいいですか、先生!」
男はペンを置き、すっと立ち上がり言った。
「先生なんて呼ぶなっつってんだろ!このボケ!!」
「す、すいません」
「先生っつうのはな、一時だけ、指導や治療してくれるだけ、弁護してくれるだけの存在じゃねえんだよ。手当たり次第に先生なんて呼ぶから皆勘違いして日本はこの有様になったんだ。お前もよく分かってるだろ。本物の先生っつーのはな、この人なら魂を捧げてもいいと、人生をかけてついていきたいと、そう思える存在なんだよ。先生は自分の心に一人でもいりゃ十分なんだよ、分かったか!」
その言葉を聞きながら、自分の先生は誰なんだろうと加賀は考えていた。父親のような気もするが、ピタッと当てはまるわけでもない。もしかしたらまだ本物の先生には出会ってないのかもしれない。
ふと本橋を見ると、すっかり小さくなってしまっていて、男は何事もなかったようにまた机に向かって書いていた。居心地の悪くなった加賀はお暇しようと立ち上がって、代金をテーブルに置いた。
「怒鳴ってすいませんでしたね。これに懲りずにまた、お越しください」
男はそう言って軽く頭を下げた。
「もちろんです。いつも興味深い話聞かせて頂き、ありがとうございます」
と頭を下げると、机の上にある紙が加賀の目に飛び込んできた。
そこにはあの見慣れたネコ型ロボットのネームが描かれていた。
~完~
クリエイトすることを続けていくための寄付をお願いします。 投げ銭でも具体的な応援でも、どんな定義でも構いません。 それさえあれば、わたしはクリエイターとして生きていけると思います!
