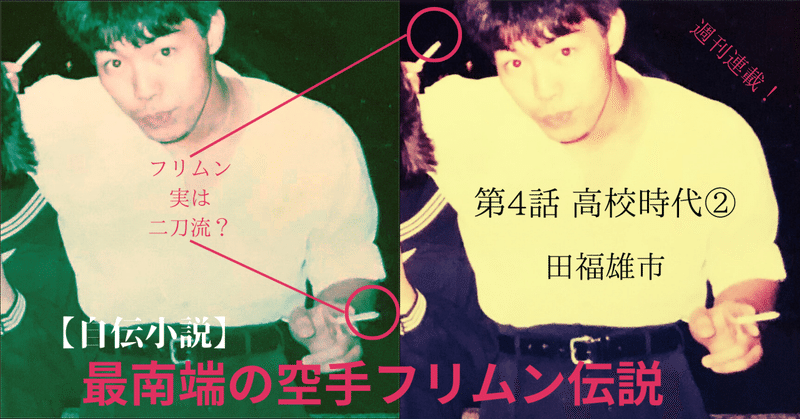
【自伝小説】第4話 高校編(2)|最南端の空手フリムン伝説|著:田福雄市@石垣島
ケンカ空手
部活を辞め、町道場に通う決意をした少年。
退部した後も、顧問の先生から執拗に戻るよう説得されるも、意固地な少年の心が揺らぐことはなかった。
これが少年の良いところでもあり、悪いところでもあった。
しかし、この一本気な性格のお陰で、俗に言うミラクルを何度も引き起こすのだから、それはそれで良かったのだろう。
ただ、それもまだまだ先の話しである。
それから暫くして、知人の紹介で極真有段者のN先生が指導を務める道場の門を叩く事となったが、ここでも少年の実力は頭一つ抜きん出ていた。
組手の強さはもちろん、フィジカル面やメンタル面でも他の道場生とは一線を画した。
あの中学時代のバカげた功夫の猛特訓は、決して無駄ではなかったのだ。
最初から拳立て100回なんてお茶の子さいさい。
やれと言われれば、スクワット100×10セットでさえ最後までやり切った。
それくらい、とにかく少年は負ける事が大嫌いであった。
例えそれが空手に関係ないことでも、勝負ごとになれば歯を食いしばれた。
そしてこのN道場での経験が、彼の過剰なまでの自信に更に拍車をかける事となる。
そんな入門から2ヵ月ほど経ったある日、何の前触れもなくある男が道場を訪れた。
小柄だが、ガタイの良い、見るからに強そうな20代前半の男であった。
当時、県内初の直接打撃制空手団体として名を馳せていた、ある流派の県大会(軽量級)で準優勝したばかりだという。
もちろん、大会は流派を問わないオープントーナメンントである。
国際空手道連盟「極真会館」が、正式に沖縄進出する遥か以前の事である。
筋骨隆々の肉体を誇示しながら、空手着に着替える男を一瞥した少年は、動物的本能により嫌な予感を感じ取っていた。
今日は絶対に何かが起こる…背筋にゾクッと悪寒が走った。
果たして、稽古は始まった。
基本稽古、移動稽古、補強などを一通り終え、最後は組手で締めるのがこの道場の慣わしであった。
そして、いよいよ組手の時間となった。
ちなみに当時はサポーター等という高価なものはなく、道場では素手素足が当たり前。組手も常にガチンコの真剣勝負であった。
稽古が始まってから、ずっと少年の動きを追い続けていた男の“お眼鏡”にかない、思っていた通り「組手」の指名を受けた少年。
そう、今晩の「ディナー」として選ばれたのだ。
嫌な予感は…的中した。
ただ、道場生の中では実力No.1で通っていた少年にとって、これは願ってもないチャンスでもあった。
「この世界で、今どれくらいの位置にいるのか知りたい…」
直接打撃制の大会が無かった当時、道場での組手しか経験のなかった少年は、自分の腕を試したくてウズウズしていた。
そんな昂ぶる気持ちを抑えきれず、そして溢れ出る恐怖心を振り払うかのように、スタミナ配分などお構いなしに最初から突っ掛かって行った。
しかし、流石は県大会準優勝者。自力では少年の遥か上を行っていた。
このままでは確実に叩き伏せられる。
そう思った少年は真っ向勝負を嫌い、サバキ(相手の攻撃を受け流す)を駆使しながら得意技を仕掛けてみた。
道場では、“ほぼほぼ”の確率で決まっていた得意技、足掛け下段突きである。
注:「足掛け下段突き」とは、回し蹴りを放ってきた相手の軸足をローキックで刈り、ひっくり返った相手に残心(寸止めの突き)を決めるかなりの高等技術である。
それはどちらかと言えば、肉体よりも精神的にダメージを与える技で、綺麗に決まれば「犬神家の一族」のような恥ずかしいポーズを余儀なくされる事もある。

よって少年の中では、「できるだけ貰いたくない技」の上位に食い込んでいた。
しかし、それから38年後の全日本大会決勝戦のことである。
思いっきりその技を掛けられ、私はその決定的瞬間を全国紙のフルコンタクトKARATEマガジンに載せられちゃった事がある。

誰一人として知る由もなかった。
そんな技を、初めて手合わせする大先輩にドンピシャで決めて見せた少年。
「ドスンッ」という音と同時に、尻もちをつきながら男は照れ笑いを浮かべた。
それを見た少年は、心の中で思わずガッツポーズ。
しかし、立ち上がる頃には男の顔からスッカリ笑みは消え、サメのような感情の無い冷たい目となっていた。
そして赤っ恥を欠かされた男は、汚名を返上しようと間髪入れずにラッシュを仕掛けてきた。
「ドスッ!ドスッ!ドギャッ!」
ギアを一段上げ、猛攻を仕掛ける男に、少年は防戦一方となりイッキに壁まで追い込まれた。
「つ、強ぇぇぇぇぇぇぇええええ!」
やられながらも心の中で感心していたが、応戦する余力はまだ十分に残っていた。このままでは倒されると思った少年は、直ぐさま反撃に打って出た。
二人とも、もう完全に後に引けないところまで来ていた。
その一部始終を見ていた他の道場生たちは、ゴクリと唾を飲み込み、二人の真剣勝負に釘付けとなった。
その光景は、まさにケンカ空手のそれであった。
ちなみに当時の極真のイメージは、「ケンカ空手」や「ぶち壊しの空手」等、悪い印象を与えるものばかりであった。
それもそのはず、余りにも脚光を浴び続ける極真に対し、他流派や他格闘技団体が吹聴した負のイメージが浸透した結果であった。
しかし、その戦略は功を奏さなかった。
何故なら、こういうヤンチャなイメージにこそ、若者は食い付いてくるからだ。
極真が世界中の若者を虜にした要因のひとつに、このケンカ空手というキャッチフレーズがあった。そして、少年もまんまとその虜になった一人である。
閑話休題……話しを戻そう。
そんなドン引きするようなバッチバチの打ち合いの中、男が突如少年の首に腕を回し、躊躇なくある技を仕掛けてきた。
なんと空手の技ではなく、柔道の技…「首投げ」であった。

少年は完全に「虚」を突かれた。
ちなみに道場の床はコンクリートの上に絨毯を敷いただけで、畳やジョイントマットのようにショックを吸収するような代物ではなかった。
そんな硬い床の上に、男は全体重を乗せたまま少年を背中から叩き落とした。
「…ガハッ…ウグッ…」
完全に息が止まり、陸に打ち上げられた魚の如く、少年は口をパクパクさせながら呼吸が戻るのをひたすらに待った。
その光景を、男は鬼の形相で見下ろしていたが、ハッと我に返り、慌てて少年の手を取り優しく引き起こしてくれた。
「君…強いね…」
気が張り詰め、静寂が続いていた道場内に少しだけざわめきが戻った。
そして誰からともなく、自然と拍手が沸き起こった。
大きな溜息交じりの拍手が。
ーーー
この記事を書いた人

田福雄市(空手家)
1966年、石垣市平久保生まれ、平得育ち。
八重山高校卒業後、本格的に空手人生を歩みはじめる。
長年に渡り、空手関連の活動を中心に地域社会に貢献。
パワーリフティングの分野でも沖縄県優勝をはじめ、
競技者として多数の入賞経験を持つ。
青少年健全育成のボランティア活動等を通して石垣市、社会福祉協議会、警察署、薬物乱用防止協会などからの受賞歴多数。
八重山郡優秀指導者賞、極真会館沖縄県支部優秀選手賞も受賞。
ーーー
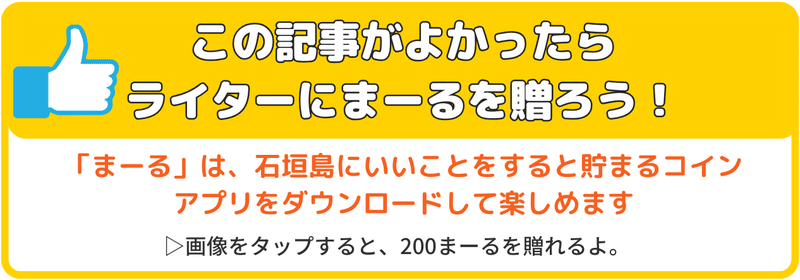
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
