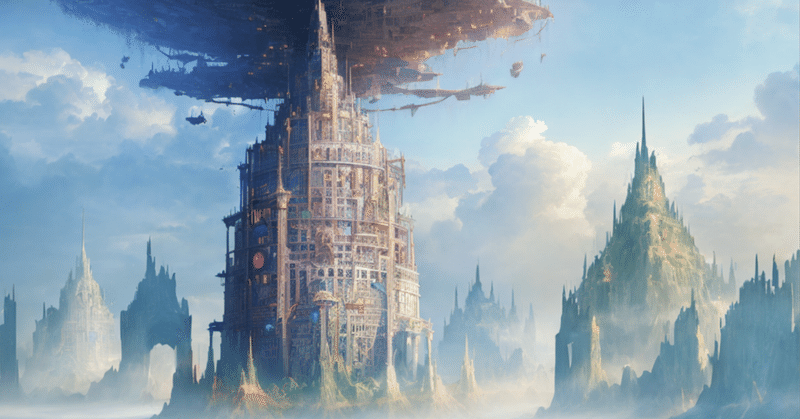
日本の生産性が低い理由
なぜ、生産性向上を目指さなければならないのか?
そもそもなぜ、生産性向上をしなければならなかったのでしょうか?大きく分けて2つあるとされています。
労働人口の減少
国際的な競争力の低下
国全体の問題として、誰もが取り組まなければならないという認識だと思います。
労働人口の減少は2025年から急速になり、2030年をすぎると、働いていない人のほうが多くなってしまいます。
そして、日本は先進国の中でも労働生産性が低く、働く人達が減って、生産性が低い状態だと、より働く人たちがいなくなってしまうということが懸念されているのです。
生産性向上には2種類ある
生産性の向上は以下の2つがあります。
物的労働生産性
付加価値労働生産性
物的労働生産性は、より多くのものを作れるようになったり、より大きなものを作れるようになったり、より小さなものを作れるようになったりと、物に関する生産性アップです。これは、人が作っていたものを機械で作るようになるだけで十分生産性がアップします。新しい機械を導入するだけで解決してしまうのです。特に製造業では、こちらの生産性向上は昔からやっています。
付加価値労働生産性は、同じものでも、利益をより多くのせて販売することによって得られます。付加価値の正体は利益です。付加価値生産性を上げるには、利益率を向上させれば上がります。利益率の低い商品をやめ、高い商品のみに絞っていくだけでも生産性は向上します。
どちらの生産性も、すでにやっている企業はありますし、今更ということもあるでしょう。その2つの生産性をアップできないのは、構造的な問題があるのです。
生産性をアップできない構造的な問題
一番大きな問題は、取引先です。
特に、下請けで仕事をしているところは、コントロールが出来ません。
100%下請けで、取引先に完全にコントロールされてしまっている会社では、取引先の意向が全てになってしまいます。
数量を増やしたとしても、単価を下げられます。機械の導入には、資金が必要です。その資金を出してくれればいいですが、基本的には出しません。
付加価値をつけようものなら、価格交渉で値段を下げられます。下請け企業のことを生かさず殺さずというところでコントロールしています。
そして、下請け構造は日本にはかなりはびこっています。この構造を変えない限り、国際競争力など生まれません。大企業ばかりがより生産性が高まり、下請けの中小零細企業はずっと大企業の奴隷として働かざるを得ないのです。
値上げ転嫁出来ない企業は生き残れない
原材料費の高騰などもあり、利益率は圧迫され続けています。そうした中で、利益を確保できるよう、値上げ交渉によって価格に転嫁出来なければ、もはや生き残ることは出来ません。
日本はインフレに突入しているので、社員の給与も上げる必要があります。
下請構造では、このあたりが上手く交渉できるかどうかにかかってきます。
相手方も理解を示してくれればいいのですが、
「出来ないなら、他に頼みます」
と言われてしまうと、なかなか言い出せません。
独自の技術やサービスを提供しているのであれば、そうしたことも無いとは思いますが、世の中に同じ品質のものを作れるところや販売できるところがいくつも存在する場合、競争力はなく、言われるがままになってしまうのです。
もっと本質的価値をあげる努力
日本のこうした状況の中で、生産性を上げるにはもっと違ったアプローチが必要です。どうしても、より多く作れるようになるとか、より早く作れるようになる。
より高く売れるようになるといったことにフォーカスしがちですが、本質的な解決にはなりません。
本質的な問題は、顧客との関係性にあるため、その関係性を変える必要があるのです。
顧客との関係性を変えるというのは、下請けから脱却するということです。
そのために必要なことは、マーケティングとブランディングです。
企業の本質的価値を高めていく努力がなければ、いずれ淘汰されてしまいます。
宜しければ、サポートお願いいたします。サポートは、私の原動力です!
