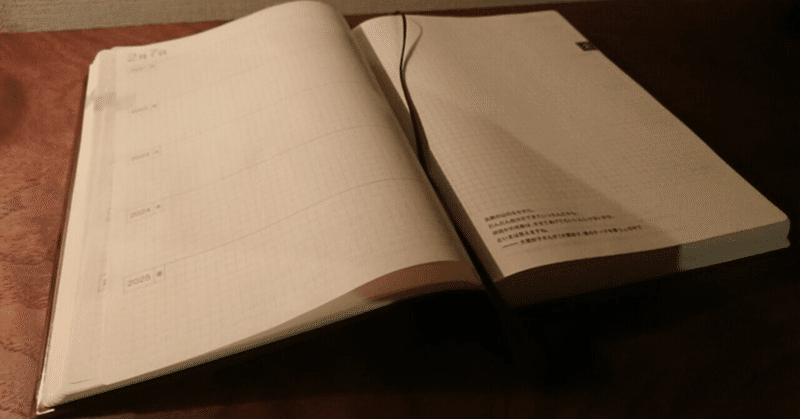
エッセイ/三人三様
太宰のなにか好きかといえば、おそろしいほど文章が巧いところである。反論も多々あろうが、私は巧いと思う。つまり、舌を巻くほど巧いのだ。それだけである。『晩年』や『廿世紀旗手』の一歩目から息切れた篆刻のようなアフォリズムから、あるとき、なぜだろうか、短中距離走の神髄を体得する。戦後の『人間失格』も『斜陽』も、喧伝のわりにはとんだ駄作であるが、もう、それで構わない。そこまでに残したものは、どれも最高水準の巧さなのだ。どれも短篇だが、『佳日』『散華』『眉山』、忘れてはならない『津軽』『トカトントン』、小学校から数えて何百回読んだか、それでもまた、あの呼吸を、ふと味わいたくなる。
安吾は太宰や織田作と並べられるが、同世代のご愛嬌である。太宰は炬火、織田作は蝋燭、安吾は原子炉だ。いずれも fragile で vulnerable ではあるが、それは決して、同類を意味しない。安吾は、泣きながら情に訴えなどしない。本気を出せば、小林秀雄を議論でコテンパンに伸すことができた同世代の作家は、安吾以外にはいまい。但し、太宰の比ではないほど、安吾は迷走に迷走を重ねる(詳細は Wiki 参照)。アドルムヒロポンから国税庁攻撃から競輪不正告訴のコンボ時代は、同時代の筋だった作品がなければ、ただの廃人だ。『いずこへ』『イノチガケ』『日本文化私観』『肝臓先生』、いいですよ。
漱石は、彼らとは少し違う。私にとって、夏目先生は、何を措いても、英語学畑の偉大な先達なのであり、二十三歳で英訳した『方丈記』には、三十歳の私が嘔吐しそうになるほど、驚愕した。小説はもちろん拙くはないが、世の評判ほど巧いとは思わない。当たり前だ。漱石鴎外紅葉露伴から、売れそうな上澄みを掠めとった巧さのエキスが、いまの『小説』の原型なのだから。私的に、その文章の匂いがとても好きではあるが、たとえば『草枕』を寝ころんで楽しみ、『門』を新聞で毎朝読む庶民を持つ文化水準を、私は到底想像できないので、それはもう、カルチャーギャップとしか言いようがない。本音では、『吾輩は猫である』だけでも、私は漱石をここに容れるのだ。令和人が(不要不急の)教養を愛するとは、この小説を愛おしく思えることかもしれない。これを認めない者は、何しろオタンチン・パレオロガスである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
