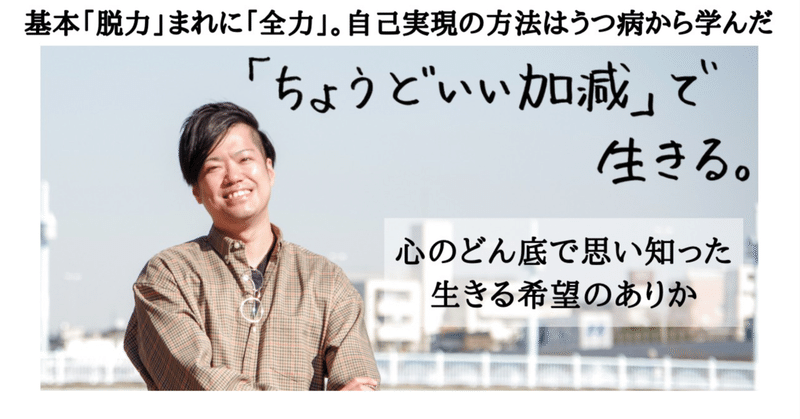
心のどん底で思い知った生きる希望のありか|連載『「ちょうどいい加減」で生きる。』うつ病体験記
本文中に、うつの症状や自死に関する記述があります。そうした内容により、精神的なストレスを感じられる方がいらっしゃる可能性もありますので、ご無理のない範囲でお読みいただくよう宜しくお願い致します。
「死にたい……」
私が初めてそう願ったのがいつだったかは、もはや正確には覚えていません。いまの社会には残念ながら「死にたい」があふれています。原因は多様です。地獄のような人間関係のしがらみや激しい病苦から逃れたくて「死にたい」とつぶやく人もいます。あるいは漠然とした虚無感を抱きながら、静かに、しんしんと、ただ静かに「死にたい」と語る人もいます。
「死にたい」の真意はどこにあるか
「いかに生きるか」ということと「いかに死んでいくか」ということは表裏一体です。死は、生の裏返しでもある。決して遠い存在ではありません。
心理的な距離として、死が「近い」人がいます。死に親しみを抱いている人さえいます。重く、痛く、暗い闇のなかで、ただ一つの光明も見いだせずに独りうずくまっている。声を発しても自分の声がこだまするだけ。何の反応もない。そんな孤独に押しつぶされるようにして、人は死を選びます。
自殺願望の一言にふくまれるメッセージも、多様です。たとえば「本気で自殺をしようと考えていて、自殺の準備も完了しているよ」という状態の人が「死にたい」の一言を発する場合もあります。または、「死にたいほどのこの思いを、誰かに聞いてほしい……」という悲鳴のメッセージがこめられているケースもあります。
「死にたい」という一語をつぶやく人は、このように、さまざまな状況のなかにいます。ただし、共通項もあります。「死にたい」というメッセージは、必ず「死にたいくらいつらい」ということを意味するのです。そのつらさを少しでもやわらげることができれば、「死にたい」は「ほんとうは生きたい」に変わります。その「ほんとう」が表現として相手からでてくるまで、ぜひサポートする人は耳を傾けてみてください。
自殺未遂者が目覚めたときに発する第一声とは
精神科医の大原健士郎氏は、自殺に失敗して病院に救急搬送されてきた人を大勢みてきました。彼らがベッドの上で目を覚ましたときに、どんな第一声を発するか。みなさんはおわかりになりますでしょうか。大抵の人はこう聞かれると「『ああ、(死ななかったのか、)生きてて良かった』と言うのではないですか」と答えるそうです。ですが、大原氏は「まったく違う」と言います。自殺未遂者がつぶやく第一声はほぼすべてが
「助けて!」
なのだそうです(本当に、ほぼ全員がそう言うそうです!)。彼・彼女らのように「死にたい」と願う人は、同時に「助けてほしい人」でもある。この現実が、彼らのうめき、叫びからうかがい知れます。「死にたい」が「ほんとうは生きたい」である可能性は相当に高い。自殺を願う人は、切迫感をもって助かりたいと願っているのです。何から助かりたいかといえば、多くは「悲しみ」だったり「苦しみ」だったりする。だから、苦衷から"助かる"ために自死を選ぶ人もいます。誰かにSOSを発する人もいます。
この実際を知ったうえで、あなたがもし「死にたい」と言われたら、どうサポートしますか? この問いは、じつは学問的な幸福論の探究における究極のテーマの一つでもあります。ぜひ、熟考してみてください。
死を思いとどまる契機になったあの"大事故"
私の話に戻りますが、私も「死にたい」「死にたい」と言いつづけました。死ねば、地獄のような病苦から解放される。生きることが苦しくて、生きていることに意味も見いだせない。それなら、死んだ方がマシだと私は常々考えるようになっていました。「希死念慮(きしねんりょ)」と呼ばれる願望です。
桜もすっかり散った季節、新緑が芽吹くかなり温かいある日でした。私は、自殺未遂をしました。かなり思い切った自殺の方法をとったため、生々しいこともあり、ここには書けないのですが、自殺自体はたぶん衝動的なものだったと思います。しかし、私はそこで死に損ないます。一度は意識を失いますが、目が覚めたのです。その瞬間、視界に「ある光景」が飛び込んできて、私は思わず死への道を歩むのをやめました。
視線をテレビに向けると(つけた記憶はなかったのですが……)、何か、大事故が起きたようだということがわかりました。音声が騒がしく、乱れています。たくさんの消防車や救急車、警察車両が、マンションや電車のようなものの周辺に集まっている。そこにカットイン。被害者? の母親とおぼしき人がインタビューされるシーンがでてきます。
「うちの子が、まだなかにいるんです。どうか、生きていて! 誰か、助けてください! どうしてうちの子が!」
私はドキッとしました。そして、われに返った瞬間に、ホッともしました。自分が生きていることにホッとしたのです。同時にそんな自分に驚きました。「俺は、死にたかったんじゃなかったのか?」と。しかし、テレビ画面に入れ代わり立ち代わり流れる事故被害者の関係者に対するインタビューを見るたびに、死ぬ気は失(う)せていきました。
この事故は、2005年4月25日に起きた、あの「JR福知山線脱線事故」でした。JR発足後では史上最悪となる死傷者を出した大事故です。私はたまたまその日に自殺を図り、そして同事故をテレビ越しに目撃して自死を思いとどまったのでした。
生きる希望はどこにあるか
生きる希望を見失った人にとって、お金や物は役に立ちません。どんなものを与えられても、喜びの感情はピクリともわいてこないのです。ほんとうに疎外されたと感じてしまった人には、なぐさめや同情や説教も役に立ちません。まして、説得や納得が役に立つとも思えません。
苦しみを吐きだしたときに「みんな同じようにつらいんだよ」とか「たとえば貧困国で難民生活をしている人に比べたら恵まれてるよ」といった理性的な言葉や、「死にたいなんて言わないで!」といった直球の言葉が返ってくると、相談者は時にその言葉に虚しさを感じて、倦怠感に襲われます。「じゃあ、そんななかでも特段、落ち込んでいる私は相当な『できそこない』なんだ」と思って自己卑下のループに陥るかもしれません。あるいは相手から「つき放された」と感じて、いっそう孤独感を強めるでしょう。「ああ、この人は私の気持ちなんかわかってくれないんだ」と。
ほんとうに疎外されてしまった人がほんとうに求めているのは、「自分は必要とされている、存在を受け入れられていると感じさせるもの・こと」です。希死念慮を持つ人をサポートする上で大切なのは「あなたにいてほしい」といったかたちで関心をその人に向けつづけることです。「これは私のエゴだけどさ、あなたがいなくなると私は悲しくてたまらないんだよ」という言葉を添えても良いと思います。とにかく「あなたに生きていてほしい」と伝えること。それは、言語表現でなくても良い場合が多々あります。ただそばにいて耳を澄ましてくれるだけでも、良いのです。関心や必要のベクトルが自分に向いていると知ったとき、人は、また死のうとする人は、顔を上げることができます。生きる希望の種は、そんな感じの、「あなたが大切だ」「あなたにいてほしい」という思いに植わっています。
これは不謹慎かもしれませんが、私は福知山脱線事故のインタビューから伝わってくる「あの子の生が必要だ!」というメッセージに感化され、それを自分に置き換えて、「もしかしたら、"かの人"なら自分の生を欲してくれているかもしれない」と想像し、すがることのできる希望を見たのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
