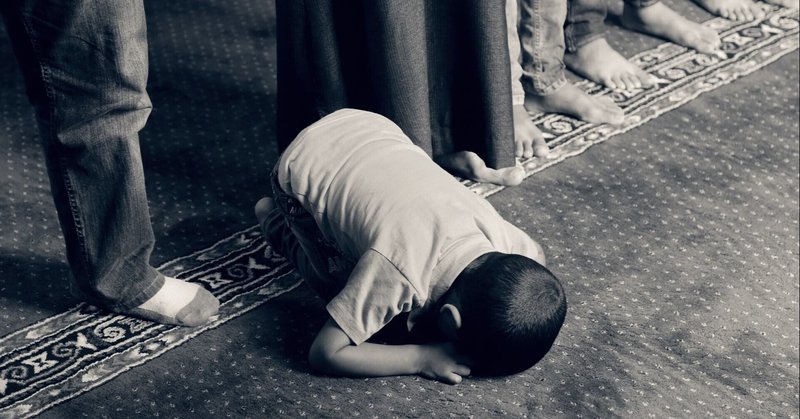
[書評]組織はなぜ活力を失っていくのか。宗教から読み解く。
高橋和巳の書をひさびさにひもときました。何の本を読んだかというと、彼の代表作『邪宗門』です。本書は、「ひのもと求霊会」という「大本教」をモデルにした宗教団体が、戦前・戦後にかけて衰退・破滅していくさまを描いています。共同体が解体していくとき、その構成員(信者)はどのように振る舞うのか。それを、これほどつまびらかにつづった作品を、私は他に知りません。
高橋和巳『邪宗門』のあらすじ
物語は二代目棟梁たる行徳仁二郎の時代から始まります。教団は「治安維持法」により、軍部権力から二度の弾圧をこうむります。教団本部は爆破・解体。仁二郎も同法違反、また不敬罪の容疑で投獄されます。その後、幹部会議は「三代」をどうするかという話題に。圧倒的カリスマだった初代・二代。それに比肩する人材がいないなか、どうやって信者を導いていくのか――。
結局、波打ち際の砂山のように、教団は徐々に崩壊していきます。
今回は、本書を組織論的に読み解きました。「ひのもと求霊会」はなぜ崩れたのか。その理由を箇条書きにして以下に記します。
宗教組織が衰退する要因
■① 初代棟梁と第二代の志向・指導性が微妙に食い違っていた。その食い違いが教団内の派閥争いを拡張させてしまう(それぞれの派閥が初代・二代の指導を持ち出して自己正当化を図った)。教団幹部が指導の体系化に着手するも、遅きに失した。
■② 初代の予言が、教団にやってくるであろう出来事すべての指針になるわけではない。初代・二代の指導に照らすことのできない新しい時代の新しい事態に教団が対応するには、新たな仕方が必要。その際に、どうするかについて意見の対立が生まれ、それが感情の対立に発展する。最終的には、古い指導性に固執する老年世代(仁二郎とともに生きた世代)が、若年層の声に耳を貸さず、教団自体が時代の変化に適応できずに終わる。
■③ 教団は、三代・千葉潔をカリスマに仕立てようとし、三代目に権力を集中させるが、カリスマを待望するメンタリティ自体が、衰退しかかった教団の再生力を奪う結果になった。「カリスマ頼り」は組織を自滅させる。
■④ 教団本部の閉鎖的で世俗と隔絶した体質が、時代性や地域性によってフレキシブルに変化すべき現場の指導性を硬直させ、信徒の「本部離れ」を助長した。変わるべきところは変わり、変わるべきでないところは変えてはいけない。そして両者の腑分けを、日常的に追求することが大事である。
■⑤ 言論や暴力による弾圧には教団は強かったが、外部から経済的基盤をおびやかされることには弱かった。「ひのもと求霊会」は国家権力に近づきすぎたために、かえって国家に警戒され、カネでゆすられ、足元をすくわれた。
■⑥ 幹部が、信仰心や良心よりも利害で人間関係を築くようになった。また世俗の息吹きを過度に教団に吹き込んだため(適度ならよいのだけれど)、教団全体が世俗化し、信心の純度が下がり、宗教的理想も次第に見失われ、教団のエネルギーが減った。
■⑦ 若者・知識人の育成に力を注がなかった。
体系的に記すと、こんなところになるでしょうか。
組織にしばられないための作法とは
宗教に限らず、地域共同体や会社、NGOなど、さまざまな集団組織の維持発展に欠かせない指針が、反面教師の形で『邪宗門』に記されています。ぜひ手に取って、ご自身で読解を試みてください。多くの発見があることでしょう。
ちなみに、別書『我が心は石にあらず』で高橋和巳は、そういった組織の衰退防止にかんするメッセージも発信しています。同書では、科学的無政府主義という奇抜な思想が提示され、主人公は組合運動に身を投じます。科学的無政府主義とは、科学の発達による労働のオートメーション化によって、労働者が、「労働」のみならず「組織」という人間の自由を奪うくびきからも解放される、という仕組みに生きる立場のことです。この信念は、いまでいうアナーキズム(=無政府主義)的な組織に適用すべきものとして、本書で紹介されています。主人公が身を投じた組織は、いわば組織内組織です。大きな組織のなかにある、チームと言っていいでしょう。
心理的安全性が高い組織が、よい組織になる
最高のパフォーマンスが発揮できる組織づくりの場で、いま「心理的安全性」が大事だと言われています。高橋和巳の『我が心は石にあらず』は、この心理的安全性を考える上で、よき“壁打ち相手”になります。驚くべきことに、Googleの実験によると、最高の組織は、「スタープレーヤーだけを集めた組織」でもなく「同じ釜の飯を食ったような仲のよい組織」でもなく、「スローガンを掲げて一致団結する組織」でもなかったというのです。
では、どんな組織がパフォーマンスを最高にするのでしょうか。
まず、心理的安全性の高い組織は、上下関係がありません(あるいは、意識されることがほとんどありません)。宗教でいえば、大幹部も現場の信者もフラットな関係にあることをさします。立場や役職は関係がない。また、その組織では、自由闊達に意見が言えて、意見が否定されることもありません。失敗をとがめられることもない。むしろ失敗は挑戦の証しとして尊重されすらします。個々人の差異や違いも大事にされて、気配りや配慮によって居心地のいい組織にもなっている、それが心理的安全性の高い組織です。加えてその組織は、「そういう組織にしていきましょう」といったルール化でなく、自然とわきだす雰囲気によって成るものです。
心理的安全性のある中間的な共同体の役割
この組織は、組織内組織、組織内のアナーキズム的組織ともいえるかもしれません。理想論だと言われるでしょうけれど、じっさいには、あなたの会社や組織、宗教にも、そういった組織内組織は、かなりの確率ですでに存在しているはずです(とても小さい組織かもしれませんが)。それこそ、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートが『〈帝国〉』で提示した「マルチチュード」――グローバリゼーションの時代にあらがうネットワークによって構成された共同体――を思わせるものの種が、すでにあるはずです。『我が心は石にあらず』はそんな共同体を先鋭化したアナーキズムの入門書としても読むことができます。
ワーク・ライフ・バランス以前の問題
同書に出てくる生真面目一本だった主人公は、ストライキとともに不倫に身を投じていきます。一人の男が信念と現実の間で揺れるさま。読んでいて胸が痛みます。怒りがわくシーンもあります。本書をとおして私が一番感じることは、革命だの何だのと大言壮語を吐いても、結局は「家庭生活」という現実を離れての思想は根無し草に等しいということでした。
ワーク・ライフ・バランスが言われるいま、革命に汗をながして家庭は置き去り、という根無し草だけにはなりたくないですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
