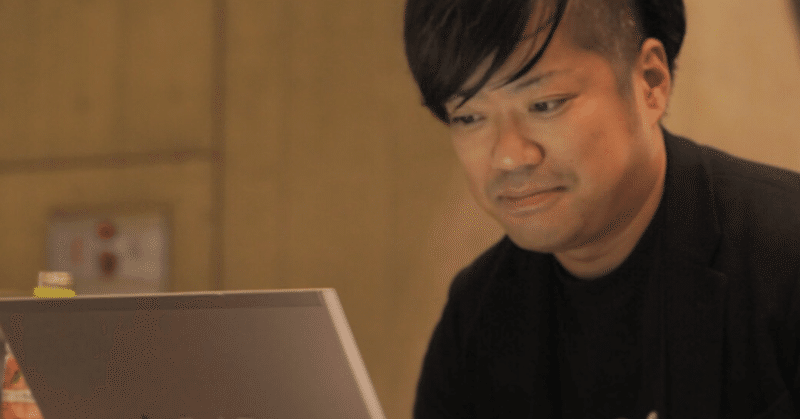
「さすが、たくさん本を読んでいる人の文章は違うなあ」について思うこと。
これ、よく言われます(だからって僕の文章が凄いって意味じゃないですよ)。でも、読書量と文章のうまさに、そこまで相関があるとは思えません。それが正直な僕の感想です。
読書量と文章力に関係はあまりない
めちゃくちゃ本を読んでいても、文章が下手くそな人は下手だし、全然本を読んでいなくても、センス抜群の文章を書く人はいます。初心者レベルにおいては、読書量によって文の巧拙もでてくるかもしれません。けれど、キラリと光る才みたいなものは、読書と関係のないところで輝いている感じがします。文才って、知識だけではなく、言語化能力とか、玉突きで比喩が連想できる感性とか、抽象概念を転がす力とか、もっと言うと人格までもが関わって決まるものだと思うのです。なので、そうやすやすと、読書のみで文筆がうまくなられては、僕が困ります。ライターの商売、あがったりです。
プロとアマより、プロとプロの差の方が大きい
かのイチロー氏が、こう言っていたのを思い出します(確か)。
「プロとアマの差より、プロとプロの差の方が大きい」(出典:拙脳)
僕は、書き手の能力を「プロ/アマ」といった感じに雑にカテゴライズするのが好きではありません。ですが、書き手が不当な扱いを受けている記事など(最近もcakesが炎上していましたね)を見ると「プロとして一家言したくなる」自分がいるので、僕は自分をプロと自認しているのだと思います。だからでしょう。「さすがプロ!」と言われると、「いえいえいえ! めっそうもございません!」と反応はしますが、心の中では野心が燃えているということは、結構あります。

FFのBGM作曲家・植松伸夫氏のように作る
僕にセンスがあるかはさておき、僕は、いろんな場で、書いて書いて書きまくって、やっとこさ「息を吸って吐くように書く」今の感覚まで来ました。現在は基本、書き始めたら一気呵成に書き終えます。推敲もほぼせず、最後まで駆け抜けてしまいます。インタビューなどは、インタビュー中に記事が脳内にできていて、PCに向かう時には「再現している」という感覚になっています。そうやって一発でざっと均してから、細かいところを修正していきます。これは、ファイナルファンタジーなどのゲームミュージックを作曲していることでも知られる、植松伸夫氏と同じらしいです。

植松氏は、たとえば町のBGMを作ってくださいと言われた際に、町のイメージ文を読みながら、読んでいるまさにその時に曲を作ってしまうそうなのです。なんか、似ている気がします(おこがましい……ちなみに、「ビッグブリッジの死闘」は植松氏的には捨て曲だったとか……)。
書きまくるといっても"打ちっ放し"にしない
ただし、書いて書いて書きまくるといっても、"打ちっ放し"には、ほぼしませんでした。必ず"壁打ち"、つまりリターンがある場で書きました。たとえば、SNSでの読み手のリアクションから編集デスクの赤字・反応まで、何かしらの手ごたえが見える場で書き、フィードバックを大事にするようにしてきました。僕はブログ黎明期からブロガーとして執筆していましたが、必ずコメント欄を公開して、読者とやりとりをするようにしていました。
書き手としての師に"壁打ち"
"己心の師"にも、不躾ながら壁打ちをさせていただきました。僕には、書き手の師が何人かいます。過去、師匠にしてきた人としては、たとえば山崎豊子氏、村上春樹氏、柳美里氏、川上未映子氏、小野不由美氏の名があがります。また、知的な方向性は違えど、レトリックにおいては内田樹氏、それから、思想信条は違えど、文章の基礎テクニックにおいては谷崎潤一郎氏、本多勝一氏を師としてきました。もちろん、実際に指導を受けているわけではないですが、自身の書いた文章を彼・彼女らに"照らして"、そして「ああ、またここが至らなかった」と恥じることを続けてきました。彼らは、僕がどうひっくり返っても生み出せないような言葉を編むのです。それに僕は驚嘆し、おこがましくも嫉妬し、その情念をエネルギーにして、彼らをマネたりしながら、言葉をつむいできました。それで、今があります。
いつか、誰かしらが興味を持ってくださるようでしたら、僕の文章トレーニング歴について書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
