FYI Chris『Earth Scum』は戦うためのダンス・ミュージックを鳴らす
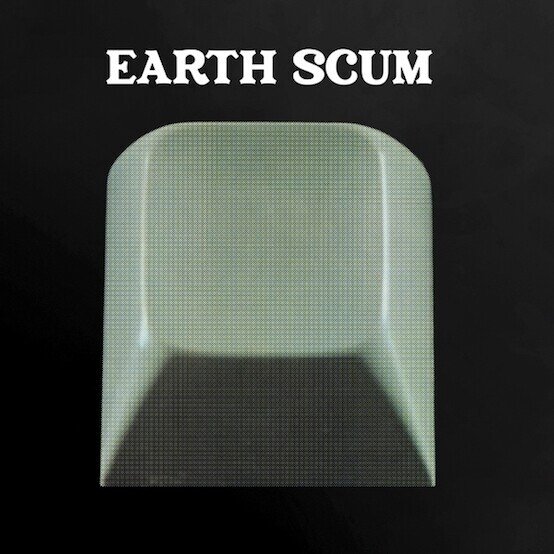
FYIクリスは、クリス・ワトソンとクリス・クープによるダンス・ミュージック・ユニット。2010年代半ば頃からサウス・ロンドンのクラブ・シーンで実力を表し、良質なトラックを数多く残している。
筆者が彼らの音楽に初めて触れたのは、2014年のデビュー・シングル「No Hurry / Juliette」だった。2曲とも素晴らしいハウス・ミュージックだが、強いて挙げれば“No Hurry”のほうが強い興味を引いた。艶めかしい雰囲気を生むヴォイス・サンプルに、肉感的グルーヴを創出するミニマルな4つ打ちのビートが交わるそれは、リリースから7年経ってもリスナーの心を飛ばし、顔をほころばせる魔力でいっぱいだ。
このデビュー・シングルで示したハウスの表情は、FYIクリスのトレードマークになった。たとえばサウス・ロンドンのレーベルChurchから発表した「Home Alone EP」(2017)でも、高い中毒性が特徴の4つ打ちを追究し、ダンス・ミュージック・ファンを唸らせた。デトロイト・テクノに通じる近未来的なシンセが響く“Oort Cloud”など、音色によってサウンドの質感を多彩にする上手さが光る全4曲は、プロダクションスキルの向上が目に見えてわかる内容だ。
FYIクリスはリミックス・ワークでも優れた手腕を発揮している。なかでもおすすめしたいのは、サラ・ウィリアムズ・ホワイト“Rainmaker”(2016)のリミックスだ。ハンドクラップ、リムショット、カウベルを軸に組みたてられたトラックはサイケデリックなフィーリングが前面に出ており、リスナーを心地よい酩酊に導いてくれる。
『Earth Scum』は、彼らにとって初のフル・アルバムだ。本作でもお得意のハウス要素は濃いが、それと同じくらい多くの音楽的エッセンスを巧みに散りばめている。オープニングの“Pizza Dust”はSFチックでスペーシーなサウンドスケープを描きながら、ドレクシアに通じる硬質なエレクトロ・ビートを刻む。ラッパーのピンティーとシメオン・ジョーンズ(ザ・カラーズ・ザット・ライズ)が参加した“On Tik”は、ジャジーなエレピの音と性急なブレイクビーツが特徴だ。さらに“The Vault”ではローファイなヒップホップ・ビートを鳴らすなど、アルバムのオープニングからラストまで自らの幅広い嗜好を全開にしている。
そうした方向性は、2020年の 「Black Dragon Loop」でもうかがえた。このEPは持ち前のハウス要素に加え、ディスコやテクノの側面を広げる意欲作だった。ちなみに「Black Dragon Loop」と本作は、共にBlack Acreからのリリースだ。そんな共通点もふまえれば、両作品の関係性がとても強いのは間違いない。
FYIクリスの社会的背景が見えるのも『Earth Scum』のおもしろさだ。参加アーティストは彼らと親しい者たちで占められ、“Scum Of The Earth”に迎えられたマンチェスターの詩人シック・ジョーンズは、ワトソンの叔父である。そこには、サウス・ロンドンの音楽シーンで築いた繋がりやコミュニティーへの感謝だけでなく、自分たちのルーツに対する敬意も滲む。
感謝や敬意を味わううえで見逃せないのは、労働者階級の匂いが漂うところだ。ピンティーはマイク・スキナーを彷彿させる庶民の視点が濃厚なリリックを得意とし、“Scum Of The Earth”で披露されるジョーンズの詩は階級差別やジェントリフィケーション(都市の富裕化現象を指す言葉。再開発の名目で地域から低所得層を追いだすことになるため、批判も多い)といった問題を容易に連想できる。
本作でのFYIクリスは、自分たちの生活に関わった人々を寿く一方で、その人々を抑圧するものへの批判的視座を隠さない。そういう意味で『Earth Scum』は、多くの人を苦しめる社会問題と戦うためのダンス・ミュージック・アルバムと言えるだろう。
サポートよろしくお願いいたします。
