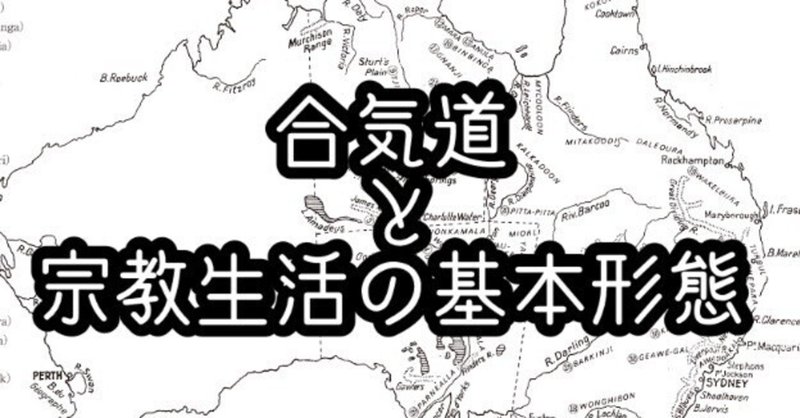
なぜ我々はムカつく上司を気軽にブン殴れないのか?:思考の型【宗教生活の基本形態と合気道⑥】
カテゴリーとは型のことだ。
だいたい人の考え方には同じ型がある。
ではそれは何によってつくられるのだろう?
霊魂と精霊の正体
デュルケームは人に宿る聖なる要素を霊魂、人以外に宿る聖なる要素を精霊として、その正体について考えている。
例えば日本人のほとんどが墓石に蹴りを入れられないように、社会的に不道徳な行動というのは、それをするのに謎の抵抗感を持つ。
その不思議な理由を説明するなら、精霊や霊魂が宿っているからということになるわけだ。

精霊とは社会規範のこと。
つまり、墓石を蹴るような人間は属している社会を追われる可能性があるからこそ、蹴れない。
えらい人に強く出れなかったりするのも同じく社会的に強い人と敵対したくないという気持ちからだ。
霊魂や精霊というのは社会が合意したことに反することのできない不思議な気持ちを別の形で説明したものだったというのがデュルケームの考えだ。
至高の儀礼
社会が決めたルールを儀礼と呼ぶ。
『聖なるもの』とは日常から区別された存在だからこそ、その象徴として聖地や祭りが行われる。
そして祭りは日常ではやってはいけないことが許可されたりして、特別感が演出されそれを信じる集団を結束させていく。
イニシエーションなどで新入りを過度に痛めつける儀式が存在して許されているのは、社会制度としての「いじめ」があり、それをすることでその集団の価値を高めるからだ。

武術の世界で「秘伝」とか「奥義」をコッソリ伝えるのはそれが本当に使えるかどうかは別にしても仲間意識を高めるという意味で有用なのかも知れない。
これが集団の価値を高め裏切りを抑制する。
宗教行事
日本の祝日は基本的には宗教行事のために存在していることはあまり知られていない。
休日も仕事(日常)から切り離す行為で、祝日に『特別感』があるのもそれに聖なる要素があるからこそなのだろう。

このように宗教というのは集団のコントロールのために生まれた社会のルールから始まっている。
集団が産んだ儀礼によって宗教ができあがっていく。
一部は全部で全部は一部
なぜ、集団行動をすると裏切りが減るかというと、社会のルールという聖なる力が拡散するからだ。

一人が行った儀式でも家族に作用し、家族の儀式は親族に作用する。
呪いの藁人形には相手の髪の毛(一部)を入れて痛めつけることで、相手(全部)に危害を加えられると考えられているのも同じ事だ。
一部をマネれば全部に伝わるという古来からの発想を利用して、それを全体の常識にして社会を保っている。
儀礼の型
神の力の拡散において、実は型で拡散される。
例えば冠婚葬祭は型でみるとぜんぶ同じ事だ。
メインとなる人物がいて、祭司による儀式があり、そして最後に見送る・終わるみたいな流れがある。

ひとつの型があらゆることに通じていく。
合気道の型
合気道も小手返し、入身投げといった技があるけど、実は原理的には同じ事をの変形だったりする。
人間のやることというのは動作にしろ儀礼にしろ大枠は同じなのかも知れない。

ただ、合気道は人口が増えて行くにあたって、技に名前をつけたり審査を行うようになり、これらは区別されて同一視されなくなってきてる。
こんな感じで宗教も同じものとは思われなくなった行事や儀礼が存在するんじゃないだろうか?
ある意味では組織のあり方みたいなものも、トーテミスムから見えてくる。
関連記事
マルセル・モースの『贈与論』と考える合気道と贈与
レヴィ=ストロースの『野生の思考』から考える合気道と人類の構造
エミール・デュルケームの『宗教生活の基本形態』から考える合気道と宗教
マツリの合気道はワシが育てたって言いたくない?
