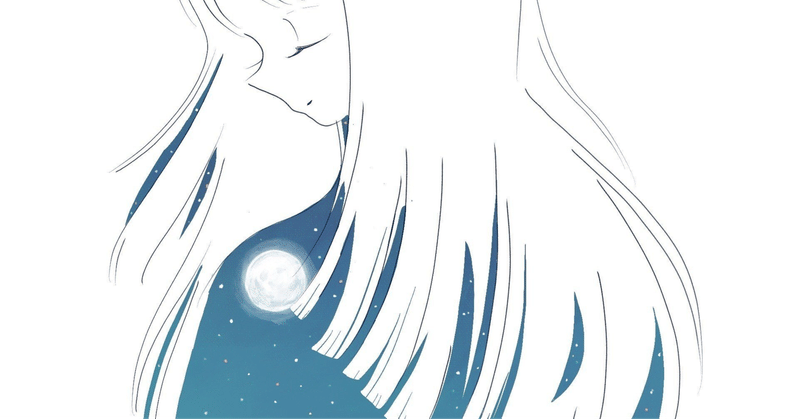
RAY
こんばんは。今回はSNSではあまり発信してなかった生い立ちのはなしを書いてみようと思います。すごく根暗な話になっていますのでよろしくお願いします。内容は暗いですが、記事タイトルの「ray」は光りという意味です。振り返ってみると、ぼくは何かと「光」という言葉を使用しています。ぼくにとっての「光」を書き綴ってみようと思います。
幼少期のころを振り返ると、4〜5歳の頃、ぼくは周囲の大人たちから「変」と言われる子どもでした。両親にも頻繁に「おまえ変わってるわ」、とこの言葉をかけられます。初対面の人や同級生にもどこに行っても言われるぼくは、すっかりこの言葉に慣れきっていました。(ちなみに今でも言われます。)
自分では、どこが、何が変わっているのか、全く検討もつきません。集団生活の中で、周囲が子どもらしく元気に遊ぶ輪には入れず、幼稚園の頃の思い出というと、動かない亀を何分もじっとひとりで見ていたり、花壇の花を引っこ抜いていたり、鳩を追いかけたり、図書室で本を読んでいる子でした。
その後、数年間、周囲と自分の関係性は幼少期と変わりません。毎日ひとりで帰った小学校、机に落書きをされた中学校、家に帰らずに蛍の光が流れる終わりの時刻までいた図書館。
どこへ行っても何歳になっても評価は「皆とちがう変なひと」です。10代になり花壇の花を引っこ抜くことはさすがになくなりましたが、教室の狭いカーテンに包まれて、窓の外を眺めていた。ひとりだけ息ができない気がしていた、そんな休み時間が学生時代で多い記憶のひとつかもしれません。
ぼくには両親との思い出はとくにありません。昭和をひきずった荒っぽい家庭環境に馴染めず、家にいた時間は絵を描いたり、なにかを作ったり、創作することだけが唯一「いま」を実感できた時間でした。
ただ、本格的に創作活動を始めた10代の頃、「情報のない地方、貧困、理解のない大人、閉塞感」と、芸術や創作とは正反対の環境にぼくは生きていました。お金がなかったので黒と白の2色だけ絵の具を買い、廃材場から拾ってきた木の板に絵を描いていました。本当はたくさんの青や、水色、紫の色が揃った24色セットが欲しかった。
そんなことばかり考えながら、家族が寝静まり夜になると2色の絵の具で夜の窓から見える「月の光り」を描く日々を過ごしていました。
この創作がどうなるのか自分では検討もつかなかったけれど、表現することはなぜか食事と同じ本能のような気がして、筆をとめる日はありませんでした。心を込めてつくることは自分をつくることに似ていると、このとき思います。
一方で、日中はやはり社会に馴染めず、居場所も見つからず、大人になればなるほど周囲への違和感を強く感じていました。生きづらさ、息苦しさは年々増していき、もう数年もしたら、この世界に必要のないぼくは静かに消えてしまうのではないかと、ぼんやりそんなことを考えていました。
そしてさらに、「頑張って生きていれば希望がある」なんて、どっかの誰かの明るい名言を吹っ飛ばすような追い討ちともいえる出来事を経験します。
突然、左耳と左脳に不調がありました。昨日までは何にもなかったのに朝起きたら前触れもなく耳が聞こえなくなっていた。病院で検査をしたら、当時難病指定だったメニエールという病気が見つかります。左耳の聴力はほぼなくなり、目眩や耳鳴り、吐き気などの不調で今までできていたことが難しくなり、日常生活をおくるのが難しくなってしまいました。
「死ぬこと以外かすり傷」「雨のあと虹かかる」なんて圧倒的に陽性の人間が生み出したような言葉を見かけるたびに「じゃあ変わってくれよ」と何度も実態のない何かを恨むぼくがいました。こんな苦しみは今の生きづらい社会ではありふれているかもしれません。
そうだとしても、生きていくことはむずかしい。この世に生み落とされてから何度この言葉が浮かんだでしょうか。
そうして自分だけの地獄の中に立っていたぼくは、創作活動を続けているうちに、生きることへの苦しみは知性を持った生き物である以上普遍的なものである、と考えるようにもなりました。
自分は空っぽだと思い、絶望しまくっていたぼくが、創作を通じて息を吹き返していくお話は、こちらの記事に詳しく綴っています。
こちらの記事では触れていないのですが、このようなギリギリを生きてきたぼくが向き合うしかなかったひとつの創作テーマでもある「死」について、「死は生命に平等に訪れる救いだ」と考えたのもこの時期です。何もかも不平等な世界で唯一等しくあたえられたのものが死だと気づき、このときにメメントモリという詩が生まれます。
メメントモリ
ぼくが最期 世界と別れる日がきたならば 炎で燃やされ 煙になって
そのまま空高く登ってゆきながら 地球のいちばん高いところで
いちばん美しいと思うような 地平線を見る 夜明けなのか
夕暮れなのか どちらかわからない色をした
地球のグラデーションをそこで見る
そうして雲と雨に溶けあって 星の祝福を浴びながら
また地上に落ちていくでしょう 大地と海に迎えられ
地球のなかに ゆっくりじっくり還っていく
ぼくは静かな場所で眠らない
この果てしない生命の輪のなかに戻るだけ
春は眩しい光になって 夏は青い緑になって
秋は広い空を泳ぐ風になって 冬は冷たい煌めきをまとう
ぼくの姿かたちがなくなって 散り散りになったとしても
世界にぼくは 潜んでる だからどうか泣かないで
だからどうか忘れないで ぼくはいつもそばにいる
終わりの日がやってきて、ぼくがどれだけ作品を言葉を生み出し、生きているあいだに多くのものを抱えたとしても、最期はなにひとつ持ってはいけない。この事実を、怖く悲しいことだと捉えるでしょうか。それとも生命の美しい定めだと捉えるでしょうか。
ぼくは自分では持ってはいけないけれど、置いていけるだけ置いていこうと考えるようになりました。こんな世界でも、未来の誰かが、いつかの自分のように生まれたことを寂しく思ったときひとりにならないように。同じように寂しく生きた痕跡を少しでも残すのがいまのぼくにとってやれることだと。そう思いました。
「光」という言葉が創作キーのぼくですが、ぼくにとっての光は太陽のように明るく元気なものではないようです。「頑張ろう!希望を持とう!」という励ましの言葉を残すことは、生涯ないでしょう。
雨のあとに顔をだす太陽ではなく、雨のなかに反射する小さな光を。寂しさえも美しく見える世界を。ぼくは人が寝静まるまよなか、月の光を見ていたあの頃のように、夜の闇から光る言葉を見つけて、紡いで生きていくんだと思います。
いまは終わりが迎えにくるその日まで、苦しくても意味なんかなくても、ただこの場所で生きることを繰り返していくんだと思っています。
それ以上もそれ以下もなく、明日からも変わらずひとつずつ小さな光を積み上げて生きていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
