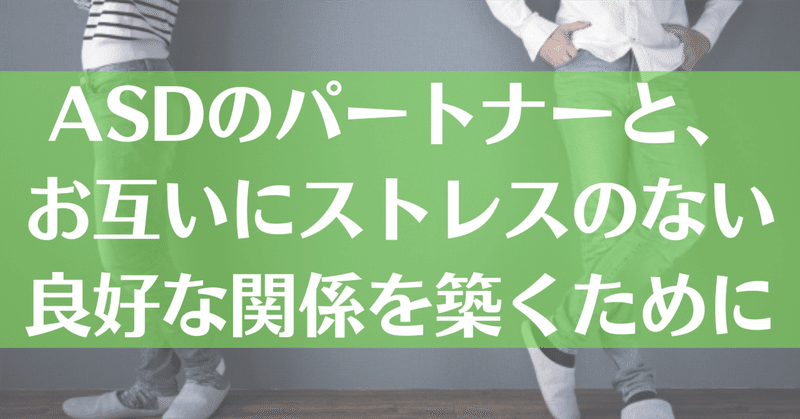
ASDのパートナーと、お互いにストレスのない良好な関係を築くために
私の夫にはASDという発達障がいがあります。
また、次男3歳もおなじく、ASDと診断されています。
過去の記事にも詳しく書いていますので、興味のある方はぜひ。
夫との関係性に悩んでいたところ、偶然にも「ASD」というものの存在を知りました。
今も、新たな発見ばかりです。
「発達障がい」と聞くとどうしても、ネガティブな印象を受ける方が多いと思います。
でもね~おもしろいですよ、うちの夫。
特性がわかると対策ができるので、私はとても助かっています。
「ASDのパートナーと良好な関係を築く」などとえらそうなタイトルをつけましたが…
まず大前提として、お互いに敬意と感謝が無ければいけないと思っています。
そこに、ASDなど発達障がいの有無は、関係ありません。
自分以外の人と生活する上で、諦めなければいけないこともあるし、どうしても諦めたくないこともある。
生まれも育ちも価値観も違う、赤の他人と一緒に暮らしているのだから、それは当たり前のことなんですよね。
私の譲れない部分があり、夫の譲れない部分がある。
私にはできるけど夫にはできないことがあり、夫にはできるけど私にはできないことがある。
お互いの欠点を補い合いつつ、2人ともがストレスなく生きていくためには、どう過ごす~?みたいなことを書いていくよ。
あわせて、夫がASDだと分かってから習慣になったことなども、書いてみようと思います。
ASDの夫が抱えていたストレス
夫が私に対して抱えていたストレスは、こんなことです。
物の場所を勝手に変えられる
口頭で要件を伝えてくる
抽象的な指示が多い
作業中に話しかけられる
「なんか嫁が不機嫌」ということはわかるけど理由がわからない
話したいことがあっても、話しかけるタイミングがわからない
ものの場所を勝手に変えられる
ルーティンが決まっている夫にとって非常に迷惑なのが、「ものの場所を勝手に変えられる」ことです。
気分で整理整頓や模様替えすることが多い私は、逐一確認したり、報告したり、していませんでした。
でも、その場所にあるはずだと思っているものがないのは、とても不安になるし、ストレスになるのです。※別にASDじゃなくてもストレスやから他人のものに触るな、私よ
口頭で要件を伝えてくる
とにかく1日の出来事を早く報告したい私は、いつも夫に「口頭で」伝えていました。
ただ、夫は話の内容を一度頭の中で組み立てるため、何を言われたのか理解するまでに少し時間がかかります。
頭の中で組み立てている最中に、別の話が始まってしまうと、それまでにしていた話は忘れてしまうらしい。※シンプルに私がしゃべりすぎ
一生懸命積み上げたブロックが下から崩されるような感じです。
また、ASDの特性で共感力が低いため、「自身が体験したことのない話」は、あまり頭に入りません。
昔は本などを読んでも、ただそこに書いている文字を読んでいるだけ、という感じで、内容はまったく理解できなかったそうです。
話の内容を理解することはできるけれども、共感ができないので、感情が一切動かないと話していました。
「その話を俺にして、一体なんの意味があるのかな~」などと感じることさえあります。
あと、大事な要件を口頭で伝えられても、長期間覚えておくことが困難です。
抽象的な指示が多い
ASDの特性上「抽象的な指示」は伝わらないことが多いです。
例えば、レシピ本などでよく見る「具材がひたるくらいの水」とか「鍋肌に沿ってまわしかける」とか、そういう表現をされると「結局どのくらいなん????」となります。
例えば、粉を入れて溶かすタイプのスープやコーヒーなど、「お湯の分量はだいたいそのくらい」「コップの半分くらいまで」とか言われても、わからないのです。
作業中に話しかけられる
メールの返信をしているときとか、何かを読んでいるときなど、夫がなにかしているとき。
そういうときは、話しかけられても、話が入ってきません。
さらに、話しかけられたことによって、今自分が何をしていたのかわからなくなってしまいます。
特にメールの返信なんかは、
まずメールを読み
内容を頭の中で咀嚼して
なんて返信するかどうか一生懸命考えて
考えながら文章を作っては添削する
みたいなことをしているため、非常に時間がかかります。
そんなときに話しかけられてしまうと、また1からやり直しになってしまうんですよね。
「なんか嫁が不機嫌」ということはわかるけど理由がわからない
例えば、私が家でバタバタと忙しそうにしているとき。
自分への指示が何もなければ、何を手伝えば良いのか、どうしてバタバタしているのか、わかりません。
ただ、自分が子どもの支度や家事でバタバタしているとき、パートナーがぼんやりテレビを見ていたり、スマホを触っていたりすると、ちょっとくらい手伝ってよ!と感じますよね。
これ、わかっていただける方も多いと思います。
しかし、「動きや表情から他人の望みを察する」というのは、夫にとって非常に難しいことです。
普段ベラベラとやかましい私が黙っていると、「なんか不機嫌」なことは感じます。※普段しゃべりすぎ
しかし、なぜ不機嫌なのかがわからず、改善策もわからない。
どうして機嫌が悪いの?と聞くのも、かなり勇気が必要で、私の機嫌が悪いときは、どうしていいかわからず、内心オロオロしていたようです。
でも、夫は感情が表情にあらわれにくいため、そんな気持ちだったことは、私には一切わかりませんでした(笑)
完全スルーされていると思ってた。
話したいことがあっても、話しかけるタイミングがわからない
ASDの性質上、「空気が読めない」「動きや表情から察することができない」というのは、先ほどもお話ししました。
そのため、ASDがあると「人とのコミュニケーション」を避けて通りがちだそうです。
人との対話経験が少ないからか、夫の場合も、「人に話しかけるタイミング」がイマイチわからないとのこと。
今忙しいかもしれない…
今言うべきことではないかもしれない…
こんなことを話しても意味がないかもしれない…
などと考えてしまい、結局言いたいな~と思ったことが言えず、消化不良を起こしていました。
また、「抽象的な表現が苦手」という特性から、心で感じていることを言葉にするのがとても苦手です。
不安や不満、悩みを抱えていても、誰にも話さず自分だけで解決しようとしてしまうのです。
ここまで書きましたが、夫にとってそんなことは日常茶飯事で、「ちょっと困るな~」程度のものでした。
夫は基本的に、嫌なことかがあっても引きずったり思い悩んだりせず、とてもポジティブな性格です。
※その代わり、1回でも許せないことがあれば、一生許しません。(怖い)
定型発達の私が抱えていたストレス
私が夫に対して抱えていたストレスは、こちらです。
怒っているように見える
話しかけても聞いているのかどうかわからない
意見を聞いても、答えてくれない
すぐに忘れてしまう
子守りを頼むと、数分で疲れ果ててしまう
怒っているように見える
夫は、とてもとても無口です。
夫から話しかけてくるのは、「話したいことがあるとき」か、「用があるとき」だけ。
その頻度は非常に低く、基本的には、この流れです。
私:しゃべる
夫:ふ~んorへ~orうん
私:しゃべる
夫:うんorふ~んorへ~
※私がしゃべりすぎ
誰かと一緒にいて無言の時間が続いても、まったく平気です。※もしかしたら相手が気まずく感じてるかもしれない、と心配になることはある
さらに、感情が表情に表れにくく、基本的には真顔です。
私は「え怒ってるの?」と、いつも思っていました。
実際に、「なんか怒ってる?」と聞くこともあれば、内心「なんでいつも夫は不機嫌なんや!」と思うこともありました。
話しかけても聞いているのかどうかわからない
私は、とにかく「もっと会話をしたい」と思っていました。
夫は、今日の出来事や愚痴、子どもたちの話をしても、「うん」「へぇ」「(^ω^)・・・」など、大したリアクションをしてくれません。
子どもが見ているYoutubeやテレビを、一緒になって真剣に見ているし、ずっとスマホ触っているし。
で、一旦画面の世界に入ってしまうと、話しかけても聞こえていない。
それなのに、自分が好きな話や知っている話になると、饒舌になります。
私に興味がないのかもな~と思い、話しかける回数は減っていきました。
このまま会話が減っていって、歳を取ったら一言もしゃべらなくなったりするのかな…と不安に思っていました。
とはいえ夫は、私を傷つけたり、裏切ったり、邪険に扱ったりしません。
とても穏やかな性格で、頼んだことは即答でOKしてくれる。
大切にしてくれていることが伝わってくるし、日々感謝もしてくれる。
私の価値観だと、「興味がない」って、「嫌いより下」なんです。
だから、「大切な人だけど興味はない」って、私にとってはあまりにも謎すぎて、理解ができませんでした。
意見を聞いても、答えてくれない
夫の意見がほしくて相談しても、基本的に「どっちでもいいよ」「なんでもいいよ」「それでいいよ」と、自分の意見を言いません。
例えば、AとB、2つの選択肢があったとします。
AはこうだけどBはあれだよね~とか。
Aはここが良いけどBのここも捨てがたいよね~とか。
私は、夫がどう思っているか聞きたいのです。
でも夫の場合は、「Aにしようと思うけどどう思う?」と聞くと「Aでいいよ」と言うし、
「Bにしようと思うけどどう思う?」と聞くと「Bでいいよ」と言います。
このAとBが、「夫が明日着る服」など、彼に直接関係することだったとしたら、はっきり自分の考えを言うことができます。
どうやら、「自分には直接関係がないのに、自分の意見を述べるなどおこがましい」と感じてしまうらしい。
すぐに忘れてしまう
夫は、あとで子どもに薬飲ませておいてね、とか、〇日は子どもの予定があるよ、とか、そういう類のことを、ことごとく忘れてしまいます。
私の誕生日を忘れられてしまったこともあり、それ以降は、「忘れられている可能性」をじゅうぶん頭に入れ、期待して寂しい気持ちにならないよう意識してきました。
やりたくないから、興味がないから、忘れてしまうのかもしれないなどと考え、夫に頼むのは諦めようと考えたこともあります。
どうしても休みを取ってもらわないといけない日は、何度も何度も口頭で確認し、念を押したこともあります。
「こんな大事なことを忘れるわけがないよね」と思って確認しなければ、やはり忘れてしまっていたことも。
「興味がないから忘れるのだ」と思っていた頃は、とても寂しく感じていました。
子守りを頼むと、数分で疲れ果ててしまう
たまに1人になりたくて、夫に「公園に娘と次男を連れて行ってきて」とお願いすると、30分~1時間ほどで、登山してきたんかと思うくらい疲れて帰ってきます。
そして、その疲労を回復すべく、小一時間お昼寝してしまうのです。
おいおいおいと。私は毎日、1日中、子どもと過ごしておるのだぞと。
思っていました。
結局、私が1人になれたのは、たった数分だけ…と。
今思えば、とてもわがままな話です。
次男がASDだということもわかっていなかったし。
でも、当時は子育てがしんどすぎて、感謝よりもそんな思いが先に出てしまっていました。
ASDの特性を知ってから、私たちがしたこと
夫がASDだとわかり、私はASDについてたくさん調べました。
ASDはこんな特性があるみたいだけれど、あなたはどう?という話を、たくさんたくさんしました。
夫はそのたびに、自身の体験談など、いろんな話を聞かせてくれました。
それも、聞かれたからしぶしぶ答えてくれているという感じではありません。
「そういうとこあるー!めちゃあるー!」と、「わかってもらえて嬉しい」と思ってくれているように見えます。
それだけ、これまで「他人との違い」に違和感を感じていたんだろうなと思ったりしました。
夫の良いところは、すぐに「自分はASDである」と受け入れたことだと思います。
HA?そんなわけないやろ!こっちが普通であなたがおかしいデス!
という思考になっていても、まったくおかしくはないと思うんですよ。
でも、夫の第一声は、「えっ!俺、発達障がい?」でした。※リアクション薄
ASDの特性が書いている記事を見せると「俺の説明書を読んでるみたい」と言いました。
それだけでもう、私はとにかくホッとしたんですよね。
私が抱えていたような不安や憤りや寂しさは、どれも間違いだったことがわかったので。
やっと今までの謎が解けた~~~というような、何とも言い難い。
冒頭でも書いたように、「障がい」という響きから、受け入れがたい方も多いと思います。
でも、社会的な困難が多いから「障がい」という区分になっているだけなんですよね。
自分自身のことを知って損することなどないと、個人的には思っています。
2人でASDの特性を少しずつ理解しながら、こんなことを試しました。
忘れてほしくない要件は紙に書いて伝える
ホワイトボードの活用
マインドマップの活用
夫のルーティンを崩さない
具体的な指示をする
子どもは1対1で見る
作業中は話しかけない/作業前に申告する
伝えたいことは、はっきりと言葉にする
順番に書いていきます!
1.忘れてほしくない要件は紙に書いて伝える
買い物を頼みたいときや休みを取ってほしい日、子どもたちの行事や私の予定などは、極力文章で伝えることにしました。
一緒にいるときでも、口頭ではなくLINEに残すかメモに書いて渡す。
予定に関しては、ASDだと分かる前から「TimeTree」というアプリで共有しています。
夫は見たものはすぐに頭に入るし、我が家の場合、休日の移動はほぼ100%夫が運転する車です。
そのため、1日の予定なども紙に書いて見せておけば、スムーズに休日を過ごせます。
やむを得ない、急な予定変更があると忘れがちです。
ここのスーパーに行くよって車を発進させて、自宅に向かってたりする。
それはそれでおもろいので良しとします。
ちなみに、私の誕生日や子どもの予定なども、忘れられて悲しい思いをすることがありました。
夫の場合は、「日にちは忘れていないけど、日にちを気にしながら生きていない」ようです。
でも、曜日は把握しているので、「来週の月曜は〇〇があるよ」などの言い方なら、口頭でも忘れないのでは…?と思ってます。※近々実験しよっと
この歳になって(35歳)自分の誕生日をアピールするのもなぁとか思いますけど、私は絶対に祝ってほしいんです!
ケーキも食べたいんです!!!
なので、今後はなりふりかまわず、誕生日の1ヶ月前からカウントダウンをしていきたいと思います。
2.ホワイトボードの活用
明日はここに行きたい!と言ってから眠っても、夫の場合は、朝起きると「で、今日はどこに行くんだったっけ?」となります。
数分後、〇〇してほしい!ということも多々あるのですが(例:洗濯機が止まったら干して/食事が終わったら子どもに薬を飲ませて、など)
これも、もれなく忘れてしまいます。
そういうときのために、冷蔵庫にホワイトボードシートを貼りました。
ただ、常に何かが書き込まれている状態だと、だんだん景色と化し、ホワイトボードすら見なくなる可能性があります。
そのため、用事がないときは真っ白をキープしています。
3.マインドマップの活用
夫の共感力が低かったとしても、私はやっぱり夫に相談したいし、夫の意見を聞きたい。
今私が1番頼りにしているのは夫だし、私の次に子どもたちと接する機会が多いのも夫で、私のことを1番間近で見ているのも、夫です。
なので、それだけは絶対に諦めたくありません。
そこで、マインドマップを書いて、夫に見せてみました。
【マインドマップとは】
マインドマップ (mind map) とは、イギリスの教育者トニー・ブザン氏が提唱した思考の表現方法のひとつで、中心となるキーワードから関連する言葉やイメージをつないでいった放射状の図のことを言います

例えば、中央の丸に「しんどい」と入れたら、左右合わせて4つの丸に「しんどいと感じる原因」を入れます。
1つの丸に「家事」と入れたとしたら、「家事がしんどい原因」を「家事」から伸びている丸に入れます。
そんな感じで、どんどん私の思考を視覚化していき、最終的にそれを夫にみてもらうのです。
すると夫は、一通り目を通したあと、「こんなことは思う必要がない」「これはこうやって解決できる」と、私の中にある問題を、1つずつ消していってくれました。
それで私の気持ちはとても軽くなったし、なによりも、夫にちゃんと相談に乗ってもらえたことが嬉しかった。
今後くよくよと悩むことがあったら、またマインドマップを使おうと思っています。
4.夫のルーティンを崩さない
夫側のストレスにあった「物の場所を勝手に変える」もそうですが、極力夫のルーティンを崩さないようにしています。
普段手伝っていないことは、手が空いているときも手伝わないことにしました。
特に、完全にルーティンが固まっている「仕事の日の朝」などは、極力なにもしません。
私は、時間どおりに弁当を用意するのみ。※朝からうるさいのはルーティンに含まれているだろうか
5.具体的な表現をする
抽象的なことば、私は結構多用しがちだったんです。
でも、あいまいな表現はわかりづらく、より混乱させてしまう可能性があるので、具体的な表現をするようこころがけています。
例えば、こんな感じです。
お湯は野菜にかぶるくらい入れて→1Lのお湯を入れて
惣菜を適当に買ってきて→コロッケと唐揚げ買ってきて
そのへんに置いといて→テーブルの上に置いといて
具体的な表現をすることで、夫の悩んでしまう時間が減ります。
私が体調を崩したときなど、どうしても料理をお願いしたいことがあるので、そういうときのために「夫の料理メモ」も作っています。
用意しなければいけない調理器具、必要な食材、どんなふうにカットしてどんなふうに加熱するか、手順を追って箇条書きに。
料理はほとんどしたことがない夫ですが、先日私が寝込んだにも、メモを見ながら1人で料理してくれました。
6.子どもは1対1で見る
我が家には子どもが3人おり、長男が中学2年、長女が小学1年、次男が3歳です。
中2は1人でも行動できますが、下2人はまだなかなか目が離せません。
マルチタスクが苦手な夫にとって、子ども2人を同時に見るのは、至難の業。
そりゃ~登山くらい疲れるよねっていうことがわかってからは、子どもを1対1で見ることにしました。
私が出かけるときはどちらか連れて行ったり、家族で出かけるときは、「私は次男を見るから夫は長女を見ててね」とお願いしています。
1人なら、それほど疲れることなく、集中して見守ることが出来ます。
7. 作業中は話しかけない/作業前に申告する
夫がなにかしているときは、極力集中を妨げないよう気をつけています。
どうしてものときは、「今いい?」と今から話しかけるよ~とわかってもらったうえで、話しかけるようになりました。
また、夫の方も、「今から〇〇していい?」と聞いてくれるようになりました。
子どもたちはそんなことお構いなしにうるさいので、「今はお父さんの邪魔しないでね」と伝えています。
8.伝えたいことは、はっきりと言葉にする
「察してよ」「わかってよ」という気持ちが強かった私ですが、伝えたいことははっきりと言葉で伝えることにしました。
少し言いにくいなと感じることでも、すべて言葉にして伝えています。
しんどいときはしんどいから手伝ってと言えばいいし、料理したくないときは今日は外食したいと言えばいい。
「夫はなにか怒っているのかもしれない」と思っていたから、いつもどこか気を使っていたんですよね。
でも、全然怒ってないし、「夫はただの無口で、ただの真顔」だということがわかりました。
さらに、「言ってもらわないとわからない」ということもわかりました。
なので、これからはなんでも言います。
もちろん、言いたい放題わがまま放題という意味ではなく、言葉によるコミュニケーションを、これまでよりもっと大切にしていきたいと思っています。
夫の「話しかけるタイミングがわからない問題」は、私にはいつでも話しかけていい、どんな些細なことでも言ってほしいと伝えました。
些細か些細じゃないかは、私が決めることなのです。
夫には少しだけ「話しかける勇気」を出してもらわねばいけませんが、それは私がどうにかできる問題ではないので、
私はこれからもひたすらにしゃべりつづけようと思います※うるさい
お互いに「共感できなくても、理解はできる」と知る
夫がASDだとわかったことで、お互い、「そんな人もいるんだなぁ」ということを理解しました。
夫にとっては、夫の考え方が「普通」だし、
私にとっては、私の考え方が「普通」だし、
しかしそれをお互いに強要することなく、「こういう人もいるんだなぁ」と理解ができました。
夫は私ではないので、共感ができません。
でも、私が「大切な人には共感してほしい」という気持ちを持っている、ということを理解してくれました。
また、私とは違った視点でものごとを見ることができます。
私は夫ではないので、共感はできません。
でも、夫が「共感することが苦手だけど家族を大切に思っている」と理解しました。
また、夫がコミュニケーション上で困ったとき、解決策を伝えることができます。
お互い、諦めなければいけないこともあるし、諦めたくないこともあります。
冒頭でも話しましたが、それは発達障がいの有無にかかわらず、他人と暮らしていくうえで当たり前な気もする。
これからも、お互いに敬意と感謝を忘れずに過ごしていけたらなぁと思います。
きちんとまとまっているかどうか謎ですが、こんな長文を最後まで読んでくださったあなた!
本当にありがとうございます!
ではまた~~~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
