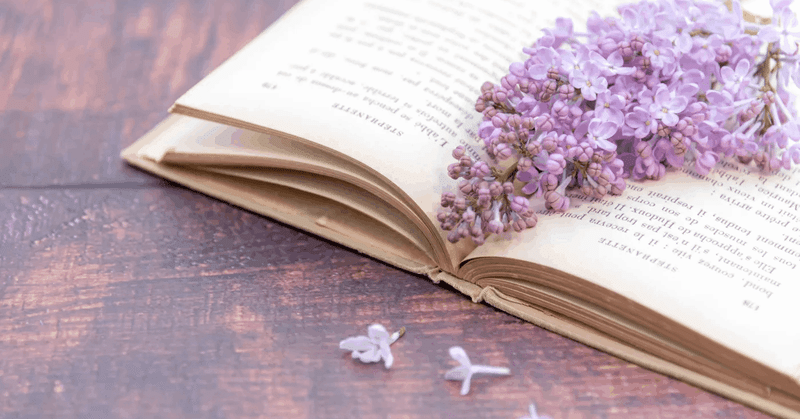
今日の本棚 : 時事エッセイの賞味期限
直前に読んでいた「極北コルィマ物語」があまりにも暗くてしんどいので、息抜きになにか気楽な本を、と読み始めました。
「真夜中の太陽」のほうは1998年から2001年ごろの時事エッセイで、文庫化されたのは2004年ごろ。こういう時事ものは、四半世紀も経てば時代の記録となるのですね。
米原さんの本を読み漁っていたことからこの2冊の本も購入したわけですが、入手した当初は、新鮮味も薄れた時事ネタにあまり興味が湧かず、それで長らく積ん読になっていたのでした。
が、今になってみれば「そんなこともあったなあ」といろいろなことが思い出されます。
PC2000年問題とかO157、銀行への公的資金投入、大企業の相次ぐ合併、不況下のリストラ、小選挙区制の導入、消費税の5%への引き上げ…
しかし、読み進むうちに、ただのんきに「時代の記録」などと言っていられない気もしてきました。25年も前にエッセイに取り上げられていた事柄の根本のところが解決していない問題がいくつもあるように思うのです。
ところでこの本のタイトル、どちらも詩的ですよね。
「真夜中の太陽」は、夜の暗闇を怖がっていた幼い米原さんが、お父様が説明してくれた地動説の話を聞いて心に抱いたイメージ。
「地球の裏側で、ご機嫌な顔をして大地を照らす太陽」は、大人になって夜の暗さもお化けも怖くなくなってからも、米原さんを励まし続けたイメージでした。
「目前の状況に悲観的になり絶望的になったときに、地球の裏側を照らす太陽が、そのうち必ずこちら側を照らしてくれると思えば、気が楽になるし、その太陽の高みから自分と自分を取り巻く事態を見つめると、大方の物事はとるに足らないこととなる」と。
もう一方の「真昼の星空」は、詩人オリガ・ベルゴリツの自伝エッセイ「昼の星」の一節から。
「星は、いついかなるときにも空から消えないというようなことを、その男は言った。昼の星は夜の星よりも明るく、美しいほどなのに、空にその姿を認めることは、太陽の光にさえぎられて永遠にかなわない。(中略)その夜からだった。昼の星を見たい! という強烈な願望にわたしが取り憑かれたのは」
現実に存在していながらも多くの人の目には見えていないもの、目に見える現実世界の裏にたしかに存在するもう一つの現実。「昼の星」はその比喩なのだそうです。
この25年のことを思います。
通り過ぎてきた時代はもはや前世かなにかのように遠く感じられますが、たしかに今につながっている日々でもあります。
その一日一日を自分はどう過ごしてきたのでしょう…
私も近視眼的な考えやものの見方に陥ることなく、はるか地球の反対側で輝く太陽を心に思い浮かべることができるようになるでしょうか。昼の星のごとく埋もれ隠れているものを見極め、掬いだせるようになるでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
