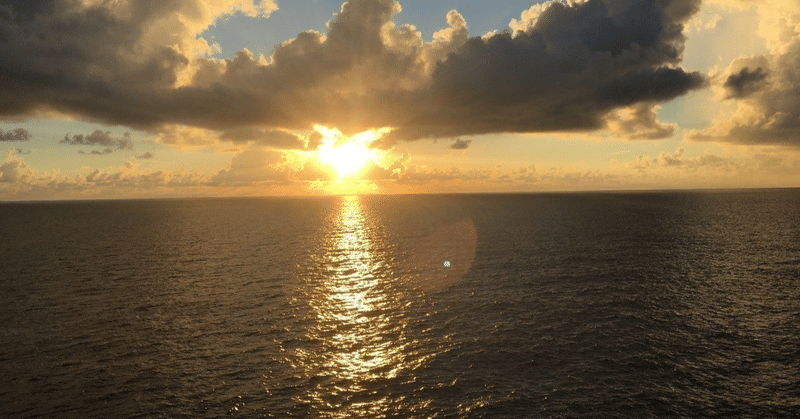
綱渡り
この記事はみえ様主催の「カニ人アドカレ2023」8日目の記事として参加しています。昨日に引き続き書き下ろしではありませんが、内容を若干修正したものをアップさせて頂きます。お楽しみ頂ければ幸いです。
7日目の記事はこちら。
◆◆◆
時は東西冷戦の最中のことである。地上で行われているニンゲン同士の血で血を洗うような争いの行く末などどこ吹く風とばかりに深海の熱水噴出孔近くで心地よい惰眠を貪っていたカニ人たちは、突如として視界が眩い光に満ち、直後に強烈な熱と衝撃が全身を激しく打つのを感じて、まるで沢山のバネが一斉に弾けるように慌ててその場から逃げ出した。
彼らが棲む深海で、高出力熱核爆弾を用いた水爆実験が行われたのである。太陽の光がまったく届かない真の暗闇を白く染め上げ、周囲の岩盤やら沈んでいたクジラの死骸やらをまとめて融解せしめた膨大な熱量を伴う火球は、しかし現れた時と同様に急速に収縮を始め、まるで最初から存在しなかったかのように忽然と姿を消してしまった。
いかに地上では破滅的な威力を持つ爆弾といえども、そこは圧力が千気圧にも達する超深海。
大いなる海神は我が物顔で自宅の庭を荒らす不届き者を決して許さず、その御手によってあっという間に握り潰してしまうのである。
とはいえ爆心地では、あらゆるものがドロドロに溶け崩れていた。もともと海底に存在した大小さまざまな岩石や沈没船の残骸、海底を這う奇妙な軟体動物、砂地を歩き回るエビやカニなど、一瞬前まで確かにそこに存在したもの全てが核分裂の連鎖反応がもたらす天文学的なエネルギーによって蒸発し、瞬時に海水の中へと消え去ってしまっていた。
驚いて逃げたカニ人たちは、すぐに元の場所へと戻ってきた。特攻があるのでニンゲンの武器は無効化できるカニ人たちであったが、それでも一時的に視力や聴力を失った者もいたようだ。しかしそういった症状はすぐに治るので彼らはほとんど気にしなかった。問題は体の傷よりも心の方だ。
人間の作った兵器に動転させられ、彼らのプライドはいたく傷ついていた。いみじくもカニ人たる者が……第二の人類を自称し、大昔から事あるごとに人類への嫌がらせを繰り返してきた名誉ある一族が……まるで落雷に怯える子供のように慌てふためき、我を忘れて逃げ回るとは。
甚だしく自尊心を傷つけられたカニ人たちは地団太を踏み、海藻の繊維で編んだハンカチを噛みちぎらんばかりの勢いで悔しがると、連日のように決起集会を開き、人類滅亡のスローガンを唱えて夜通し海底を練り歩いた。
「おのれニンゲン、我らの安息の地に爆弾投げ込んできやがるとはいい度胸してるカニ。あんなのちっとも怖くなかったけど普通にびっくりしたカニよ。この屈辱は百万倍にして返してやるカニ」
「そうカニ、これは正当な反撃カニ。ちっとも怖くなかったけどもいわゆるリベンジというやつカニ」
「人類滅亡! 人類滅亡!」
怒りに燃えるカニ人たちは一目散に浅海へと浮上して、そこを通る漁船や貨物船を襲い始めた。波を蹴立てて走るトロール船の綱を切断し、品物を満載した貨物船のバラストタンクに穴をあけ、海水浴客でごった返すビーチにお腹を空かせたホホジロザメを投げ込んだりしては、その度に右往左往するニンゲンたちの様子を見て笑い転げた。
「見たカニ、これが我々の真の実力なのだカニ」
「そうカニ。我々を怒らせるとどうなるか、思い知ったカニ」
彼らはニンゲンからの反撃を想定していた。流石にここまでやられて黙っているはずがないと思っていたのだ。しかし予想に反して、いくら待っても一向に反撃してくる気配はなかった。
超深海に半ば閉じ込められるようにして暮らしている彼らは知らなかったが、そもそもほとんどの人類はカニ人の存在そのものを知らないのである。彼らの存在は社会に致命的なパニックをもたらさないようにという大義名分により徹底的に隠蔽されていた。知っているのはごく一部の権力者たちだけだ。しかもその権力者たちにしても、自分たちの兵器がカニ人に対してほとんど何の効果も及ぼさないことを熟知していたので、彼らが起こした数々の事件は、情報操作に長けた権力者たちによってすべて偶発的な事故として処理されていたのである。
そしてもう一つ彼らにとって不可解なことがあった。今回の件には彼らの天敵中の天敵である人魚族が一切関与してこなかったのである。これまで幾度となく悪だくみを邪魔されてきた彼らにとって、これは願ってもない僥倖であった。ニンゲンから反撃もなく、人魚族の干渉もない。この状況にカニ人たちは激しく調子に乗った。それはもう乗って乗って乗りまくった。占拠した船の上で盛大な宴会を開き、一族を称える歌を大声で合唱しながら縛り上げたニンゲンたちの前でこれ見よがしに己の尻をペンペンと叩いた。そして、哀れな捕虜たちをマリアナ海溝の奥深くにある自分たちの棲み家に連れて行くと、そこでカニ人という種族がいかに素晴らしく、またニンゲンという種族がいかに愚かで滅亡すべき存在であるかということを延々と頭に叩き込み、その後で地上に送り返すという一種の洗脳教育を行った。
「愉快カニ! 痛快カニ! こんなに楽しい気分は久しぶりだカニ」
「まるでお正月とクリスマスがいっぺんに来たみたいだカニ。このまま地上征服いっちゃうカニ?」
調子のいい言葉に、周囲からワハハと喝采が起こる。彼らは文字通り有頂天であった。あまりに物事が上手くいきすぎていて視野が狭くなっていた。なぜ今回の件に人魚族が関わってこないのか、その本当の理由まで突き詰めて考えるという事をしなかったのだ。
「────」
「……カニ?」
一匹のカニ人が、きょろきょろと辺りを見回す。それに気づいた他の個体がどうしたのかと尋ねた。
「いや、今何か聞こえたような気がしたカニ」
音のした方向に耳を澄ましてみる。聞こえてくるのは周囲のどんちゃん騒ぎばかりだ。だが──。
「やっぱり、何か大きなものがこっちに近づいてくる音がするカニ……!」
音の源を探るため、そのカニ人はデッキを横切って船べりから遠くへと目を凝らした。
初め、彼はそれを島だと思った。
大海原に浮かぶ巨大な黒い塊。
だが、この海域にあんな島は存在しない。
それに、その塊は移動していた。
カニ人たちのいる方向へ急速に接近してくる。
移動する島などあるはずがない。
海がザワザワと蠢いている。
ありとあらゆる海洋生物たちが<何か>の気配を感じ取り、その場から必死に離れようとしているのだ。
やがて海面に凄まじいうねりが起き、船が大きく揺れた。
「ゆ、揺れてるカニ! 一体何事カニ……!?」
ようやく異常な事態に気づいたカニ人たちが騒ぎ出した時には、時すでに遅すぎた。身の毛もよだつ恐ろしい咆哮を上げて、山よりもなお巨大な体を持つ伝説の怪物が、彼らの前に飛び出してきた。
──人竜レビアタン。ラテン語でリヴァイアサンとも呼ばれ、数多くの伝説や物語の中で語られるその恐ろしい生き物は、人魚がいないのをこれ幸いと好き放題やっているカニ人たちの所業を見るに見兼ね、近海にある竜宮城から激昂と共に駆けつけたのであった。あらゆる海の住人から恐れられ、また崇められるその怪物は、慌てふためいていたカニ人たちを乗っていた船もろとも吹き飛ばし、彼らを一気に現実へと引き戻した。
「ギャアアアァァァァ────ッ!」
楽しい宴会は一転、阿鼻叫喚の地獄絵図となった。ある者は悲鳴を上げ、またある者はすべてを諦めて祈りを捧げた。狂ったように目の前の情景を必死にスケッチしている者もいた。それらすべてが等しく圧倒的な暴力によって蹂躙され、粉々に粉砕されていく。地形を変えてしまうほどの暴竜の怒りが収まったとき、そこに残っていたのはかつてカニ人だった者たちの無数の残骸だった。
「……あ、あと一歩だったカニ……次こそは、必ず我々が地上を征服してやる……カニ」
やがてそれらは海流に乗って遠い海へと運ばれ、誰も知らない場所へと流されていくのであった。
◆◆◆
ちなみに、人魚たちがいなくなった本当の理由は何かというと、水爆実験がもたらした強烈な放射線のせいであった。「お肌が荒れるから」というただそれだけの理由で彼女たちはあっけなくその海域を離れてしまったのである。
人類はギリギリのところで滅びの危機を脱した。実際、レビアタンが駆けつけていなければ恐らくカニ人は地上進出を果たし、人間社会に壊滅的な被害をもたらしていたに違いない。人魚族はカニ人に対する防波堤の役目を果たしてくれている。彼女たちの存在あってこそ人類は今日まで滅亡を免れてきたのだ。
だが、もしそのバランスが崩れることがあったとしたら……。我々が自らしでかした何らかの行為によって、人魚が海からいなくなってしまったとしたら。その時こそ人類は思い出すかもしれない。我々は狩る側ではなく狩られる側の生き物なのだと。
はるか遠い昔、太古と呼ばれる時代も──そして今現在も。
人類は、危険な綱渡りを続けているのだという事を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
