
【MBA/体験記】第25話「合理的経済人に花束を」
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
前回の『能ある鳩はMBA』では、
「ビジネススクールにはどんな先生たちがいたの?」
「どうやってゼミを選んだの?」
について見てきました。
今回は、行動経済学の授業の経験をとおして、人間心理の奥底へと迫っていきましょう。
1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!
合理的経済人とは
さて、さっそくいつものビジネススクールで覚える声に出して読みたい単語がでてきました。
「合理的経済人」とは、伝統的な経済学が想定する人類のことで、
「常に合理的に考え、かつ個人主義的に行動する」
人間のことです。
客観的に見て少しでも損のありそうな事象に遭遇したときはすぐにでも、
「ああ あれは やめた」
と決断できる合理性を持った人間ですね。

しかし人間、なんでもかんでもそう、頭に血を昇らせずに意思決定できるものでしょうか。
怒りに我を忘れるときだってあるはずです。

というわけで、
「常に合理的に考え、かつ個人主義的に行動する」
という伝統的な経済学が基準にするような人類は存在しないだろう、という当たり前の考えを大真面目に語り始めたのが行動経済学なわけです。
そういうわけで現在、「合理的経済人」というのは、
「そんなヤツ、現実に存在しねーよ、バーカ」
という文脈で使われているので、語感がいいからといって、上司を称賛するときに「なんだか合理的経済人みたいですね」とはくれぐれも言わないようにしましょう。
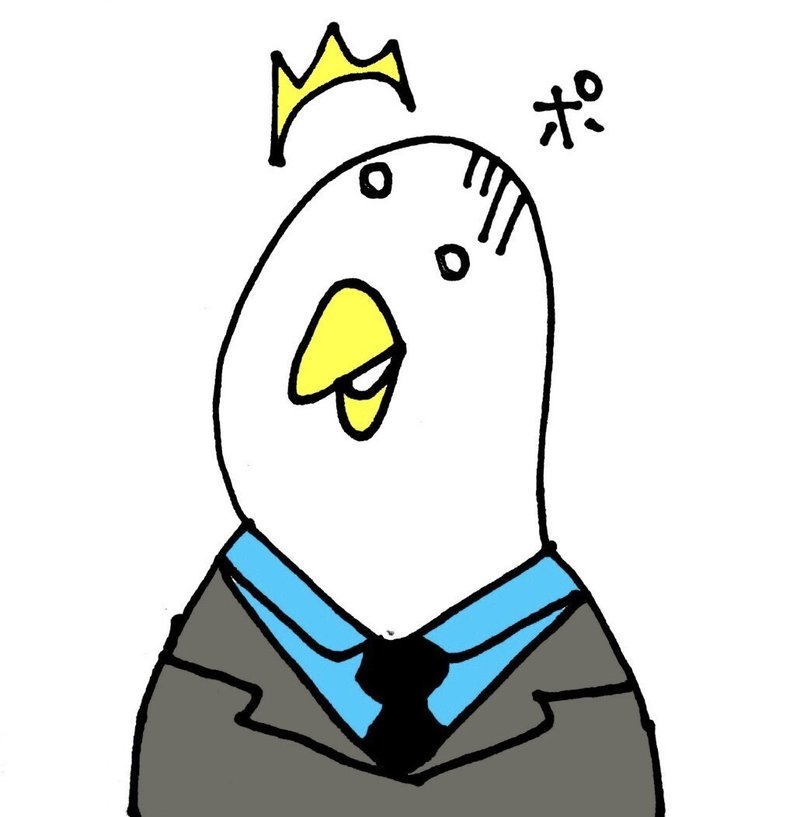
ナッシュ均衡と数当てゲーム
さて、鳩が出席したビジネススクールの行動経済学の授業では、この合理的経済人について説明するために、次のようなゲームを行いました。
これは有名な「数当てゲーム」ではありますが、『論理パラドクス・心のワナ編』に同様の事例が挙げられていたので、以下、引用します。
10人が各自、0から100までの好きな実数を、他の9人に知られずに選び、審判に提出する。
審判はその10個の数の平均値Xを計算し、それに0.9をかけてYとする。
この値Yに一番近い数を選んでいた人だけが1千万円を獲得する。
つまり、みんなの選んだ数の平均値の9割にあたる数を推測せよ、というゲームである。
さあ、みなさんはどうお考えになりますか? 少し、考えてみてください。
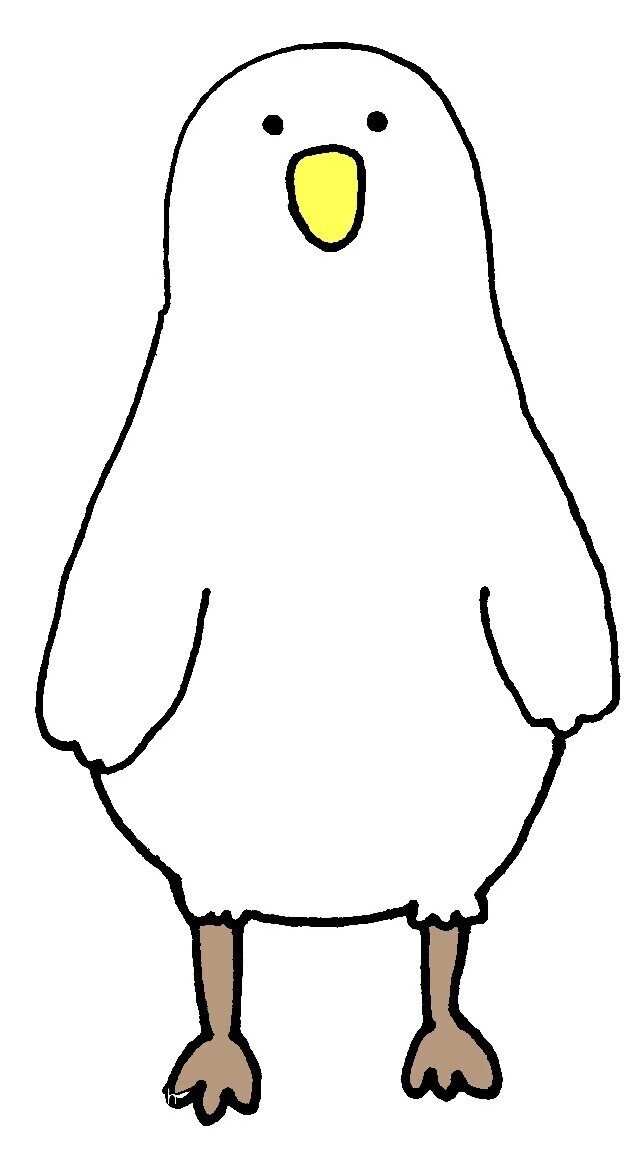
かりに全員が100を選んで、平均値が最大の100をとったとしても、
どうせ正解はそこに90%かけて得られるのだから、
90より大きな数は正解ではありえないことが容易にわかる。
したがって、あなたも含め10人のプレイヤーが「とくに頭が悪くない」人々ならば、90より大きな数を選んでいるはずがないだろう。
(中略)
かりに全員がギリギリの90を選んで、平均値が細田の90をとったとしても、
どうせ正解はそこに90%かけて得られるのだから、
81より大きな数は正解ではありえないことが容易にわかる。
(中略)
もうおわかりだろう。
「とくに頭が悪くない」といえる程度の、いわゆる「合理性」を備えた人間がこのゲームをすると、
この推論が無限に繰り返されることになり、そのつど適正な正解は小さくなってゆく。
そこで、合理的経済人は答えを「0」と予想する、というわけです。
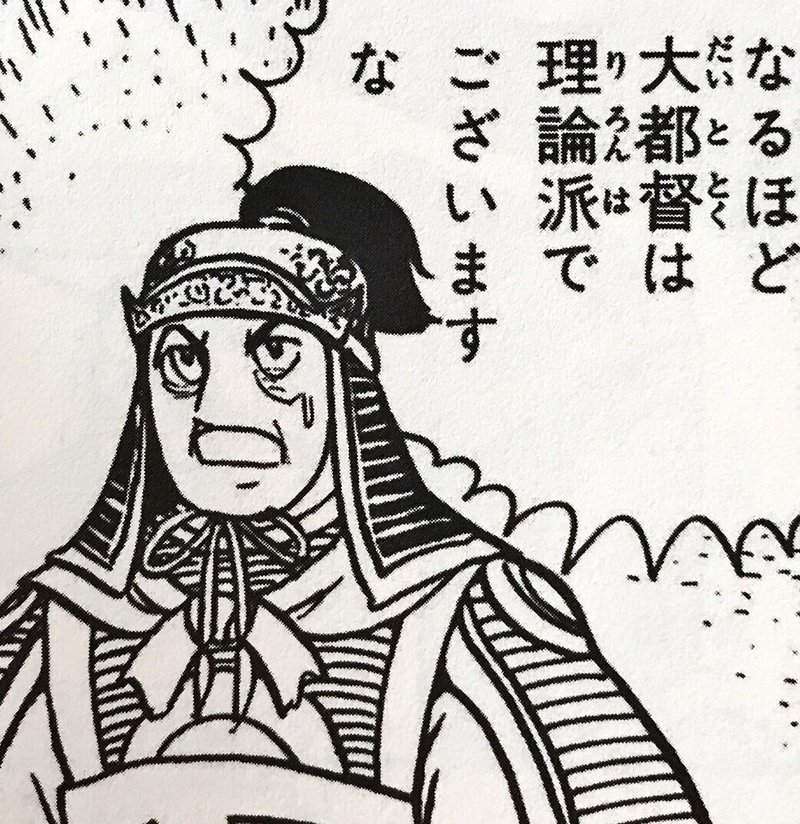
このように、
「参加者全員が完全に考え抜いた末にもたらされる戦略の均衡点」
のことを、「ナッシュ均衡」と呼びます。
参加者全員が最も合理的な行動をとった結果、自分が戦略を変えると不利になってしまうため、誰も戦略を変えない、という状況ですね。
ただし、これまでも指摘したとおり、人はとことん合理的に動くわけではなく、直感や感情などに左右されます。
実際にこのゲームを授業でやったとき、正解は「13」となりました。
ちなみにこのときの鳩は、周りの人間に対し、
「みなさんも答えを『0』にした方がいいですよ」
と布教して回ることで人為的に答えが「0」になる状況を目指そうとしましたが、あえなく撃沈しました。
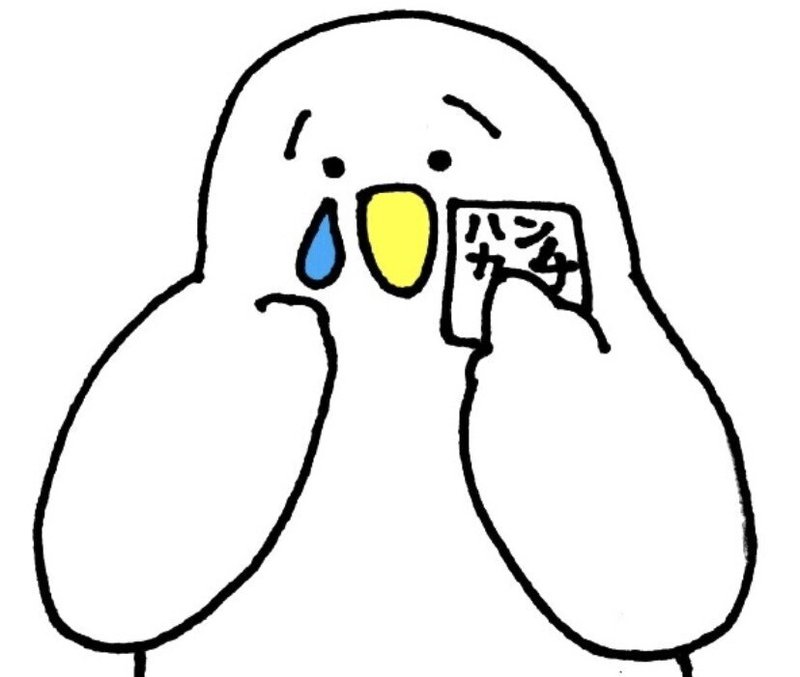
正常性バイアス・バイアスと正常性バイアス・バイアス・バイアス
さて、みなさんは「正常性バイアス」をご存じでしょうか。

自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性のこと。
自然災害や火事、事故、事件などといった自分にとって何らかの被害が予想される状況下にあっても、
それを正常な日常生活の延長上の出来事として捉えてしまい、
都合の悪い情報を無視したり、「自分は大丈夫」「今回は大丈夫」「まだ大丈夫」などと過小評価するなどして、逃げ遅れの原因となる。
wikipedia「正常性バイアス」より
(2021年4月16日閲覧)
投資家の行動などにも、この正常性バイアスは表れます。
価が下がり始めても、
「自分だけは大丈夫」
「今回は大丈夫」
「まだ大丈夫」
などと信じて、損切りができない心理にも正常性バイアスは関係していますね。

さて、ここで自分が合理的経済人になったつもりで、
先ほどの「数当てゲーム」で常に相手の裏を書こうとしたときと同じように、
「正常性バイアス」の裏の面を考えてみましょう。
その名も、「正常性バイアス・バイアス」です。
「正常性バイアス・バイアス」とは、自分にとって都合の悪い発言が出ると、
— 白山 鳩/MBA/体験記@note (@mbapigeon810) April 6, 2021
「それは正常性バイアスではありませんか」
と全てを正常性バイアスで片付けてしまうバイアスのことである
そして、こいつのさらに裏を書いたものが、
「正常性バイアス・バイアス・バイアス」
です。
「正常性バイアス・バイアス・バイアス」とは、
— 白山 鳩/MBA/体験記@note (@mbapigeon810) April 6, 2021
自分に対して、「それは正常性バイアスではありませんか」と発言してくる人間を、
「こいつは全てを正常性バイアスで片付けてしまうようなバイアスにかかってるからのだ!」
と思い込んでしまうバイアスのことである。
さてみなさん、
このさらに上を行くと、
「それは正常性バイアスではありませんか」と発言してくる人間に対して、
「『こいつは全てを正常性バイアスで片付けようとしているのだ』と思い込んでしまうバイアス」
がこの世に存在していると思い込んでしまうバイアス
という「正常性バイアス・バイアス・バイアス・バイアス」に陥ることもありえますね。
鳩自身も、自分で言っておきながら、だんだん何を言っているのかわからなくなってきました。
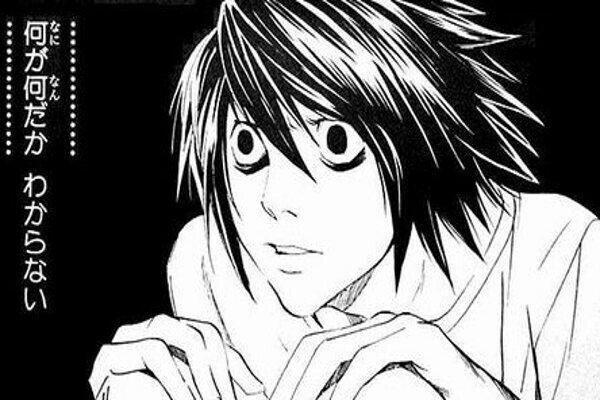
合理的経済人を意識した生き方は疲れますね。

なのに机上の空論を選んでしまう
ここまで、「あらゆることを合理的に考える人間」のことを散々あざ笑ってきました。
しかしそれでも我々は、ときに合理性だけに基づいた行動をとってしまうことがあります。
いわゆる「机上の空論」というヤツですね。
行動経済学の授業では、
「もはや老害にさしかかった会社の会長が、
既に経営的には斜陽産業と化した創業事業に固執しているとき、
どうやってこれを手放すことを説得するか」
というテーマでのディスカッションがありました。
最初に手を挙げた生徒が、
「メリット・デメリットを比較して説明します」
と発言したのですが、先生に、「そんなMBA的発想が通用するわけないだろ!」と一蹴される事態に。
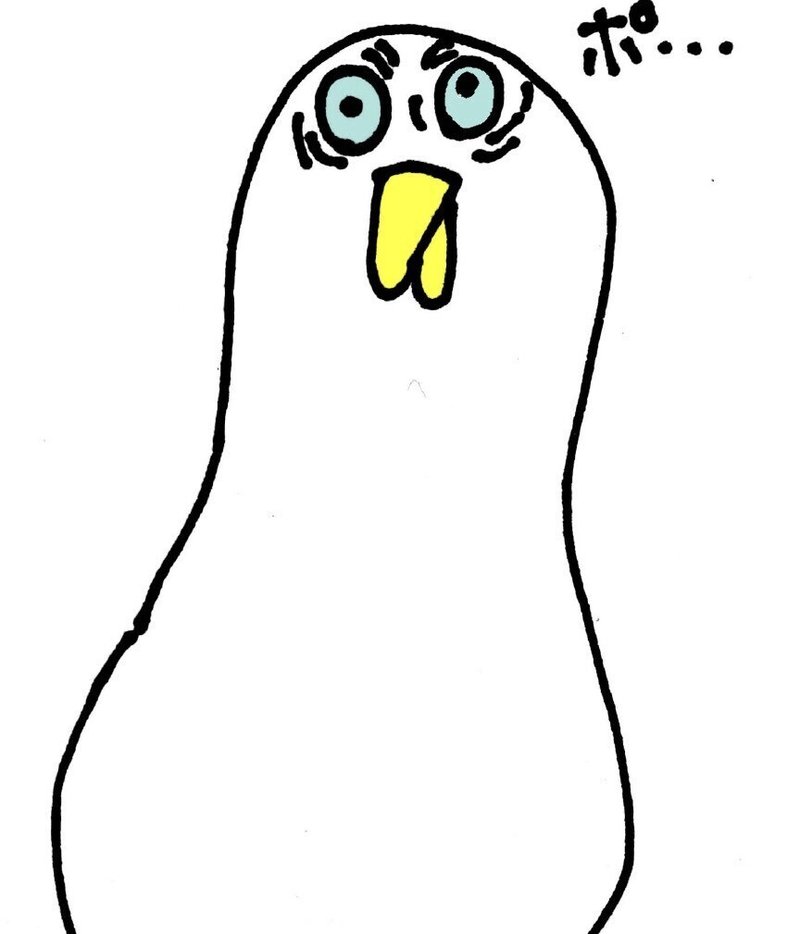
「『負け犬の創業事業』でV字回復?
出来らあっ!
と言っている人間に対してだね……」

「正面から論理的な説明をして、聞いてもらえると思いますか?」
と、先生は実にごもっともな話をされました。
「いきなり正面から理論で切り込むのではなく、
まずは相手の持っている人間としての性向に寄り添っていくというのが、
行動経済学の使い方だよ」
という、まとめで授業は終わったのでした。

次回、能ある鳩はMBA第26話「暗いオンラインで待ち合わせ」
お楽しみに。
to be continued...
参考記事:他のマガジンも見てね
行動経済学の考え方については、別のマガジンでもまとめています。
参考資料
・挿入マンガ①~③:横山光輝『三国志』(潮出版社)
・挿入マンガ④:大場つぐみ(原作)小畑健(作画)『デスノート』(集英社)
・挿入マンガ⑤:牛次郎(原作)ビッグ錠(作画)『スーパーくいしん坊』(講談社)
・三浦俊彦 (2019)『論理パラドクス・心のワナ編 人はどう考えるかを考える77問』(二見文庫)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
