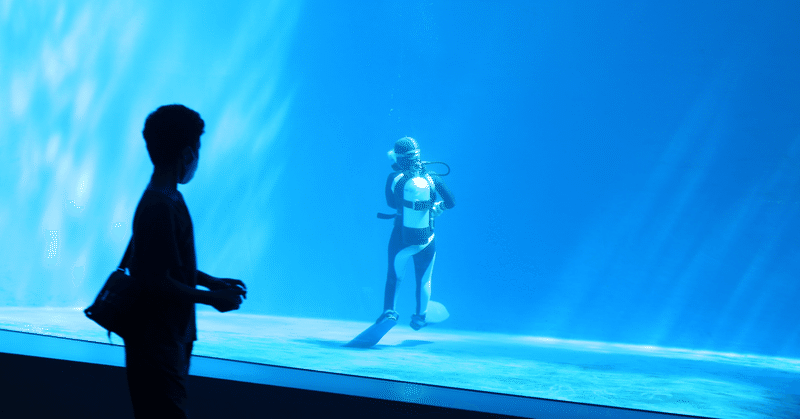
読書感想 見えているものを言葉にするってムズイ
今日は、久しぶりの平日休み。
昨日は、勤労感謝の日なのに、勤労してきた。
「今まで勤労してきた自分、お疲れ様!」と労うことだけが勤労感謝じゃないよね。
「勤労できることって有難いね!」と思うことも勤労感謝のはず。
だから、昨日働いたのもオッケーということで!笑
さて、今日も読書感想をしていこうと思う。
今日の本は、「観察力の鍛え方 佐渡島庸平著」である。

最近は、認知の本ばかり読んでいる気がするな。アートだとかデザインだとか。
「見えている(見ている)ようで見えていない(見ていない)」
とどこかで思っている自分が最近強いんだろうな。
見え方(見方)を知りたいと思っているのだろう。と自己分析。
半分読んだところで、思ったこと。
「見えているものを言葉にすることから始まる」
ということ。
厳密に言えば、「見えているものを言葉にすること」はセクションでいうと「0」で
セクションが始まる「1」は、言葉を使って「仮説」を立てること。
そして、「2」が観察。「3」が問い。
そして、また仮説に戻る。
このサイクルを回していくと、観察力が鍛えられるのだと言う。
「見えているものを言葉にする」
英語で言うと「ディスクリプション」をすること。
例えば、今私の目の前に、みんなが大好き「源氏パイ」がある。
俺はあまり好きではないと非難しないでください。
この源氏パイを、ディスクリプションしてみる。
ハートの形よりもやや丸みのある形をしている。
グラニュー糖だろうか、パイの周りは糖でコーティングされている。
キラキラ光っている。
パイの生地は縦に引き詰められていて、下の丸み部分は生地も丸くなっている。
食パンと同じ構造をしている。耳のようなものがある。
このように見えていることの言葉にしていく。
大事になるのは、主観的な感想を徹底的に排除すること。
客観的に事実のみを言葉にする。
自分の解釈、感想と事実を分けないと、観察が止まるから。
この解釈と事実がごちゃ混ぜになることは、あるあるだ。
私も例外なく、ディスクリプションをするときに、主観的な感想を入れてしまっていた。
源氏パイをディスクリプションするときも、打ってみては、
「待て待て、これは私の解釈じゃないか」
とdeleteする。
すみません。できている風に見せていました。
何を打ったかというと「この源氏パイは、金太郎飴のような切り方をしている。」
と勝手に予想して、ディスクリプションとしようとしていた。
自分の予想を事実にしてしまおうとしたのです。
ダメダメですね。勘違い野郎です。
んー、、、なかなかムズイ!!
だから、ディスクリプションは意味があるのだろうと思う。
観察力を上げるためにも、noteにでも書いてみたい。
あと本書で出てきて(本当は本書で出てくる前に自分で見つけた!嘘じゃないです)、すごいと思ったのは、
「Google Arts &culture」
やっとこのサービスにたどり着いた私は、時代遅れですかね、、、
フェルメールの「牛乳を注ぐ女」を「Google Arts &culture」で調べると、
詳しく説明してくれます。
ちゃんとピンチインしてくれて、とても見やすいし、UIも魅力的。
これは、面白い!
いろいろ調べてみたくなった。
徹底的に真似ることも本書で書かれている。
「Google Arts &culture」注目です。
最近は分からないことがあると、すぐにググる。
検索力(私は、検索ワードに何を入れると調べたい内容が出てくるかが分かる力と定義)が間違いなく、使える力だと思う。
「Google Arts &culture」も調べたら出てきて、威力に驚いた。
職場で懸賞で当たった商品を見て、同僚から一言。
「これがいくらかググってみよう」
それを聞いて、私の心の中で
「何でもかんでも調べるのもどうなのよ!」
プレゼントしてもらったものがいくらか調べるのだけはしたくない。
知らなくてもいいことってあるよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
