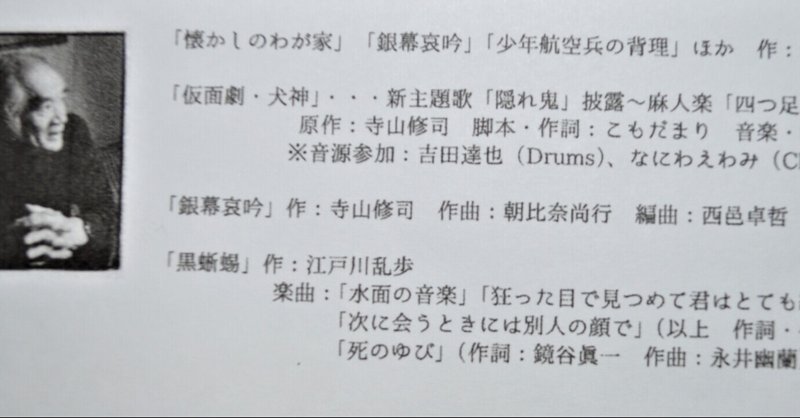
昭和精吾事務所「氾濫原3」
言葉というやつが、なりたいものになろうとする願望は人間のそれとはおおよそ比較にならない。
なにかになりたいという願望や欲望なしに、言葉は言葉でありえない。
言葉はいついかなる時にも何かになりたがっているし、
人間の思考力とは別次元で、何かになる自分(自分たち)を考えていて、何かになっている。
昭和精吾事務所「氾濫原3」のテーマは、<命懸けの恋>。
なりたいものになろうとする欲望の喚起が充満する言葉なしにはありえない恋愛、テンション上がるじゃないか。
上がり過ぎちゃったんだけどね、観ていて聴いてて......
じつは観劇の数日前から「断食」をしていて、神経が鋭くなりすぎ、幻覚と幻聴が過剰に襲ってきた感もあるにはあるが。
この公演では、音楽でステージを震撼させるのが昭和精吾事務所・音楽監督の西邑卓哲さんだけでなく、永井幽蘭さんも出てくれて、さらに10日のマチネでは幽蘭さんが『死のゆび』をやるというので、私は公演を見る時には自由席の場合、たいてい最前列に座るのだが今回も真ん前の、幽蘭さんが弾くピアノのそばに座り込んだ。
まず初めに、寺山修司の詩の朗読。バサラな出で立ちのような外観の創り込みが、朗読によって、ひじょうに淡々とした味わいになる。しつこさがなく、静然としているのだが、過剰なイメージがたっぷりと蓄積されている。
言葉が初めにあって、その後ろにストーリーの影かたちが付いてきている。
詩であってもストーリーがちらつき、言葉が濃厚に覆っている。「少年航空兵の背理」には特に、そこを掴めた。
*
「氾濫原3」初めっから終わりまで「ふてぶてしさ」の連続だった。
朗読劇が、こんなにもぶあつく、ふてぶてしく聴こえるとは。
恋愛がバトルだから、言葉がふてぶてしさを得たのか。そうなのかも。
永井幽蘭さんの『水面の音楽』に導かれるように、乱歩の『黒蜥蜴』がステージに立ちあがる。女賊<黒蜥蜴>と対決する名探偵・明智小五郎。黒い宝玉のような黒蜥蜴の、こもだまりさんと、辻真梨乃さんの・・・明智?
おおっ、
こんなにも綺麗で可愛い明智に出遭ってしまうとは!!!
満島ひかりがNHKのドラマで披露した、耽美の化身ともいうべき明智小五郎を瞬時に忘却......
いやいや満島ひかりの明智も最高なんだがwww
断食で冴えわたった俺の五感におしよせる乱歩の言葉を、脈々と謳いあげてくる明智小五郎が、こんなにも麗しくて、健気で、儚くて、未曽有の妖しさにみちみちているなどとは・・・#おい冷静になれ
幽蘭さんの音楽に導かれると書いたのは、演者たちが時折、朗読のことばを発せず、息を呑むようにうつくしいマイムを、音楽とともに披露するのだ。
『狂った目で見つめて君はとても綺麗』『夜のほとり』まるで乱歩のために作曲したかのような永井幽蘭の曲と歌とともに、マイムにも言葉が蓄積されていて、聴く喜びはパノラマ仕掛けの幻惑のようにひろがっていく。
かつて舞踏の公演を貪っていた頃に聴いた話だが、薄物を纏って踊るというのは、写本のページを巻き付けることをイメージするのだとか。その話を聞かせてくれたのはアフリカや中東に長く暮らしたモルドヴァ人で、その人もダンスをおやりになっていたのだが、とすると舞踏には、言語の氾濫が籠められているということになる。
そして『死のゆび』は奏でられ、歌われた。『黒蜥蜴』のなかでもとりわけ好きな、黒蜥蜴とその部下の松吉(に化けた明智)の対話の直後であるから喜びもひとしお。マイムの美しさもひときわ染み入る....
なるほどと思ったのは、『死のゆび』には<言語の氾濫>という面が確実にあって、昭和精吾事務所もそこを見てくれていたのだなという事。白蛇(しろへび)と、黒蜥蜴のからみあいとは、そうそう味わえるものではない。
....などと、美食の余韻に耽る心地をもぎ取るように響き渡る、『次に会うときには別人の顔で』。荘厳な切なさが、明智と黒蜥蜴の決着と、黒蜥蜴の最期を見守る。
歌詞のなかでも、とりわけ切ない場面を・・・永井幽蘭ではなく、黒蜥蜴が歌う!命懸けの恋!
好敵手から永遠の恋人となった明智が女賊終焉を朗々と謳いあげると、我知らず、マスクの奥から嗚咽がこみあげてきた。
『黒蜥蜴』が音楽と朗読の背の高さがほぼほぼ均等な相克劇だったのに対し、『ロミオとジュリエット』では朗読が、頭ひとつ分くらい突き出しているように思えた。朗読は『黒蜥蜴』よりも光と影の濃さを増している。
ぶあつくて、ふてぶてしいと前述したけれど、『ロミオとジュリエット』の場合はそれがひときわで、この劇って、<愛によって人間性の普遍を描いた物語>というとらえ方をしがちだが、それは美化し過ぎではないだろうか。ロミオはジュリエットに出会うまえは、別のひとを愛しまくっていたのに、ジュリエットが現れるとさっさと前の恋人から心が離れていくような図々しく、ふてぶてしい男であるのだと、長田大史さんのロミオをみていて(聴いていて)思わずにいられなかった。
つまりロミオとジュリエットは、「人間的であり過ぎた恋人愛を描いた物語」なのだと、今回の「氾濫原3」でそういう思いを改めて噛みしめたのです。
西邑卓哲さんの音楽が、これが凄く良かった。イタリアの武家貴族の屋敷で鳴らされるリュート曲の、「緊張感の高さ」だけを抽出したギター曲を、朗読の緊張感と咬み合わせている。ここは咬みあい過ぎてもいけないのだと言わんばかりに、朗読と音楽がおたがいに「不連続面」を、わざと作っている。
思い返しても、異様な緊張感が張り詰めたロミオとジュリエットだった。これは朗読劇だから出せる緊張感なのだろうか。梶原航さんのロレンス神父の、口調とまなざしの冷え切った否応なさ。これほど冷酷なロレンス神父には初めて出会った。ある小説家が「夜の死体は底なしに白い」と書いたのが脳裏で炸裂する。永井幽蘭の曲も冴えわたる。ロレンスとロミオとのすれ違いが、冷酷な夜の視界をひろげる。
もはやストーリーなど弾けとんで言葉と音楽の表裏一体だけがそこにある。目の前には、終焉でもラストでもない、完璧な構図の沈黙がよこたわり、『月の雫 星の涙』の静かな静かな「語りかけ」が、愛し合うふたりの死に降り注ぐ。
『仮面劇・犬神』が、短かったけれど炸裂の度合いが最も強烈で、もしあの中に投げ込まれたらどうなるのか・・・・と思うと狂喜しそうな世界だった。
西邑さんの音楽はまったく凄い。マクロコスモスの膨張の中心に、すべてを捨てて飛び込みたくなる。
10日のマチネでは、この回だけのスペシャル朗読者として常川博行さんが登壇し、寺山修司の『読まなくていいあとがき』を朗読した。
死にみちあふれた夜が明けて、田園に朝がやってきて、お味噌汁といっしょに胚芽米をたっぷり混ぜたご飯を食べるような味がひろがった。
そして『曾根崎心中』。
公演のテーマは命懸けの恋、なのだが、興味深いことに朗読の骨格を見ると、ロミオとジュリエット」と「曾根崎心中」は男性ふたりの相克が重心になっているのが面白い。徳兵衛と九平次の対話がぶあつく、徳兵衛を破滅へと陥れる九平次の呪いの言葉のひとつひとつが火にくべた鉛の重たい活字であり、徳兵衛の、怨みの調をたたえた血の涙の湿り気が終焉まで残留する。
公演をみるまえに、脳内で『曾根崎心中』の人形浄瑠璃を、『死のゆび』の人形時計になぞらえた妄想をひねり回していた。『死のゆび』は、『曾根崎心中』で弾くのかな....と。
公演の実物は、けっこう生々しい芝居の姿でせめてきたので、おおっ、こうきましたかと。
妄想のうえをゆく、肉厚な江戸芝居の言葉が礫のようにとんできて、冬の幻影がめらめら立ち上ってくる。
肉厚と言えば、辻真梨乃さんによる、講釈師調の朗読の説得力も凄い。
クライマックスは燔祭の人身御供のような徳兵衛とお初の終焉。
火盤の上の生首のような終焉のような九平次にも奸雄の風格が。
徳兵衛とお初の、舞台のそとへと走っていく終幕には、静寂だけがひろがる。
公演のラストは絶対に『アメリカ』だろうと思っていたが、やっぱり。
「裏返しの柔弱」のような、幼劇の、圧倒ではあっても、骨太には決してならない、行方を詛う握りこぶしのなかで、征矢の束を握りしめるようにアメリカの星条旗は丸まったまま、決して広げられることはないのだろう。
じっと聞いていると、息が続かない。彼岸まで心身もろとも攫われていきそうになる。『曾根崎心中』の終幕がつくりあげた静寂に降りてきた、言葉だけが、聴く者の咽の渇きをどこまでも膨張させる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
