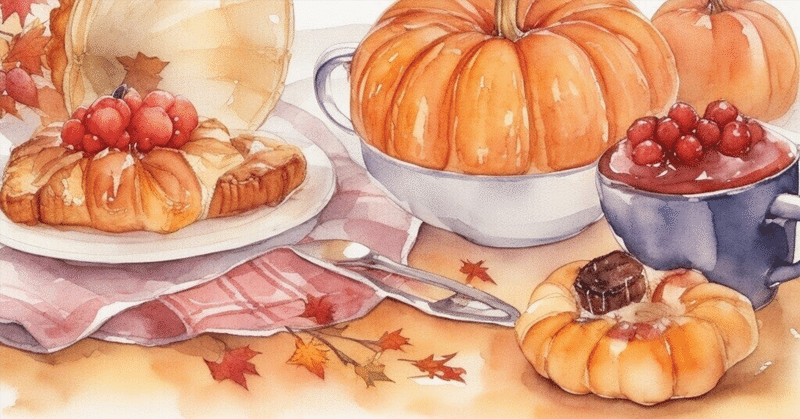
『ケーキの切れない非行少年たち』②
前作はこちらをご覧ください。
本記事は、話題になった『ケーキの切れない非行少年たち』を批判的に考察することを目的としていますので、ご了承ください。
さて、今回は筆者の描く「犯罪者の異常性」について考察していきます。筆者は人を刺した少年を例に出して以下のように述べています。
ある少年は、人を殺してみたくてある成人の方を刺しました。しかし、幸い一命をとりとめ、その少年は少年院に入ってきました。数年いて出院する直前になり、私との面接の流れの中でその少年はこう切り出しました。
「法務教官の先生には叱られるから殺したい気持ちは”なくなりました”と言ったけど、実はまだ消えていません」
「またやってみたい」
その少年がニヤニヤしながらそう答えていたのを鮮明に覚えています。
これは、別の記事でも指摘したいと思っているのですが、筆者はこのように「犯罪者の異常性」を描くことが多いなと感じます(ここでは「ニヤニヤ」など)。犯罪者の異常性自体は「犯罪を犯す」という点からも、否定はできないのでしょうが、本書では「犯罪者=知的障害者や発達障害者」というカテゴリー分けを随所で採用しているので、「知的障害者や発達障害者」も「異常」なのではないかとミスリーディングさせる恐れがあります。
実際、上記引用の後にはASD(自閉スペクトラム症)を例に出して、以下のように述べています。
特に自閉スペクトラム症(ASD)をもった非行少年は独特のこだわりをもっている感触があります。そのこだわりがいい方向に向けば素晴らしい偉業を成し遂げることに繋がったりするのですが、例えば”人を殺してみること”という方向に向いたなら、それを消すことはなかなか難しいことがあります。
この一文を読んだ、ASDを持つ子の親はどのように感じるでしょうか。僕は支援級担任の経験もありますので、自分が過去に受け持ったASDを持った子どもたちを思い浮かべながら、悲しい気持ちになりました。
彼らに「独特のこだわり」があることは否定しません。手をヒラヒラさせたり、換気扇をずっと眺めたりすることもあります。しかし、だからと言って「人を殺してみる」というこだわり(それを「こだわり」というカテゴリーで呼んでもいいのだろうか。倫理的に気になる。)を例に出すのは、あまりにも無神経なのではないでしょうか。
さらに、ASDの話の後には、長崎・佐世保での女子高生による殺害事件を例に出します。つまり、ASDの文章の前には「人を刺した少年」、後には「殺害事件」を入れ込む文章構成になっているのです。これでは、まるでASDを持った人が「人を刺し」たり「人を殺したり」するような誤解を招きかねません。
本書を通して感じるのは、筆者の持つ「障害への忌避感」です。そして、それを「改善するための方法」としての、筆者考案の「コグトレ」の推奨です。しかし、障害を持った子どもたちを本当に支援したいと思うならば、彼らの持つ「特性」を「犯罪を犯す異常性」と結び付けずに、彼らを「障害者」でなく「一人の人間として」関わる方がよほど健全ではないでしょうか。
