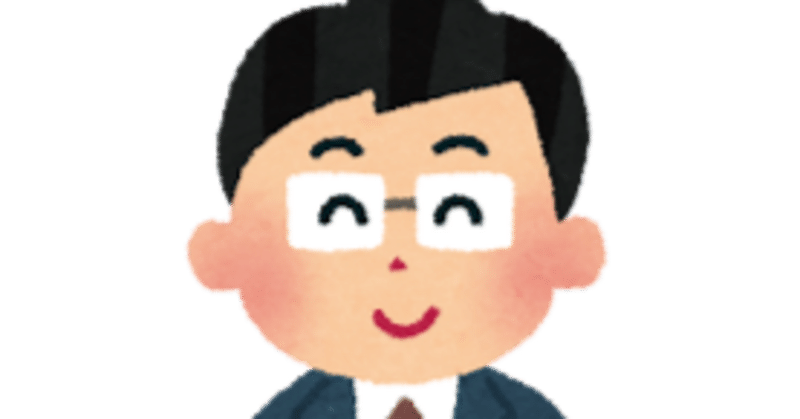
ASDがチームリーダーを目指す
ASD(自閉症スペクトラム障害)はリーダーになれないのか
マネージャーやチームリーダーに求められるスキルの一つが、複雑な問題に対して方向性を示す決断力です。しかし、決断力を発揮するには、①部下の感情や文脈を咀嚼し ②時に自分の経験則と異なる判断を下す という2ステップが要求され、これら2ステップの両方がASDにとって苦手とする分野になります。2023年は「決断力の欠乏」に悩まされましたが、ようやく光明が見えてきました。
拘り特性を克服する「ドキュメント文化」
私のASDとしての特性の一つが拘り(こだわり)です。決めたことに対して誰かに変えてほしいとお願いされたとき、変更を受け入れることが人よりも苦手です。友達とご飯を食べに行くとき、一旦イタリアンにすると決めた後、ほかの店の前で「やっぱココにしない?」と言われようものなら、頭が真っ白になって立ち尽くしてしまうくらいには酷いです。
そんな私がエンジニア仕事で愛用しているのが業務手順書です。今までに携わったエンジニアの開発業務について、注意点や達成条件を書き記したドキュメントになります。この業務手順書が、拘りの克服に非常に役に立ちます。
エンジニア業務は変更が日常茶飯事ですし、しかも、上長が口頭で変更を打診してくることが多いです。お客様のために必要な変更であっても、急に言われると頭が真っ白になります。こういう時に業務手順書があると、自分の拘りが合理的かそうではないかを直ぐに判断できます。手順書に書いていない項目で拘っているならば、基本的には現状維持に足る理由ではない(=しょーもない理由)と判断します。ドキュメントを用意したお陰で、ASDの自分でも柔軟に業務を回せるようになってきました。
会議のお供に業務手順書
業務手順書には、要件や手順を定めた背景まで書いてあります。背景が役に立つ場面が会議です。ASDの私には、会議はかなり過酷です。参加者の喋っている内容が明文化されず、文脈によって会話が進んでいくからです。文脈を追うには頭のリソースを全て投入しなければいけません。
周りに付いていくのがやっとの状態で「では、○○について異議のある方はいますか?」と合議になると、通常の状態では応答できません。ちょっと待ってください!と言っても、与えられる待機時間は数十秒といったところ。そういう場面では業務手順書の該当箇所をガーっと開き、「2020年に○○でトラブルが起きています、こちらの資料をご覧ください」と該当箇所を画面に表示するのです。私が饒舌にしゃべらなくても、私の手順書が全てを語ってくれます。これがとても心強いです。
終わりに
ASDは発達障害のひとつであり、チームワークを重視する会社や組織において不利になりやすい特性であることは、まあ、認めざるを得ません。しかし、それを理由にしてキャリアを諦める必要はないと思います。今の立場でやれる範囲でやれば良いと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
