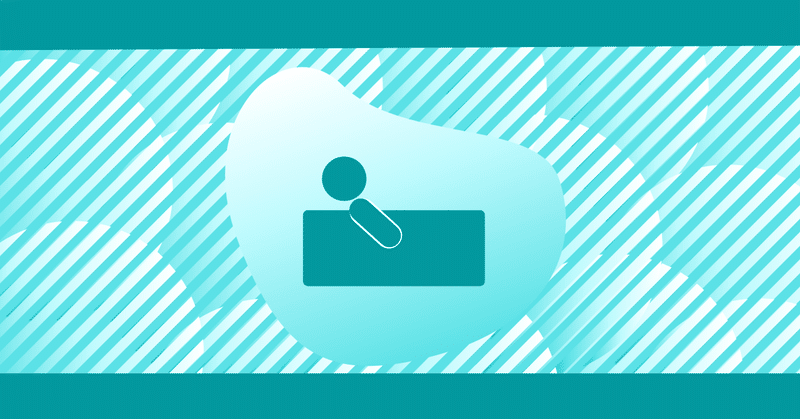
愛人の終わりに
「愛人業のひとなんて見たことないな」と思っていたのだけど、意外に身近にいた。母が住んでいるふたつ隣の家の人が、現役ではないが、ある男性の愛人として生きたらしい。まだ存命なので「生きた」は失礼かもしれない。
年齢がいくつなのか知らない。たぶん70前後だろう。みんなからは「タカコ先生」と呼ばれている。いちおう仮名だ。かつてピアノを教えていたとかで、先生と呼ばれている。地元にはそれなりに教え子もいて、時たま電話をしては菓子折りを持って来させるという。
菓子折りを持って来させる。まずこの発想が自分にはないなあ、と思う。ひとから何かを貰うのに慣れた人は、そんなものなんだろうか。お菓子って好き嫌いがあるけど、もらって困るものとかないんだろうか。
タカコ先生は、もともと裕福な男性の愛人として長く暮らした。男性の奥さんのほうは何も知らなくて、気づいたら夫がタカコ先生と別荘暮らしをしていたらしい。子育てを一人で担っていた奥さんの気持ちは、どうしたって気持ちいいものではなかったと思う。
それでもタカコ先生の愛人生活は続き、景気のいい時期にはゴルフ三昧だったらしい。やがて男性が死ぬと、今度は地元に帰ってきて「彼氏」なるひとにお世話になる。「彼氏」は、性的な関係は一切迫ってこないで、ただただタカコ先生に尽くす人だった。
わからん、と思う。何をどうしたらそういう人生になるんだ。人間をやってそれなりの時間が経っているはずだけど、世の中にはまだ私のわからないことがたくさんある。そしてその大半は、わからなくてもいいことなんだろう。
とはいえ、実際わからんものを前にすると、これってなんなのかなあと疑問がわく。男性を次々に頼って生きる人生は、どうやって出来上がるんだろう。自分にとってそれは、まるでサーカスの曲芸みたいだ。
タカコ先生の人生を簡単に説明してしまえばそういうことで、ずいぶんイージーモードに見える。でも実際にはそうイージーでもないのは、ほとんどの人が推定70前後になった彼女と付き合いたがらないあたりに見て取れる。
事実、タカコ先生は「彼氏」が死んだとき葬式に呼ばれなかった。ひたすら彼女に尽くしてきたはずの男性でさえ、最後には彼女のことを疎ましく思うようになっていた。無理もなかった。タカコ先生はわがままで恩知らずだったから。
夜中に水道管が壊れたと彼氏に電話し、彼氏の知り合いが夜間にも関わらず出てきて直してくれた。むかしほど裕福ではないタカコ先生は、修繕代を値切った。すべてがこの調子だから、最終的には誰もが嫌になってそのそばを離れてしまう。
うちの母は、それでもなぜかタカコ先生を放っておけなくて、ときどき家に顔を出す。そのたびに「これを料理してくれ」とタダで使われたり、他人のあらぬ愚痴を聞かされたりしながら、やっぱり時々は様子を見に行くらしい。
「放っておけない」と思わせる才能のある人、なんだろう。タカコ先生に関する「わからない」は、いまのところそういう形を取って無理やり「わかる」に分類されている。あれは才能なのだ。
実のところ、自分は才能というものをそれほど信じてない。誰かのなにかが普通以上にうまくいっているように見えたとき、都合よく使う言葉。「あの人は才能があるから/あったから」。そんなのは、実際には何も言ってないに等しい。
誰かがそうである理由について、考えるのを止めるため、すべてをそこに叩き込む便利なブラックボックス。才能。
タカコ先生のところには、なんだかんだ通ってきてくれる知人がいて、母親はじめ近所の人々もうっすら見守っている。愛人をなりわいに生きた人の晩年として、たぶん悪くないほうだと思う。
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
