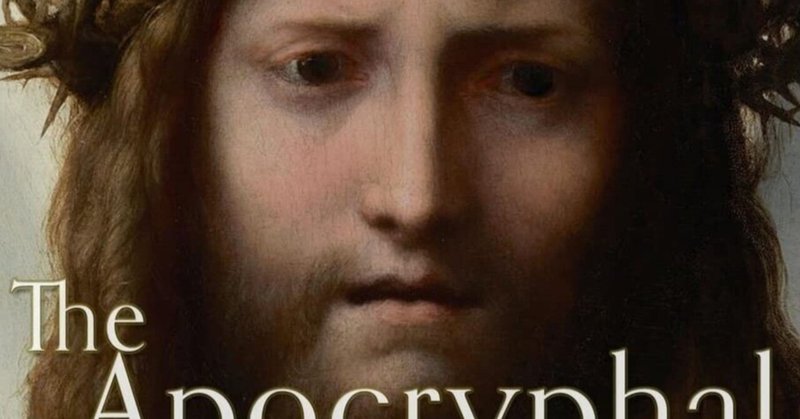
[書評] 新約外典の文献ガイド
Gustavo Vazquez Lozano, 'The Apocryphal Gospels: The History of the New Testament Apocrypha Not Included in the Bible' (2017)

新約聖書の外典を読もうとすると、あまりの数の多さに、どれから読んでいいか途方にくれることがある。そんなときに本書のようなガイドがあれば便利だ。
ただし、〈読書〉ガイドとは言いにくい。なぜかというと、本書を読んで興味を惹かれた新約外典があったとして、いざ読もうとなったとき、どの本を選べばよいかで困ってしまうからだ。
例えば、個別に本を選ぶのでなくて、新約外典をまとめて収録してある選集や全集のたぐいを読もうとしたとする。
巻末の文献リストには、その種のものが3種あげられている。ところが、最初の Montague Rhodes James 編のも、次の Wilhelm Schneemelcher ら編の2巻本も、入手しにくい(この2巻本はたまたま評者は持っているが)。
唯一、現行版として入手可能なのが、J. K. Elliott 編の 'The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation' (1994) だが、この本は、とても一般読者が買おうという価格ではない。電子書籍版は、その十分の一以下の価格だが、それでもかなり高い。評者はたまたまこの本を持っていて、良い本であることは知っているが、とても勧められない。
では、どうすればよいのか。本書には紹介されていないが、自分で個別の本の適当なものを探すしかなくなる。幸い、探せば、そういう本はあることはある。探せば、中には日本語訳があるものもある。
*
ともかく、本書はガイドとしては優秀なので、紹介されている、読む価値がありそうな本を少し紹介してみる。
本書の第4章に、もう少しで正典になりそうだった外典福音書がいろいろ挙げられている。まず、
The Gospel According to the Hebrews
がある(『ヘブル人福音書』『ヘブル人による福音書』)。ヘブライ文字のアラム語で書かれており、2世紀初頭に引用されているところから、1世紀(の後半頃)には流通していたと思われる(2世紀前半の成立とする説もある)。書いたのはマタイであるという説もある。4世紀末頃にラテン語のウルガタ訳聖書を完成させた聖ヒエロニムスが、この書のヘブライ語版の完本をカエサレアの図書館で見たという。
この書には、正典福音書に言及がない、復活のイエスのヤコブへの出現(apparition)が含まれていることが注目に値する。ただし、この出現はパウロが報告している(「次いで、キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒に現れ、」コリントの信徒への手紙一 15章7節、聖書協会共同訳)。
このように、内容が部分的に他人の引用などで分ってはいるものの、この本じたいは失われて、伝わっていない。今後、写本が発見されるかもしれないが。
ただ、断片は、聖ヒエロニムスによる引用などで、読むことはできる。参考までに、ヤコブへの出現の箇所を挙げておこう。
ヘブル人によると呼ばれ、最近わたしがギリシア語およびラテン語に翻訳し、オリゲネスもしばしば用いている福音書もまた、救い主の復活のあとに次のように述べている。「しかし主は、布地を祭司の奴隷に与えてしまったあとに、ヤコブのところに行って彼に姿を現わした」。なぜならヤコブは、主の盃を飲んでしまったあの時から、主が眠っている者たちの間から復活するのを見るまでは、パンを食べないと誓っていたからである。そしてしばらくたってまた「食事とパンを持って来なさい」、と主は言った。そしてすぐ次のようにつけ加えられる。「彼はパンをとり祝福してさき、義人ヤコブに与えて言った。『わが兄弟よ、きみのパンを食べなさい。なぜなら、人の子は眠っている者たちの間から復活したのだから』」。(断片17、川村輝典訳、『聖書外典偽典6 新約外典I』、63-64頁)
*
つづいて本書が挙げる次の書
The Gospel of Thomas
は、名前は比較的よく知られている(『トマスによる福音書』)。グノーシス派のイエス語録であるため、位置づけがむずかしい。
だが、純然たるイエス語録を114件集めた本の完本が、ナグ・ハマディ文書の一つとして1945年12月に発見されたことで、福音書の原資料の可能性(Q資料仮説)もあり、興味は尽きない。福音書の系統とは別の独立した伝承に属するものかもしれない。
いづれにしても、早ければ紀元50年に成立したとする説もあり、正典問題とは別に、歴史的存在としてのイエスに光を当てる重要な資料であることは間違いない。
20世紀最大の聖書学的発見の座は、全貌がまだ明らかになっていないオクシリンコス・パピルスに譲るとしても、分っている範囲では、『トマスによる福音書』は最も注目を集める聖書資料の一つだ。
*
本書は、つづいて
The Gospel of Truth
を取上げる(『真理の福音』『真理の福音書』)。
グノーシス派のウァレンティヌスらのグループが聖書として用いていた書といわれる。
これも、ナグ・ハマディ文書の一つとして1945年に発見された。成立は2世紀半ばとされる。
*
つづいて本書が取上げる
The Gospel of Peter
は、評者が一番興味を惹かれた書(『ペトロによる福音書』『ペテロ福音書』)。外典福音書としては最初に、1886年に発見された。
テクストは不完全であり、完本はまだ見つかっていない。
イエスの裁判から受難に至る部分の記述は正典福音書と似ているが、より短いので、こちらのほうが古いのではないかとも推測されている。
評者が興味深く読んだ十字架上のイエスの描写の箇所を引用する。
そして、彼らはふたりの犯罪人を連れてきて、彼らのまん中で主を十字架につけた。しかし、彼自身はなんの苦痛もないかのように黙っておられた。(第四章10節、小林 稔訳、『聖書外典偽典6 新約外典I』、149頁)
この続きで、イエスが十字架上で息をひきとるときの描写も引用しておく。
そして、主は叫んで「わが力よ、〔わが〕力よ、あなたはわたしをお捨てになった」と言われた。そして、(こう)言ってから上げられておしまいになった。(第五章19節、小林 稔訳、『聖書外典偽典6 新約外典I』、150頁)
『ペトロによる福音書』が特別なものであるのは、共観福音書がイエスの復活を神秘のベールで覆っているのに対し、『ペトロによる福音書』はそれを具体的に描いていることである。イエスが二人の光り輝く若い男性(二位の天使)に支えられて墓から出てくる。うしろに、十字架がついてくる。そこへ天から「(冥府の)死者たちに宣べ伝えたか」との声がする。十字架は「はい」と答える(第十章)。
奇想天外とも思える描写であるが、評者には妙にリアリティをともなって感じられる。
*
このほかに本書が第4章で取上げるのは、The Egerton Gospel と、The Secret Gospel of Mark である。前者は独立した伝承をしめすと考えられ、後者は議論の余地のある、マルコによる2番めの福音書である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
