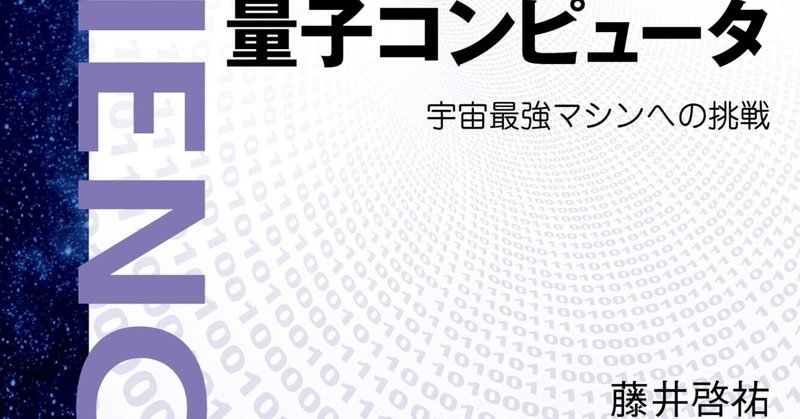
[書評] 量子力学のふしぎな性質を情報科学的な観点から理解しなおし、その量子性を積極的に応用する量子情報科学の誕生
藤井啓祐『驚異の量子コンピュータ 宇宙最強マシンへの挑戦』(岩波書店、2019)

2022年のノーベル物理学賞が「量子もつれ」に与えられたことで、世の中の視線は量子の可能性に向いている。某国が量子コンピュータを使って何やら世界を動かすようなことをやっているとも囁かれている。
現代人にとって、量子コンピュータを知ることは喫緊の課題となった。量子コンピュータとは何物なのかについて、少しでも理解できればと思う人が手に取るのにふさわしい本だ。また、未来はこういう研究をしたいという若人にこそ読んでもらいたい本だ。
著者が量子コンピュータに興味を持ち始めた2004年当時、まだ量子コンピュータの実現はSFの域を超えなかったという。それから15年経って、2019年4月に著者は大阪大学大学院基礎工学研究科教授になり、同年11月に本書が上梓された。まさに〈量子的飛躍〉を遂げたといえる。
著者によれば、2000年代半ばにおいて、量子コンピュータの実現は30年先とも50年先とも言われていたという。ところが、本書の校了時点では、〈従来コンピュータの頂点に立つスーパーコンピュータが1万年かかる計算をグーグルが開発した量子コンピュータは数分でやってのけてしまう〉段階に達していた。本当に〈量子的飛躍〉が起こっているのだ。
グーグルによる発表の報道が世界をかけめぐったのは2019年10月下旬のことであるが、著者は実はこの研究と接点がある。〈人類史上はじめて量子力学の原理で動くコンピュータが従来のコンピュータに対して数学的にきちんと定式化された問題において圧勝するという歴史的瞬間、量子超越性を達成したというのだ。私は、この論文の査読をした3人の研究者のうちの一人である。〉と著者は書く。この歴史的瞬間の当事者そのものではないか。
この文章に出てくる「量子超越」(quantum supremacy)という言葉は、2011年にプレスキル(John Preskill、1953- )がソルベー会議 (Solvay Conference on Physics) で「量子コンピュータによるエンタングルメントフロンティア」(Quantum computing and the entanglement frontier) の題で講演したときに初めて登場したという。〈量子コンピュータが従来型のコンピュータ(古典コンピュータ)よりも高速であることを指す〉(8章)。
プレスキルは「量子超越」という言葉だけでなく、現在の量子コンピュータの段階を指す NISQ 時代 (noisy intermediate-scale quantum era) という言葉の創案者でもある。
*
以下、本書で印象に残った点を拾いあげてみる。
「古典物理学」という言葉が本書に頻出するが、「古典」とは〈今でもなお高く評価される代表作という意味に近く、決して古臭いという意味ではない〉(1章「古典物理学の限界」)。
*
〈原子はマイナスの電荷をもつ軽い粒子である電子と、プラスの電荷をもつ重い原子核から構成されると考えられていたが、ここに矛盾が生じる。プラスとマイナスの電荷が引き合って潰れてしまわないためには、ニュートンの運動方程式に従って、マイナスの電荷が原子核の周りをぐるぐる回転している必要がある(まさに地球の周りを回る月のように)。一方で、マクスウェルの理論に従うと、電荷をもった粒子が回転すると電磁波を放射するため、電子はエネルギーを失い、原子核の周りを回転し続けることができない。つまり原子がどのようにして原子の形を保ち続けられるのか、古典物理学はうまく説明することができなかった。〉(1章「古典物理学の限界」)
*
本書には山ほど知的興奮にあふれた記述があるが、一つだけ、研究の未来を示唆するエピソードを紹介したい。
超伝導量子ビット(superconducting qubit)の専門家であるマルティネス(John M. Martinis, 1958- )が2014年に、量子誤り訂正のしきい値の要求を満たす超低雑音の超伝導量子ビット(5量子ビット)とそれに対する演算を実現したことが、著者に衝撃を与える。学部生の頃から量子誤り訂正の研究をしてきた著者は、実現には程遠いと思っていたからだ。
ちょうど2014年の量子情報に関する国際会議が京都で開催され、マルチネスが招待講演者として来日することになっていた。著者は、この機会に大阪大学で量子コンピュータの実現に範囲を絞ったサテライト研究会を開催することにし、そのワークショップにマルチネスを招待した。
マルチネスの京都から大阪への移動を著者が案内する途上、阪急電鉄と大阪モノレールを乗り継いで千里中央のホテルまでマルチネス教授を送り届けるあいだに、量子コンピュータ実現に向けた展望を根ほり葉ほり本人に訊いたという。そのときに著者はマルチネスから次の言葉を聞いた(7章)。
大学の研究体制では学生は論文を書いて卒業する必要があるので、どうしても基礎的であったり、論文が書きやすいようなファンシーな(見た目が派手な)テーマの研究をする必要がある。しかし、本当に量子コンピュータを実現したいなら、究極的なエンジニアリングをしなければならない。そのためにはファンシーなテーマに目もくれず、ただひたすら量子コンピュータの実現だけに興味があるギーク(オタク)たちが必要だ。今世界でそのようなギークが20人以上いるのは我々のグループしかない。このようなギークな研究者たちを我々は守り続けないといけない。
この大阪大学でのサテライト研究会の翌週、グーグルがマルチネスをグループごと取り込み、量子コンピュータのデバイス開発に乗り出すことを発表した。まさに、グーグルによる量子コンピュータ開発の前夜の雰囲気を著者は開発者本人から聞いたことになる。
*
およそ、科学(物理や数学)に関心がある人で、量子コンピュータの現代世界における役割が知りたい人は、一度は手に取る価値のある本だ。近来まれに見る名著。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
