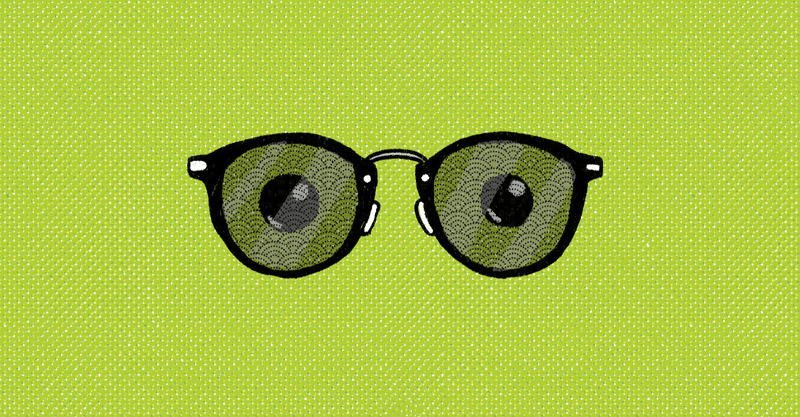
リアリティーショーとライティングの共通点
すこし前の結婚報道ニュースをきっかけに、タイムラインを流れてきたブログに目がとまった。
SEO狙いの量産される系記事なのかなと、さっとみて離脱しようと流し読みをしていたのだが、これがまんまとハマってしまって。一気読みをして次のブログもしっかりと熟読した。
その後、バチェラー1と3のポイントになりそうな部分を復習。考察ブログの内容をこの目で確かめるために2日ほど没頭した。
何がそんなにおもしろかったんだろうと考えてみると、2つのブログには制作者側の意図が書かれていた。
最初に私がバチェラーを見た時は、きれいに編集されたものを視聴者として、ストーリーを楽しむ側として、だ。誰が残るか、女の子同士のあれこれや男女の駆け引きを作り手が用意してくれた通りに楽しんでいた。しかしブログを読んで、別の(作り手側の)視点が入ってきたことで、一気に世界が変わって見えたのだった。新しく得た視点から見るそれも、違った意味でおもしろい。
*
“リアリティーショー”はここ数か月でマイナスなイメージを強くさせてしまった。「台本無し」と言いながらもシナリオの概要は書かれている、番組を面白くさせるための仕掛けはされている。嘘か本当かわからない情報が、悪のように報じられている。
もちろん“リアリティー”の範囲を超えて本人の意向と離れた行為を強いることは、あまり賛成できることではない。けれど平和な毎日をただ流すことが「視聴者が見たいもの」にもならないし、日々の撮影でどこを切り取るかは企画側の意図にゆだねられるものでもあるよな、とも思う。
あくまでこれは、リアルではなく“リアリティー”。けれど私たち視聴者は、作り手のフィルターが入ったその人を“リアル”だと思い込み、その側面だけを見てコメントをしてしまうのだ。
人の言葉や行動を切り取って記事にする、編集者やライターにも同じことは言えるだろうなと思った。インタビュイーが言ったことを文字起こしのまま記事にしても、読者に伝えたいことは伝わりづらい。だからこそ、話してもらった内容をどんな軸でまとめるかを決めたり、インタビュイーの意図を汲み取って言葉を調整したりして、読者に読み進めてもらえる記事を作っている。
編集者が企画した内容に沿って、インタビュイーの言葉を整えていく。嘘を書くことはなくても、元にある題材をもとに、必ずライターというフィルターを通ってインタビュイーの言葉は記事になる。インタビュイーの意図とは異なる解釈で公開して、さらに炎上なんてしてしまったら、炎上案件の“リアリティーショー”と変わらなくなってしまうんだろうな、なんて考えたのだ。
伝えたいメッセージを届けるために。受け取った人が楽しんでもらうために。出発点は純粋に、誰かを思う気持ちから始まる。けれど誰か自分以外の言葉や行動を題材にする作品は、作り手の意図よりも“演者”だけにスポットライトが当たってしまうことを、私たちは忘れてはいけない。
映像や本で誰かの情報を見るとき、それは必ず誰かの編集が入っていることを、私たちはもっと自覚的になるべきなのだろう。もちろん直接会って話しているときも、「私」という思考のフィルターを通して相手を理解している。自分の見ている一面が、その人のすべてではない。
「この状況において、この人はこうだった」と、場面ごとに区切ってみることができたら、その周りにある背景や、周囲の人の思いにも気づけるのかもしれない。
一昨年の毎日note
最後までありがとうございます!いただいたサポートは、元気がない時のご褒美代にします。
