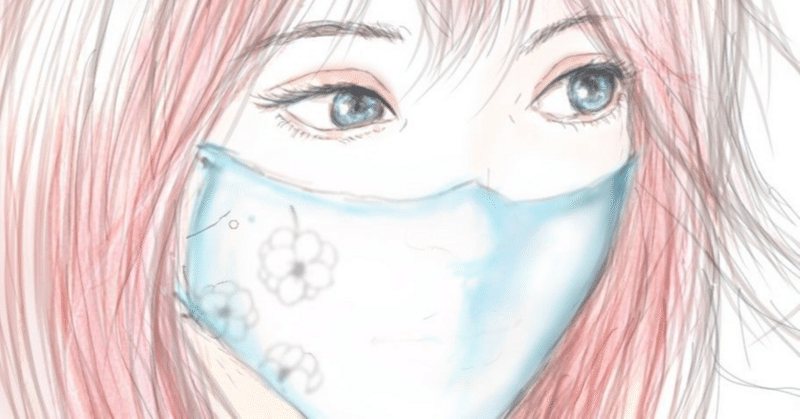
恋愛掌篇「マスクガールと停電の夜」
リリコがマスクをつけるようになったのは、新型コロナウイルスの流行より何年も前のこと。両親でさえ、彼女の顔を幼少期以降はほぼ覚えていないくらいだ。リリコは時折真夜中にこっそり鏡で自分の顔を確かめることがある。だが、グロテスクな代物だ、という以上の感慨がわかない。
というか、人間は全般、グロテスクなものだ、とリリコは思う。よくみんな、マスクの一つもつけずに外出ができるものだ、と感心と疑問が同時にわき起こる。
そして、そういった感慨と矛盾するようだけれど、リリコはまた、他人にはぜひともありのままをさらけ出してほしい、という内なる願望を秘めてもいる。マスクをつけないだけではなくて、もっともっと、ありのままを、一方的に、と。
じつのところ、マスク自体は好きではない。いっそ世界中が停電になれば、マスクを外すことができるのに。そんなことをよく考える。夜から一切の光が失われてしまえば、夜だけは自由に生きることができるだろう。だが、実際はそうではない。一歩外に出たら、都会の街並みはいつでも街灯で溢れている。だから、リリコはいつでもマスクをする。
友人たちは、いつしかふざけてリリコのことをマスクガールと呼ぶようになった。その渾名のせいで、男の子たちが最近になってリリコのマスクの下にある素顔に興味を持ち出した。わざわざ渾名をつけなければ、こんな時代、マスクをずっとつけている人間なんて珍しくもなかっただろうに。
なかでもしつこいのが、同じサークルの中野くんだ。中野くんは、ちょっと変わっている。海洋生物が好きで、居酒屋に行っても生け簀の水槽にへばりついているような子だ。
それが、なぜかリリコに興味をもっている。今日もそうだ。本来ならリラックスできるサークルのたまり場なのに、その視線が煩わしくて、全然リラックスできなかった。だから、リリコは頭痛がする、風邪かも知れないから、と言って早退した。どうせ授業が一コマしかない日だった。どうってことない。
けれど、帰宅してからも、中野くんからのメッセージはしつこく続いた。そのたびに適当な嘘で誤魔化していたら、「薬、届けようか」ときた。これはさすがにまずいかな、と思った。世にいうストーカーとはちょっと違う。中野くんはたぶん病気の人間に当然するべき親切をしようとしているのだろう。傷ついたマンボウに治療をするような気持ちで提案しているに違いない。
やれやれ、どう返そうか、と悩んだ。時刻は間もなく夜の九時。このまま眠ってしまったことにしようか、と思っていたそのタイミングで、停電が起こった。
レンブラントの絵画について考えてしまうくらいには、長い間その停電は続いた。はじめのうち、リリコはそれが停電だとは思わなかった。居間の電球が切れたのだと思った。でも廊下の電気を代わりにつけようとしてもつかず、洗面所もつかないので、ああこれは停電だと考えるしかなかった。すぐスマホのライトで廊下を照らしながら、玄関の靴箱の上にある分電盤のスイッチを上げた。それでも電気は戻らない。
これまでの人生で、リリコは真夜中に停電を経験したことがなかった。大抵の場合、停電というのは昼間に、何気ないふうに始まり、夜店の金魚の寿命みたいに唐突に終わる。ところが、その晩の停電はどういうわけか終わらなかった。
リリコはこのまま寝てしまうのがいいと考えた。中野くんからのメッセージを無視する口実にもなる。真夜中に業者を呼んでまで修理を頼むのは馬鹿げている。第一、これは我が家だけの問題ではなく地域全体の問題かもしれない。だとしたら、慌てるだけ馬鹿げている。
それから、リリコは音楽を聴いた。坂本龍一、クラーク、テレフォンテルアヴィブ、ナイトテンポ、とにかくスマホの電源が切れるまで音楽を聴いてやろうと思った。
けれど、そんな目論見は唐突なノックの音でとりやめとなった。誰かが自分の部屋を激しくノックしていた。インターホンだってあるのに、わざわざノックをするなんて。でもすぐ考え直した。そうか、停電中だからインターホンも使えないわけか。
リリコはすぐに玄関のドアのチェーンを外した。本当なら魚眼レンズから覗いて来訪者を確認するべきだったが、なにしろ真っ暗だから、手探りで玄関に辿り着く以外のことは考えられなかったのだ。
そうして、ドアを開けたとたん、何者かがぬっと部屋に入ってきたのがわかった。その人物は何もモノを言わなかったけれど、靴を脱いだのはわかった。それだけの分別はあるらしかった。
リリコはスマホの灯で室内を照らした。入ってきたのは、中野くんだった。彼のほうは、まるで留守の家に侵入した泥棒みたいに堂々としていた。もしかしたら、ほんとうに泥棒に来たのでは、とすら思ってしまうくらいだった。でもそうではなかった。
「突然の訪問、突然の停電をお詫びするよ。でも、きっと君のためにも、電気はないほうがいいと思って」
「……それじゃあ、この停電は中野くんが?」
中野くんは言葉なくうなずいた。中野くんは理工学部だから、そんなことは朝飯前なのだろう。
「ちょっとね。送電塔のねじを抜いておいた。君のためにも電気はないほうがいいと思って」
「さっき聞いたよ。でも要するに、それは私にマスクを外してほしかったからでしょ?」
「エクセレント。君はどんなことがあっても素顔をさらけ出したくない。けど僕はどうしたって君の素顔を知らずにはいられない。そこで、君に素敵な提案を持ってきたんだ。つまり、停電の真っ暗な夜をプレゼントするから、マスクを外してくれないかな? いまは君の手元の、そのスマホの灯が邪魔だけどね」
彼は誠実であろうとするつもりか、目を閉じていた。
リリコはスマホのライトを消した。
「あなたはここに入ってくる時、灯一つ持たずに来たわね。闇でもよくモノが見えるの? だとしたら、停電だろうと何だろうと、あなたの前で素顔をさらけだすわけにはいかない。そんなグロテスクなことは私にはできないの」
「その点は安心して。僕は視力が0・3程度しかないし、猫みたいに闇に適性があるわけでもない」
「それなら、私にマスクを外させる意味がないわね」
「とんでもない。大ありだよ。僕は君の顔に触れたいんだ」
「私のために停電を起こしたあなたに、そうさせることが対価だというの? 冗談じゃない。この停電は私の望んだものじゃないし。だいたい、停電が途中で終わったらどうするの? そうなれば、私はあなたの前に素顔を晒すことになる。もしそんなことになったら、どうするの?」
「そのときは、君が知りたい僕のありのままを見せるよ」
「……本気で言っているの? あなたが変態だということは、今までの会話でよくわかったけれど、それでも最後の覚悟はそれを上回る狂気の沙汰よ。あなたは、停電が途中で終わったら、本当にありのままを見せてくれるというのね?」
もちろん、と彼は答えた。リリコは、自分の顔を晒すのはグロテスクな行為だと思うのに、他人に対しては今すぐにありのままをさらけ出してほしい、と思ってしまう。
そして、中野くんはその厚かましさを受け入れようとしている。けっこうじゃないの、とリリコは思った。いいわ、とリリコは言った。いいわ、近くへ来て、私の顔を触りなさい。
その言葉に従って、中野くんは闇の中を手探りで進み、リリコが立てる衣ずれの音や何かを頼りに近づいてきた。その間に、リリコは服をすべて脱いだ。それはグロテスクな素顔を晒す相手に対するせめてもの誠意のつもりだった。そして最後にマスクを外す。何一つ身につけていない。いま、この瞬間だけは。
やがて、中野くんの手がリリコの顔に届いた。最初は頬に、それから恐る恐る唇の形を撫でた。リリコの唇は薄く、海月のように柔らかい。中野くんの指がリリコの唇の間に侵入する。歯の形を確かめ、それから自分の唇を重ねてきた。
反則だよ、中野くん、と思ったけれど、わるい感触ではなかった。この瞬間が、ほどよく数十秒続き、ゆっくりと離れることを望んだ。それはまったく意外なことだった。マスクを外して、誰かに顔を触られるということが、こんなにも心地よいことだなんて、誰も教えてくれなかった。
やがて中野くんはリリコを抱きしめ、その皮膚の感触をしっかりと指先で確かめはじめた。
この遊戯はあとどれくらい続くのだろうか、とリリコは考え始めた。すべてが心地よい。でも、今夜はこれでじゅうぶんだ、とも思った。まだその先まで望むには刺激が強すぎる。できれば、あと数分のうちに、そのまま停電が続いているうちに中野くんが立ち去ってくれますように。
そうでないと、中野くんのありのまますべてをさらけ出してもらわなければならなくなる。それを欲する自分を、抑えきれなくなる前に、この素敵な時間が完結してくれることを望んだ。
が、現実は無慈悲だった。その刹那、室内の照明がついた。壁の鏡に、裸の、マスクすらつけない自分とそれを抱きしめる中野くんの姿が露わになった。なんてグロテスクな、とリリコはぞっとした。でも、それを誰かに受け止められているのは悪い気はしなかった。しかし、問題はそんなことではなかった。
「こ、この部屋は……」
中野くんが戸惑っているのがわかった。
部屋には、人間の臓物が陳列されていた。いずれも、過去にリリコの素顔を見たがった男性たちの残していったものだ。リリコの素顔を求める男たちに、リリコは「あなたのありのままをさらけ出すのが先よ」といつも言ったものだ。
みな一様に首を傾げつつ「いいよ」と不用心に近づいて、背後から頭部を打撃され、臓物を取り出される。ありのままを、さらけ出す。
その点、中野くんはうまくやった。少なくとも、彼は初めて先にリリコの素顔をさらけ出させることに成功した男なのだから。リリコは、その名誉を讃えながら、室内のオブジェたちに戦慄する中野くんの背後から、大理石製の灰皿を振り下ろした。
「さあ中野くん、約束どおり、見せてもらうね。あなたのありのまますべてを」
全身の血が喜んでいるのがわかった。それなのに、リリコの頬からは、なぜかとめどなく涙が流れて止まらなかった。それで、思っていたよりもずっと自分は中野くんのことが好きだったのかもしれない、とリリコは思った。それからひとしきり、マスクを付け直すのも忘れて、嗚咽をもらした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
