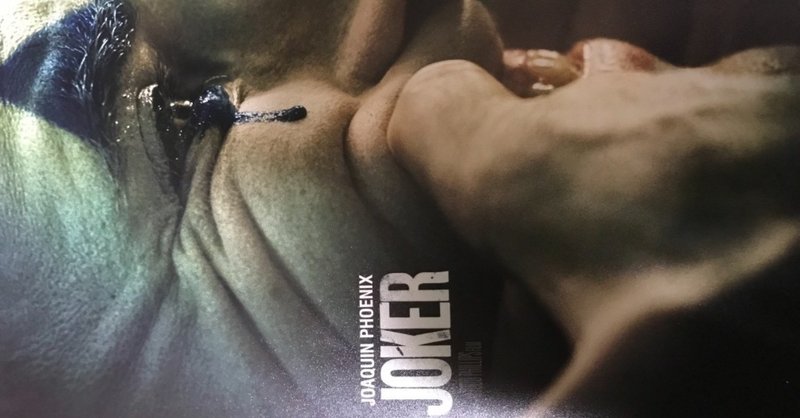
誰もがジョーカーになり得るのか?
『ジョーカー』という映画を観てきた。
妙な感じがした。この映画は何だろう、という感触だ。
誰が言ったのか「だれもがジョーカーになり得るのだ」という感想が脳裏をよぎった。そうだろうか? と思う自分と、そうかもな、と思う自分がいた。
誰かが言っていたほど精神的ショックは受けなかったし、鬱を誘う映画だとも思わなかった。総じて映画的に好ましい作品だった。
なので、この作品に映画的な批評を述べるつもりはない。世間の評に異論も賛同もどちらも控えておきたいのだ。言ってみれば、この作品は「個人的体験フォルダ」に入れてしまいたくなる、そういう映画だった。
映画館を出た後、考えていたのは自分の小中学時代や高校時代のことだった。
小中の頃は、集団でいじめる相手には奇襲攻撃を仕掛けていた。中学時代はほぼナイフと同等の鋭さをもったペーパーナイフをつねに筆箱に隠し持っていた。そういった安易な凶器より「笑い」と「知恵」という凶器のほうが役立つということを知ったのは中学の終わり頃だったか。
高校に入ると、少しは落ち着いたものの、教室の隅でいつも本だの漫画だのを読んで誰とも話さずにぼんやりしている変人になった。「変人」というのは、ごく好意的な評価だ。ある者は気色悪がってもいたし、こわがっている人もいた。いろんな人がいた。実際、僕自身、常軌を逸した行動をわざと取ってもいた。自分の机に置き忘れられていた誰とも知らぬ制服の上着はゴミ箱に捨てたり、女子が弁当箱と一緒に使用済みの油取り紙を忘れていた時はその油取り紙ものせて返したり……。「しんじられない…」「やっぱり頭が…」という陰口がよくそこかしこで囁かれていた。いつも虚空を見上げているので麻薬中毒者だと囁かれたこともある。廊下はいつもくねくねと踊るように歩いた。あの頃、極端な奇行をとることが、ひとつの精神安定につながっていた。
その「陰」な奇行が、大学に入ると一転、「陽」の奇行に変わった。誰にでも気安く声をかけ、どこへでも行き、誰の家でも泊まる。相変わらずの奇妙な言動をちりばめつつも、それを陽のエネルギーと調和させることでユニークだとか頭がおかしいとか、より好意的な解釈をする者は天才とも持ち上げた。だが、いま思うと、大学という場所では、高校時代のキャラのままでも、じゅうぶん過大評価をされたような気がする。大学は「違い」を評価する場で、高校は「同じ」を評価する場だった。それだけのことだという気もする。
ただ、いま思えば小中高も大学でも、一貫して善悪の区別はついていなかった。今もあるのかないのかはよくわからないけれど、もっと混沌としてはいた。わるいこともいっぱいやった気がする。駅前に放置された自転車を投げて遊んだり、飲み屋の二階から一階にグラスを投げて出入り禁止を喰らったり、となりの客のテーブルの上に立ったり、本当に最低な奴だった。目覚めたら顔じゅう血まみれでびっくりしたこともある。よく生きていられたな、と今になると思う。そういったふるまいがやんだのは、社会に出る前後、たぶん結婚したり子どもが生まれたりのあたりからだった。
そして社会人は、ふたたび「同じ」を要求する場だった。社会に出てからもずっと朝、出社する前は唱え続けた。「狂気を保て」。どこかで狂気を保つことが、まじないのようになっていた。ふつうのふりをして勤務をしてはいるが何かの拍子にはそんな仮面はすぐ剥がしてやるよ、という気持ちをつねに持ち続けていなければ、勤め先に向かうことすらできないほどに、社会全体にストレスを感じていた。
とにかく、そんなとき、結局ひとつの防波堤になっていたのは、つまらないことに、大学三年の時に生まれた長女だった。子の前で父親を演じること。どれほどすべての仮面を捨ててしまいたくなっても、子にとっての父という仮面は、いつも一つの防波堤になってきた。もし、大学三年の時に、長女が生まれていなかったら、どうなっていたんだろう? 自分は1年でも会社員なんてものをやっていられただろうか?
そんなことを、『ジョーカー』を観終えてから考えた。どこかで、完全にアナザーワールドへ行ってしまってもおかしくない人生ではあったのだ。「誰もがジョーカーになりうる」という言葉には今も懐疑的だ。少なくとも、この映画を観て「鬱になりそうだ」とか「かなりショッキング」とか言ってる人間はたぶん一生ジョーカーにはならない。かつてのクラスメイトの中にもなりそうな奴がいたとは思えない。そして、自分もやはりジョーカーにはなり得ない人間だったのだ。
それでも、どこかでボタンをかけ違えていたら、とは思わないではなかったし、その「ボタン」はタイミングこそ違え、やはりどんな人にもあるのかも知れないな、とも思い直したりした。揺れている。「誰もがジョーカーになり得た」はイエスか、ノーか。答えは出ない。ただ、今はまだ「個人的体験フォルダ」から外には出せずにいる。これはそういう映画だし、客観的な評価を同時代に下す必要もない作品だろう。
あえて言及するなら、監督自身が影響を受けたと公言しているとおり『カッコーの巣の上で』や『タクシードライバー』の系譜に連なる作品であり、「同じ」を強いてひとつの「粗い物差し」だけで物事を測ろうとする社会が封じ込めようとする「影」を暴き出す作品だ。その影をみても、「おや、あれは影というものですね、私にはありません。みんなにもないですが、あれはたしかに影という名のこわいやつですよ」というほど他人ごとには、まだなっていない、ということだけは確かなようだ。あなたは『ジョーカー』を観ようか迷ってこの文章を読んでいるのだろうか? それとももうすでに観た後で読んでいるのか? もし前者なら、なんの参考にもならないし、もし後者ならたのむから「うんうんわかるよ」だけは言ってくれるな、と思う。僕はたしかにここに鑑賞後の心境を残した。でもこれはただの心境であって感想なんかではないのだ。
ただ一つ、もしもあなたがこの映画を観て、過去に思いを馳せることがあるのだとしたら、あなたにも影があったのかもしれないし、影はそう簡単になくなったりもしないよ、ということは言えるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
