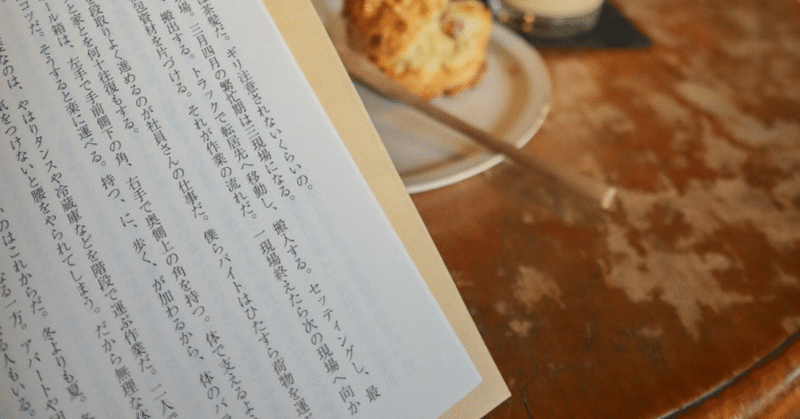
対話篇「僕はあの日、作家にブックオフで買ったと伝えたかった」
その日は、好きな作家、大池恵子さんのサイン会だった。僕は中学校のときに図書館で大池さんの本を読んで、その濃密な心理描写に酔い、サスペンスフルな作風に興奮して以来、全作図書館で読み漁ったくらい好きだ。
高校でも、大学でも読んだから、四十冊くらいは読んだのかな。
現在は地元の家具屋で家具製造に明け暮れる日々。まだ入社三年目だから薄給もいいところで、だから大池さんの新作も新刊では買えないけど、推したい気持ちはすごく強い。だから、細々とだけどブックオフに通っては、学生時代に図書館で買った本を集める日々だ。
そして、ついにこの日を迎えた。感激だ。こんな小さな町に、まさか大池恵子さんがやってくるだなんて。
いよいよサインの順番になった。僕はブックオフで買った最新作『魔女は昼まで起こせない』を出して言った。
「大池さんの新作、いつもブックオフで買って楽しんでいます! ずっと応援しています!」
そのとき、なぜだろう、一瞬だけど大池さんの表情が曇ったような気がした。気のせいかな。すぐに大池さんは笑顔になって「ありがとうございます」と言ってくれた。
「お名前は?」と僕に尋ねて、僕の名前も添えてサインをして渡してくれた。これは一生の宝にしよう。そう思った。
家に帰って、恋人の紗英にサイン本を自慢した。今日のサイン会で大池さんにずっと応援してることを伝えられたことも話した。すると、紗英の顔色が急に変わった。
「え……あんた、『ブックオフで買った』ってわざわざ言ったの? どうして?」
「ん? だって、自分が大池さんの本をどんなふうに集めてるか、自分の体験をしっかり伝えたいじゃん」
「うーん……いや、わかるよ、私だって推しのコンサート行ったら部屋にポスター貼ってますとか、自分がどんなに大事にしてるか伝えたいもん。体験を伝えるって大事だよね。でもさ、『ブックオフで買った』は微妙じゃない?」
「なんで? ブックオフはいい店だよ!」
「もちろん。それはいっさい否定しないよ。私だって必要があれば行ってるし。いやむしろヘビーユーザー」
「じゃあ何も問題ないでしょ?」
「いや、あんたがブックオフで買ったことが問題ってわけじゃなくてさ、それをわざわざ伝えたことよ」
「だから、それは体験を伝えたいっていう素直な気持ちじゃん」
「んん、だろうけどさ、それ聞いて、相手嬉しいかな? 相手がどう思うかって、考えた?」
「相手がどう思うか?」
そこで初めて僕は気づいた。大池恵子さんのことを「相手」みたいに考えたことが自分があっただろうか、と。ずっと読んできた作者。自分のなかではちょっとばかり「絶対ハズレのない本を書くゴッドハンド」的な感じで神格化したりもしていた。
そのせいなのか、自分の体験を語るのに夢中で、相手がそれをどう思うかなんてまったく考えていなかった。
というか、なんとなく、すべて受け止めてくれるだろうと思っていたし、いまこうして相手がどう思ったかと問われても、まったく想像できなかった。
「わかるよ。私も推しのお笑い芸人に『いつもコント映像、ユーチューブで拾って観てます』って言ったことあるからね。伝えたいんだよ。でもさ、ライブのDVD出てるのに、ユーチューブで動画漁って見てもらっても嬉しくないと思うわけ。
作家も同じじゃないのかな。ブックオフで買われても、出版社にはお金ぜんぜん入らないし、ってことは重版にもつながらないから作家にもお金いかないよね」
「ああ……それはそうかもしれないけど……だけど、ブックオフはちゃんとしたビジネスじゃん? 古本屋って、違法アップロードとは全然ちがうし、新刊の値段じゃないけど、お金もちゃんと払って買ってるんだから」
「もちろん。それはそのとおりだよね。あんたはちゃんと体験をお金で買ってるし、何も間違ってないよ。そして、その何も間違ってない体験を、作家に伝えたい。うん、それも何も間違ってない。でもさ、あんたの正しさが相手にとっても正しくなきゃならないわけじゃないと思わない?」
「まあ、大池さんには大池さんの捉え方があると思う。実際、彼女は一瞬だけど、顔を曇らせた気はする……気にしてたのかな……でも、僕はちゃんとブックオフで買ったし、そのときの興奮を伝えたい気持ちもあったんだ。ずっと図書館で読んできた本に、ブックオフで手ごろな値段で出会えた興奮を。それが、大池さんを傷つけたってこと?」
「あんたがブックオフで買ったことも、それを伝えたいという気持ちも、何も悪くないよ。ただちょっと相手の気持ちが見えてないだけ」
「作家の気持ちなんて、考える必要あるのかな……アイドルとか歌手みたいな人間そのものが商品化されてるような存在でしょ、こっちは尊敬はもちろんしてるし、僕みたいなモノがどこで買って読んだかなんかでいちいち目くじら立てたりしないんじゃ……」
「いや、実際、表情曇ったんでしょ?」
「そうだけど」
「それとも、目くじら立てるほうがおかしいって言いたい?」
「そうじゃないけど……僕なんかの体験ごときに、って気持ちはあるよ」
「先日さ、海外のアーティストがライブ会場でセクハラにあったでしょ。たぶんあのとき、さわったファンってみんなそんな感じだったんだと思うよ。アーティストが近くにやってきた。嬉しい。触りたい。ご利益がある、くらいの感じだよね。でも、それ立派なセクハラなんだよね」
「え、まさかそれと同じだって言いたいの? いやいやいや……待ってよ待ってよ……たしかに舞い上がって体験を語ったしその内容が相手に嬉しくなかったかもしれないけど……」
「少なくとも、相手に人格があることをまったく無視していたのはたしかでしょ。その点は同じだよね」
「そうかなぁ……っていうか、そもそも『ブックオフで買った』ってそんなに嫌なことなのかな……そこがどうも……」
「これはちょっとデリケートな問題ではあるよ。たとえば、作家がネイマールとかメッシなみに稼いでたらさ、『ブックオフで買いました!』って言われても大笑いして許してくれたと思うよ。ちょっとは苦笑するだろうけど。
でも重版かかること自体が珍しいような出版不況で『ブックオフで買って読んでます!』って言われても、微妙だよね。あんたが十代の学生ならべつだよ? お金の仕組みがまだわかってないんだろうから。でも立派な社会人でしょ」
「え、でもそれ、出版不況のせいじゃん。ぜんぜん僕わるくない……」
「出版が大盛況だったら見逃してもらえるってだけ。相手が失礼だなと感じることには変わりないと思うよ。っていうか、相手が何を失礼と感じるかまでは、こっちは選べないわけよ。もちろん、『何を伝えるかは皆さんの自由』っていう主義の作家さんもいっぱいいると思うけどね。
でも、あんたは仮にも好きな作家の意志を尊重したい気持ちはあるわけでしょ?」
「まあそうだけど……失礼なの? 不況で儲からないから? よくわかんないな。それ僕に関係ないじゃん?」
「そうね、直接はね。じゃあ、逆にこう考えてみて。あんたはいま家具屋で家具を製造して販売してるよね。友達がそれを買ってすごく使いやすいって言ってくれたらどう?」
「めっちゃ嬉しいよ。当たり前じゃん」
「じゃあ、中古家具屋で買って使ってるよって友達が言ったら、どう?」
そう質問された瞬間、僕は言葉につまった。
具体的にそう言われる場面を想像したら、すごくグロテスクで気持ち悪かった。
「なんでうちの店で買ってくれないんだ?って思うかな……っていうか、どこで買ってもいいけど、わざわざ中古で買ったことまで報告するなよ……って……ああ……」
「そういうことなんだよね。私の実家は農家だけどさ、スーパーに仕入れてるの知ってて『値下がりの札がついたらすぐ買ってる』って教えてくれる近所の人がいたんだ。無邪気なのよ。悪気はない。わかるんだ。自分の体験を話してるんだよね。でもだから失礼じゃないってことには全然ならないと思わない?」
「そう……だね……」
「それは不況だとか不況じゃないとか、その次元の話ではないよね?」
「そうか……」
「ま……まあまあ。もちろん、読んでくれたこと自体は嬉しいと思うよ。図書館でもブックオフでもさ。だからきっと大池さんも読んでもらえたことは嬉しかったんじゃない? だからそんな落ち込まないで。済んだことだし」
僕はなんだか居たたまれない気持ちになった。内心は複雑だった。もう言ってしまったことだし、自分は悪くないと思いたい気持ちもある。そのときの気持ちに嘘もなかったわけだし。単純に、体験の喜びを言葉にしただけだから。だけど、もしも相手にとっては失礼だったのなら……と。
その夜、大池恵子さんのSNSを覗いてみた。大池さんの投稿はいつもと何も変わらなかった。ためしに今日はサインありがとうございましたってコメントしてみた。すぐにイイネがついた。なんだ、怒ってはないみたいだ。
やっぱり、紗英は気にしすぎなんじゃないかな。さっきは紗英が弁がたつからすっかり丸め込まれちゃったけど、本当は大池さんはまったく気にしてなかったのかもしれない。まあいいや。
ビールを開けた時、電話が鳴った。高校時代の同級生の和治からだった。ひとしきり雑談が済んだあと、和治は本題を切り出した。
「おまえ、家具屋の社員だったよな? 俺さ、今度子ども生まれて引っ越すから、引っ越し祝いで椅子を一つ格安にしてもらえないかな。おまえの会社の家具かっこいいらしいじゃん」
「いいけど予算は? うちの椅子、ひとつ五万くらいするから、安くって言っても三万はすると思うよ。まあ俺が頭下げて、それで二万九千…かな」
「マジかよ……それは無理だな。中古家具屋回ろうかな……おまえんとこのも売ってるよな? きっと」
「ん、ああ……まあ、探せば……どこかには……」
「わかった、ありがとな! また飲もうな!」
電話が切れてから、僕はじっとスマホを見つめていた。
それから、また和治と飲む日がくるんだろうか、とぼんやり考えながら、ビールをぐびぐびと飲んだ。その日のビールは、なぜかひどく後味がわるくて、いつまでも舌に苦みが残り続けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
