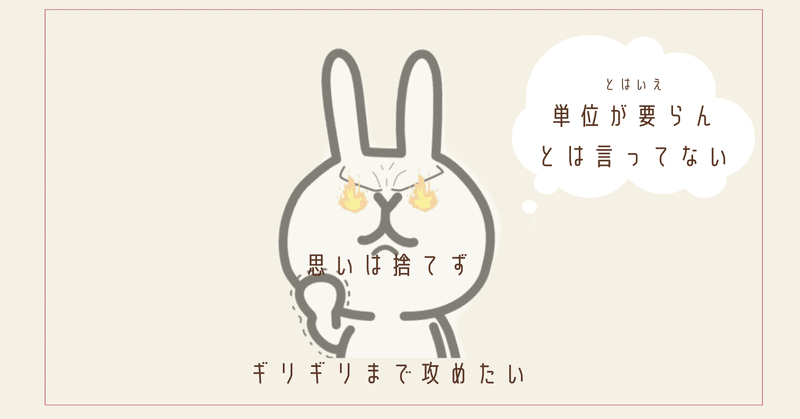
レポートの「述べなさい」と「まとめなさい」
これまで、「参考文献に論文も便利」とか「論文はGoogleで探せる」とかの話を書いてましたが、これらは小論文タイプの課題のときの話になります。「〜について考えを述べなさい」みたいなやつです。
大学のレポートには、他に、キーワードや概念(コンセプト)を説明させるものや、キーワード同士の関係などをまとめさせるものがあります。
正直なところ僕は、「説明しなさい」や「まとめなさい」タイプのレポートにも、ついつい自分の考えや意見を書いてしまって、苦手ではあるのですが、それでも少しでもなにかヒントになりそうなことが書ければと思います。(ひとに聞いたものもあります😅というかだいたい、そう)
出題の意図を意識する
こまかく見ると、「考察しなさい」なら分析まででよく、「論じなさい」になると主張と根拠を論理的に、とか違いはあると思いますが、まあ小論文だと思って書いてもそれほど評価に影響はほとんどないでしょう。
ただ、「説明しなさい」や「まとめなさい」に自分の考えや主張を入れてしまうと、たいがい字数が足りなくなります。とうぜん、根拠を書くスペースもないので、下手をすると勝手な思いを書いてしまうことになりかねません。
ちなみに説明やまとめを求められるのは、「授業やテキストの内容をちゃんと読み聞きして理解してますか?」ということなので、考えすぎるとかえって書けなくなります。あと、「自分の言葉で・・・」とかよく言いますが、これは「コピペ禁止」の意味です。オリジナリティのある表現とかを求められているわけではないです。
ーだけど思いは捨てない(捨てたくない)
とは言え、たかが単位試験とは言え、根本思想は捨てたくない!という気持ちはよくわかります!(少数派かもしれませんが😅)
そういう方に、有料記事なので紹介までですが、あくまで“けっして模範回答ではない“としたうえで、自分のやり方を公開してくれている方もいます。
有料記事ですが、ご本人のnoteメンバーシップ『仕立て屋タケチヒロミの「好奇心の小部屋」』でも読めます(かるく宣伝🤣)。
言葉を“因数分解“する
とくに説明タイプのレポートの話になりますが、少しコツっぽいやり方を紹介します。とは言え、手順でいうと、
① 出題のキーワードを、用語集・テキストの“索引“などから調べる
② 該当箇所から、さらに“索引“にのってる単語をピックアップする
③ バラバラでいいので、解説をメモっておく
④ メモしたものを再構築する(一つの文章にまとめる)
だけです。
ちょっと作業っぽいやり方ですが、テキストなどの考え・主張にたって、かつ丸写しではない形にできます。
「自分の考え」と「出典(外部)からの知識」を区別する
これは、コツというより「課題から何を身につけるか」という話だったと思いますが、「その話(意見・情報)が、どこから来ているのか」を意識するというのは、学問うんぬんだけのことではなく、普段の生活でも大切になることです。
僕は、なんでもかんでも「客観的」であることが良いことだとは思いません。
客観的だったり論理的であったりすることは大切だとは思いますが、人間はもともと主観から逃れられるものではありません。何より、自分の考えや想いを捨ててまで、評価をえたり「正解」することに面白みもなにもない。と思います。
ただ、それが自分の意見・想いなのなのか、どこから得た情報なのかは意識しておくのは、逆に自分の思いを大切にする意味でも大切なことになるのだと考えています。
(ちなみに、僕は、これは自分の考えたことという意味もあって、「思います」「考えています」を多用してますが、レポートや論文ではNGです😅「ですます」調も、「である」調で書くよう指導されます)
最初に「設計図」をかいておく
これは、とくに「まとめなさい」をかくときに、やっておくと良いコツかなと思います。
出来事の流れや概念(用語)の関係をまとめるタイプの課題は、それぞれのつながりや関係性を理解しているかが出題の意図になっています。しかし、結構書いていると「思い入れ」のあるところで文字数を使ってしまい、偏りが出てしまうことがあります。とくに思い入れがなくても、自信のあるところが長くなってしまうという偏りもあるでしょう。
設計図といっても、①目次の案、と②項目ごとのだいたいの文字数をメモしておくだけです。
これも、仕事で文書を作ることがあるひと、将来つくるときに、身につけておくと良いコツになるでしょう。
(今回、参考にしたものについて)
本題とは関係ないのですが、
言葉を因数分解するとか、自分の考えと情報を区別するというのは、昔に講義を受けているなかで雑談的に教えてもらったことだったと思うのですが、誰に聞いたか忘れてしまっています。“因数分解“という表現は、記憶にのこっているのですが、どういう内容の講義だったかも思い出せません。
なので、出典や参考として明示できないのですが、先生の“教え“は今でも覚えています!ということで😅(クラスメイトからだったかも、、、。)
タケチヒロミさんの記事も紹介させていただきましたが、「ギリギリまで攻めていきたい」とある部分にすごく共感して、タケチさんの“やり方“にも触発を受けました。
「設計図」のやり方は、自分が呼びかけている方の学び合いグループの方で、「こんな記事かきたいですが、まとめタイプ苦手で、、」と相談して教えてもらったアイデアになっています。
この場をお借りして、お礼をもうしあげます。ありがとうございます🤗
自分の方のグループも参加者募集中です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
