
冬の夜、月に罰せられる
女を殺す夢をまた見るようになった。
その女が誰かというと、きっと誰でもない。夢のなかに現れるヒロインという具象でしかない。ただその姿形は、自分が知っている幾人かの女性たちなのだ。かつての交際相手が、代わる代わる夢に出てきた。そして僕は彼女たちを殺してしまう。その夢のなかでは、そうせずにはいられない。
それをやり遂げようと、あるいは未遂に終わろうとも、ラストシーンはいつも同じだ。僕は天を仰いで慟哭。そして「ああ、こんなに愛していたのに!」などと泣き叫ぶ。そうやって一方的な想いが殺意に変わるという古典的な愛憎劇を、浅い眠りのたびに演じさせられた。
彼女たちは、もちろん現実の彼女たちではない。誰でもない。人格もない。あくまで自分のイメージの産物だ。おそらくは女性への恐怖心がそこに反映されている。女性不信、女性嫌悪、女性蔑視といった一方的な被害者意識が心の奥底で渦巻いているのだろう。
自己憐憫の醜悪な世界に、どうやら僕は迷い込んでしまったらしい。
——待てよ、これはミソジニーというやつの典型じゃないか。
およそ典型的、分かりやすい、平凡、そのような言動を、これまで自分は避ける傾向にあった。複雑で難解、なるべく例外的な存在でありたかった。それがなんと類型的な非モテ男の深層心理に陥ったものか。
無論、そのように自己を特別な位置に規定すること自体が凡百の心理に他ならず、まさに厨二病もいいところ。いよいよ三十路を迎えてのそれは、もはや醜い。その自覚は充分にあって、それがまたやり切れない。
——いや、さらに待て。
そのような年齢相応の振るまい、生活態度、ましてや精神状況などという固定観念こそが、この空虚な社会がでっち上げては押しつける「空気」という窮屈な檻に過ぎないのであり、如何様にして実体のないその獄を破るか、それが我らの勝負所なのだ……。なんて具合に「自由でありたい自分」という空々漠々たるイメージに囚われ、芋焼酎ロックでも飲みながら薄汚い居酒屋の片隅で数少ない友人相手にまた語るのだろう、明後日あたりの自分はまた。
たかが知れた近未来、予定調和の酒宴を予知して、自己嫌悪は再燃する。もう速やかに消えたい。されど消えないのが自我である。
はたして明後日、予言は見事に的中。薄汚い居酒屋を出たところで友人と別れ、家路の途中でひとり嘔吐した。吐瀉物の欠片をまとわせて、芋くさい僕は散らかったアパートにようやく辿り着く。
そして寝床につけば、また女殺しの夢がはじまる。
主演女優はローテーション組んだ過去の恋人たち。まるでアイドルグループ。私家版AKBか? でも四十八人もいない。僕がそんなにモテるわけがない。グループ展開はしない。だから総選挙も推しメンも何もない。でもどうせならオールスターで出てきたらいい。そうなるとドリフかな? 全員集合。それは困る。いや別に困らないか。
現実の彼女たちは僕のことなどすっかり忘れ、日々それなりの現実を生きていることだろう。それがリアル。そこに僕の夢などリンクしない。
……そうか、だから殺すのか。
夢のなかで、かつての恋人に殺意を抱く理由は、そこにあるのだと思い当たった。僕を忘れた彼女たちを、僕は憎んでいる。
もう手に入らないものならば、いっそ壊してしまえという幼稚な精神の持ち主、ミソジニーのうんこにまみれた醜悪なる乳飲み子、それが僕であった。
汚れたオムツを替えてくれる無条件の慈愛にあふれる母性、それと同時に刺激にまみれる性的サービスまで提供してくれる完全なる恋人、そんなものは存在しない。そんな空虚なイデアからは、とうに離脱した。したつもりだったが、この有様だ。
「行かないでくれ!」
情けない自分の叫び声で目が覚めれば、枕は濡れていた。肌着も寝汗でぐっしょりしている。まるで陳腐なソープオペラに、心はすっかりかき乱されている。
ああ情けない。勘弁してくれ。勘弁したってくれ。
『わが泣くを乙女等きかば病犬の月に吠ゆるに似たりといふらむ』
ふと石川啄木先生の歌が心に響く。先生は自分の歳にはもう死んでいる。一方の僕は死に損ね、これからも漠然と生きるつもりでいた。
『この先のへたれた生に寝ころびて乳を吸いたし三十の心』
それがどうした、なんだそれは。自作が我慢ならない。ああ深層心理は正直だ。典型的、類型的。恥ずかしいくらいに分かりやすい。分析の甲斐もない。一山いくらの塵の山。
——ああ、こんな自分が、この僕だとは!

夢に出てくるヒロインたちの一人には、まだ連絡がついた。だから彼女を呼び出した。
駅前にある工夫も素っ気もないチェーンの喫茶店で向かい合って「もはやあなたは必要ない」という彼女の言動及び態度に接するうち、僕の精神世界はドブ水に満たされてヘドロが沈殿、いつの間にやら「やらせろ」と連呼していた。はじめは冗談半分だったが、連呼するうちマントラのように「やらせろ」が効いて自己暗示にかかる。浅はかで低級動物霊じみた深層心理に、僕は自ら踏み込んでいった。
心象の壁面に穿った空洞から、類型的ミソジニーの怨霊が喜悦満面に噴出する。やらせろ、やらせろ、やらせろ、どうでもいいから、とにかくやらせろ。現実の自分が、その精神ゲロリズムに唱和する。
「ねえ、目がいっちゃってるよ」「なんか病んでるよ」「……もう止めてよ」
僕の目がいっちゃってるとしたら、それはお前が素直にやらせないから。ホテル代は全額こちらが出すと言っている。だから、やらせろ。や・ら・せ・ろ。YARASERO。もし僕が病んでるとしたら、それは全部お前のせいだ。お前はこの僕に圧倒的な負荷をかけている癖、それに対してあまりに無自覚だ。それが許せない。ずっと以前からだ。せめて自覚しろ。そして対価を支払え。受けたエネルギーが出口を見失えば停滞して腐る。ほらほら、このように。眼前の腐敗物を見よ。わが魂の停滞に吐き気を催せ。エントロピーとフローについて考えろ。病んでいるのは、お前も一緒だろう。僕が一番それを知っている。その症状を改めて披瀝し絡め合い魂のカウンセリング世界へ一緒に行こうじゃないか。誰も入れぬ密室で。僕はきっとメディスンマンになれるから。患者でありながら治療者。たとえばガンジャでもキメながら。さあイラン人はどこだ。上野か。いやもうイラン人は売ってないか。まったく、むかしの話だね。まだコンドームは鞄に入ってる。どれくらい前のか忘れた。賞味期限過ぎか、僕と君の青春にゴム製品もまた。……ああ、どうでもいい、どうでもいいんだよ、大体全部。とにかく、やらせろ、なんでもいいから、やらせろ。以上を計三十六回あまりリピート。
全身全霊、すっかり汚れた泥になりきって、その自分に沈み込んだ。
改札手前、別れ際の長話。二人で共有していたささやかなノスタルジーにアクセスし、それを否定して徹底的に損なわせるような言葉を、僕はその場に吐いて捨てた。途端に彼女は巻いていた青いマフラーをグッと上に引き上げて口元を覆い隠し、なにも言わずに去っていく。
途中までは追いかけた。改札を通り、ホームへの階段を上っていく彼女に声をかけようとしたが止めた。これまでも繰り返した愁嘆場をもしまた繰り返せば、あるいはまた情交の糸口を掴めるだろう。それで、なんになる。なんにもならないことは自分でもよく分かっていた。
波ゆく他人の背中に、彼女が入り混じって消えていった。もうこれで会うこともないだろう。
この瞬間のすべてが酷くつまらなく思えた。そして勿論、いまこの世界観において文句なく一番つまらない存在、それは僕だ。
○▷●
小さい女の子が夢中で作った可愛いらしい雪だるまの頭を、通りすがりに高めの打点で思い切り蹴飛ばしたような、安い罪悪感を味わっている。ややこしい形容の仕方をしたのは、実際にそうして歩いているからだ。
東京に数年ぶりの大雪が降った日の夜で、誰かが作った雪だるまが、人気の途絶えた住宅街の至る所に点在していた。僕はそれを一つずつ粉砕して歩いた。作成者のささやかな幸福に思いを寄せながら、ハイキックや回し蹴りを食らわせた。
しばらくまともな運動をしていなかったから、息が切れるのが早い。吐く息は白く、手先や耳のあたりが凍えてジンジンしてくる。降り積もった雪が街灯の明かりを反射して、普段の光景とはまったく違っていた。雪の夜は橙色の異世界だった。
僕は曲がり角を曲がるたびに次の雪だるまを探した。そこかしこにターゲットが潜んでいる。すれ違い様に蹴りを浴びせ、その仮想敵を粉砕していく。自分の蹴り技にバリエーション不足を感じた。もっとテクニックを身につけたい。八つ当たりとヘイトの発露を工夫したい。そういった暗黒の鍛錬を地道に積み重ねていきたいと本気で思った。そして固く大きく鋭く尖って、刺し貫きたい。誰を? 誰でも、なんでもいい。目の前にある僕の気に食わぬもの、なんでもだ。
いっそ清々しいくらいに心は黒々うねって、それに痛がゆい快感を覚える自分を嘲笑する。まるで思春期だ。なるほど厨二病は不治の病で、一生の付き合いになりそうだ。しかし三十にもなって、なにも繕えぬむき出しの小さな自分が、ひどく見苦しい。
無残な感傷に浸りながら、冬の夜をさまよい歩いた。
夜空を見上げる。
雲を絡みつかせた月が、こちらを見下ろしていた。
「見てんじゃねーよ」
思わず僕は、月に悪態ついた。

「……月に唾吐きゃ、矢が振るわ!」
突然、甲高い声があたりに響いた。僕は立ち止まり、その声の主を探した。
雪が積もった民家の塀の上に、人が立っていた。
ちょうど月を背負うような、そのシルエット。やや逆光になっているが、極端に短いスカートとノースリーブという格好なのが分かる。太ももに二の腕まで剥き出しだ。寒くはないのだろうか。
露出狂一歩手前の格好からして、腹の据わった変態女かもしれない。まあどう考えたって、まともな女ではないだろう。
「自分がモテないからって、可憐な乙女にヘイトを向ける。そんな男はクズ同然。下手に自覚があるだけ、なおタチ悪い」
やや舌足らずな発声が、幼さを感じさせた。しかし舌鋒は辛辣で、その尖った舌先は、どうやら間違いなくこちらに向けられている。
その少女に、僕は問いかけた。
「……ねえ、なにしてんの? そんなとこ登って。寒くないの?」
「愛と正義のセーラー服美少女戦士……」
中学生くらいに思える体格の少女は問いに答えず、あんな不安定な足場でよくバランスを崩さないものだと関心してしまう位に大仰な身振りのポーズを決め、一方的な名乗りを高々と上げた。
「セーラー✖️ーン!」
——大変だ。とうとうセーラー✖️ーンが現れたぞ。
少女が名乗りを挙げた途端、月にまとわりついていた雲が流れ去り、輝きを増した月光が、はっきりとその姿を照らし出した。
ああ、もうこれは完全にセーラー✖️ーン……。
紛う事なき三次元、リアルタイム実写版のセーラー服美少女戦士が、そこに立っていた。
じつは薄々勘づいていた。しかし分からなかったのだ。自分が狂ってしまったのか、狂っているのはこの世界なのか。いや、どっちでもいいのか。結局は同じことなのだろう。
「さあ、すべての女性に懺悔なさい!」
クロスさせた腕の先、ピストルの形にした右手の人差し指を僕に向け、彼女はぴしゃりと言い放った。その表情はまだ幼いながらも凜として、迷いがなく真っ直ぐな目をしている。

「月に代わって、お仕置きよ☆」
……ああ、ついに出た! 出てしまった!
この伝説的な決め台詞を耳にして、生き残った妖魔は誰もいないと聞いている。まさか自分にその死刑宣告が下されるなんて。人生には意外なことが待っているものだ。
「とぅ☆」
彼女は愛らしい掛け声と共にジャンプ、軽やかに地上に降り立った。すぐに臨戦態勢を取り、こちらの様子をうかがっている。
「……ちっ。やるしかないか」
勝ち目などないことは最初から分かっていた。なにせ彼女は正義の代行者だ。しかし男には、無理と分かっていてもやらなくてはならないときがやって来る。それがいまなのだろう。
彼女と対峙した瞬間、自分のなかで吹っ切れたものがあった。そして理解した。これは使命なのだ。
自分の存在は、もはや一話完結のレギュラー回、残り五分であっけなく倒される仇役に成り下がった。いや、言い方を変えれば、世間にごくありふれた、しかし必ず滅すべき悪の一要素、その代表を仰せつかったのだ。決して自分で望んだわけではないが、そうなってしまったのだから仕方ない。
教育、勤労、納税という国民の三大義務を受け入れるように、この状況を受け入れるしかないのだ。
「さあ、セーラー✖️ーンよ、かかってこい!」
ならば義務と役割を果たそう。それが男だ。これまで小馬鹿にしてきた古典的かつ封建的な、いわゆる「男の美学」という心意気……それに殉じることに自分は決めたのだ。他に選択肢はない。
「こないなら、こちらからいかせてもらう!」
義務を果たす。それが男。オトコだからだ。漢なのだよ。イッツ・ア・メン。男、オトコ、漢、チンコ、ペニス、チンコチンコチンコ……男だ、おれは。チンコ、ペニス、食らえマ✖️✖️!
血がたぎった。魂が屹立する。男根の観念がマグマのように血流して全身を巡る。その奔流と同調するように、僕の、いや、おれの肉体は走り出す。
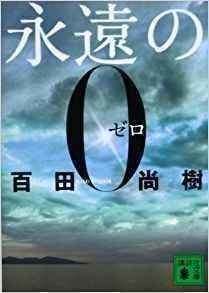
まるで特攻精神。永遠におれはゼロなのか。小数点以下は切り捨て。やり切れぬ思いはいまもある。だが、それがどうした。だからこそ行け。行くべきだから、行くのだ。全国の心正しい乙女たちが、おれという悪鬼の束の間の跳梁跋扈、そして定石めいた破滅を待ち望んでいる。それに応えてやればいい。
……ああ、これぞ晴れ舞台。さあ花道を開けろ。拍子木を鳴らせ。おれは男として逝く。君のためにこそ死にゆく。とにかく突っ込め。あのマ✖️✖️……!
ドゴォッ!
「くっ……!」
少女は咄嗟に腕をクロスさせ、おれの跳び蹴りをガードした。中学生らしい華奢な細腕に、渾身の攻撃が防がれた。やはり足技の鍛錬が必要かもしれない。
「フシュウゥゥゥ……!」
おれは獣じみた大きな息を吐く。クリーンヒットは逃したが、たしかな暴力の手応えを感じていた。それが野蛮に支配された心に痺れるような快感をもたらし、思わずニヤリと下卑た笑みがこぼれた。自分の犬歯が、いつになく存在を主張していることに気がついた。
「月の力に守られているのに……。なんて威力……!」
おれの与えた暴力と苦痛に歪む少女の表情、小刻みに震える、たよりなく細い発展途上の手足……。両の眼を爛々と見開き、舐めるようにその姿を見つめれば見つめるほど獲物に対する加虐心は否応なく昂ぶり、さらなる興奮を渇望した。
その獣欲の疾走が脳をかき回し、おれの全身にオーバーランを引き起こしていく……!
「うおおおおおおおお……!」
大量噴出するドーパミンと破壊衝動が凝縮して、おれの骨格と筋肉に異様な力学を加えた。狩りと虐殺に最適化されるべく四肢が大きく伸び、半獣化の歪みが生じた。肉体の変容と同時に、硬い体毛がワサワサと全身を覆い尽くした。そして両手の爪は獣じみた凶器に、犬歯は鋭く大きな牙へと進化した。
「ワォォォーーーン!」
血に飢えた野犬、いや、かつてこの国で駆逐された野生のオオカミのように、おれは頭上に浮かぶ月に吠えた。吠えずにはいられなかった。
おれはとうとう、一匹の狂暴な獣人に成り代わってしまったのだ。
……さあ、目の前の少女を食い殺してやろうじゃないか。こうなっては、己の本能に従うのみ。
まずは思う存分にいたぶってやろう。ようし殴ってやれ。殴れ、殴れ殴れ殴れ殴れ。引き倒せ。そして足蹴にしろ。やらせろ。とりあえず、やらせろ。やらせないのなら、とにかく破壊しろ。切り裂け乙女、切り裂け乙女。切り裂け乙女ぇぇぇ……!
ヒュウウン!
「きゃあっ!」
すっかり人間離れして、禍々しく鋭く伸びた大爪が、さっきまで彼女がいた空間を引き裂いた。加虐心を煽る叫び声を上げ、少女は咄嗟にそこから飛び退いた。
「……げひゃひゃひゃひゃ! うまく避けたな。しかし逃げてばかりでどーするぅぅ? ええええええ? セーラー✖️ゥゥゥゥン!」
必要以上に長く伸びた舌のせいだろう、可憐な乙女をなぶる自分の声は、より下劣なものに変容していた。生臭い唾液が、大きく裂けた口の端からこぼれ落ちる。
「げひひひひひ!」
胃の腑から哄笑がわき上がってきた。愛らしい乙女のポリシーを、ズタズタに引きむしって辱めてやる。ああ、たまらない。ひどく楽しみだ。美少女戦士の成れの果てを、白日に晒し出す。明朝の雪解けに赤黒い血の彩りを添えてやるのだ。無残の美が、そこにある。ぷしゃあああ!
「なかなか手強いわ、この妖魔……!」
美少女戦士は右に左に軽やかに跳躍、おれの攻撃は惜しいところで避けられる。しかし確実に少女に迫り、とうとう袋小路に追い詰めた。
「……このままじゃ、やられちゃう!」
「ああ、やってやるともさ! 思う存分やってやる。やってやって、やりまくってやるぞぉぉぉぉ!」
残虐な結末の予感に、おれは大量の涎をダラリダラリと垂れ流した。押し止めようのない獣欲に身を任せきっている。気分はおそろしく最高。大きく口を開き、血に飢えた牙を剥く。追い詰められ、恐怖に怯える少女に舌舐めずり、ゆっくりと歩み寄らんとする、まさにそのときだった。
どこからか一輪の真っ赤な薔薇が飛んできて、おれの足下に突き刺さった。

「ああん! タキ✖️ード仮面様あぁぁん☆」
とろん、と甘く蕩けた食べ頃のハーゲンダッツじみた声を、少女は突拍子もなく上げた。彼女の視線の先を、おれは目で追った。追った直後に、その目を疑った。
そこにいたのは、どう考えても場違いであろうタキシード姿にシルクハット、そして目を覆い隠す白い仮面の男だった。
たとえば仮面舞踏会とか、あるいはそういう名目で開催される秘密の乱交パーティとか、そんな場面でしかお目に掛からないであろう現実味のない扮装の男は「可憐な乙女がうんたら」とか「自分はそれを支援してどうたら」とかいう繰り言を、グタグタ得意げに語り出した。
美少女戦士は男の言葉に「きゃあ」とか「ステキ!」などと黄色い声援を上げ、まるでジャニヲタOL、あるいは旅役者の追っかけオバさんの如くに目を♡型に変形させた。
お約束のコメディパートらしい状況から一人だけ取り残され、どうもまだこの寸劇は続きそうだ、しかしもう馬鹿馬鹿しくなってきた……そうか変に遠慮とかせずに、いま攻撃しちゃえばいいかな? あーマジでそうしようかな、なんかムカつくしなこいつ……そんなことを考えていたら、なんとこのタキシード野郎は「じゃあ、そういうことだから。頑張りたまえ」とだけ言い残して、何処かへと去っていった。優雅に黒いマントをひるがえして。
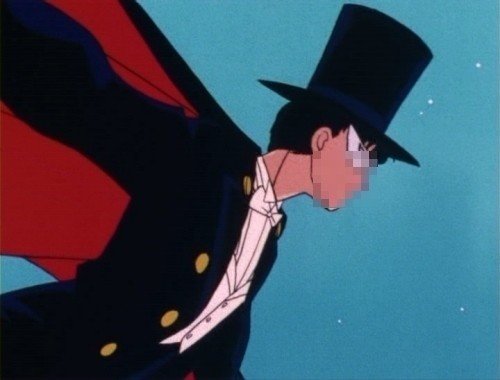
……え、嘘だろ。
お前、薔薇投げて、ちょっと応援して、それで終わり? 自分では戦わないわけ?
え、それで本当にいいの?
「よおし、元気百倍! やるわよ、覚悟なさい!」
どうやら本当にそれで力を取り戻したようで、セーラー✖️ーンは、こちらに向き直って威勢よく啖呵を切った。
……可愛くて健気で性格も悪くない風俗嬢が、ホスト崩れとかバンドマン崩れとか、とにかく崩れてるけどそれなりに二枚目、でもやっぱりろくでもない男に貢ぎ倒している。それで身も心もすっかりボロボロになってるのに「お前がいないと、おれダメなんだ……」なんて無料みたいに安い演出と台詞で実際のところ元気になっちゃって更にハードな店へと移っていく……。
そんな構図を把握して、おれは激しい怒りを覚えた。おれはもはや完全に悪役ではあるが、これは義憤というやつに違いない。
「目を覚ませ小娘! おれが人生を教えてやる!」
汗臭いジャージ姿で竹刀を振り回す、マンガ的な体育教師の気分になった。ときには体罰も必要だ。彼女たちを間違った道に進ませないため、自分が憎まれ役を引き受けよう。まったく女というのは、これだから始末におけない。よし、ここは一つ教育的指導を与えてやろう……!
おれは大義名分と入り混じり下劣に歪んだ欲望を、あらためて目の前の少女に向ける。制服の乙女に、再びジリジリと迫っていく。体罰セクハラ教育委員会上等、かかってこいや。揉んで揉んで揉み潰す。……ぷしゃああ!
「危ない、セーラー✖️ーン」
ドガッ!
背中につよい衝撃を受け、おれは前のめりに吹っ飛ばされた。どうやら背後から強烈なキックを食らったようだ。
起き上がって後ろを振り返ると、そこには茶髪のポニーテール少女が腕を組んで立ち塞がっていた。
「次は、わたしが相手だ!」
緑ぽいセーラー服を着たその少女はこちらを見据え、威嚇するようにすぐ横にある電信柱にパンチ。
ミシッという音を立て、少女の拳がコンクリートの柱に食い込んだ。なんという怪力だろう。
「わたしのことも、お忘れなく!」
どこからともなく金髪の少女が現れ、バシュッという音、それから何かが焦げた匂いがした。やや遅れて、おれの右腕に灼熱の痛み。どうやら超高温の熱線が上腕部を貫通したらしい。
咄嗟には信じがたいことであったが、金髪少女の指先から謎のビームが照射されたのだ。焼け焦げたおれの右腕は、もう動きそうにない。
「今度は、大やけどを覚悟なさい!」
長い黒髪を振り乱し、勝ち気な表情をした少女が、祝詞を唱えて両手を前に突き出す。少女の手の先から巨大な火球が発生して、おれの眼前に迫り来る。
無様に走り回り、全身を仰け反らせ、なんとか直撃をまぬがれた。しかし火球が少しかすめただけで、おれの体毛や皮膚は容赦なく焼け焦げた。自分が焦げる匂いを、拡張された嗅覚でたっぷり感じた。口の中がカラカラに渇いている。周囲の空気が一気に熱くなったのだ。
「それなら頭を冷やしたらどうかしら?」
全体的に水色ぽい衣装をまとったショートカットの少女が指をパチン、と鳴らすと、おれの頭上から大量の冷水が降り注いだ。
最初は「水だ! これは助かった」と思ったが、考えてみれば、いまは師走の真夜中過ぎで、あたりには雪が積もっている。すぐに全身が凍てついた。しかし今度は消防車のホースから発射されたような激しい水流が襲ってくる。容赦のない攻撃に、おれはまた無様に逃げ惑うしかない。
「みんな! 来てくれたのね!」
月の代行者たる少女は強力な援軍を得て、喜び叫ぶ。それから彼女は、いかにも玩具のように乙女チックな鈍器をどこからか取り出して、すっかり疲弊してへたり込んでいたおれの側にやって来て、おもむろに頭部を殴打した。
メキャッ……という頭蓋の一部が確実に粉砕されたであろう音が、頭に直接響いた。同時に視界が赤く染まる。とうとう致命傷を受けてしまったようだ。

「ね、さっき、タキシード仮面様」「マジ?」「うん」「やばいそれ、やばい」「やばい、やばい」「だから、ね?」「うん、がんばろ!」「やるっきゃないね!」
月よりの使者とその眷属たる四人の少女たちが、キャアキャアかしましい。女子中学生たちの場違いに騒がしいやり取りが、幻聴のように聞こえている。おれの意識は、すでに朦朧としていた。
不自然なほど、あたりに人通りがない。
かつて夢のような王国が栄え、銀色に輝く宮殿があったといわれる月。
もの言わぬ静かな月だけが、この惨劇の目撃者だ。
おれは仰向けで雪の上に倒れ、その冷たく無慈悲な月を見上げていた。

リンチとしか言いようのない惨劇が続いていた。
すでにダウン状態のおれは、無邪気にはしゃぐ少女たちに順番にマウントを取られた。ボコボコに殴られ、蹴られ、ストンピングやジャンピングエルボーを次々に食らい、さらに無理やり引き起こされては投げられ、遊び半分に間接技を決められた。骨はボキボキと何本でも折れ、面白いように血が噴き出し、馬鹿みたいに肉片が飛び散った。少女たちがそれぞれに持ち合わせている超常現象的な必殺技も、満遍なく全種類味わった。
もはやおれは「ぐぅ」とか「ぶべら」とか意味をなさない喘ぎをときおり漏らすだけの肉塊であり、かつておれであった妖魔の残骸として辛うじてこの世に存在しているだけだった。
「……そろそろいくわよ! 今回も、これで決める」
たしかに聞いた、三石✖️乃ヴォイス……。ああ最後のトドメはやはりセーラー✖️ーンの担当らしい。さすがに主役だ。いつも美味しいところを持っていく。
しかし苦痛を一刻も早く終わらせて欲しいばかりだったおれには、それは救済の合図、待ち望んだ福音であった。
……さあ早く、このおれを逝かせて、きれいに終わらせてくれ。
「ムーンヒーリング、エスカレーション!」
まばゆいスポットライトのなか、セーラー✖️ーンは両手で大きく円を描き、さらにフィギュアスケート選手のようにその場でクルクルと全身回転する。それが一段落すると手に持ったファンシーな鈍器をこちらに指し向けた。そこから得体の知れない虹色光線が放射され、おれを包みこむ。
きっと測定すれば何シーベルトとかベクレルとか、恐ろしい数値になりそうな虹色の輝きのなかで、おれは焼き尽くされていく。
異形と化した肉体と共に消え失せんとする意識の残滓が考える。
「この必殺技からすると、これは第一シーズンの後半。するとおれの最後の台詞はもう決まっている」
おれは両手を真っ直ぐ頭上に上げて、大きく開いた掌を天にかざして、ここぞとばかりに全身全霊で叫んだ。
「リフレ———————ッシュ!」
かくして、かつておれであった妖魔または悪鬼あるいは低級動物霊は、冬の満月の下、跡形もなく燃え尽き滅びたのであった。
●▶○
……そして新しい朝が来た。希望の朝だ。
ベットから起き上がり、まずは大きく伸びをした。それから窓のカーテンを開けた。眩しい光が部屋に差し込んでくる。
いつにない爽快な目覚めだった。
近頃はずっと得体の知れない悪夢に悩まされていた。ろくに眠れず、疲れも抜けきらなかった。それがまるで嘘のようだ。
家の外に出て、早朝の澄んだ空気を大きく胸に吸い込む。
昨日は関東地方には珍しい、かなりの降雪だった。見慣れたいつもの街を、白い雪がデコレーションしている。
目に映るものすべてが新鮮で、キラキラと輝いて見えた。
なんだか憑きものがすっかり落ちたような、そんな気分だった。
まるで長い悪夢から、やっと目が覚めたような。
かつての恋人たちを、私は恨んでなどいない。
考えてみれば、彼女たちを傷つけたのは私の方ではないだろうか。
いまはただ、それぞれ幸せな人生を送っていることを願うばかりだ。
洋服に着替え、往来で雪かきをはじめた。すると隣家の主婦が声をかけてくる。
「あら、精が出るわね」
「いいえ。休みで暇なもんですから。少しでも皆さんのお役に立てればと」
「あら感心しちゃう。じゃ、こっちも頼むわね」
私は隣家の前の雪かきもする。こういうのは持ちつ持たれつだ。
「……あ、なにこれ、ヒドい!」
向かいの家の女の子が、外に出てきた途端にそう叫んで、ベソをかき出した。
昨夜のうちに作っておいた雪だるまが、誰かに壊されていたらしい。……まったく、酷いことをする奴がいるものだ。
私は女の子に声を掛け、なんとか慰める。
「大丈夫、お兄ちゃんが、またすごいの作ってあげるよ」
「……ありがとう、おじさん」
「おいおい、お兄ちゃん、だろう」
「あははは」
「あははは」
「あははは」
その場にいるみんなが、朗らかに笑う。
ああ、この世界はなんて素晴らしいんだろう……。
目には見えないけれど、昼の間も月は出ている。だから私はそこにあるはずの月を見上げて、こっそりと呟いた。
「ありがとう、セーラー✖️ーン……!」
【劇終】
あとがき
以上が、数年前の出来事だ。
この前、ベランダに出て、月を見ながら酒を飲んでいた。そこで突然、失われていた記憶がよみがえった。
あの夜、セーラームーンたちの活躍によって、私は三十路のミソジニーという妖魔から解き放たれ、新しく生まれ変わることができたのだ。
おかげで私は元カノにストーカーをして起訴されることもなく、埼京線で痴漢をして捕まるわけでもなく、はたまたネトウヨ化してヘイトスピーチをまき散らしたりもせず、いたって平穏な日々を送ってこられた。
ただ一つ付け加えたいことがあるとすれば、それはタキシード仮面は大学生で、中学二年生の月野うさぎと真剣交際してる(※アニメ版。原作のマモちゃんは高校生らしいけど、それだってどうだろうね!)という驚愕の事実であります。
こいつをロリコンと言わずに、なんと言おうか。この変態め。イケメンで慶応ボーイでスポーツカー乗り回しても、あいつ変態だよ。あのコスプレも冷静な目で見ると凄くやばい。
そういうわけで、気をつけてね、うさぎちゃん。
了
お読みいただき、ありがとうございます。他にも色々書いてます。スキやフォローにコメント、サポート、拡散、すべて歓迎。よろしく哀愁お願いします。
