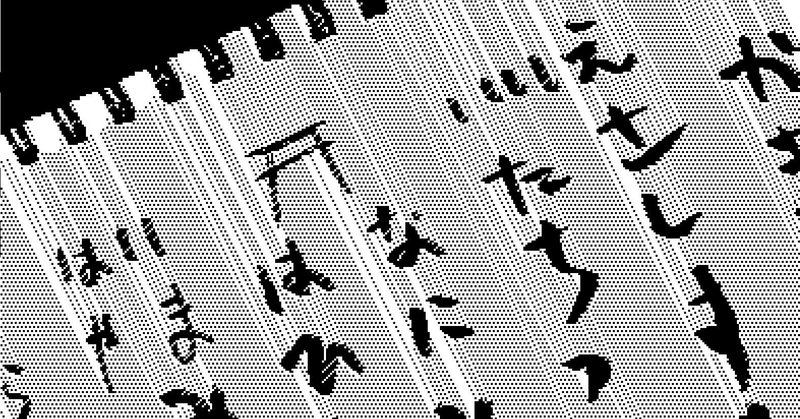
ぽっくりさん 1
じわじわと苦しめられて死ぬのは厭だなと、多分ほとんどの人が思う。たとえば死が確実に目前に迫りつつある事を日々自覚せざるを得ない老人は——逆説的になるが元気な老人ほど、現状ある程度健康であるだけ、とくにそう思うのだろう。だから世の中には「ある日突然ぽっくりと、苦しまず自覚なく死にたい」と願う人たちが一定数いて、そんな彼や彼女たちが一カ所に集まって「ぽっくり、ぽっくり、どうかぽっくり死なせて下さい……どうぞ死なせたまええ!」とか、そんなような祈りを意気軒昂と捧げている寺院が日本の何処かにあるのだと、たしか十数年前にテレビで観た。
それで、自分の友だちは実際にぽっくりと死んでいる。
まだ二十代の前半で、まさに突然死だった。文句なく、如何にも「ぽっくり」と死んだ。しかし本人は別にそのぽっくり寺院に参列していたわけでは勿論なく、多分その存在も知らなかったはずだ。
「コサちゃん(と小学生時代から自分はそう呼ばれていた)、またそうやって、おれをネタにするのかよ」と自分に対して苦言を呈するスギチ(と彼は皆に呼ばれていた)の声がまた聞こえた——ような気がした。
あくまで聞こえた気がするだけだ。しかしそうやって聞こえる気は、十数年前に彼が死んで以来、ずっとしている。

「こっくりさん、こっくりさん、どうぞ教えて下さい」
なんて、それは当時の子供にしたらお約束の遊び、ごく身近で手軽な禁忌だったわけで、小学生の頃に放課後だか昼休みの教室の片隅で何人かの女子がそれをやっていたような、遠く曖昧に霞んだ思い出は自分にもある。しかしその女子たちとはとくに親しくもなく、小学生時代の自分はまだ屈託がなく素直に明るかったことだし、ああいった如何にも後ろ暗くて罰当たりなムードの集いに参加することもなかった。なので実際に「こっくりさん」と唱和しながら十円玉に指先を置いたとか、そんな記憶はない。
しかし後年、スギチが死んで暫くして、気がつくと自分は同じような呪文を繰り返し唱えるようになった。
「ぽっくりさん、ぽっくりさん」
そうやって地下鉄の中だったり病院の検査室やなんかで定期的に頭のなかで呟くように、ときには実際に声に出して唱える。つまり主には現実が辛く耐えがたく、どうにもやりきれない気分のときに唱えるわけだ。
「……ぽっくり逝きやがって、うらやましいな、おい」
呪文に続けて、自分からすると斜め上、たとえば部屋の天井の隅の辺りに浮かんでこちらをじっと見下ろしているように見える——つまり見えると自分で想定している、いわば透明な存在に向けて文句をつける。生前と変わらない調子で、わざとらしく絡んでみせる。
「お前はぽっくり楽に死にやがったけれど、おれは何だかんだこうやって苦しんで生きてる……もう、それだけで偉いだろ? だからちょっとは何とかそっちの世界から手を回して、おれの人生もっと上手い事やってくれても全然いいんだぜ?」
ここ十数年の自分は、そんなふうに存在不確実な彼の霊魂に対して幾度も語りかけてきた。考えようによっては健気な友情のようでもあるが、実際の所はどこまでもいっても罰当たりな自己満足でしかなく、それにすっかり開き直っている。自分でもよく分かっている。
✗
さて、これもまた罰当たりな話だが、大学を出た後に働いていた沖縄から搬送され埼玉の実家の一室で棺に納まっていたスギチの死に顔を見て、やっぱりそれは全くの冗談のように思えた。
和室に横たわる白い棺、顔の位置にちょうど開いた窓から覗くスギチの顔はただ眠っているようで……つまり、まるで安っぽいコントのような光景としか言いようがなかった。しかし若くしての突然死であるだけに事件性も疑われて司法解剖に回されたらしく、そうなると何かの切っ掛けで突然息を吹き返すという可能性は決定的に絶たれているわけで、ようするに圧倒的に取り返しのつかない状況——不可逆性の最たる「死」というもの——をリアルタイムに自分が目撃しているのだという、そのドラマ性によって逆にまた現実味が失われていくような、そんなややこしい気分でもあった。
「うおおおーん」
その一方、急遽連絡をつけて地元の駅前で待ち合わせ、間に合わせの喪服が如何にも似合わないと言い合った小学校の同級生数名のうちの一人であったケンケンは棺を前にしてウワッとばかりに突然そこで泣き崩れ、その様子に自分はちょっと引いてしまった。
「……でもこうやって感情を素直に出せるのがケンケンの素朴な良さだったなと改めて思いはするけど、実際ちょっと吃驚するよな」
斜め上の天井を見上げて、自分は頭の中で何となくスギチに語りかける。すると何となくそこから自分を見下ろしているような気配があり、そのとき何となく「……やっぱ性格悪いな、コサちゃんは」というスギチの声が、如何にも彼らしく思える返事が聞こえたような気が、何となくした。いまになって考えてみても、やっぱりそれはどこまでも「何となく」という事でしかないのだが。
「う、おおおおおお、スギチぃぃ……こんなん、なっちまってよぉぉぉ」
そんな事を自分が考えている間もケンケンはさらに派手に男泣き、いまにも棺にすがりつかんばかり。同じ部屋にいるスギチの両親はそれまで感情を押し殺しているように見えたが、さすがに堪えきれないように俯いた。一緒に来た数人の同級生も皆下を向いて神妙な表情を浮かべている。自分としては、どういった感情に身を任せるべきなのかやっぱりよく分からず、そこで「笑え」と言われたら笑えるような気もしていた。
「にしたって、ちょっと泣きすぎだよな? ……まあ、そこがやっぱりケンケンらしさなんだけど」
「だからコサちゃん、性格悪いぞ」
「でもそうやっておれを『性格悪い』って指摘する、その視点があるって事自体、スギチもおれと同じように性格悪いって事じゃん?」
「それは、たしかにちょっと否定できない。でもケンケン、昔から純粋だから……」
「そういえば、大学入るくらいのタイミングでケンケンに関係切られた、電話もメールも全無視されて、すっかり音信不通になったとか、そういう話つい最近もネタにしてたろ? おれたち二人で」
「いや、まあそれは」
「むしろスギチの方が気にして、よくこの話題出してなかった?」
「……」
そんな会話で架空上のスギチを言い負かしたような気分になり、現実の空間では彼の遺体が入ったお棺を前にケンケンはいつまでも吠えるように泣き続けている。やっぱりコントのようだなと、そのとき自分は思っていた。
ところで何でそういう場面で斜め上を見上げるようになったか、それには理由がある。
まあしかし別にそう大した理由でもない。自分の母親が以前に大きな手術をした際に臨死体験をして、そのときはベッドに横たわる自分の身体を上から見ろしていたらしい。その話が頭にずっとあって、だから祖父が亡くなった場面では何となく二人して病室の天井を見上げたもので「……あの辺から見てるのかしらね」と母親はそこに向けて手を振ってみせたりもした。それを思い出したのだ。
「そういうわけで、スギチもいまその辺漂ってたりする?」
「……」
魂的な存在なのだから、とくに語りかけずとも自分の考えていることは伝わっているだろうと何となく想定する。「うぉぉぉーん」ケンケンの泣き声が響く。
「おー、ケンケン、いよいよベタすぎる泣き演技だ。おれが監督だったら完全にNGな。……まあ実際演技でもないんだろうけど」
「……」
「って、おれ、さっきからちょっと発想が罰当たりかな? この場の主役的には、どう思う?」
「……」
宙に浮いている——と自分が想定している方のスギチは今度は何も応えず、如何にも厳かな死者の魂のように、この場面をただ黙って見下ろしている……ようにも思えた。それはこの場面における適切なスギチの台詞が自分の中で浮かんで来なかったからだろう。
そういえば「罰当たり」の意味で、スギチはよく「罰被り」という表現を使っていたなと思い出される。あれはどこからきた言葉なのだろう。……いま検索したら、どうも九州地方の方言らしい。しかしスギチの田舎が九州にあるというわけでも多分なかった。きっと何か漫画や映画だの小説から拾ってきた言葉だろう。「ばちかぶり」という語感も何だか面白い。思えば小学校の頃からスギチはずっと変な奴で、本や映画の趣味も他の同級生とは違っていた。あの頃はネットもそこまで一般的ではなかったわけで、一体どこからそういう文化知識を仕入れていたのだろうか。そういうスギチの影響を昔から自分も受けており、それで現在の自分が構成されているともいえる。
まあそれはともかく、スギチの「罰被り」な行動を思い返してみる。
「コサちゃん、また罰被りやっちまったよ」
そんな言葉でいきなりはじまる報告のような愚痴のような告解めいてもいる電話を東京のアパートで自分は受けたり、あるいは帰省してきたスギチと地元をドライブしながら直接話を聞いたものだった。
スギチは海洋系の学部がある大学に進学して、二年次からは三陸海岸近くのキャンパスに通うため一人暮らしをしていた。たしかイソギンチャクだかフナムシだかの研究が専門だと言っていた気がする。そういう如何にも不気味そうな実験対象生物が蠢く水槽の成分調整をうっかり誤って大量死滅を引き起こして責任を問われたとか、酒の席で偉そうな人生訓を垂れる教授にそこにあった氷をつい投げつけたら大問題に発展したとか、長く険悪な関係だったギャル男みたいな院生のスキューバダイビングの道具一式に何人かの学部生と一緒に小便を引っかけたクリスマスの飲み会帰り、それがあっさり発覚して小便小僧たちを代表して散々に殴られたとかで「……とんでもないサンタがやって来たもんだぜ」なんて意味が分からない決め台詞でその話を締めてたなあ……なんて、いますぐに思い出せる限りでも「罰被り」ぽい話は沢山聞いた。
勿論、そういう単なるミスとか不注意あるいはアルコールと人間関係上のトラブルによるものだけでなくて「罰被り=罰当たり」行為としてはごくポピュラーで正統な迷信・俗信における禁忌、そういうものも万遍なくよく侵していた。
好奇心の赴くまま地元の心霊スポットの古い神社の社なんかにどんどん踏み込んでいくとか、そんな類いの行動は小学生時代からごく頻繁にみられた。しかしそういった「罰被り」行為が己の良心に全く咎めず何もビビらず感じない……とかそういうわけでもなく、むしろ怖い話だったり怪奇味のある漫画や小説、カルトぽい映画を子供時代からずっと愛好して「人知を超えたもの」に対する恐れや尊崇の念も充分に持っているようでもあった。しかしどこまでも好奇心を優先させてしまう結果「また罰被りしちまったよ……」と自分の行為を反省して嘆きつつ、でもどこかしら嬉しそうに報告をしてくる。スギチはそんな奴だった。
✗ ✗
「……御神域」
「あー、あそこな。あれだ、ケンケンが」
「白い車が来てる! って、いきなり叫んだ」
「そうそう」
遺体が置かれた部屋の天井斜め上をまだぼんやり見つめていると、スギチの方から語りかけて——きたような気がして、それを思い出す。
自分たちの地元の近くには、何年かに一度、皇室による祭祀が催される為に保護されているらしい「御神域」と呼ばれる一帯があった。
十八とか十九の夏に自分とスギチは一応浪人生で、ケンケンはたしかパン屋の早朝バイトをしながらボクシングとかテレビ番組のSASUKEの選手に漠然と憧れていた……つまりとにかく暇とエネルギーを持て余しており、それを深夜の無意味な長時間ドライブあるいは小学生時代に逆戻りしたように雑木林や公園での昆虫採集、それから誰かの部屋に集まって対戦ゲーム、あとはその辺の電柱に無意味に登ってみるとか平日の昼間から全力でフリスビーをやる……そんな事に費やしていた。ようするにいつも退屈で、これといった意義も意味も感じられない毎日がダラダラと続いていた。
そんなある日の夕暮れ時、何の意義も生産性もなく何となく自転車で地元周辺を流していた我々三人は、やたら壮大で立派な門を前にした。もちろんその門は厳格に硬く閉じられていて、だからこそ自分たちはそこをよじ登り始めた。ただの思いつき、意味のない衝動的な退屈しのぎだった。間もなくして、自分たちはその門の上に立った。
門の上から見渡せば、鬱蒼と生い茂る木々、夏の緑が暗く色濃い広大な敷地が目の前に開けた。奥に何かが秘匿されているような気配の静けさで、その奥へと続くのだろう門からの道は抜かりなく整備されていた。どこか不自然でちぐはぐな公共的な整然さ、そして何かしら張り詰めた空気を肌に感じた。幅の狭い道路には、木の枝の一本も落ちていない。なるほど、ある意味で神域だものなあとそこで思い当たり、自分は妙に納得をした。御神域の奥深くには古代の朝廷にゆかりのある墳墓のようなものが保全されているのだと、そんな噂もあった。

「よし行くぜ」とまずはスギチ、それから自分が門から敷地の中へと飛び降りてスタッと軽やかに地面に着地、それであっさりと侵入は成功した。続けて飛び降りようとしたケンケンが、門の上でいきなり大声で叫んだ。
「……白い車が来てる!」
要するに、その「白い車」というのはパトロールとか敷地を常駐管理する職員の車で、防犯カメラなどで我々の侵入を察知してやってきたのだと思われる。しかし門の上からケンケンが「コサちゃん、スギチ、白い車が! 向こうから!!」と如何にも慌てた声で繰り返し何度も叫ぶものだから、自分もスギチもたちまち慌ててしまった。
今度は内側から急いでその門をよじ登りながら「謎の白い車……皇宮秘密警察……隠匿された聖域では侵入者は殺され或いは洗脳もしくは改造手術……おれたちは三人とも何となくまつろわぬ民、たとえば土蜘蛛族とか鬼の末裔くさい所もあるから、そういう因縁や因果も発動するかもしれないカルマ……よし、逃げよう。とにかく逃げなくては」なんて、その頃ちょうど読み耽っていた伝奇SF漫画だとかオカルト本から仕入れた怪しげなイメージが頭の中を急速に駆け巡り、とにかく必死に逃げ出した。多分スギチも似たような事を考えていたのだろう、いつになく素早い動き。そしてケンケンは壊れた機械のように「白い車が……」と繰り返す。何となくだが、ケンケンは伝奇オカルトというよりはXファイル的な恐怖を感じていたように思われる。あの頃の趣味趣向的にケンケンはそっちだ。まあ実際その敷地内——御神域に、極秘来日したVIP宇宙人が隠れ住んでいる……そんな可能性だってなくはない。つまり高天原は別銀河にあり、天孫降臨は実の所は……とまあ、そんなことはともかくとして。
「ジグザグに逃げろ!」
中学の頃に広い農道の真ん中で典型的な郊外型ヤンキーの集団に囲まれてカツアゲされかけるも田んぼや畑のあぜ道をとにかくジグザグに走って見事逃げおおせた……そんな成功体験を持つ自分が指示を飛ばし、スギチとケンケンはそれに従った。しかし御神域周辺は河原だったり林だったり畑だったりの平野地帯の典型的な田舎風景でジグザクに走り抜けるような裏路地などそもそもなく、御神域から恐ろしい追っ手が放たれているような気配もなかった。しかしそれでも何となくジグザグ気味に草叢や林をかき分けたり休耕中の畑を突っ切ったり、ともかく気の済むまで自分たちは走って逃げた。
✗ ✗ ✗
「……っていう、懐かしい思い出な」
「あそこでもし捕まってたら、どうなってたかな?」
そうやってスギチが聞いてくる、ような気がした。
「別にどうもなってないだろ。ちょっと注意されて終わりだよ」と自分は答える。
「そうかな?」
「そうだろ。それに、こんな話は他にもいくらでもあるじゃん。それこそ、罰被りなやつが沢山」
「うん、罰被りだな」
と言って中空に浮かんでいるスギチが頷いてみせた、ような気がしたのだった。
そうやって中空に浮かんで話しかけてくるスギチという自分の妄想の一方で、お棺の窓から覗ける現実の死に顔はやっぱりただ眠っているように固まりきっていて「うおおーん」とケンケンはまだ泣いている。一体いつまで泣くのだろうかと思った。
ところで、そのときのケンケンは暫く会わない間に昔のテレビドラマ『とんぼ』に主演していた頃の、いわゆるチンピラ期の長渕剛みたいな風貌になっていた。だからいまこの場面に長渕の曲をBGMとして流しても面白いんじゃないかなとふと思いつき、帰り際の玄関で「なんかこう、長渕ぽいケンケン……通称『ブチケン』みたいになったね、ケンケンは」と本人にそれを伝えると「え、そんなことねえって。やめてくれよお」と否定しながらも短髪で白シャツにシンプルな黒いスラックスに革靴、でもベルトだけ妙にギラギラしていて「これは蛇皮で何万円もした……」とかケンケンは言うわけで、そこら辺がまた如何にもブチケンぽいなと自分は感心した。
そんなどうでもいい会話をしていると玄関先で見送ってくれたスギチの両親と自分たちも一瞬ちょっと空気が和んだような気がしたが、ごく近い親戚らしいゴマ塩頭の中年男性が玄関から急に入ってきて、彼は入ってくる時点で既にもう涙を目に一杯に溜めていて、その人を迎えたスギチの父親が堪えきれずにワッと泣き出して、自分たちは結局いたたまれない気持ちでその場を後にした。
「……こいつの弟のね、リョウも死んじゃったでしょ。だから私たち、この現実をどういうふうに受け止めていいか、どうにも分からなくて」
最初に部屋に通されてお棺を前にしたとき、しばらく皆が無言になったところでスギチの父親が言ったこの言葉も、よく覚えている。

スギチが死ぬ数年前に、スギチの弟であるリョウも若くして亡くなっていた。元々心臓が弱く、長くは生きられないだろうと、じつは小さい頃から言われていたらしい。そんな事は全然知らなかった。リョウが死んでしまったという報告の電話をスギチから受けて、そのときはじめて知った。電話を受けた自分は旅行中で、屋久島の安宿で寝転んでいる所だった。だからリョウの葬式には出ていない。
小学校の頃からスギチの家に遊びにいけばリョウがいて、たしか二つか三つ下だったリョウはスギチに比べたら大人しい性格で身体もまだ小さく、しかし生意気な所もあるとスギチはよく言って兄弟喧嘩も頻繁にしていたようだが基本的には仲は良さそうだった。兄弟二人で妙にマニアックな漫画やゲームなんかを共有していて、一人っ子の自分としては、それが随分とうらやましく思えた。そしてどちらかと言えば自分のゲームの趣味はスギチよりもリョウの方と合って、無職で根無し草の侍になり異様に物騒な大菩薩峠みたいな土地を彷徨いて気まぐれに辻斬りしたり逆に困った人を助けたりしながら剣の腕をひたすら磨く……というゲームがまだ借りっぱなしで、多分いまでも実家の部屋の押し入れにあるはずだ。しかし自分がスギチに貸した剣闘士として古代ローマのコロシアムで闘って最終的には皇帝を暗殺したりもしつつ基本的には地道に身体を鍛え続けるというゲームもそのまま貸しっぱなしになっている。だからお相子。むしろ剣闘士の方は軽くプレ値がついていた気がする。まあそんな事、如何にもどうでもいい話だが。
✗ ✗ ✗ ✗
「……だから食ったんだよね」
「え、マジかよ。そんなん実際によくやれたな」
「焼き場で隙を見て、パッと口に入れて、すぐ飲み込んだから」
そんなふうに「弟の骨を食べた」という話を聞いたのは、たしかスギチが三陸海岸から帰省してきた年末の休み、スギチが親戚に譲って貰った後部の屋根が幌になっている古いジムニーの助手席だった。
その頃読んだ本にあった「母親の骨を火葬場で食べる」というエピソードを自分が話題にすると、スギチはあっさり「そういえば、おれも食ったよ」と言い出したのだ。
「自分の中で生きたらいいっていうか……そのときは『おれを通して見てろ』って思ったかな」
いつになく改まった口調のスギチがクラッチを踏みシフトレバーでギアチェンジをかけると、ガクッと車全体が振動する。前輪のスプリングが駄目になりかけているが、型が古すぎて交換するパーツが見つからないらしい。車体後部を覆う黒い幌の隙間からは冬の外気が絶えず入ってきて、とにかく音がうるさいヒーターの熱風、それと冷気が相殺し合って温冷渦を巻いている……そんな車内の空気感はよく覚えているが、そのとき自分たちがどこに行こうとしてたのかは思い出せない。
たしか夜のバイパス道路をまた意味もなく走って何処かの心霊スポットに行ってみようとか、あるいは年明けの初日の出スポットでも探していたのだと思う。自分たちの地元は関東平野の真っ只で小高い山とか高台なんて見当たらない、どこまでも平坦とした殺伐。だからきれいな日の出を拝める場所なんてそうそうない。しかし何にせよ、その頃スギチが地元に戻ってくれば、とりあえずそんなふうに車で出かけたものだった。
「でもセミなんかは、揚げるとエビと殆ど一緒だぜ」
「それは何だか想像つくな」
「一番キツかったのはカブトムシかな。あれ生で食べると、いかにもカブトムシだなって……あのカブトムシの匂いが、口中に広がる」
「げえ、何だよそれは。何で生で食うんだよ。いや、そもそも食おうとするなよ。おれは調理してるやつでも食いたくないね、絶対食わない」
「あと幼虫とかザリガニはもう普通に食えるじゃん」
「いや、食えないだろ」
こんな会話もよく覚えている。スギチは弟の骨も食ったが、そうやってその辺で捕まえた昆虫もよく食っていた。
「ポールシフトなんかで地球環境が激変しても昆虫だけは確実に生き残る。だから昆虫食にいまのうちに慣れておけば、どんな世界でもきっと生きていける」
たしかそんな思想に基づく訓練とか予行演習という名目だったが、結局はやはり行き過ぎた好奇心の為だろうと思われる。昆虫の他にもウシガエルとか蛇を食ってみたという話も聞いた。そもそもウシガエルは食用に輸入されたとかで普通に美味いけど、まずは息の根を止めるときにハンマーで頭を叩く、その頭蓋骨が恐ろしく固い……なんて語っていた。そのうちに倫理とか法律的な縛りを超えて、そこら辺を歩いている人間も「捕まえて食ってみた」とか言い出しそうだなと思っていたけれど、よく考えれば現実に弟の骨も食っていたわけだ。
「……ほら、罰被り。さっきからコサちゃんも結構ひどい事言ってるぜ。こうやってまたおれと、それにリョウまでネタにしてよ」
そうやって現在の自分に語りかけてくるのは、十数年前にぽっくり死んで、いわば「ぽっくりさん」だとか、そんな妖怪や憑神の類だったり、あるいは曖昧な死の概念と化して自分の周りを浮遊している、そういう透明な存在なのだった。
【この先上手くまとまらず、次回につづく ※なるべく近日中に上げます】
お読みいただき、ありがとうございます。他にも色々書いてます。スキやフォローにコメント、サポート、拡散、すべて歓迎。よろしく哀愁お願いします。
