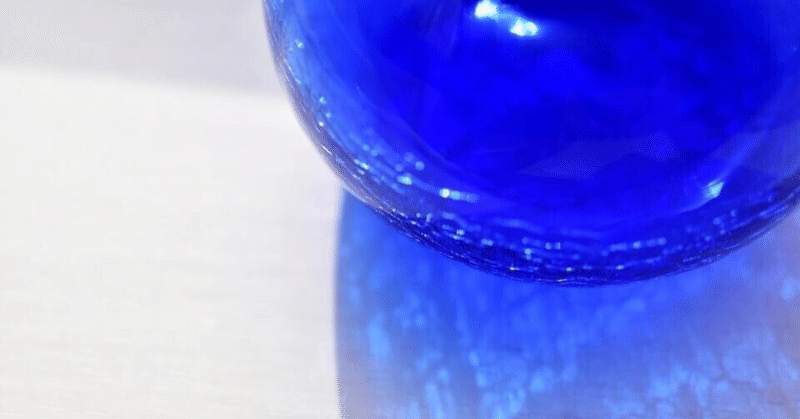
完璧な人 第6話
夕暮れになってさえ
外はしつこいような暑さでも、
ほどよく冷房のかかるリビングでは
気持ちがいい。
窓際の席を陣取って
キョーコさんと野々宮さんが
向かい合ってボードゲームをしていた。
「シーカ?」
「凛、お前分かるのか」
「珍しいわね、拓実なんかは
全然知らなくて
教えるの苦労したけど」
子どもの頃よく
やったから、と
痛んでボロボロのゲームを見る。
「これ、汚いわよね。
でもアタシたちの宝なのよ」
今のところ互角みたい。
「それにしてもこの色と
デザインはないわ。
もっと美しくしてくれたら
気分もアガるのに。
海斗、アンタみたいに
美しく、ね」
バチンとウインクしたキョーコさんに
野々宮さんは全く動じない。
「あ、分かります。分かる。
私、以前ベトナムのホテルで
象嵌の精巧な作りの
ボードゲームを見たんです。
木はマホガニーみたいで
艶があって。
それで、日本でも
こんな美しいゲームを作ったら
売れるんじゃないかって、
思い、思って」
「象嵌、か」
駒をクルクルと
指で回しながら
野々宮さんが呟く。
「そうなんです。
そんなに高級なものじゃなくても
色合いをもっと可愛くしたり
素材を変えたら
素敵だと思う」
はい、ゲット〜!
海斗、何ボーッとしてんのよ!と
駒を取ったキョーコさんを気にせず
野々宮さんは急に
私の方を向いて言った。
「凛。
そのアイディア
貰ってもいいか?」
「え?は、はい」
何だかよくわからないうちに
返事をしてしまった私を見るなり
ガタンと席を立つ。
「悪い!用事が出来た。
凛、あと続けておいてくれ!」
えっ、と動揺する私に
「ま〜た、始まったわね。
凛ちゃん、相手してくれる?」
と、慣れた様子のキョーコさん。
途中から拓実くんやのんさんも来て
ゲームを見守る中、
結果は2対2で
引き分けだった。
「凛ちゃん、すげ〜。
キョーコさんと引き分けだなんて!」
「途中まで野々宮さんが
やっていてくれたから」
野々宮さんが触れていた
駒を自分が使うのは
何故かドキドキした。
私は優しく包むように
それを扱った。
「凛ちゃんは手がやり慣れた
感じよね。
楽しかったわ」
そうそう、と
キョーコさんは思い出したように
リビングに一人ひとり
振り分けられた引き出しから
封筒を出し、
派手な色合いの紙を一枚、凛に渡す。
「これ、アタシの
個展のチケット。
あまり日がないけど
暇があったら行ってみて」
えっ、いいの?と
チケットをジロジロ見ながら喜んでいると
拓実くんが言う。
「何だ〜。
凛ちゃんと一緒に
行きたかったな!
俺、先週行っちゃったんだ。
俺には絵は全然分からないけど
感動するよ!」
一緒に行きたかったな、を
再度繰り返す。
残業のない日の帰り、
幾らか暑さは抑えられた時間帯に
キョーコさんの個展に
行ってみた。
10畳ほどの部屋が
2つ、繋がっている。
人の入りがすごい。
最終日間近なのに
数多く飾られた入り口の花から
甘い香りが漂って来る。
キョーコさん、
人気あるんだな。
中に入ると
見たこともないような色の存在に
圧倒される。
抽象画なのに
メッセージがダイレクトに
伝わってくるみたい。
派手なようで
力強いようで
混沌とした
抜け出せないような弱さ。
苦しみに
押しつぶされそうでも
負けまいとすっくと
姿勢を正して立っているような、
見ているだけで
自然と涙が出てきそうな
絵の数々。
金縛りにかかったように
立ち尽くして見ていると
声をかけられた。
「凛、お前も来ていたのか」
「......野々宮さん」
泣きそうな感極まった顔を
知り合いに見られてしまった。
バツが悪いな。
少し赤面したような気がする。
「圧巻だよな」
2人で絵に向き合っていると
腕を組んだ野々宮さんがポツリと言う。
「こんなの
今まで見たことがないです」
「そうだな、アイツにしか
表現出来ない技だ」
一緒に絵を見て回る。
「凛は絵が好きなんだな」
「はい、子どもの頃から
よく美術館に連れて行かれて
それで」
野々宮さんと一緒にいると
緊張して
上手く話せない。
どうしても丁寧語が
まじってしまう。
硬い人間だって
思われていないといいけど。
「どんな絵を?」
「好きなのは、
西洋画家なら
ジョン・エヴァレット・ミレイ」
「ああ、オフィーリア、
あれは凄い。
明るい色彩と
水に浮かんだ、死のコントラスト。
一度目にしてしまったら
忘れられないな」
「野々宮さん、分かるの?
オフィーリアもそうだけど
アヒルの子も好き、です」
「意味が深い少女の絵か。
女性が好みそうなモチーフだな」
「すごい!よく分かりますね!」
「ラファエル前派は俺も好きだ。
画家たちの人生も
ドラマみたいだろう」
そうなんです!と
半分興奮し
半分緊張したままで言う。
野々宮さんは無表情を
崩さない。
美しい横顔と
すらっと長い四肢、
優雅に動く仕草が
完璧で、怖い。
「日本画も見るのか?」
「はい。東山魁夷が1番好き」
「あれは色が深いな。
そうか、色か。
ミレイも色が特徴的だし
凛は色に敏感なんだろうな」
だからコイツの絵にも
泣きそうになる訳だ、と
キョーコさんの絵を指して続ける。
「私、泣いてません」
そう言った瞬間、
彼はポケットを気にする。
「悪い、電話だ。
凛、またシェアハウスでな」
颯爽と外に出て
電話を受ける野々宮さんを見て
思わず一つ、大きく息をついた。
緊張したぁ。
でも不思議。全然嫌じゃない。
色に敏感、なんて
初めて言われた。
そうかな、そうだったら嬉しい。
夏にシェアハウスに入居したのは
正解だった。
花火大会やBBQなどの
イベントが続き、
人見知りする私でも
早く慣れることが出来た。
会話に混じっていたていねい語も
いつしか自然になくなっていった。
イベントにはいつだって
拓実くんが私の近くに
寄り添っていて、
いろいろと気遣ってくれた。
「凛ちゃん、線香花火競争しよう。
どっちがいい?」
「凛ちゃん、肉焼けたよ。
すげぇ、いい匂い!」
凛ちゃん、と
いつでも優し気に
呼びかけてくれる。
日の当たるところにいると
拓実くんの明るい色合いの髪や目は
光って淡い茶色に見える。
彼はお日さまだ。
明るい黄色のような
白に近いような
そんな色。
私に暖かさや元気を
与えてくれる。
「凛ちゃ〜ん、
今度一緒に下着買いに行かない?
セクシーなやつ〜!
ダーリンがね、
キワドイのが見たいんだって〜!
きゃ〜っ‼︎」
のんさんは1人で興奮して
ぎゅっと私を抱きしめる。
「あら〜、酷いじゃない?のん。
アタシも混ぜてよ」
「え〜っ、キョーコさんも行くの?」
「そうよ、
オンナ3人で
仲良くしましょうよ」
のんさんやキョーコさんは
妹のように私を
可愛がってくれた。
ただ1人、野々宮さんだけは
多忙なようで
あまりイベントにも
顔を出さなかったけど、
何故だかイベントの
ご馳走だけは
作っておいてくれることが
多かった。
「まあ仕方ないわよね、海斗は。
仕事の鬼だから」
「それにしてもよく
こんなご馳走を
作る時間があるよね〜」
彼の作った
柔らかいローストビーフに
至高の気分に浸りながら
考える。
野々宮さん、
オフィスではどんな感じで
仕事しているんだろう。
たまに野々宮さんを見かけると
心臓が跳ね上がるように鳴り始め、
暫くドキドキが止まらなかった。
心臓は魂のすみかだって
誰かが言っていたけれど、
この人にだけは
緊張が解けないのは
完璧だからかな。
だけど同時に
彼に会えた日は、
まるで子どもの頃
お気に入りのフワフワのぬいぐるみを
買ってもらえたときのように
嬉しくて自然と
口角が上がりっぱなしになった。
会話が出来た日の夜は
ベッドで何度も何度も
そのたった数秒の出来事を
頭の中で反芻し、
幸せな気分に
どっぷり浸って眠った。
こういうのって、
推し、っていうのかな。
野々宮さんは高嶺の花だ。
あんな完璧な人
到底私にはおよびじゃない。
アイドルのように
見かけるだけで、
テレビ画面の数分の1のところで
踊っている姿を見るだけで、
勇気を貰えるような
全身から女性ホルモンやら
アドレナリンやら
その他生きていくために必要な糧が
自然と溢れて出てくるような
そんな、天上の、存在。
一緒のシェアハウスに
推しと同居しているなんて
最高に幸せ。
そんな風に
ニヤニヤしながら
彼のことを考えて、眠った。
葉の色づきの美しさも
だいぶ見慣れた頃、
新しい毛糸を買いに
チェーン店の手芸屋に足を運んだ。
この間買ったばかりの
あの白いコートに
似合うマフラーを編もうかな。
いろいろと見て回ると
ふと、濃い青色の
純毛の毛糸に目を奪われる。
高級な作りが
偉そうな態度に見える。
野々宮さんみたい。
いつだか
彼はこんな色のネクタイをしていた。
濃い青色に緑。
その青色と、
同じ種類の明るい緑の
毛糸を幾つか買って、
スキップでもしたくなるような
嬉しい気分で
帰途についた。
アイドルを推している人って
その推しの色を
身につけるって聞いたけど、
気持ちが分かるな。
この色を身に纏っていたら
まるで野々宮さんと
いつも一緒にいるみたい。
シェアハウスに帰ると
リビングに拓実くんがいて
英字新聞を読んでいた。
「凛ちゃん、買い物?」
「うん、新しいマフラーを
編もうと思って」
「へえ、どんなの?」
拓実くんに近寄って
さっき手にしたばかりの
まるで宝物のようなその毛糸を
丁寧に見せる。
綺麗な色でしょう?
嬉しい気持ちを隠せないまま
笑いかけた瞬間、
普段穏やかな拓実くんの顔が歪んだ。
「拓実くん?」
いきなり強く
抱きすくめられて
持っていた毛糸が
ぽん、ぽん、と落ちる。
「拓実くん?
どうしたの?」
それ以上の上手いことばが
見つからなかった。
拓実くんがくぐもったような
苦しそうな声で
吐き出すように言う。
「凛ちゃん、好きだよ。
初めて会った日から
ずっと好きだったんだ。
俺と付き合って」
「え......」
どうしてそんなに唐突に
苦しそうに想いを伝えるの。
まるで何か
どうしても壊せない
障壁が目の前にあるような
言い方だった。
でも、普段助けてくれるこの人を
苦しみから救うことが
出来るのが自分だったら嬉しい。
拓実くんと付き合ったら
きっと毎日楽しいだろう。
幸せな、優しい日々が
過ごせるだろう。
「ありがとう、拓実くん。
すごく嬉しい。
うん、いいよ。付き合おう」
第7話はこちら↓
前回はこちら↓
ありがとうございます!頂いたサポートは美しい日本語啓蒙活動の原動力(くまか薔薇か落雁)に使うかも?しれません。
