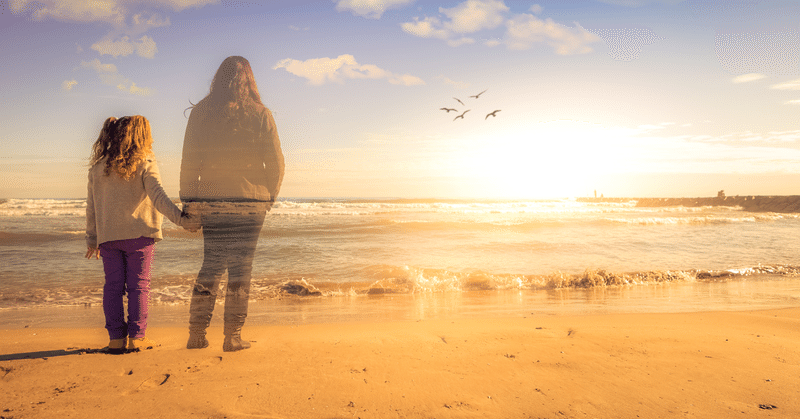
不在に馴れまいとして思い出し、言葉によって存在させることで、無常に抗う
拝啓
お手紙、ありがとうございます。
あなたからのお返事を心待ちにしている自分がいました。お返事が来たときはやはり嬉しく、手紙とはこんなにときめくものなのか、と思っております。
何かを「待つ」時間。
来るかもしれない、来ないかもしれない、いつのことかわからない――けれど、こうしてお便りを待つということは、なんて贅沢なことなのだろうと感じております。
本日は暦の上で入梅ですが、ひと足先に梅雨入りしたところも多いようですね。静かな部屋の中で聴く雨音は風情がありますが、近ごろの線状降水帯はどうもいけませんね。この頃は雨と聞くと、つい「大きな被害になりませんように」と考えてしまいます。
『幻の光』、読みました。
宮本輝さんは、実を言うと私には馴染みが薄い作家さんでした。読んだことがないわけではありませんし、嫌いなわけではなかったのですが、なんとなく読むたびに胸がつかえるような感傷を感じてしまい、若干避けてきたように思います。
今回、改めて短編を読みました。映画はまたいずれ観ようと思います(余談ですが、是枝監督についても私はぼんやりと「感傷的(良くも悪くも)」という感想を持っており、宮本輝さんとはとても相性がいいのではないかと感じています。いずれ鑑賞するのが楽しみです)。
さて、死者に問いかけ続けるゆみ子の心持は、実を言うと私にも覚えがないわけではありません。悲しい別れを選んでしまった親族がおります。ですからその、最後の時をなぞり続け、理由を問いかけ続ける人の姿には見覚えがあるのです。
じめじめと暗い尼崎から、海鳴りの響く極寒の奥能登へ。幻の光の主人公ゆみ子は、祖母と夫との理由のわからない突然の別れに翻弄されます。
これまで姿を消してしまった人と同じように、もう戻らないのだろうと思った「とめのさん」が嵐に遭わずに戻ってきたとき、彼女はようやく奥能登に根を下ろしたのではないかと思います。
いつも彼女の意思とは無関係な場所で、決定的な物事は起る。
しかし生と死は、人生とは、そういうものなのかもしれません。
尼崎を出るときになぜかついてきて見送ってくれた漢さんと、能登でゆみ子の過去を受け入れるとめのさんが、どちらも男とも女ともつかない雰囲気を醸しているのは偶然ではないように思えます。
『幻の光』を読み終わったとき、筒井康隆『ジャックポット』の中の「川のほとり」という短編を思い出しました。
『ジャックポット』については、以前「シミルボン」で記事を書いています。
ひょっとしたら筒井康隆はあまりお好みではないでしょうか。作風としては宮本輝とはある意味対極にある作家かもしれません。しかしどちらも大阪の出身で、年齢は10ばかり筒井氏が上ながら、文学賞の選考委員として肩を並べたり、同時代の作家として文学界を牽引してきたふたりであろうと推察いたします。
筒井氏は、2020年にひとり息子の筒井伸輔さんを癌で失っています。「川のほとり」はその息子さんと夢の中で再会する短編です。『ジャックポット』の表紙の装丁は画家であった息子さんの絵のコラージュになっています。
結局は自分の見ている都合のいい夢でしかないんだろう、と言いながら、小説の中の「おれ」は夢の中の息子に見惚れ、去らないで欲しいと願い、語りかけ続けます。「おれ」に何か、思ってもみないことを語りかけてくれる息子は、「おれ」の想定外ということだからもしかしたら夢ではないのかもしれない、という祈りに似た切なさを感じます。夢うつつの中の「対話」によって成り立つ物語です。
ミステリと違い何か特別なネタがあるわけではないので、あなたが未読か既読かわからないまま引用させていただきますが、「川のほとり」の中には次のような描写があります。
「死んだあと、こんなに長いことわしと話してくれたのは初めてだな」と、おれは言う。「今までは端役みたいにちょっとだけ出てきたり、すぐほかの誰かと入れ替わったりだった。あれはやはり、お前があまり長いこと出ているとわしの感情が昂って夢から醒めてしまうからだろうなあ。夢には睡眠を持続させようとする機能があるからね」「そうだろうね。だから今はもう、あまり気にしなくなっているんだよ。父さんは僕が死んだことに馴れたんだ」怒りもせずに息子はそう言った。
亡くなったことに、馴れる。
これは親しい人が亡くなった時には非常に恐ろしいことに感じます。大切な人を忘れてしまうなんて、不在に馴れてしまうなんて、恐怖でしかないと思います。しかしもし慣れずにいたら、それはそれで地獄です。日々びんと張り詰めた悲しみの緊張の中にいることは、大変なことです。慣れたくないけど慣れなければいけない。慣れないけれど慣れていく。
死によって別れることは、どのような形の別れでも辛いものですが、自死による別れ、しかも遺書もなく理由もわからないと言うのは到底、受け入れることができません。たとえ遺書があったところで、とても納得できるものではなく、残された遺族は悔恨に苛まれ続けるのです。
たとえ病と言う理由があったとしても、逆縁は同じように強く自責や後悔を感じるものと思います。
ゆみ子は女性としてはこれからという時に未亡人となり、再婚して新しい家族を得ます。新しい土地で人々は皆穏やかで優しく、貧しく辛いことの多かった彼女の人生は少しずつ豊かになり、女性としてもそれなりに愛され満たされていきます。
彼女が夫に話しかけ続けたのは、不在に馴れる恐怖と、「なぜ」の堂々巡りからの納得できない悔恨もあったと思いますが、なにより罪悪感があったのではないかと思います。夫は不幸を背負って黙って行ってしまった。行かせてしまった。止められなかっただけでなく、自分は幸せになろうとしている。
「川のほとり」の主人公(ほぼ筒井氏だと思いますが、一応これは小説)もまた、若い息子が先に逝き、自分が生きていること、息子の死に馴れていくことに対する恐怖と罪悪感があるのだと思います。
現実には、前夫は亡くなっています。しかし、ゆみ子がいま「思い出す」、そして語りかける限り、前夫はいまを生きています。だから『幻の光』は、ゆみ子のひとり語り、現在形で書かれているのです。
小林秀雄のいう「思い出す」は、想像すること、とあなたのお手紙や記事にありました。
『ROCK』と『悪女について』、読んでくださったんですね。(少々話がそれますが、『ROCK』のころから何も変わらず、いまだに連綿と続くルッキズムの遣る瀬無さを感じていただき、嬉しかったです)。
『チワワちゃん』も『悪女について』も、死者を「思い出して語る」話ですね。『悪女について』ではあなたのおっしゃる通り何十人もの人が同じ人物を思い出し語るけれど、語られた女性の像は一色にはならず、モザイク模様のように違っています。深く食い込まれた人もいれば表層しか知らない人もいる。でもみんなが彼女を知っていると思っている。『チワワちゃん』も同じですが、同年齢の若い友達はもっとドライでした。しかし語っている間、思い出している間は、その人はまさに「いま、存在している」のだと思います。
『幻の光』のゆみ子も「川のほとり」の「おれ」もまた、思い出すことで死者を存在させたかったのでしょう。いえ、「させたかった」というよりも
「いま、させている」——現在形なのでしょう。そしてどちらも、海や川の向こうに「彼岸」を見ているように思います。沖縄の「ニライカナイ」や「三途の川」のように、死者に近いのは水辺なのだと思います。だからこそゆみ子は海で泣いたのではないか、と思うのです。
そういえばサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』に忘れられない一節があります。この物語も『幻の光』のように全編独白ですが、実を言うと何十年も前に読んで、再読はしていないので細部はよく覚えていません。ただ最後のここだけは忘れられずに記憶に残っています(村上春樹訳が出たときに読もうと思ったのですが、読みそびれていました。今久しぶりに本棚から取り出してきて確認しています)。
大勢の人に話したのを、後悔しているんだ。僕にわかっていることといえば、話に出てきた連中がいまここにいないのが寂しいということだけさ。たとえば、ストラドレーターやアクリーでさえ、そうなんだ。あのモーリスの奴でさえ、なつかしいような気がする。おかしなもんさ。誰にもなんにも話さない方がいいぜ。話せば、話に出てきた連中が現に身辺にいないのが、物足りなくなって来るんだから。
「話す」「語る」「語り掛ける」「対話する」ことによって、死者や今そばいない人が「あたかも存在しているか如くに蘇り」、語っている、思い出している人にとっては、今まさに存在しているかのように感じられるものなのでしょう。
しかし語り終えた後、対話の後に、いや、やっぱりいないんだと思うことの寂しさや悲しさ、物足りなさ。
だからこそ、断たれる前の、生命いのちがみなぎっている言葉を、声を、ありありと「思い出す」ように読みたい。
「思い出すことは現在の営み」とあなたのおっしゃる通り、私たちは読みながら、聞きながら、作者の存在を「今」まざまざと感じているのだと思います。
それほどに、存在とは言葉によって形作られるのかもしれません。
そうやって私たちは「無常」や「孤独」に抗おうとしているのかもしれません。
町田康は『私の文学史』の中で次のように言っています。
「魂」というのは形がないじゃないですか。目に見えない。自分しかわからんわけです。でも、自分しかわからん魂を持っていることが、人間はたまらなく寂しいんです。孤独なんです。だから、この、自分しかわからん魂を一人一人が持っているということに形を与えたいんです。魂自体は形がないから、その外側に対して形を与えたいんです。魂自体は形がないから、その外側を、なんか、樹脂みたいなもので塗り固めて乾かすことによって、形を与えて、それを見たいんです。自分でも見たいし、人にも見せたい。その外側に塗り固める材料というのが言葉やと思うんです。
またとりとめもなく長くなりました。
こうして、お互いの手紙の中から新しい小説に出逢ったり、その感想を述べあったりすることができて、本当に幸せを感じています。これこそが、往復書簡の醍醐味だと感じております。
お手紙をくださり、そして私の手紙を読んでくださって、ありがとうございます。なにしろ私の手紙が長いので、ご迷惑になっていないかだんだん心配になってきました。
あまりご負担にならない程度に、またやり取りができたら嬉しく思います。
敬具
みらっち こと 吉穂みらい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
