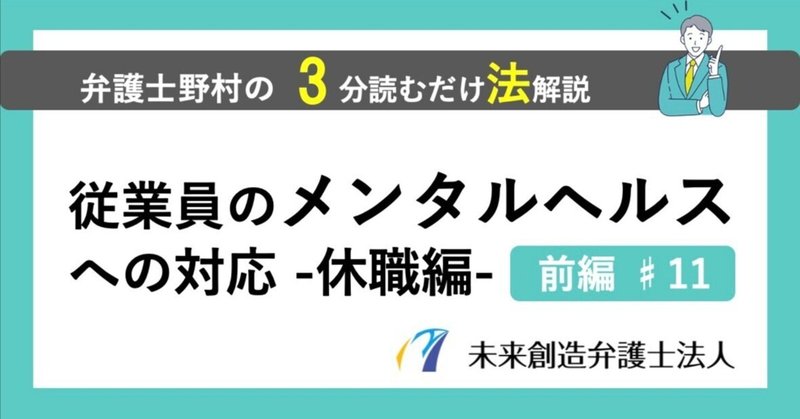
知っておきたい『従業員のメンタルヘルスへの対応~休職編~ #11』
1. 会社は従業員のメンタルヘルスの問題に気づかないといけない
2014年の労働安全衛生法(以下「労安衛法」という)改正に伴い、事業者は、1年に1回、定期に労働者に対し、
①職場における労働者の心理的負担の原因
➁心理的負担による心身の自覚症状
➂他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
について、医師等(医師、保健師、所定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士または公認心理師)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならないことになりました。(労安衛法66条の10第1項等)

また、裁判例ではうつ病等の従業員に対して、何もせずに様子を見守っていたこと自体が違法とされた例もあります。
そのため、会社は、従業員にメンタルヘルスの問題が無いかを常に注視して問題がある者またはその疑いがある者については、適切に対応しなければなりません。
まずは、従業員のメンタルヘルスの原因を調査しなければなりません。会社の業務に起因する場合には、労災事案となり休職の対象ではありませんので注意が必要です。
メンタルヘルスの問題は、自殺の原因にもなる重要な問題であり、職種によっては第三者への加害にも繋がる重要な問題であり(例:運送業等では事故の原因となることは容易に想像できます。)社会的関心も高い(※新入社員が長時間労働等の苦に自殺した電通事件は社会的耳目を集めました。)ため、対策は必須です。
2. 従業員がメンタルヘルスの問題を認めない場合はどうする?業務としてのSNS利用で炎上した場合、会社はどうする?
相談事例
経理課のAさんが最近職場で些細な事で大声を挙げたり、監視されていると騒ぎ立てたり、業務上の指導に対していじめだと泣き出したり感情の起伏が激しくなりました。これに伴ってAさんは勤務時間中に居眠りをしたり、遅刻が月の半分ぐらいになったり、経理の間違いが増えたりしています。
Aさんにメンタル疾患についてそれとなく話をしても「私は大丈夫です。健康です。」と言うだけで会社としてはどうすればいいか分かりません。どうしたらいいでしょうか。
① 素人判断はしない
何らかのメンタルヘルスの問題が疑われる場合であっても、産業医等の面談を経ずに素人判断で休職命令等を出さないようにしましょう。
メンタル疾患であると決めつけず、まずは任意の受診を勧める対応をしましょう。
※ あくまで任意の受診を勧めるものなので、費用は本人負担が原則です。会社としてどうしても受診して欲しい場合には「初回」に限り会社が負担をすることを前提に受診を勧めましょう。
➁ 受診命令を検討する
任意の受診を促しても受診しない従業員に対しては、業務命令として受診するように命じましょう。
その際には、就業規則に受診命令の根拠があるか確認し、就業規則に根拠があれば就業規則に基づき、就業規則に根拠がない場合でも合理的かつ相当な理由のある措置であれば受診命令が出せるので、顧問弁護士と協議の上、受診命令が適法になるよう準備しましょう。
もっとも、経験上受診命令を受けるような社員は相談事例の状況に至らないので、リスクを冒しての受診命令はお勧めしません。
➂ 休職命令を出す
本件でAさんは健康であると話をしていますが、会社での様子および遅刻が続き、業務時間中に居眠りを行っており業務遂行にも支障が生じています。
会社としては、Aさんが受診命令に従わない場合であっても、就業規則に基づき休職命令を出し、Aさんが治療に専念できるように環境づくりをする必要があります。
もっとも、休職の原因が会社にあるという反論があることを想定して休職命令の発令前には、直近1年間の勤怠記録や人事評価の面談資料等を参考にメンタルヘルスの不調の原因が会社に無いことは確認しておかなければなりません。

3.休職させればそれで終わりではない!
(1) 休職にあたって家族に連絡していいか?
メンタル疾患は周囲のサポートを得ることが望ましいですが、メンタル疾患であることは個人情報であるため、家族といえども従業員の同意なしに伝えるとトラブルのもとです。
そのため、入社時誓約書等で「心身の不調が生じた場合に、会社が当該事実を緊急連絡先に伝えることに同意する」と記載しておいた方が安心です。
(2) 休職期間中も連絡をとる
休職は、休職期間が満了し職場復帰することを前提とした治療期間であるため、会社は休職期間中も休職した従業員の心身の調子を確認する必要があります。
そのため、休職期間中も従業員と連絡をとり、治療状況について確認をしておく必要があります。
(3) 社会保険料に対応を決めておく
休職期間中の賃金については、就業規則の定めによりますが多くは無給となる定めをしていると思います。休職中も社会保険の被保険者資格は継続するため、休職した従業員について社会保険料が発生します。
しかし、自己負担分について控除すべき給料が存在しないので、控除ができません。
そのため、
① 従業員に自己負担分を送金してもらう
➁ 会社が一時的に立て替えておく
➂ 傷病手当金から控除する合意を取る
のいずれかの対応をしなければなりません。
社会保険料を確実に取り立てるためには、➂の方法が良いので傷病手当金を代理受領できるように合意を取り付けておきましょう。
以上のように、従業員のメンタルヘルスに問題が生じた場合には、周囲への影響や解雇等の誤った手段をとった場合に会社に与える影響が大きいです。
会社でメンタルヘルスに問題があると疑わしい社員がいた場合には、会社がいち早く察知して、産業医および弁護士の意見のもとに対応しなければなりません。
【未来創造弁護士法人】 www.mirai-law.jp
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
弁護士 野村拓也(神奈川県弁護士会所属)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
