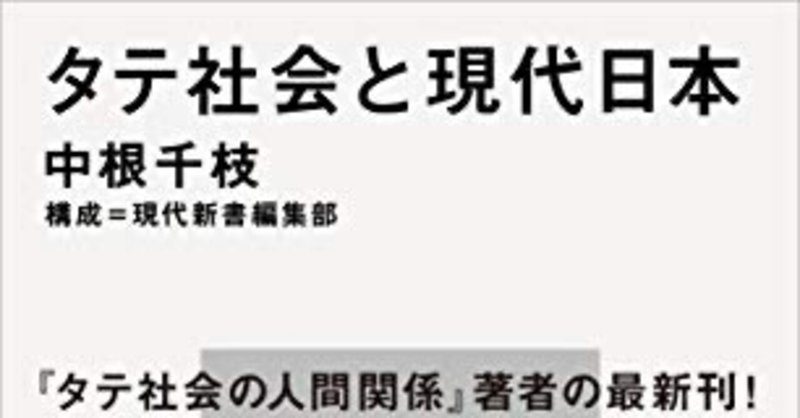
「タテ社会の人間関係」
50年前の高度成長期に出版した「タテ社会の人間関係」は当時の現象を取り扱ってはいるが、その奥に潜む理論の提示であるから、中根千枝の展開した「タテの理論」に変更はない。「失われた20年」といわれるように、低成長の時代が長年続き、新卒一括採用から定年まで、すなわち入口から出口まで面倒を見るという日本型経営が形を変えつつあると報じられている。しかし年功序列のようなものが薄らいだとしても、タテのシステムは残るところに残る。その大きなものが、先輩後輩の関係である。
タテ社会の人間関係の要点は、日本における機能集団の構成は、その人の個人の属性・資格よりも「場(一定の個人が集団を構成している一定の枠。テリトリーとは異なり「場」はよりスタティック)」によることを指摘した。ここでは特にキー・コンセプトとして先輩・後輩の秩序の認識について述べたい。
集団が形成されることとなるに最初についたもの<A>を頂点として、次の<B>がその下位となる。<B>の次は<C>となり、これがいわゆるタテの関係で、変更を許さないシステムを生む集団構成の原則となる。小グループの中で、最も古株なのが頂点となり、その「場」に在籍する時間の短いものが最も下位となる。いつ、その場に入ったか、その順番が大事。
こうしてできる小集団は上位の大集団に統合される体制であってもそれ自体の機能は持ち続ける。企業や政党の中の派閥を想定すればわかりやすい。この小集団は閉鎖性という特性を持つ。
この集団の形成の古い形は「親分・子分関係」によってできる集団につながる性質を持っている。昔は違ったが、現代社会ではたまたま採用された会社の都合で個人が配属され、その中の人間関係は良くも悪くもなりうるため、人間関係は予知できない。
タテのシステムにより新入社員ほど低い位置に置かれ、その責任者からは時に厳しい態度を取られ、その結果自殺するケースもある。小集団はそれ自体封鎖性を持つものなので、やられる方は社内でも相談する相手もなく一人苦しむことになる。
「最近の若いものは……」という言い方をするが、最近の学生であっても、上級生、下級生の区別は依然としてある。社会の組織が変わることはあるが、社会の構造は変わらない。
こうした人間関係を分析する鍵となるのが「資格」と「場」である。集団を構成する第一条件が、個人の「資格」の共通性によるものか、「場」の共有によるものかといういうこと。
資格とは、社会的個人の属性、つまり、その人が持っている特性。氏・素性、学歴・地位・職業、地主・小作人など。
一方、一定の枠によっていっておの個人が集団を構成している場合、「場」による設定ということになる。会社などの所属期間もそうだし、〇〇村も「場」になる。こうした場において、場に来た順番というのが重要になる。場においては、資格が同じであるかどうかは問われない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
