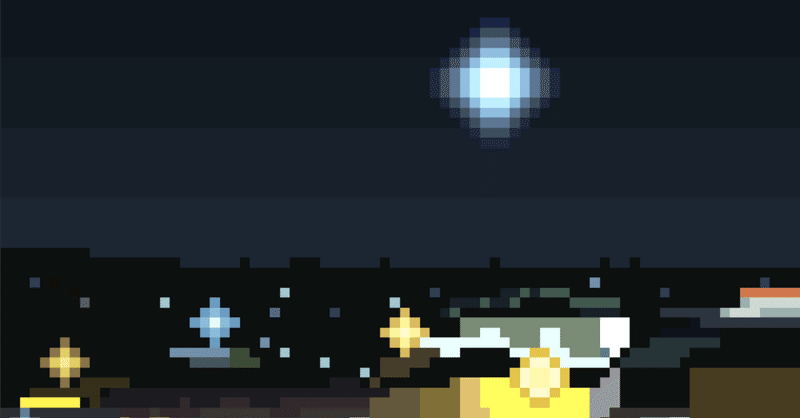
235:大森荘蔵『新視覚新論』を読みながら考える02──1章 見ることと触れること
脳が予測に基づいて外界を認知・行為していくことを前提にして,大森荘蔵『新視覚新論』を読み進めていきながら,ヒト以上の存在として情報を考え,インターフェイスのことなどを考えいきたい.
このテキストは,大森の『新視覚新論』の読解ではなく,この本を手掛かりにして,今の自分の考えをまとめていきたいと考えている.なので,私の考えが先で,その後ろに,その考えを書くことになった大森の文章という順番になっている.
引用の出典がないものは全て,大森荘蔵『新視覚新論』Kindle版からである.
1章 見ることと触れること
1 純粋視覚
「視覚固有のカラフルな豊かさがどんな抽出作業にも抵抗する」と大森は書いている.「カラフルな豊かさ」とは何だろうか.触れることなく,見えるものとして,私は瞼を閉じたときのカラフルなモザイクを思い出す.光が満ちた空間で瞼を閉じても暗闇がやってくるのではなく,カラフルと言っても,赤緑青・RGBの3色しかないモザイクが私の視界に見えてる.瞼という私の皮膚を透過してきた光は,何かの像を見せるのではなく,RGBのモザイクを見せる.何かしらの像を形成できはしないが,RGBのモザイクは見えている.私はそれらには触れたことがなく,ただ見ている.純粋知覚と聞いて,私が想起し,実際に体験できるのは瞼を閉じたときに視界を満たし,形を変化させ続けるRGBのモザイクである.このRGBのモザイクは条件さえ整えば,つまり,瞼が光の情報を単調にしなければ,「識別的多様さ」を示す情報として処理されて,認知的差異をつくり,何かしらの像として処理されて,視界に現れてくるだろう.
こうしてバークリィの努力は,生活の必要から視覚風景の中に忍び入り,そこに腰をすえてしまっている[[触覚]]的意味をいぶり出し,そこに残った純粋視覚風景,すなわち純粋視覚的「残余」を描いてみせることに向かう.その「残余」は,フッサールの「現象学的残余」が,残余と呼ぶのが間違いであると思えるほどにそっくり元のままなのとは反対に,まことに乏しい,ただ光と色のたわむれといったものになる.それはあらゆる哲学的抽出作業が陥るべき運命に陥っている.形相を抽出された質料的残余,規定を抽出された感覚与件や直観の多様,内容を抜かれた認識論的主観,こういった抜けがらの運命である.もっとも,バークリィの純粋視覚風景はそれほどまでの徹底的骨抜きはうけてはいない.視覚固有のカラフルな豊かさがどんな抽出作業にも抵抗するからである.またバークリィにとっても,最小限の「残余」が残っておらねば困るのである.触覚の前触れ機能を果たすだけの何かが残っておらねばならないからである.多様多態な触覚風景を識別的に予告するには,それに見合った識別的多様さが視覚的残余にも残されておらねばならない.p. 18
2 視覚と触覚の断絶
瞼の裏に見えているように感じられるRGBのモザイクにも空間性はないように感じる.奥行きがない.瞼の裏という表面に展開している.している.それは何かモノがあるというよりも,青空が示す面色の青のようにRGBの光がつくるモザイクがある.手を伸ばそうとも思わないのは,手が見えないから.手の動きはわかるけれど,手でRGBのモザイクを掴もうとは思わない.しかし,手を動かすとモザイクの奥が生まれ,空間が生まれ,そこで手が動いていると感じる.
明らかにバークリィは純粋視覚風景から空間性を奪おうとしているのである.事実,彼にとって真正の意味での空間は触覚(運動感覚を含めて)にしかない.p. 20
予測という観点から考えると,バークリーが視覚を触覚的接触の「目印」「予見」や「予知」を与えるものとするのは合点がいく.けれど,視覚から触覚へという向きだけでなく,触覚から視覚へという向きも考える必要があるだろう.視覚と触覚とは別々に外界のあり方を予測しながらも,情報は共有して,世界に対する予測モデルを精緻なものにしていく.マルチモーダルに外界の情報を得た方が,予測の精度が上がる.見ると触るとを行き来しながら,外界からの情報を構造化して,モデルをつくっていく.そして,そのモデルが「われわれの行動を誘導する」のである.
この元来は全く空間的関係がない視覚と触覚の間に関係が生じるのは,「全く経験の結果」( 3, 31, 49, 61)である「習慣的結合」( 17)によるのである.当然,この結合は外的な結合であり,言葉と対象との結合関係にその最も自然な比喩を見出すことになる( 64, 32, 73, 115, 143, 159).そして,或る語がそれに習慣的に結合した対象を呼び起こすように,一つの視覚的対象は或る触覚的対象をわれわれの心に呼びおこす( 45, 50, 64, 77).例えば,「彼が見るものが彼の知性に,触覚的知覚である身体運動で測られる或る距離を進めばかくかくの触覚的観念を知覚するであろうと示唆する」( 45)のである.だから,視覚は「造物主の普遍言語」( 147),「造物主の声」( 152)として,われわれの触覚的接触の「目印し」( 115, 117),「予見( prenotion)」( 148),「予知( prognostics)」(『原理論』 44)を与えるものとしてわれわれの生命に奉仕するのである.すなわち,「続いておこりそうな危害や利得を予見し」( 59),「人生の快と利便のために」( 87),「われわれの行動を誘導する」( 86)のである.p. 24
3 視覚空間の次元
私も大森と同じ意見.では,どのような感じで同じ意見となっているのか.触覚的生活は基本的に正しいとしても,触覚と視覚との完全な断絶はあり得ないと考えると大森の考えをなぞっただけにすぎない.これから大森が詳しく述べることを参照しつつ,自分の考えをみていけばいいと思われる.
われわれの動物的生活,すなわち肉体を守り食物をとり子供を生むという生活は触覚的生活である.このバークリィの基本的視点は全く正しい.しかし,それを強調するあまり,視覚風景を触覚空間から完全に断絶したもの,そしてただ規則的対応によって触覚的経験の符号となるだけのものとするのはこれまた基本的な誤りだと言いたい.p. 25
大森があっさりとバークリィから離れてしまうのがいい.私たちは「二次元視覚空間」を体験しているのか.見えているものは三次元空間であると思うが,網膜は二次元である.そして,網膜の細胞は電子の数をカウントしているのみだとすると,二次元のセンサーから平行してのびる視神経という一次元の繊維を外界の情報が伝わっているとすると,そこには二次元も,三次元もないことにある.しかし,私の視界に三次元空間が広がっているように見えるのはなぜなのか.三次元空間が広がっていると感じられるのは瞼を開けているときで,瞼を閉じたときには「二次元視覚空間」が広がっているように感じる.網膜の届く情報が瞼というフィルターと透過するさいに次元の情報を失うのか.いや,次元の情報というよりも,何かしらの像を形成する情報が失われて,単調になって,RGBのモザイクを形成する情報しか持たなくなっていると言った方がいいのだろう.だとすれば,私の生活に説いては,「二次元視覚空間」は瞼を閉じた際にRGBのモザイクとして現れるということになるだろう.
ここで,バークリィ自身が正確にはどのようなことを考えていたかということから離れよう.そして,一般に,二次元視覚空間というものがありうるか否かについて検討をしてみよう.ただし,一般に,といったがそれは単に哲学史的にではなく,といった意味であって,何か架空の生物の架空の視覚空間について考える,ということではない.あくまでわれわれが現に毎日毎時面している視覚風景が二次元的であることができるか,ということなのである.だがそのためにも再びバークリィが好適な糸口を与えてくれる.p. 27
「物のボケ具合や明瞭度,眼球調節の緊張感には距離なる概念は全く含まれていない」を前提に,私はかけている眼鏡を外して世界を見てみる.世界がボケて,明瞭度が落ちる.私はいつもこのことを不思議に感じている.私と対象との距離は変わらないの,対象の見え方,私の視界における対象の現れ方が変わってしまう.眼鏡は対象からの光を調節して,網膜に届けて,対象の明瞭度を上げる.対象との距離は変わらないけど,光が網膜に届く経路の変化によって,対象はボケる.この変化は,バークリィが主張しているように距離を考えない方がいいのかもしれない.いや,眼鏡を透して見る世界をボケていない明瞭な世界として,眼鏡を外して見る世界と比較している時点で距離は入っている.光線の経路といった書いた時点で網膜と対象とのあいだに距離はある.光線という触れられないものによって,対象の現れ方が変わるとすると,触覚抜きでも視覚は奥行き距離を構成できている.世界と共にある私は世界に対して,予測を常に行っていて,その予測において奥行き距離が生成される.この生成には,私が外界から得ているすべての情報が関わっている.そうだとすれば,眼鏡を取ったときにも,世界は明瞭に現れるべきではないのか.眼鏡をとった世界からのデータを予測して,眼鏡付きの世界になるようにデータを補正すればいいのではないか.でも,それはできない.私は世界を見たいようには見れない,世界が私が見る視界の現れ方を制限している.このとき,網膜からの情報が二次元の視覚風景をつくるとしたら,この視覚風景が三次元の触覚空間から得られる奥行き情報を抑制して,視界の明瞭さを落としていると考えられるのかもしれない.
だから,バークリィが両眼視をあとまわしにして,見ている物の明瞭度やボケ具合,それに焦点調節のための筋肉感覚(ただし,これは触覚に属しよう)をあげるのに対して性急な反対をすることはできないであろう.両眼視の機能については彼は語らないが,この単眼視の場合の特性を二倍あるいはそれ以上に増幅することによって針仕事をやり易くする,と言ったっていいであろう.しかしそれよりもはるかに大切なことは,バークリィの意図が奥行き距離の概念を一切含まない何かをあげることであったことである.彼の言う,物のボケ具合や明瞭度,眼球調節の緊張感には距離なる概念は全く含まれていないのである.彼の純粋視覚風景には奥行き距離がないのである(と私は推測する).この奥行き距離の概念はただ触覚的運動感覚にだけある,これがバークリィの基本的主張なのである.だから彼の基本的テーゼは,この触覚的運動感覚的な『距離』の目印しとして,視覚風景の中からこの『距離』と一切無縁な或る適当な特性を探し,それをその『距離』に経験的慣習によって結合する,ということだったのである.換言すると,触覚や運動感覚と,経験的慣習で連合する以前の視覚風景の中には,一切「奥行き距離」はないのである.さらに換言すると,視覚風景の中だけでは「奥行き距離」なるものはどうあがいても構成できないのである.したがって,バークリィの「言語の比喩」を使えば,二次元の視覚風景が三次元の触覚空間の言語になることになる.そこで,三次元空間の二次元表示,例えばわれわれの地図での等高線や色の濃淡(濃い茶色はより高く,濃い青はより深い)にあたるのが,物の見え具合でのボケや明瞭度になったのである.p. 29
4 映写幕の比喩
「視覚的奥行き」なしにスクリーンやディスプレイを見ることは難しい.網膜が二次元であるのに三次元を見てしまうように,私は世界を「視覚的奥行き」を持ったものとして見てしまう.私の予測モデルは二次元→三次元の変換装置が組み込まれた状態で,世界と相互作用している.さらに,スクリーンを見るということから,「離れて見える」ということですでに「視覚的奥行き」を前提にしているという指摘も最もだと思う.私と世界との相互作用からつくられる予測モデルが三次元空間を前提にして出来上がっている.ここからどうやったら「視覚的奥行き」を抜き取ることができるのか.
人が二次元視覚風景を想像しようとして例えばスクリーンの画面を思い浮かべるとき,何かこれに似たことをしているのではなかろうか.なぜなら,第一に,人がスクリーンの画面を考えるのは,そこに映っている風景が奥行きがあるように見えるにもかかわらず実は奥行きがないからである.つまり,「視覚的奥行き」が視覚的に既に了解されているからこそ,スクリーンに思いがおよぶのである.だから,今私に見えている視覚風景が「スクリーン様のもの」だと考えることは,この風景が視覚的に二次元だということではなくて,逆に視覚的に三次元だということなのである.p. 30
第二に,スクリーンがスクリーンであるがためにはそれが「私から離れて見える」のでなければなるまい.すなわち,スクリーン上の風景は「離れて見える」風景なのであり,そして「離れて見える」ということはとりもなおさず「視覚的奥行き」をもって見える,ということである.そこでアリストテレスの天球のような壮大な全天シネラマを想像するとしても,そこには「私の前方」と「私の後方」という「視覚的奥行き」がある.その天球的パノラマは数学的には二次元球面であるが視覚的には三次元,つまり,「視覚的奥行き」をもって見える風景なのである.また,数学的にも幾何学的閉曲面は三次元空間の中にあるものである.p. 31
予測モデルないにつくられた視覚世界を天球面に張り付いたものだと考えることはできる.視覚世界は二次元だとは言えるかもしれない.しかし,視野という枠でし続けを切り抜くと,天球面と私とのあいだに距離が生じる,というか,厚みが生じるように感じられる.モデルはモデルであって世界そのものではない.そこに私という生物が動き回るための処理が必要で,それが視野でモデルを切り取るということだと思う.視覚世界を視野で切り取る際に,視覚世界はクッキー型で切り抜かれた生地のように厚みを与えられて,現れる.その厚みが三次元空間として視界に展開される.天球に貼られたクッキー生地はどこを切り抜かなければ,その厚みを確かめることができない.
では,と人は言うであろう.私の今言った意味での「視覚的奥行き」があることは認めよう,しかしなお視覚風景は実は天球面にべったり貼りついていると想像することは可能ではないか,と.それはたしかに可能である.ただし太陽や月がお皿に見えると言ったエピクロスのように,遙かに遠くそして静かな風景の場合,あるいは芝居の書割り風景や絵や写真のようにきわめて局部的な場合に限ってである.われわれの日常の視覚風景──ここではそれを問題にしているのであって架空の風景や極めて異常な風景のことを問題にしているのではない──にあっては身近にも多くの事物があり,また多くの事物が動いたり形を変えたりしているのである.さらに,われわれ自身が移動するのである.いやそれは触覚的運動感覚的な要素を持ちこむことだ,とバークリィが異議をはさむならば,私自身は身動きもしないが風物の方が代わりに動くと想像してもいい(主人公の眼の場所にカメラアイを固定した映画に似た想像である).p. 32
視覚風景は私を包むものだが,そこからつくられる予測モデル=視覚世界は私のなかにつくられる.もちろん,視覚世界は三次元の私を包む視覚風景からつくられるが,それ自体が三次元かどうかはわからない.ホログラフィ理論で考えると視覚世界自体は2次元かもしれない,コンピュータのメモリのアドレスのような構造を持っているかもしれない.三次元の視覚風景のなかに二次元で見える絵とかスクリーンがあるというモデルを脳に組み立てるとき,それが三次元なのかどうかはわからない.視覚風景そのものをコピーするのではなく,その光の情報から視覚世界を構築しているとすると,視覚世界が三次元である必要はない.けれど,視野で切り抜いて,視界として展開するときには,三次元である必要があるし,三次元になるように処理されて,私は世界を三次元としか体験できないし,三次元の中に二次元平面のディスプレイに三次元を認めるような回路もすでに出来上がっていて,何もかもが三次元に見える.しかし,私の視界は三次元の世界に対応するように処理されているから三次元なのであって,視界の情報源である視覚世界は三次元である必要はないと考えてみたい.
二次元の視覚風景とは想像できないものなのである.絵とかスクリーンの上とかの風景が奥行きをもって見られる.しかしそれらが「実は二次元だ」ということそのことが三次元の視覚風景の中で初めて言いうることなのである.絵が三次元の画廊の風景の中で壁にかかっているからこそそれが(例えば)遠見に二次元に見えるのである.しかし,その中に立っている私を含めてその画廊全体の風景が二次元であるということは想像不可能なのである.
だいたい,視覚風景とは私を包む風景である.私を中において私の前後左右上下の風景なのである.そして,その私自身は三次元の肉体,体積をもつ肉体としてしか考えることができない.この身体図式は視覚的であるとはもちろんいえない.しかしそれが視覚的であろうとなかろうと表と裏と中味がある三次元のものとしか考えることができず,そして視覚風景とはこの三次元の私の身体を包むものとしてしか見ることはできないのである.だから当然,この三次元の私の身体を包むものとして視覚風景は三次元でしかありえないのである.p. 33
大森は「視覚風景にはその「固有直接の対象」として「光と色」のみならず「視覚的奥行き」がある」と書くが,それは私が見ている視界を覆う視覚風景であって,視覚風景からの情報で構成される視覚世界には必ずしも「視覚的奥行き」は必要ないのかもしれないと,私は考えるようになっている.それは,瞼を閉じたときに見えるRGBのモザイクという「光と色」が視界を覆うときがあるからである.瞼を閉じているとき,その向こうがあるいう感じがあり三次元空間が前提とされているが,視界そのものは二次元に覆われていて,視覚だけの情報ではその先にいけないという感じも,私は強く感じる.触覚や運動感覚からの密輸をしなければ,RGBのモザイクに視覚的奥行きは生じない.瞼を閉じても世界を見ていることには変わりがない.瞼を閉じたときに視覚的奥行きを持たない「光と色」の視覚風景が生まれている.瞼を開けたときと閉じたときとで,視界=視覚風景のあり方が変わると考えられないだろうか.
こうして視覚風景にはその「固有直接の対象」として「光と色」のみならず「視覚的奥行き」があるのである.そしてそれはバークリィが主張するような触覚や運動感覚からの密輸品ではない.純粋視覚風景の原産品なのである.p. 33
5 視覚と触覚の接合
「私」とは視野の中心,視点であると言うのが興味深い.視界を見ている視点としての私.大森が「瞼」を登場させる.瞼が閉じられると視点はなくなり,触覚と運動感覚が出てくる.しかし,瞼を閉じたとしても,視点として私は視界を見ている.瞼を閉じると,視界が三次元空間=視覚的奥行きを持った状態から奥行きを失ったRGBの光のモザイクの状態へと変わる.私という視点が見ている視界は視覚世界の二つの状態とリンクしている.瞼を閉じることで,二つの状態のリンクが切り替わる.この点よりも「視野の視点近傍が触覚的瞼に定位された」を考えたほうがいいだろう.瞼に対して,触覚的と言う言葉が与えられている.視点から見た視界が二つの視覚世界とリンクしていて,そのリンクを瞼の開閉で切り替えると言うときには触覚は入っていない.
われわれは前節で述べた視覚風景の三次元性から出発する.それは,私を包む三次元の風景である.だから当然この風景には「私からの遠さ近さ」というものがある.この「私」とはこの風景のいわば視野の中心,すなわち視点である.そしてこの視野の中心に対して視覚的対象,例えば「見えている鉛筆」が「近づいたり遠ざかったり」すると見えるのである.その鉛筆が,眼と称するものがあると私が思っているあたり(見えてはいない)に近づいてくるのを見る.そしてもうこれ以上近づけぬ程に近づいたと見えたときは私は瞼を閉じる(触覚と運動感覚).するとその鉛筆と思われるものが瞼に触れるのを感じる.だが事を簡単にするために,瞼を閉じないで,その見えている鉛筆が下瞼に触れるのを感じるとしよう.いずれにせよ,視野の視点近傍が触覚的瞼に定位されたのである.p. 35
大森が書くように試してみる.私の方に近づいてくる鉛筆のような先に尖ったものは瞼のところで止まる.ただ瞼の少し先,眼球に当たって止まっている感じもある.瞼を通り抜けて,頭蓋骨も通り抜けて,脳にまでは至らない.瞼を閉じてみても同じ感触である.こちらは,瞼のところで鉛筆が当たって止まる感じがある.眼球に奥に鉛筆が入る想像をすると,私の中に入り込まれたと言う感覚がある.境界を侵犯されているような感じである.
もちろんこれは正常な状況の描写である.だが,正常でない状況を想像することにも何の困難もない.近づいてくる鉛筆を含めて私に今見えている視覚風景全体が通常「幻覚」と呼ばれているものであると想像するのはたやすい.すると,鉛筆がいくら眼のあたりに近づいてくるのが見えても,何の触感もおこらない.だがそれにもかかわらず,その幻の鉛筆が近づくと見える場所は瞼の開閉の触覚的運動感覚がするあたりであるはずである(これは自分で想像してみる以外に確かめる方法はない).幻であろうと,それは私に近づくのであるから.このことこそ視覚風景と触覚との空間的位置関係を定める座標原点であると思われる.つまり,視覚風景の視野中心を身体上の或る場所に定位することである.p. 36
大森が興味深いのは,釘一本では方向が決まらないと想像するところである.瞼は二つあるから釘も二本必要.確かにそうなのだが,想像してみると,私の場合は,釘は一本でやってくる.自分の指を二本こちらに向けて近づけても,最終的には一本に見えてしまうし,そのときは瞼にあたるのではなく眉間の真ん中に当たるという感じがある.身体をとにかく視覚風景に定位できることを感じさせるために,釘を二本持ち出すのはやはり面白い.定位されるとき,私は瞼の開閉によって,定位されるのが瞼一枚の薄さだけ異なる感じがあったのが,私的には興味深い.瞼を閉じているときは瞼,瞼を開けているときは眼球で定位される.でも,これは誤差なのかもしれない.瞼を重要視するかどうかで決まる誤差.
そしていったんこの定位ができれば,触覚的(というより,より広く体感的)身体図式の全体が視覚空間の中に定位できる.なぜならば,この五体の体感的(触覚を含む)身体図式の中では瞼の場所は体感的に定位され済みだからである.ある額ぶちの中に紙人形の瞼のところを釘でとめれば,その紙人形の他の部分もその額ぶちが囲む平面上で位置がきまるようにである.だが数学者ならすぐいぶかるだろう.釘一本ではまだ方向(回転自由度)がきまらないではないか,と.それに対して,瞼は左右に二つあるから打たれる釘は実は一本ではなくて二本なのだと答える.さらに立体人形を持ちだされれば,触覚的瞼には触覚的前方と後方(また上と下)があり視野風景はその前方に定位されるしかない,などと答えることはできよう(この答えの後半は片目の人の場合をもカバーする).しかし,大切なのは,視覚風景の中に体感的五体がいかに定位されるかということではなく,とにかく定位できるということなのである.p. 37
大森が「その視野の中心を体感的身体の或る場所にもつ風景」と言うものを,私は「視界」と呼んでいる.視野の中心には常に私という視点があり,その視点から見えるとされる視覚世界が視野によって切り取られて,視界として現れている.瞼はその視界世界の二次元と三次元との切り替えを行う装置として存在している.大森が考える視覚風景の空間と触覚空間とが接合されてできる一つの空間は,瞼の開閉に関係なくある世界そのものだと考えられる.その世界から得られる情報から構成され,瞼の開け閉めによって次元が切り替わって視界に現れるのが視覚世界となる.視覚世界は一つの空間を瞼を閉めること視覚と触覚とに分けるのではなく,視覚と触覚との差異をなくして,単調化していく.この言い方も違う.視覚は単調化して触覚を求めないけれど,身体図式は残り続けて,一つの空間の中に私の身体があることを感じさせてくれる.視点以前に,私の身体が一つの空間にある.私の意識に世界とその相互作用から視覚世界が構築され視界をつくるのとは関係なく,世界は視覚と触覚とが接合した一つの空間として私を取り囲んでいる.しかし,私が見ているのは視覚世界から切り抜かれた視界であって,そこで何か触れたときに一つの空間としての世界が私の意識に現れる.この考えは視覚優位すぎる.けれど,やはり視覚優位でヒトの体験は構成されている.世界の側には感覚の優劣がないが,私の予測モデルに生じる視覚世界,聴覚世界,触覚世界などの感覚世界には優劣があると考えられる.
バークリィが視覚的対象と触覚的対象との間の距離,すなわち,それらの間の相対的位置を語ることは全く無意味だと考えたのは,視覚的性質(光や色や視覚的形状)と触覚的性質(手ざわりや触覚的形状)が「全く異質的」で「両者に共通なものは何もない」( 127, 129)からである.なるほどたしかに,一方に光と色に溢れた視覚空間を思い浮かべ,他方に手ざわりだけの触覚的世界を思い浮かべたとすると,その一方の中の或る対象と他方の中の或る対象との相対的位置を定める手掛りは全くないようにみえる.それはまるで,昨夜の夢の中の事物と一昨晩の夢の中の事物との間に相互の位置を定めようとするようなものだ,こう感じられよう.しかしバークリィが見落としているのは,その視覚風景は体感的身体(図式)を包んで見えているということである.言い換えると,その視野の中心を体感的身体の或る場所にもつ風景,として見えているということである.だから例えば今私が右手を斜め前方に伸ばして何か固い物を摑んでいるとすると,たとえその物も私の手も全く透明で見えないとしても私の手先とその物がどのあたりであるかの大よその見当を視覚風景の中でつけられるはずである.つまり,右斜め前方の(手の届く)身近な場所,というものを視覚風景の中で見当付けられるだろう.同じことを暗闇の中で行ない,その場所を闇の中で凝視し,そして電気をつけてみれば見えた手の位置に大きな見当外れはあるまい.もちろんそれには長年の経験が参与していよう.その経験や練習によってこの見当付けはいくらでも精確になるだろう.しかし私の言いたいのは,たとえ全くの無経験であっても,右のかわりに左,前方のかわりに後方,仰むくかわりにうつむく,といったひどい見当外れはない,ということなのである.そんなことがない程度に,視覚風景の空間と触覚空間とが上に述べた瞼と身体図式によって接合されているのである.より正確に言えば,「一つの空間」の中で接合されているのである(相互に位置関係がある,ということがすなわち,「同一空間」の中にあるということなのだから).p. 37
6 「同一の事物」
「瞼を蝶つがいとする」と言う言葉がいい.大森は瞼を「蝶つがい」にして視覚空間と触覚空間とを接合する.私は瞼を視覚世界の複雑さを切り替えるスイッチとして考える.世界そのものは大森が書くようになっていると思う.しかし,私が視界に見るのは視覚世界という意識が世界からの情報で組み立てた予測のためのモデルである.視覚世界の情報の粗密は瞼によって切り替わる.瞼は世界からの光を単調にするフィルターであり,予測モデルを切り替えるスイッチである.
先にも述べたように,この視覚空間と触覚空間との,瞼を蝶つがいとする空間的接合はまことに大まかでおおよその見当付け以上のものではない.それ以上の細部の仕上げは様々な経験に依存するものとして当然心理学者の領分に属する.ここでは,その細部の仕上げの大まかな道筋を推定することができるだけである.p. 41 [
視覚と体感的身体図式との関係について,私は次のように考えていた.「世界を見る.瞼を閉じる.瞼に触れる.私を原点にして,外側へと広がっていた世界が,瞼を閉じると,私に収斂されていって,皮膚が境になるというが,世界に触れているところだけが意識に上がるようになる.身体はあって,その境界も分かるが,それがだんだんとぼやけてくる感じがあるようなないような.このようなことを書きたいと考えているから,そのように感じてしまうのだろう」.大森が「全く大よその位置や大きさや方向が合いさえすれば」と書くような感じで,視覚と触覚と言う二つの感覚がそれぞれもつ身体の座標が大体合っていると処理すれば,視覚世界で一つの物体として,さらに自分の手として感じられる.瞼を閉じると視覚に関する座標に関する情報が視覚世界の単調化とともに曖昧になり,視覚情報ではなく,右手がどこに触れているのかという触覚的な感じから右手の座標メインで右手の位置が決定されていく.
例えば,現在の私の右手の体感的位置や形を眼を閉じて感じてみればそれは決して明確な境界をもって一定の立体的空間形状をしているわけではない.だから,あらかじめ一方に明確に境界付けられた視覚的右手があり,他方に同じく明確に境界付けられた触感的右手があり,まるでギプスを手にはめるようにそれを合わせるというのではない.そうではなく,全く大よその位置や大きさや方向が合いさえすれば,視覚風景の中では視覚的右手を触角的右手だとして見るのである.p. 41
「視覚的接触と触覚的接触との一致」はその通りという感じだが「一致」と言うのは正確を求めすぎた表現になっている感じがする.大森も大他所の位置と書いているので,二つの感覚の一致は幅を持った事象と考えたほうがいいのかもしれない.あるいは世界としては一致しているが,そのとき,予測モデルを構成する視覚世界の座標と触覚世界の座標とはおおよそ一致でしかないと考えられるかもしれない.予想モデルは世界のコピーではなく,モデルであるから粗い=単調なモデルのときもあれば,精密なモデルのときもあり,それぞれにおいて座標が示す情報の正確さが異なるのだろう.大森が「透明上皮層」と書いているのが興味深い.右手と左手とで蚊を叩くときに,手の皮膚の少しうえの「透明上皮層」で行為が起こり,不透明な皮膚にそれらの行為が及んだときに音が出る.視覚的接触と触覚的接触とが世界で一致すると同時に音という聴覚的イベントが発生する.視覚は世界における不透明な皮膚に対して行為をするのではなく,蚊と皮膚とがつくる「透明上皮層」に対して行為を始める.「透明上皮層」の座標が視覚世界で生成される.「透明上皮層」を潰すように右手を動かすと,右手はまず蚊に当たり,透明な空間を潰し,左手にあたり,蚊が潰れる.蚊と左手双方のピンポイント座標ではなく,蚊と左手を含んだおおよその座標を視覚世界で割り出し,その座標を含む空間を潰すように右手を動かして,蚊を潰す.
そのときの決定的要因は,視覚的接触と触覚的接触との一致ということである.例えば,視覚的な蚊が私の視覚的右手の上方一センチで停止したとき私はチクリと感じる.左手でそれをピシャリと叩こうとすると,視覚的左手が蚊の上方一センチにくるのが見えたとき蚊はつぶれ同時に左右両手に叩かれる衝撃を感じた.もしもこういうのが通常の経験であれば,われわれは当然,「透明上皮層」で被覆された太巻きの触覚的両手をもつことになろう.これには何の奇妙さもない.現在のわれわれの手の皮膚の表皮真皮層がたまたま不透明である,といったことと同様の経験的偶然的事情にすぎない.p. 41
蚊の例から考えてみると,「同じ一つの」灰皿を見て,触れているときには,その周囲の空間を含んだおおよその座標が視覚世界に生じて,その空間に対して行為を行うことで,灰皿に見て,触れるということが起こるのではないだろうか.視覚世界の座標は世界からサンプリングされた点にすぎない.その座標の隣の座標とのあいだに「透明な空間」があるというか,視覚世界から切り抜いた視界が世界に貼り付けられるときには,座標のみではスカスカになってしまう.ピクセルが物理的な光によって,拡散して像をつくるように,視覚世界の座標も世界に貼り合わせられるときに,拡散していく.視覚世界と世界とで対応する座標のあいだを埋めていく拡散していく視覚素=ディスプレイエレメントのようなものがつくるピクセルを拡散してできるニュートラルな色の広がりが視界を埋めることで,視界は連続的に見えているのかもしれない.
こうしてわれわれは,「同じ一つの」身体を体感し,また,見る,ということになるのである.そしてこの視覚的でもあり体感的・[[触覚]]的でもある手を,例えば,視覚的に見えている灰皿に近づける.そして,灰皿に手が視覚的に接触するのを見るとき,或る感触と抵抗とを手に受ける.このとき私は「同じ一つの」灰皿を見,そして触れているのである.これがわれわれの,見ることも触れることもできる「事物」の観念なのである.p. 42
ピクセルと拡散するピクセルについては,アルヴィ・レイ・スミスが『A Biography of the Pixel』で書くピクセルとスプレッドピクセルとの関係を参照している.
ディスプレイメーカーはしばしば,ディスプレイ内の小さな光り輝く要素を "ピクセル "と呼ぶ.しかし,これではスプレッドピクセルとピクセルを混同してしまう.これらはピクセルではなく,ディスプレイエレメントと呼ぶべきである.このような表示素子の1つの輝き(中心が高く,中心から離れるとゼロになる発光照度)は,特定の表示デバイスのスプレッダーである.ピクセルが表示素子に入り,広がったピクセルが出てくる.一般的に,光り方の形状はメーカー独自のもので,同じ会社でも製品によって異なることさえある.p. 64
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
