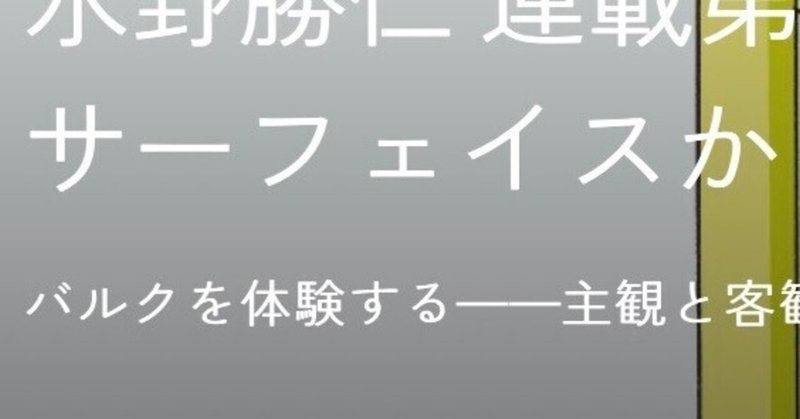
238:大森荘蔵『新視覚新論』を読みながら考える05──4章 「表象」の空転
脳が予測に基づいて外界を認知・行為していくことを前提にして,大森荘蔵『新視覚新論』を読み進めていきながら,ヒト以上の存在として情報を考え,インターフェイスのことなどを考えいきたい.
このテキストは,大森の『新視覚新論』の読解ではなく,この本を手掛かりにして,今の自分の考えをまとめていきたいと考えている.なので,私の考えが先で,その後ろに,その考えを書くことになった大森の文章という順番になっている.
引用の出典がないものは全て,大森荘蔵『新視覚新論』Kindle版からである.
4章 「表象」の空転
1 主客構造の不在
何度も書いているが,私が見ているの私と世界との相互世界から生成される視覚世界で,そのなかに私と世界は含まれている.私が動けば,その通りに世界も動くのは,それらがそれらを媒介する視覚世界のなかに存在するからである.瞼を閉じるというのは,世界を見ないことではなく,視覚世界の解像度を落とすことであって,私と世界とは視覚世界から抜け出すことはできない.この意味で視覚世界には主客構造はないと,私は考えている.私と世界とは視覚世界を媒介にしてリンクしていて,私が動けば世界も動き,世界が動けば私も動くいや,視覚世界が動けば,私も世界もともに動く.まばたきや眼球のサッカード運動などで,24時間中1時間は世界を見れていない状態があるとされるが,ヒトは世界を見続けている.それは,世界を見ているのではなくて,視覚世界を見続けていて,視覚世界はまばたきや眼球のサッカード運動で世界が見えづらくなっているときも,過去の履歴から予測された情報が世界を補完するのである.また,世界を見ていると言っても,私は視野の全てをみているわけではない.視野の全てを私が見るということはありえない.視野を埋め尽くする視界は私と世界との相互作用でつくった視覚世界の一部であり,そこの登場している私とされる現れもまた,予測モデルの一つに過ぎず,他の現れと同じ視覚世界のなか一部でしかない.
なるほど,私が一つの方角を眺めるとき,その風景は__ここにいる私に対して__見えている,と言いたくなる.私はその風景と__向き合っている__のだ,と言いたくなる(一方,私は吐き気に向きあっているとか,吐き気は私に対してこみあげてきているとか,と言いたくなる誘惑はあるまい).しかしこの「私に対して」というときの「対して」は空間的関係以上のものではないのである.そしてその空間的関係はまさに「風景が見えている」という状況の__中での__位置関係であって,その状況を作り上げる関係(それが主客関係である)ではない,ということは承認できるのではなかろうか(三章).そしてまた,「向かい合っている」というのも同じようにこの状況の中での空間的対面以外のものではない,ということも.私はこの空間的風景(あるいは,風景空間ともいえる)の__中にいる__のであり,その__中で__移動したり向きを変えたり瞼を開閉したりしている.その中で動作主体であるのである.だが「私」は登場していない.つまり,その空間風景が(どんな意味であれ)認識論的に「__私に対して__見えている」というのでは__ない__.吐き気や歯の痛みがただあるように,空間風景はただ見えているだけなのである.吐き気や痛みがただあることの中に何の主客構造の紋様もないように,空間風景がただ見えていることの中に何の主客構造もないのである.私が,「見えている」ことの条件なのではない.「見えている」こと(その状況)が,「私がいる」ことなのである.p. 87
視覚世界は世界のコピーではない.同時に.私の妄想や幻でもない.視覚世界は私と世界との相互作用の予測モデルであって,世界のコピーではないということはどういうことか.私には何かしらの意図があり,世界には物理法則がある.この二つを含んで,ある認知とその認知に基づいた行為が行われる私と世界と相互作用を予測していく.ここには世界の表象というよりも,おそらく,私と世界との相互作用における重要なポイント=座標の集まりが意味を持つ考えられる.石斧をつくる際に,石の形のポイントが次に打つポイントを示し,同時に,手の現在のポイントからそのポイントへの行為を予測していき,手を動かす.スナップショットのような表象は役には立たない.ワイヤーフレームでもいいので,動的なモデルが求められる.私と世界とは動き続け,動きとともに視覚モデルは構成されていく.視覚世界はワイヤーフレームでもいい.このように書くと,ワイヤーフレームを視野で切り抜くと,視界もワイヤーフレームで埋められるのではないかとなる.これは,私やあたなが今視界に見ているものとは異なる現われである.となると,ワイヤーフレームの視覚世界で動き続ける私と世界との相互作用を認知しつつ行為を続けていくときに,ワイヤーフレームにテクチャが貼られて,視界が現れると考えてみたらどうだろうか.「表象」のように仕立て上げらるのは最後の最後で,それまではワイヤーフレームのような視覚世界が,私と世界との相互作用を予測し続け,少し先の私と世界との関係を決めていき,最後の最後で「表象」のようなテクスチャが貼られる,そのテクスチャは網膜に入力された色情報と私が今いる座標の記憶から仕立てられて適用されると考えてみたらどうだろうか.
こうして,「見えている」ことに何の主客構造もみられないということは,そこには何の認識論的構造もないということに他ならない.ということは特に,およそ「表象」と呼ばれるものに類するものがそこにはない,ということを含む.主観が客観的対象を認識する(見る,聞く等)ということがあってこそ,その対象の「表象」というものもありうるものだからである.主客構造がないところでは「表象」なるものは宙に浮いてしまうのである.このことは上に述べた吐き気や痛みの場合に特に明瞭にみてとれよう.およそ,吐き気だとか痛みだとかを何かの「表象」だと思う人がいるであろうか.吐き気を胃潰瘍や二日酔の表象,歯の痛みをムシ歯の表象だとは,ただ冗談で言えるだけである(医者もちゃんと「症状」だと言う).吐き気や痛みを表象だと言えない理由は,それらを「幻」だと言えない理由と全く同じでないまでもそれに極めて近縁である.それらの贋物が考えられないのと同様に,それらのコピイが考えられないのである.こうして吐き気や痛みの「表象」というものが考えられないことは逆に,吐き気や痛みに主客構造がないことを間接的であるにせよ示すことになろう.p. 88
2 「表象」の空回り
写真機の比喩が面白い.写真ではなく3Dモデルの比喩で視覚を考えてみる.私と世界との相互作用からワイヤーフレームのような視覚世界がつくられる.視覚世界は私と世界との相互作用を予測し続けるための座標が集まりで,その座標をリンクする線がワイヤーフレームようになっている.私と世界とは視覚世界において認知と行為を行うが,その際に世界からテクスチャの情報を取得する.この点では「視覚表象は客観対象にはりついていると想定されている」と言えるだろう.客観対象に張り付いてい視覚表象=テクスチャ自体は二次元のデータとして切り抜かれる.「情報」や「データ」を媒介にすると,大森の比喩を活かせるのではないかと今気づいた.視覚表象そのままを切り離すのではなく,情報・データとして客観対象から取得することが重要であり,大森にない視点を付け加えることができるのではないか.客観対象から取得されたテクスチャは,視覚世界のモデルに貼り付けられて,客観対象の現れが視界を隙間なく埋め尽くす.テクスチャを取得するためのモデルは視覚世界に予めあり,テクスチャは世界に予めあるとすると,視覚世界と世界との座標を合わせると,自動的にその座標に合致した視界がレンダリングされるとも言える.まして,予測されているとしたら,世界のテクスチャをモデルに適応させるときにそれほどの処理は必要ないのではないか.カラーパレットのように,世界のテクスチャパレットが用意されているとしたら.あるいは,同一座標における時間別テクスチャパレットがあると考えると処理はより効率的に考えることができる.3DCGモデルで考えると「空間に瀰漫する感光主観」というものはいないけれど,私と世界と視覚世界とは座標でリンクされていると考えることから「空間に瀰漫する座標主観」というのはあるかもしれない.
さらにこの想定においては,蜃気楼,鏡像,レンズ像等の光学像や幻覚のような場合の他は,視覚表象は客観対象と同一の場所に見えるとされている(光学像の場合は五章に検討する).いわば視覚表象は客観対象にはりついていると想定されているのである.このことによって視覚表象を何か写真のフィルム像のような「写像」とする比喩は拒否される.もしそれを写真のフィルムのようなものと考えるならば,そのフィルム像は写真機のレンズの後側ではなく前方に,それも被写体にはりついている,しかも三次元的にはりついていることになるからである.たといわれわれの眼球を写真機のレンズに,脳をフィルムにたとえることができるとしても,視覚表象をそのフィルム上の像にたとえることは不可能なのである.もし強いて光学的写像の比喩を考えるならば,写真機よりも密着複写装置の方がいくらかましであろう.しかしこの複写の比喩をとるならば,こんどは眼球も大脳もこの比喩のどこにも登場できないことは明らかである.そして「主観」なるものがこの比喩に登場するとすれば,この三次元空間にエーテルのように漂う感光材エマルジョンとしてでしかありえない.だが,空間に瀰漫する感光主観といったものを真面目に考える人はいまい.カントは,感性が物自体に触発される,と語ったが,その触発機構については何も語らなかった.もし語れば感光作用のようなものになることが不可避であるからであろう.p. 90
視界に現れるものは,それ以前の視覚世界における私と世界の相互作用によって決定している.私は視覚世界における一つの視点となって,視界を決定する.「見るー見られる」という関係はワイヤーフレームの視覚世界にはないけれど,視界に関しては,私が視界を見て,視界が私に見られているということはあり得るかもしれない.ただし,私と視界とのあいだに「見る‐見られる」の関係があったとしても,そこで生じていると思われている私と世界とのあいだの認知と行為に関しては,視界として切り取られる前の視覚世界というのっぺらぼうというかスカスカの場で生じている.ここに認知の行為とがあって,それは「見る‐見られる」の関係ではなく,もっとデータの流れのような「見る」ことも「聴く」ことできないような情報の場である.そこで決定した認知と行為の情報が視覚世界から切り抜かれて,視界となる.その際に,視界には世界のテクスチャが適用される.このように考えると,視界と私との間には「見る-見られる」の関係があることになり,「見る」ということを力動的な「働き」として感じてしまう要因になっている.しかし,視界となる前の視覚世界は「主客構造に関してはのっぺらぼうの場」であり,その場に私と世界との相互作用が密になってワイヤーフレームが構築されていると考えることができ,そこには視点が「見えている」というに囲まれた静態的な「場」であって,私も世界も存在せずに,その相互作用のデータ・履歴しか存在しないのである.
カントに較べるならフッサールの方がわかりいい.「私の先験的自我は明らかに自然的自我とは違う.しかし,決して普通に理解されるような意味で後者と分離された第二の自我ではない.しかしまた逆の意味で自然的自我と結びつき組み合わされているというのでもない.私の先験的自我はまさに(完全な具体性において捉えられた)先験的自己経験の場であり,しかもこの先験的自己経験は,見方を変更しさえすれば,いつでも心理学的な自己経験へ変貌しうる」( Husserliana, Bd. IX, p. 294.立松弘孝氏の指示).フッサールの言いたいのはおそらく,空腹とか私の体や私の今の気分とかを度外視(エポケー)しても残る視覚風景の「見る‐見られる」の構造のことであろうと思う.そしてその構造には今この経験的私がいる「ここ」という視点が不可欠なことを言いたいのであろう.猫が消えてもその眼の視点は残るのである.しかし,視点があるということは何もそこに「見る」というノエシス的な能作とか作用だとかがあることではない.今までに度々繰り返したように,「見えている」という状況は静態的な「場」なのであって,力動的な「働き」なのではない.働きなり主体的動作があるとすればそれは,視線を向ける,そらす,とか,見つめる,気を抜く,といった肉体的心理的動作なのである.そしてこれらの動作は「見えている」という「場」の中で行なわれる動作なのであって,その「場」自体は何の動作でもない,つまり,主客構造に関してはのっぺらぼうの場なのである.ちょうど,われわれの肉体的動作は空間という場の中で行なわれるが,空間自身は何の動作でもないように,である.あるいは,生きるためには食べたり呼吸したりという動作をするが,それらの動作がなされる場である「生きている」というそのことは何の動作でもないように,である.そうして,生きている,ということに何も「生きる‐生きられる」という構造がないように,「見えている」ということにも「見る‐見られる」の構造はないのである.p. 93
3 記憶像の場合
大森の言葉を借りて,私の世界の見え方を説明すると,「想起という立ち現われの様式」が予測モデルとして立ち現れる視覚世界であり,「知覚という立ち現われ様式」が視覚世界が視野によって切り抜かれ,そこにテクスチャが適用されて立ち現れる視界として考えられる.『新視覚新論』にコメントを始めた当初は視覚世界は鮮明な世界のモデルだったが,今ではワイヤーフレームのようなモデルとなり,認知と行為の予測に役立てばいい粗いモデルになっている.低解像度であっても,そこに「浅間山」があるという感じがわかればいいわけである.解像度を持ち出すとワイヤーフレームとの整合性が取れなくなってくる.私と世界との相互作用の集合としてはワイヤーフレームのようなラインベースのモデルで問題ないと考えられる.低解像度の「浅間山」が立ち現れるのは,ワイヤーフレームのモデルが立ち現れると同時にというか,私と世界とは常に相互作用している,瞼を閉じていたとしても世界からの光は入ってくるという常時データ処理をしていて,どこかに明確な始まりがない状態だと,予測モデルにおけるワイヤーフレームと低解像度の状態は,絶えず入れ替わっているか,パラレルに現れていて,世界との誤差を最小化するためのチェックとして使われているのかもれない.どちらが先か言われるとワイヤーフレームの方が先だけれど,45年も生きてくるともうどちらでもいい感じで,予測モデルはワイヤーフレームの状態と低解像度の状態との二つの状態のどちらかで,互いの間違いを修正して,高精細な世界のテクスチャを適用するためのモデルづくりの準備をしているのではないだろうか.予測モデルはワイヤーフレームと低解像度という冗長性を持つシステムなのではないだろうか.しかし,ワイヤーフレームモデルは世界を三次元で捉える,低解像度モデルは世界を二次元で捉えるとすると,冗長性を持ったシステムではなく,同一の情報に対して,二つのモデルで対応しているということになるだろう.二つモデルで予測されたものに,知覚で得た情報である世界のテクスチャを適用したものが,視界として私が知覚している世界ということになる.視界に立ち現れているものは鮮明であるためえこひいきしてしまうが,それはワイヤーフレームと低解像度でできた粗い予測モデルがなければ知覚的現れはないのである.
しかし上越から遙か離れた街で浅間を思うとき,それはあの本物の浅間山をじかに思っているのだといくら言われても,その浮かび出る浅間の姿は何とも心もとない姿ではないか.その稜線も定かならず地肌の色も模糊としてしかと把え難い.その姿には何か夢幻的なものがある.本物のもつ偉容と迫真とを欠いている.そこで再び,それは何といおうとやはり本物ではなくそのイメージ,その浮遊的な似姿ではないかという思いが頭をもたげてくる.だがこの思いは,くっきりとした視覚風景と定かならぬ想像風景とのコントラストを,客観的実物とその主観的表象というコントラストに取り違えているのである.晴れ渡った日のくっきりした眺望と煙霧にけぶる風景,透明なガラス越しの眺めと曇りガラス越しの眺め,ピントの鋭い写真とぼけた古写真,これらの実物同士の間のコントラストを実物とその写像のコントラストに取り違える人はいない.しかし,知覚現場の明確な視覚風景と,知覚ならざる想起における模糊とした風景,このコントラストを客観と主観的像のコントラストに取り違えるのである.知覚という立ち現われ様式と,想起という立ち現われの様式,この事物の立ち現われ様式の差異を,事物への接し方の直接性と間接性の差異だと思い込む.じかに見える浅間山と,イメージとか表象だとかを通して間接的に思い浮かべられる浅間山の差異だと思い込むのである.ここには知覚に対する無意識のえこひいきがある.知覚が本当の現場で想起は二次的な伝聞だとするえこひいきである.しかし,知覚現場であるのと全く同じ資格で想起現場もまた現場なのである.知覚的立ち現われがじかであるのと同様に,想起的立ち現われもじかなのである.想起風景が知覚風景の知覚的明確さをもたぬことは何も想起風景が二番煎じであることを意味しない(知覚にその明確性において優るとも劣らない想起能力は十分に想像できる).結局,想起においても浅間山がじかに立ち現われるのであって,浅間山の「観念」なるものの役回りはないのである.p. 97
上のように書いたけれど,テクスチャは高解像度というわけではない.むしろ,テクスチャが低解像度で予測モデルのワイヤーフレームと結びついて,そこから視界に立ち現れる知覚的立ち現れが生成されていくと考えた方がいいだろうし,以前もそのように考えていた.視界を考えるようになったのはこの記事からだった.
4 知覚現場での表象
「対象」は「表象」として私の視界に現れているときに,そののようにその場所に在る.私の視界を覆う表象が対象を定義する.視界は世界のコピーではなく,視界が世界のあり方を決める.世界は表象言語=視界と対象言語=視覚世界との「重ね描き」されて現れるとは考えらない.視覚世界は対象言語として世界を予測するためのモデルである.私の脳には私と世界との相互作用から生じる予測のための視覚世界があり,これは大森が対象言語と書くものに近い.対象言語としての視覚世界内の一つの視点として私の生物学的視野が視覚世界の一部を切り抜いたとき,それは視界となる.このとき視界は世界からのテクスチャを得ているが,それは世界のコピーではなく,予測モデルに基づいて処理されるデータである.世界テクスチャの低解像データを予測モデルに基づいて処理して生成される高解像度の表象が視界に展開される.世界の対象が精細にそこにあるという意味では,視界の表象がそのあり方を決める.しかし,視界を形成するためのデータは,もともと私と世界の相互作用から生じる予測モデルと世界テクスチャという対象から入手したものであるから,対象が表彰のあり方を決めていると言える.なので,双方入り乱れつつも,ある秩序を持って重ね描きされた結果として,視界の高精細な表象があり,対象がその時その場所にあるという感じ生じるということになるだろう.
この不定性を取りのぞくには唯一つの道しかない.それは「対象」の時空位置を「表象」によって定義することである.例えば,「対象」はその「表象」が見える,その時その場所に在る,と.だがこうすることは同時に,「対象」と「表象」との関係を根本的に変更することである.もはや「対象」が本物で「表象」はそのコピーではなくなる.そうではなく逆に,「対象」は「表象」に基づいて定義され,考えられたものとなる.「対象」は「表象に」時間空間的に重ねて「考えられた」ものとなる.そして世界は表象言語(知覚言語)と対象言語(物理言語)によって時空的に「重ね描き」されることになる(五,六,七章に詳述).こうして「対象‐表象」という二元的設定は,それ自身の論理的構造によって変質せざるをえないのである.p. 102
「物理的状景」が予測モデルとしての視覚世界だと,私は考える.大森は「大脳の物理的状景と視覚風景が連動して変化するからに他ならない」と書いているとこは,もう少し複雑というか,二度手間の処理をしているように思われる.大脳の物理的状景はまずは世界からの視覚に関する生データと連動して,ワイヤーフレームの視覚世界を形成する.そして,この視覚世界が世界を予測している中で,低解像度の世界テクスチャのデータが合流して,視覚世界による予測と世界テクスチャとの誤差を最小化していくプロセスで,世界テクスチャが高精細化していき,視界として切り取られて,世界の認知と行為のために使われる.そして,その際,常に大脳の物理的状景は世界テクスチャを持つ世界,予測モデルとしての視覚世界と連動しつつ,視界をつくり,視界が展開された状態では,視界も大脳の物理的状景に連動することになる.
私に今見えている視覚風景,それに対応すると想定されている物理的状景,この二つは同じ空間の中,同じ時間の中にある.視覚風景は「見えて」おり,物理的状景は「考えられて」いる,それだけの違いであって,後者の物理的状景を把える「主観」などどこにも登場していない.いや,かりに登場するとしてもそれは,視覚風景を「見る」とともに物理的状景を「考える」主観としてである.いわば両者に等距離にある,あるいは両者に共有される主観なのである.デカルト的生理学者は,私の大脳の物理的状景を主観が把えたものが今見えている視覚風景なのだ,と言って物理的対象を視覚風景の前に置くかもしれない.しかし彼はその把える現場に立ちあったこともなく,また立ちあえるものでもないことを知っている.それにもかかわらず彼が「主観の把え」を言うのは単に,大脳の物理的状景と視覚風景が連動して変化するからに他ならない.だとすれば,彼はただその連動の事実のみを言うにとどめるべきであろう(また生理学者もその専門論文ではそこにとどまっている).p. 103
大森が書くように「幽霊がそこに見えていることは墓石がそこに見えていることと変わりがない」と,私も考える.私と世界との相互作用において,幽霊のような触れることがないけれど,見えるようなデータが生まれた結果,視覚世界に「幽霊」が現れ,低解像度の世界テクスチャが適用されて切り抜かれ,視界に現れたものが幽霊とされる.このプロセスの中で誤差が視覚世界と世界テクスチャとのあいだの誤差が最小化されないで,テクスチャの高精細化が生じなかったものが幽霊や錯覚のようなモノもどきとして視界に現れる.しかし,このときは視界だけで考えることはできない.モノもどきを感じるときは,触覚の視界に当たる触界など感覚データから生成される私と世界とのインターフェイス相互の情報にズレが生じている可能性が大きいからである.このように考えると,世界は一つだが,私と世界との相互作用で生じるのか,視覚世界,聴覚世界,触覚世界,嗅覚世界,味覚世界など感覚ごとに予測のためのモデルがあって,それぞれが私と世界とのインターフェイスである視界,聴界,触界,嗅界,味界を持つことなる.普段はこれらは統合されて世界を感じているが,ある条件ではバラバラになって,モノもどきを生成する.
ではあの幻覚は一体何なのだ,少なくとも幻覚こそ純主観的なものとせざるをえないではないか,と問われよう.別に何でもない,立派な視覚風景の一つであると答えたい.幽霊がそこに見えていることは墓石がそこに見えていることと変わりがない.ただ違いは墓石のようにぶつかることも触れることもないものだということだけである.またそれに対応する物理的状景ではそこに空気や電磁場があるというだけである.このことは幽霊を極めて興味深い種類の「物」にするだろうが,そこに「主‐客構造」を思わせるものは何もない.たかだか,それを見ている人の視覚器官や大脳の状態についての示唆を与えるだけである.本当の幽霊はむしろ「主‐客構造」という考え方なのである.そして,客観の主観的表象,という概念こそ幻の概念なのである.p. 105
と書いたけれど,複数の感覚モダリティの情報を統合した物体というのはあるのかという議論があり,聴覚や触覚においては「そもそも「物体」と呼べるものを知覚することが可能なのか」ということも議論されているらしい.となると,それぞれの感覚が統合されているのではなくて,もともとバラバラであって,ある条件になるとそのバランスが崩れて,物体を認識するとされる視覚の視界において,物体が物体として見えることが崩れながらも見える状態ができて,そこにモノもどきが現れるということになると書いた方がいいと思われる.
さらに,特徴統合の結果として知覚される「物体」の定義についても,感覚モダリティを超えた議論は容易ではなかった.特徴統合理論の枠組みにおいては,視覚的注意を特定の位置にに向けることによって,その位置に存在する複数の資格特徴の集合体としての「物体」が認識される.視覚研究における「物体」の専門的定義については様々な議論が存在するが(Feldiman. 2008: Stoll, 2001),それでもなお,たとえば果物やコップ,椅子といった,我々が日常生活において視覚的に認識しているものの多くが「物体」であることは疑う余地もなく,当然の事実として受け止められている.一方,聴覚や触覚といった他のモダリティにおいては,そもそも「物体」と呼べるものを知覚することが可能なのか,可能なのであれば「物体」とは一体どのようなものかといった議論からら出発することになる(Bregman, 1994; Kubovy & van Valkenburg. 2001). 当然ながら,感覚モダリティを超えて適用できるような汎用的な「物体」の定義が可能かどうかは,依然として不明なままである.一部の研究者によって,複数の感覚モダリティの情報を統合することで,多感覚的な「物体」が知覚されるという主張も行われているが,このような場合における「物体」の定義も明確には示されていない(Busse, Roberts, Crist, Weissman, & Woldorff 2005. Turatto, Mazza, & Umita. 2005).このことも,特徴統合理論を視覚以外の感覚モダリテイや,クロスモーダル処理における情報統合の枠組みとして応用することの因難さにつながっていると考えられる.p. 122
「モノもどき」について書いたnoteとテキスト.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
