
アーカイヴ月モカ❗️ /Vol.6「 ルーツ/松谷みよ子」(2015.04.06)
※ルーツとは、ことの起源、という意味です。
そして本編は過去の月モカのアーカイヴです。新しいものたちはこちらのマガジンにありますゆえ!
✴︎ ✴︎ ✴︎
わたしのパブリックな処女作は「蝶番」であるが、わたしがいちばん最初に書いた物語は「あきちゃんとアヤメちゃん」という、シリーズものの短篇集だ。
書き始めたのは幼稚園のときで、おそらく小学二年生くらいまで書き続けていた。単に自分と妹の日々を、松谷みよ子さんの「小さいモモちゃん」シリーズになぞらえて書き連ねてゆくだけの、もはやタイトルにすら独創性のないーーシリーズ4作目「モモちゃんとアカネちゃん」を自分たち姉妹の名前に変えただけというーー模倣作品である。
しかし幼稚園児が小学生になるまで、コツコツと、落書き帳数冊にわたるシリーズ短篇を書いていたという、その持続性の部分は評価したい。
この短篇シリーズは、なんとこの物語の重要な主人公のひとりである「あやめちゃん」との姉妹げんかによって、シリーズの半分がビリビリに大破する、という惨劇で幕を閉じた。
その後、破れ残った部分に物語を書き足すということを試みたが、どうも気乗りがせずに、新しい落書き帳はほとんど白紙のまま、この執筆をわたしは投げ出してしまった。積み上げたものが壊れるという出来事は、いつなんどきも、人の心を打ち砕く。
ときどきあの事件を思い返しては、あやめは確か、自由帳数冊分の「あきちゃんとあやめちゃん」をその自由帳接続部分(つまり何冊かを貼り合わせている)をメリメリっとやってゴミ箱に捨てたが、実際、紙ごとをびりびり破ったのは、エピソードにして1話分くらいであったのだから、なんで屑籠から出して、使わなかったんだろうと不思議に思うことがある。
同時になんか、ゴミ箱(屑籠)というゾーンに一度入ったならばそれは、それらの「死」を表していた、つまり、わたしにとってゴミ箱(屑籠)というものの概念があまりに圧倒的であったのではないかと考えて、あの原稿が今はもう存在しないことを残念に思う気持ちを静める。

(これはそのめっくすの家に先日飾られてた絵。素敵だ、誰の絵!?と思ったら、なんとベスフレが描いたらしい。素敵だ)
✴︎ ✴︎ ✴︎
「松谷みよ子さんが亡くなったよ」と、電話をもらったのは二週間ほどまえで、電話をくれたのは、わたしにそれら「小さいモモちゃん」シリーズを買い与えたそのひと、母であった。
松谷みよ子さんはいわゆる大往生とまではいわないが、命をまっとうされて、この世での日々を終えられた亡くなり方であったようで(と事務所HPには)、清志郎やマイケルのときのように「まだまだいっぱい聴かせてほしかった…」という悔やんでも悔やみきれないというような感情は沸かなかったが、勘三郎さんや斎藤憐さんや井上ひさしさんのような顔見知りではない著名人の方の悲報の中で、いちばん、大きく、家族を失ったようにこみあがってくる、「喪失」であった。それはどこか自分の血肉の一部の「喪失」であった。
わたしは初めて、青山斎場に行った。
この怠惰なわたしが土曜の朝という、自分にとっていちばん辛い時間に起きて、傘を持って行った。
入り口に白い花と「松谷みよ子 お別れの会」という白い布があがっている。それを目にしたらば、途端に涙がとまらなくなった。
エディットピアフが流れ、白い花々で埋め尽くされた斎場を、わたしはほとんど嗚咽といえる状態で前に進む。
お別れの会は喪服でなくてよいですと書かれてあったし、わたしはあまりに大きな出来事に頭を支配されていると、普通に考えつくことの機能がすっかり停止してしまうきらいがあって、喪服でなくてよいですという言葉を信じきって、うっかり濃い紺のパーカーを着ていってしまった。
そのわたしの服装はお悔やみを表していなかったかもしれない。
けれどその服の中にいる「わたし」があまりにも大切なひとを失った佇まいでいることが、会場にいる、ほとんどが年配のみなさまに伝わったのだろう、みな優しかった。知らないひとしか場内にいなかったが、ここにいるみなと、「小さなモモちゃん」を通して、語らずとも通じ合えることができる。あるいは「まちんと」を通して。あるいは「ふたりのイーダ」を通して。

まったくの関係者でなかったが、わたしは青山斎場をとてもホームに感じた。だって、わたしは、「あきちゃんとアヤメちゃん」を書いたのだもの。幼稚園から小学低学年という数年をまたいで、片手に「小さいモモちゃん」を抱えながら「あきちゃんとアヤメちゃん」を書いたのだ。
そして、その大きくなったあやめちゃんが、「その出来事は突然にやってきた」と語る冒頭で始まる、姉の、いわゆるあきちゃんの失踪物語で、わたしは本当に小説家になったのだ。
つまり「蝶番」と「あきちゃんとアヤメちゃん」は繋がっている。だから小説家であるわたしのルーツはこの、青山斎場に溢れている本と、その本に関わった人たち、つまり、いまここで白い花をお骨にたむけている人たちすべてにあって、
ここは悲しいお別れの場所であると同時にマジュリス(アラブの言葉でたくさんの親戚や仲間が集う応接間)でもあるのだ。
みんながあの勇敢な黒猫のプーを知っている。
アカネちゃんが生まれていちばん最初に仲良くなった、双子の靴下のタッタちゃんとタアタちゃんも。
そして、パパとの不仲に苦しむママの元に、毎晩、靴だけがかえってくる、あの悲しくて寂しい夜の感じも。
児童文学の中で両親の離婚を描いた、新しく、勇気ある作家さん。
松谷みよ子さんが亡くなって、すぐに「モモちゃんシリーズ」を読み返した。幼いころに何百回と読み返した本の内容の、覚えていること。覚えていること。
同時にわたしは36歳になっていて、初めてこの「ママ」の視点からもこの物語を読んだのです。そうして知ったことは、当時26歳でわたしを生んだ母が、この物語を愛し、この物語のようにわたしを育ててくれていたこと。
雨が降ったら赤い傘に、赤い長靴。
その色までもおそろいに。
帰りの遅いママなんて放っておいて銀河鉄道に乗っりましょう。ほら、空色のきっぷが、もうこの手の上にあるよ。
当時働きながらわたしを育てた母が、母とはいえ、今のわたしから10歳も若い、20代の若い母親が、やっぱりこの物語に救われながら、まだ幼いわたしを育て、妹になる「あやめちゃん」を産んで行った。
その過程は、わたしたち家族の物語とぴったり重なって、
わたしは生まれたときから「小さいモモちゃん」の人生を生きていたようにも思えた。
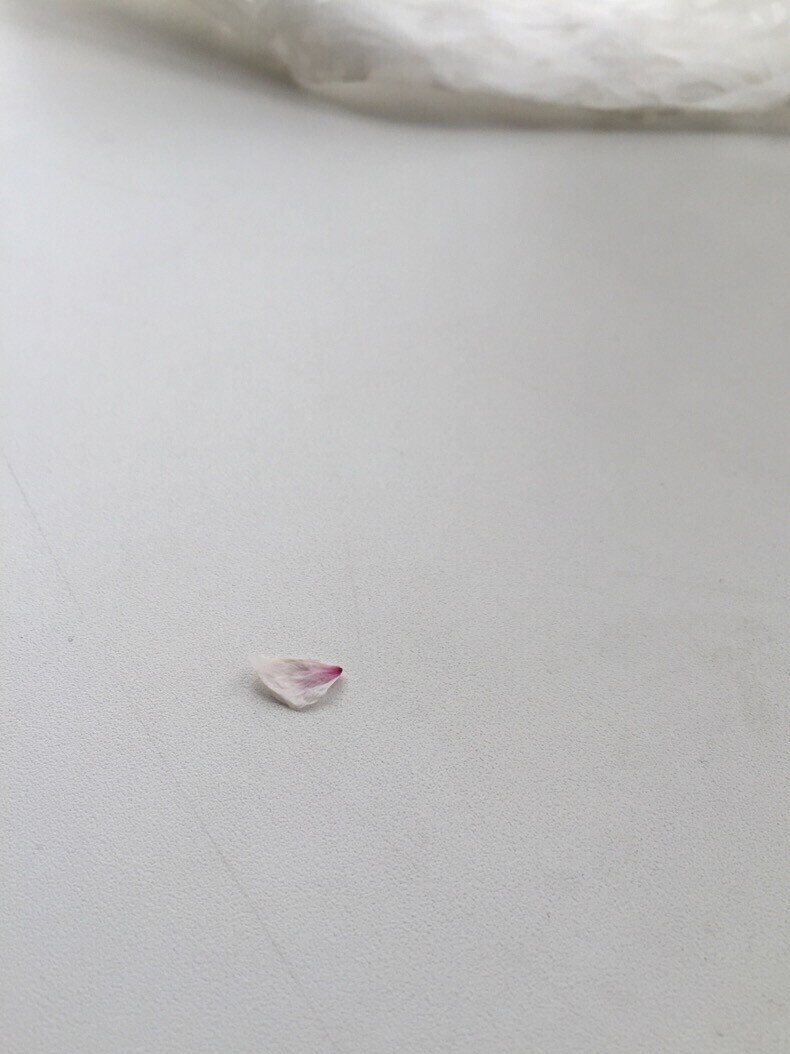
いや、ちょっとまってください、それはわたしです。わたしこそがモモちゃんです。モモちゃんのママはわたしのお母さんです。
いやそれはうちですよ、だって、お客さんのパパが、さよならしたあともこっそりわたしに会いにきてくれたんですからね。
こうやって言いたい読者が、この日本に何人いるだろうか?
こうやって言いたい読者しか、この日本にはいないかもしれない。
あの物語を、誰かの物語として、うまく距離をとりながら読むなんてことが、できようか。みんな自分の愛しい誰かとの日々を重ねて、あれを読んでいる。
エディットピアフが、流れていた。
わたしは松谷みよ子さんのお骨に向かって花をたむけた。
そして約束した。
あのね、むかしね、自分のことがねえ、モモちゃんだって思っていた女の子がいたんですよ。でも真っ黒なプーや、おいものおばさんには会えなかったから、アカネちゃんみたいな妹が生まれたときは、それはそれは喜んだんです。それでね、その女の子はお話を書き始めたんです。
お話ったって、てきとう、じゃないんです。
ほんかくてき、なやつですよう。
ちゃんとタイトルがあります。
その女の子のママは、もうせん「本にはタイトルがなくちゃね。あきちゃんもいちばんさいしょにあきちゃんって名前を貰ったでしょ」と言ってました。だからちゃんと最初にタイトルをつけたんです。
え?その女の子がその後どうなりましたかって?
ちゃんと立派に作家さんになりましたよう。
そしてね約束したんです。約束の印に白い花を置いてね。
きっといつかほんとうに「小さなモモちゃん」みたいに、読んだすべてのひとたちが「わたしがモモちゃんよっ」って思えるような物語を、わたしきっと書きますよ、って。

実は”がんこエッセイ”の11月号は「モモちゃんとがんこ堂」です。
こちら、その存在を知らずに育った、幻の6巻について書いています。
本日アーカイブした月モカは2015年、なんともう7年前のエッセイ。
未だわたくし、読んだ全ての人が「わたしがモモちゃんよっ」って思える物語を書いていませんが「ちいさいモモちゃん」最終巻のあとがきを読んで、長い歳月にさらしながらいつか紡げる物語を待っていいのだと思えています。詳しくはこちら↓ご覧ください。
まさに「#わたしの本棚」という感じの内容です。
40年越しの本棚!って感じのね。笑。
また「がんこエッセイ」のマガジンでもアーカイヴしますがこちらにも。
↑今週のレディオ放は映像でお楽しみいただく【OFF AIR】でした〜
✴︎ ✴︎ ✴︎
《モチーフvol.5 “ルーツ/松谷みよ子” 》
☆モチーフとは動機、理由、主題という意味のフランス語の単語です。
がんこエッセイの経費に充てたいのでサポート大変ありがたいです!
