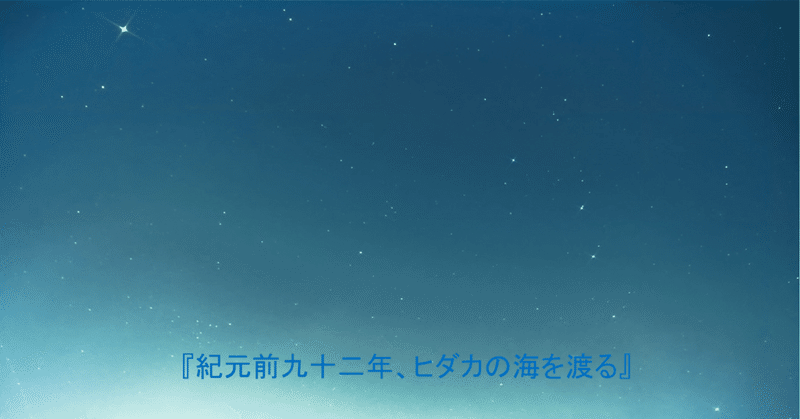
『紀元前九十二年、ヒダカの海を渡る』[106]若き匈奴たちの企て
第5章 モンゴル高原
第4節 エレグゼンが負った槍の傷
[106] ■2話 若き匈奴たちの企て
二十歳になったばかりの頃に、エレグゼンは小石と岩の沙漠を西に越えてみようと企てた。もちろん、はじめにションホルを誘った。
匈奴として生まれた男は、その生まれだけで戦士として受け入れられるわけではない。ともに戦う仲間として、馬も、弓も、格闘も、戦場で頼るに足ると認めてもらわなければ匈奴の男とは呼ばれない。いまでは部族で一、二の勇者とされているエレグゼンも、つい数年前までは、周りに子ども扱いされては目をむいていた。
匈奴の兵士仲間に入ろうとするとき、一緒に生まれ育った若者たちはみなで語らって、何か、とんでもなく無謀なことをする。男を示すにはそれが一番早い。同じ年頃の娘たちは、あるいは愚かなことはするなと言い、あるいは嗤って見ている。
大人は止める。しかし誰もが通って来た道だ。止めはしても、心のうちでは、きっとやるだろうと思っている。それでもし死ぬようなことがあれば、匈奴の男ではなかったというだけのことだ。
エレグゼンたちの企ても、そのような後先を考えないものだった。
冬の牧地に移って間もなく、沙漠を越えるにはまだ暑さが残っているという初秋のある日、エレグゼンとションホルは他の友二人とともにオンギン川を越えて、ひたすら南に向かって急いでいた。目指すのは右賢王の支配地の最も西にあるハミル。
その地まで行くのに、漢兵が見張っているゆえに通ってはならぬと固く戒められている東西のボグド山の南の原をわざと選んだ。その原を真西に向かって走る。行き帰りにはおよそ一月。しかし、幾日掛かるかなど、みな、考えてはいない。
「せっかくここまで来たのだ。漢の居延城のすぐ北、エチナ川が注ぐガシュン湖の南岸を馬で駆け抜けようではないか」ということになった。
――漢兵などいるものか。もし見つけたら蹴散らす。
怖いもの知らずの四人はそう勇み立っていた。
毎夜、草むらと小山の陰の砂地で夜を明かし、単于の支配地のはるか西、右賢王の直接の支配地にまですでに入り込んでいる。そこら一帯は、決して断りなく近づいてはならないと部族間で取り決められていた。
これも近づいてはならないと言われているエチナ川下流の二つに分かれた黒い流れを軽々と西に渡り、
「このすぐ南は漢の居延の城だ」
「城兵どもは、吾れらの馬があまりに早いので驚いているぞ」
などと、恐れる気持ちを紛らわすように、走る馬の上で互いに向かって叫び声を上げた。
いよいよ、南に広がる山の向こう側は漢の兵が護る砦と砦をつなぐ広い道だという辺りに近づこうとしていた。ボグド山から連なる西の峰々はもはや遠く背後に去って見えない。
――ようやくゴビを越えた……。
漢兵の気配はないかと気を付けながらアレマリの水場を探し、オオカミの遠吠えに慌てて火を焚いて岩陰で仮り寝した。
西になお二日進むと、真西の方角に沙漠から突き出たような高い山が見えてきた。思わず、駆け足を緩める。ションホルが、
「あの山はハミルの手前のカルリク・タグだ。吾れらが向かうのはあの山の北のバリク盆地。もう遠くはないぞ」
と、みなに伝えた。
その高い峰が落とす影に隠れるようにして、トゥルクレの市にぽつぽつと上がる白い煙が見えてきた。山に遮られて、日の入りは早い。
漢兵が多く駐屯する酒泉からここまでは匈奴の早馬を繋いで四日。右賢王が支配するとはいっても、周囲の小国のうちには、匈奴の威光はもはや過去のものとみなしているところが少なくない。どこに敵が潜んでいてもおかしくはなかった。
いま渡った川沿いに下れば、ハミルを北から護るトゥルクレの土城だ。モンゴルでは珍しく、低い土塀を巡らせて中に匈奴が他の部族とともに定住している。八つの隅においた矢倉と正面の高い門の上には衛兵が配してあった。
その土城には、西のかなた、カザフから連れてこられたイリ人の女が数多く捕らわれているという。伯父のメナヒムが西から東へと移ってきたとき以来ずっと付き従っている老兵が、ヤギの乳で作った古酒に酔った勢いでエレグゼンに漏らしたのだ。ションホルも聞いた。
この世で最も美しいと噂されるそのイリの女どもを一目見ようと、エレグゼンたち四人ははるばるここまでやってきたのだった。
第4節3話[107]へ
前の話[105]に戻る
