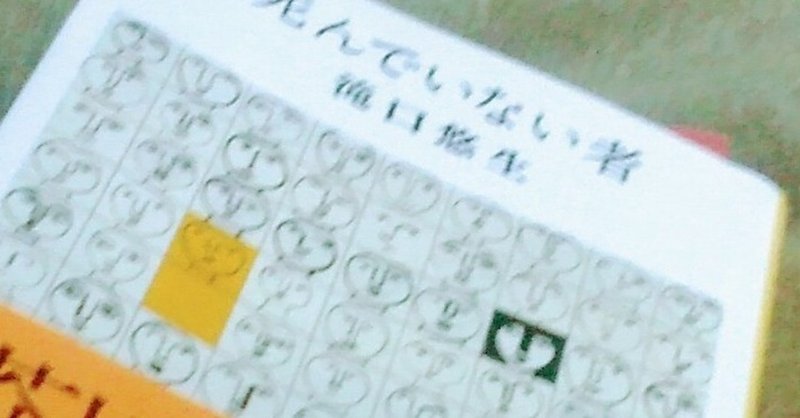
30の視点で語られる、あるお葬式の一夜
滝口悠生『死んでいない者』(文春文庫)を読んで
それ息で吹いたらだめなんだよ。
え。
線香の火、こうやって振って消さないと。
え、うそ。どうしょう。小説の中に出てくるシーンで、高校の制服姿の知花が、祖父に線香をあげようとしたとき、叔父の一日出(かずひで)にダメだといわれ、動揺する。どうしょうと聞き返され、口にした一日出も困ってしまう。こうした、だれもが一度は経験してきたような些細なことが、一夜を描いた物語のなかには詰まっている。過ぎれば忘れてしまいそうなことだ。いや、線香の話は思い出すか。ある「お通夜」の様子を綴った小説だ。
一夜の物語であって半分はそうで、半分はそうでもない。
たとえば、後半に語られる「故人」の初孫にあたる寛が、祖母のお葬式でべろんべろんに酔っぱらって父親から叩きだされたという、もう十何年も前の話がきのうのことにように明かされる。読んでいて、ああ、うちの家系にもこういうひとがいたなぁと顔がうかんだ。寛はアルコール依存症だったらしいが、よりによって、なんでこんな日にまでと思う。だが、こんな日だからこそ飲まずにはいられなかったのだろう。
だから切ない。本当にせつない。
それにしても、ビミョウなタイトルだ。
「死んでいない者」とは、死者から見たまだこの世に「生きている人たち」を指すのか、死んでしまってこの世から消えた人間(たとえば「故人」)を意味するのか。どらちらの「いない」なのか。読めば、おのずと答えはわかるものだと思いつつ読んでみるのだが。
変わっているという点では、特定の主人公の視点にそって描かれるわけではない。「通夜」に集まった親族や故人のおさななじみたちの目線で語られるものの、ふわふわ、ふらふらっと手持ちのカメラのように視点が移動する。時間も巻き戻される。小説の世界でしばしば「神の目線」といわれる描き方で、さらにこれは作者の癖なのだが、全員の台詞に「」が付けられていないので、なれていないと最初は読みづらかったりする。
加えて登場人物が多すぎる。
高齢で亡くなった「故人」(名前は出てこない)の息子や娘が五人、その子供たち(故人からすると孫)が十人とその連れ合い、さらにその子供(曾孫)たちが会し、つまりは甥とか姪とか伯父とか叔母たち、たがいに年に一度会うかどうかの人間たちが、賑やかに酒をくらったりワイワイ話していたりするものだから、一度読んだくらいでは誰がだれの子供で親なのか相互の関係がススッと覚えきれない。
まあ、わからずとも読めるし、わからないなりに支障はない。というか、そのほうがごちゃっとして面白くもある。
実際、わたしの子供の頃には何十人も知らないおっちゃんおばちゃんが盆や正月にやってきては、たがいに「バンガチャはああだこうだ」「トリシマがなぁ」と言い合うのを耳にし、いったいどこの国のひとたちかと思っていた。
とくにバンガチャヤと呼ばれるおじさんは顔が真っ黒。けっこう日本語のうまい人だくらいに思いこんでいた。ずっとあとになって、家のある村の番地で呼びあっていたのだとわかった。タナカさんだとかシオミさんだとかの姓で呼ばれている人たちは総じて、叔母や叔父の夫にあたる人たち。親しくしていても外様な「お客さん」だった。
まあ、そんなふうな親戚が大勢集まった日のことが思い出される話で、これといった大事件など起きたりはしないのだが、舞台劇のように線香の話のような細かなやりとりから相互のつながりがわかってゆくのが面白い。
結局、あまりにもごちゃごちゃしているので再読する際、家系図を書こうとした。しかし、落語の「代書屋」に匹敵するくらい途切れとぎれにそれぞれの関係が語られるものだから、ぐにゅぐにゅっと消したりして、きれいに書きなおそうかと思ったが、自分さえわかればいいと三度目でやめた。
もっとも気になる人物は、故人と暮らしていたという美之(よしゆき)で、冒頭にあげた知花の十歳ちがいの兄にあたる。
故人の次女・多恵の長男で、美之は故人の五番目の孫にあたる。中学のときから、これといった理由もなく学校に通わなくなり、なんとか高校を卒業はしたものの、自分から申し出て祖父の家に引っ越した。ひとと接するのが苦手らしく、通夜が行われている間、斎場には出向かず、祖父の家の敷地にあるプレハブの物置小屋(冷蔵庫やギターや電子ピアノなどを持ち込んで改造した部屋)にこもっている。
祖母が亡くなったあと、ひとりになった祖父とふたりで暮らしをしていた。にもかかわらず、どうして通夜に出ないのか。
困ったやつのようだ。たしかに大人たちの目に働きもせず、何しているのだろうということなのだが、妹の知花との会話を通して、美之は美之なりにけっこうちゃんと考えている。通夜に顔を出さないのは、ひとが大勢いる場所でどうしていたらいいかわからない。彼なりの「弔い」をしようとしていたのだと、斎場から家に引き上げてきた大人たちが「仏壇のお鈴」が消えていると騒ぎしている。犯人がじつは美之だったというあたりから、いわれるほど変わった人間ではないということが見えてくる。
どうやって社会とかかわればいいのか。美之なりに糸口を探している途中で、周囲もまた彼を無視するでもなく、また強く干渉するでもない。「故人」がそうしたように、微妙な距離感で彼を見守ろうとしている。
なかでも妹の知花とのやりとりから、兄妹恋愛を想像させたりもするのだが、そういうエロいことを思うのはゲスだというツッコミを天上目線でさせていたりもする。そうそう。そういうナレーター的な存在がいるのが、この小説のポイントだ。
そしてもって固定の主人公を据えてないため、読者によって、そのときの気持ちで大勢のうちの誰に親近感を抱くかも異なるだろう。
たとえば、米国人のダニエル。妻に付き添い、日本のお葬式や、なりゆきから健康ランドのお風呂に入り、彼は遠い異国で「家族」というものを考える。そういう外国人の視点に興味をもって読むのも面白いし、寛という行方不明で連絡がとれずにいる、喪主の長男(彼は祖母の葬儀のときに泥酔しての大失態をしたらしい。そのときのことが後半に詳しく語られるのだが)、その別れた妻・理恵子にも詳しくふれられていて、いまどこでどうしているのか、彼らの二人の子供は両親が育てていて、通夜にも来ている。預けたままの「不在者」が気にかかってならなくなる読者がいても不思議はない。
というか、できることなら作者には、美之もそうだが、寛と理恵子のその後をいつか書いてもらいたい。
子供を残して行方知れずとかいうとひどい親だと思いがちで、たしかに離婚にいたる寛の行状はちゃらんぽらんで問題はあるのだが、寛にもそれなりの事情があることがわかっていく(登場人物たちは断片的にか知らないでいる)、というふうに一人ひとりが誰一人、いわゆる「その他」的な扱いではキャスティングされていない。意味を持たされている。飛行機が飛ばず、未だ到着していない人物を含めて。
つまり、誰もが脇役であり主役でもある。そういう構造になっている。なかなか、このコンパクトな作品の長さでもって、そういうふうに物語を書くというのは難しいことなのに。
ところで一度、親本は読んでいるのだが(芥川賞受賞作でもある)、文庫本を買い直したのは「夜曲」という未収録短編が併録されているのと、津村記久子さんの解説がついていたからだ。「夜曲」は、「故人」やそのおさななじみのはっちゃんたちが通っていたらしい駅前のスナックが舞台になっていて、本作を読んだあとにつづけて読むとまた世界が深まるし、解説を読むと、ぼんやりとしていた感慨にきちんとした輪郭を与えてもらえた。

そういえばだが、うちの父が亡くなったときに実家で「家族葬」にしたのだけど、兄姉の子供たち(父からすると孫)が一人もあらわれなかった。近隣に居てるのにどうして? 兄が「(息子から)行こうかと聞かれたんで、行かなくていいと言うたんやけどな」説明を聞いて、え、なんで? 「いや、ミノルちゃんが家族だけでする言うたからな。来んほうがいいやろう思たんや」。……しばらくクラクラした。父と兄夫婦らとは長年犬猿の仲だった。そうした事情もあり喪主は末っ子のわたしがつとめた。兄たちが示しあわしたかのように気を回したことも時間とともに理解はできたが、「家族」のその線引きに、うろたえた。晩年いろいろあったにせよ、お葬式やんか。そうですか、と言うのが精一杯だった。七回忌もとうにすんだけど、曾孫まで集まる、かなしいが楽しげなお葬式の話、いいお葬式だなあと思うと、ふいにざわざしてしまった。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
