
ヒロさんが仕掛けたワナ

【10000字インタビュー】
ぼくが『テレビで会えない芸人』のプロデューサーを引き受けたわけ
語り手=阿武野勝彦さん(東海テレビ・プロデューサー)
聞き手🌙朝山実
カラー写真=©️2021 鹿児島テレビ放送
『テレビで会えない芸人』より
東海テレビの阿武野さんは、ときおり、ひねったもの言いをする。ご実家がお寺さんで、父親に連れられて檀家まわりなんかもしたというから幼少期に身についたものかもしれないが。一休さんみたいだ。
プロデューサーを引き受けた、2022年1月公開の『テレビで会えない芸人』のタイトルについて、阿武野さんは当初異をとなえたそうだ。これまで彼がプロデュースしてきた東海テレビドキュメンタリー劇場シリーズのタイトルはぜんぶ決めてきた、意見が通らなかった初めてのできごとだったらしい。そう話し、悔しがっているのかというと、そうでもない。案外そのことを面白がっているようだった。
阿武野勝彦(以下同)「ぼくは、四元(よつもと)、牧、両監督に『テレビで会えない芸人』というタイトルはやめたほうがいいと言ったんですよ。郷土の偉人シリーズ「芸人・松元ヒロの半生」でいいじゃないか。「テレビで会えない」というタイトルは、松元ヒロさんの罠なんだよと。
ヒロさんが舞台で「いま鹿児島のテレビ局がわたしを追いかけている」としゃべり、タイトルまで口にしちゃった。それがシーンに見事にはまっていて、外せなくなってしまったんだけど……。
もしも、この『テレビで会えない芸人』というタイトルじゃなかったら、この映画は芸人・松元ヒロというひとに出会うストレートなお話で終わったんです。『テレビで会えない芸人』というタイトルのおかげで、ぼくたちテレビマンはヒロさんから宿題を課されてしまったんだと思います。
81分間、松元ヒロというひとの人生を旅し終えたあとも、ぼくらはずっとこの問題を考えざるをえなくなった。なぜいま、テレビで松元ヒロに会えないのかと」

1月29日より東京はポレポレ東中野、大阪の第七藝術劇場、京都シネマ、神戸・元町映画館にて(鹿児島では14日から鹿児島ミッテ10、ガーデンズシネマにて)ロードショー公開となる『テレビに会えない芸人』は、鹿児島出身のひとりの芸人を追いかけたドキュメンタリーだ。
80年代末のお笑いブームの頃、政治風刺を盛り込んだコント集団「ザ・ニュースペーパー」を結成、一躍人気を得たものの98年に突然グループを脱退する(ヒロさん、46歳のときだった)。その後ひとりで舞台活動を続け、東京・新宿の紀伊國屋ホールでの恒例新作ライブは毎回満席の客で賑わっている。
なぜ、彼はテレビの世界から離れたのか。生まれ故郷、鹿児島テレビのテレビマンたちがコロナ禍の東京、岡山、鹿児島と、その活動に密着する。
番組は当初30分枠として放映されたのち、1時間に再編集したものが日本民間放送連盟賞最優秀賞などを受賞。さらに81分の映画作品にバージョンアップして、全国で劇場公開となる。
プロデューサーとして名を連ねているのは、『ヤクザと憲法』『人生フルーツ』など「東海テレビドキュメンタリー劇場」シリーズを手掛けてきた東海テレビの阿武野勝彦プロデューサーだ。同じ系列局とはいえ、なぜ他局の作品をプロデュースするに至ったか。
ほかの会社のものを担当するというのはかなりイレギュラーなことだ。不思議におもい、経緯を聞いてみることにした。取材場所は、配給・宣伝会社「東風」の都内の事務所だ。
🌙阿武野さんが今回プロデューサーを引き受けられたのは、松元ヒロさんのことをよく知っていたからですか?
「いえ。ザ・ニュースペーパーという名前は覚えているんですが、そのグループが何人いて、松元ヒロさんがメンバーのうちのどのひとなのかも分からなくらい。で、長い眉毛をつけたコントの場面を見て、ああ、あの村山元首相をやっていたひとだったんだとわかったんですね」
🌙え、そうなんですか。わたしは阿武野さんがプロデューサーだというので試写に出かけていったんですが。
松元ヒロさんは若いころテレビに出たいと思っていて、その夢がかないテレビに出続けるようになったはものの、なんか違うなあとグループを抜け、舞台活動をするようになる。その松元さんのいまを鹿児島ローカルのテレビ局が追いかけていく。阿武野さんは、そもそも松元ヒロさんのことをよく知らなかったとは。
「ああ、そうですね」
🌙そうそう。質問の前に映画の感想を言うと、この映画の面白さは、ファーストシーンに尽きると思うんです。渋谷のスクランブル交差点の前で、松元ヒロさんがインタビューに応えている。カメラに向かって話していた松元さんが突然、誰かに声をかける。
カメラが向きを変えると、白杖を手にした若い女性にヒロさんが近寄り「手助けが必要ですか」と話しかけている。
それから女性を先導し、歩道を渡り、動く歩道に乗る。女性が松元さんの肩に手をおき、そのふたりをカメラは映していく。
「じつは、ぼくは芸人でね、いまぼくをテレビが追いかけていているんですよ。だけど自分はテレビに出ない芸人だ」とニコニコ自己紹介をし、女性も、そうなんですかと笑顔で聞いている。
そして、山の手線の車内。ふたりは座席に座っている。いったいこのひとは、どこまでついて行くんだろう?
親切というか、変わったひとだなあというシーンから始まるんですね。
観終わったあとも、あの場合、自分だったらどうしたのだろうか。
せいぜい改札までじゃないか。
相手が若い男性だったら違っていたのか、態度は同じなのか。もう一瞬の映像からいろいろ考えたりした。
いや、そもそもインタビューなんか受けている最中に、白杖は目に入らなかったかもしれない。そういう冒頭の5分くらいがすごいインバクトがあって、面白いなあと。
「ああ、なるほど」

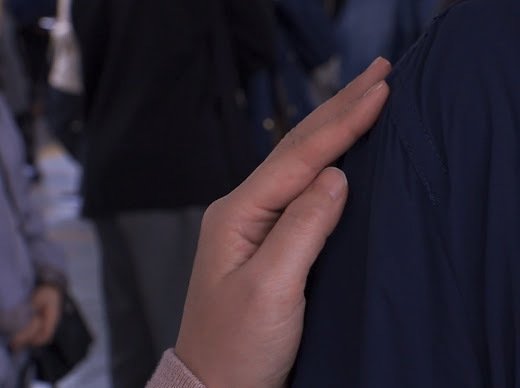



🌙以前、阿武野さんが出された『さよならテレビ』(平凡社新書)の本のインタビューを平凡社の一室でさせてもらったその日、東京に来られていたのは松元ヒロさんの舞台を観にいく用があったと。そううかがい、東海テレビで松元さんを取り上げるのだとばかり思っていたんです。だけど、そうではなかった。鹿児島テレビのこの映画のためだったんですね。
「じつは、鹿児島テレビの、今回監督をした四元(良隆)さんとのつきあいは長いんですね。ぼくが鹿児島に呼ばれていったり、彼が名古屋に来たりと。それでね、よく彼はぼくにSOSを入れてくるわけですよ。「どうも番組がうまくいかないんです……」って。
それで、これまでにもいくつかの番組に関わったりしてきたんですね。まあ、同じフジテレビの系列局でもあって、かれこれ十年ちょっとくらい行き来が続いているのかな。
もともと、どこで出会ったのか覚えていないんですけど。彼には、十歳くらい上のオジサンを上手に転がす才能があるんですね。会社の中で孤軍奮闘している様子を聞くと放っておけない気にさせる。
そう、まあ似ているというか、顧みるとぼくも、会社の中で孤立しながら突き進んできたので。そういう意味では、ぼくの十年前の姿かなあと思いながら。
それで『テレビで会えない芸人』も、最初はFNS九州ブロックの30分番組として制作中に、「阿武野さん、ちょっと空いてませんか」と電話がかかってきた。ぼくは、もうある程度出来上がっているものだと行ってみたら、二泊三日、鹿児島テレビの編集室に深夜まで缶詰にされて、昼間の桜島を眺めることもないまま帰ったという……」
🌙助っ人として呼ばれていった阿武野さんは、そういうときには具体的にどういうことされるんですか?
「それはまず、アサヤマさんがさっき言った冒頭の、目の見えない女性と出会う。そのあと山手線に乗り、さよなら、と電車に向かって手を振るまでのシーンについてアドバイスをすることですね。あのシーンを見たら、もう松元ヒロがどういう人なのか全部わかっちゃう力があるからと」
🌙あれは、たまたま撮れたシーンですよね。あの前にもいろいろ撮影していたと思うんですが、最初に編集されていた中にあったものなんですか?
「短く編集されていましたね。だから、これ全部見せてよ、全部使おうよと言ったの。それは、ヒロさんがもうあそこで「ぼく芸人なんです。テレビに出ていない」と自己紹介までしちゃっている。そこに醸し出る人間性ですよね。
そのあと自宅でお酒を飲みながらの場面で、ヒロさんが奥さんと山手線に乗っていたときのエピソードを彼が語るんですが、白杖の女性とのシーンが前にあると、話だけで生き生きと車内の様子を彷彿させる、と。このシーンは何気ないものだけど、このドキュメンタリーをすべて包み込んでくれる。神様がくれたシーンなんだからって」
🌙論理的に説得されたんですね。ひとつひとつがすごく計算された積み重ねなんだというのがわかりました。その後のリビングで妻と話しているシーン、たわいない夫婦の会話でいいんですよね。
「あれも、すこしつまんでありましたが、あのやりとりが家庭の中でのヒロさんなんですよね。奥さんに頭が上がらない、一見こわそうな奥様なんだけど、彼女がいないといまの彼はなかっただろう。つまり、権力者にははっきりモノ申すけど、家庭では……というバランスが面白いんですよね。
一緒に編集していると、監督の牧さんが映像の積み上げ方について、どんどん進化していくんですね。コツですね。ここはカット尻をもう少し伸ばそうとか。このカットはこういう二つの意味で使うんだな、とか。牧さんはシャープなんで、こっちも面白いんです」


🌙71年生まれの四元良隆さんと、83年生まれの牧祐樹さん。おふたりの監督作となっていますが。
「四元さんは、プロデューサーをしながら、取材にも行っていて。牧さんは編集もする。カメラは鈴木哉雄さんだけど、四元さんも牧さんもカメラを回す、ビデオジャーナリスト的な動きをされていますね。ふたりともカメラも上手だし、編集も手慣れたもの。だけど、プロの編集マンを見ていないから自己流なんですね。このへんで切っちゃおうかと我流のリズムが長年のうちに身についてしまっている。
ぼくの役割は、このシーンとこのシーンを入れ替えるとこう膨らむでしょうという、編集と構成を言語化して手渡す作業をしに行っていたということでしょうかね、最初のころは」
🌙編集教室の実践教室みたいなことですか?
「教室とちがうのは、放送日時が決まっていて、すごく時間に追われているということですかね。おおむね、牧さんとぼくが編集室にこもって、四元さんは制作部長でもあるから、他の番組も動いていて出たり入ったりする。ですから、外から見ると、あのオジサンは何者だという感じだったでしょうね。しかも、ぼくは最初、松元ヒロって誰やねん?という状態から入っていましたし、ぼくも、これは仕事なのか、何なのかという感じですよね」
🌙編集に携わりながら、主人公のことを知っていくというのがいいですね。
「そう。白い眉毛をつけた村山元首相のネタを見て、ああこのひとだったのかと。鹿児島県人にとってみると、郷土のスターとして記憶に残っているのかもしれませんが、伊豆半島出身で何のかかわりもない人生を送ってきたぼくにしてみたら、松元ヒロっていうひとについて、25分の尺に収めないといけないものが、倍の50分の状態であったわけです。でも、その50分がすでにとても魅力的で、とくにその中で、いちばん輝いていたのが山手線まで白杖の女性に連れ添う冒頭の場面だったんです」
🌙短くするだけではなくて、足しては削ったということですか?
「そうですね。短くしてあるシーンでも、何かありそうな予感ってあるんてすよ。そうやって、最後の着地をどうしたらいいのか。25分ですから。そこで、世界報道自由度ランキングを入れてみよう。いったい日本の言論状況はどうなっているのか、と。そこで終わりにする。荒業を使ってねじ伏せるという構築ですね。
もうひとつ。ナレーションが用意されていましたが、まったくナレーションは使わないでいこう、と。理由は、松元ヒロさんは話芸の人、もう全部自分で語っているんだから、補足は字幕だけで十分だと。
次に呼ばれたのは、1時間番組にするというとき。コロナもあり、ネットにアップロードしてもらい、こういうふうにしましたと送ってきたのを、こうしたほうがいいよと返す。何回も繰り返してやっていた。そうしてテレビバージョンが25分、60分と2本出来、ずいぶんたくさんの賞をとったんですよね。
ぼくとしては、松元ヒロというひとを、いまこの時代にたくさんの人に知ってもらうにはどうしたらいいのか。FNSドキュメンタリー大賞グランプリに選ばれたといっても、ヒロさんも言ってましたが、例えば東京では「朝の4時半からの放送で、やっばりテレビでは会えない芸人でした」とネタになったくらいで……。
そのあと、四元さんから、ある配給会社から映画化の問い合わせがあったと電話がありました。そのときぼくは「すでに映画化の計画がありますからと丁重にお断りして」と言ってしまったんですね。
つまり、ヒロさんを広く知ってもらうことが大事で、自分の局じゃないとか、鹿児島は遠いとか、ほかにも仕事があるとか言っている場合じゃない、自分がやればいいとぼくのエンジンが猛烈に稼働したんですね」
🌙映画化は、阿武野さんのほうから提案したわけではない?
「考えたこはありましたが、鹿児島テレビが何か言う前に、ぼくが映画化したいと言い出すのも(他社ということもあり)ヘンですし、遠慮というのか、二の足というか……」
🌙これまで映画制作の経験がなかった鹿児島テレビにとって、劇場公開にもっていくのに阿武野さんの存在は大きかったということでしょうか?
「まず、ぼくがやったのは、東海テレビのドキュメンタリーを配給している「東風」の力を借りて、配給面で大きな経費がかからない構造をつくる。というのも、たいがいこういう話は、お金のことで潰れてしまうんですよ。「赤字になったら誰が責任をとるんや」と後ろ向きな論議が出て、会社の中で揉んでいるうちに映画化がつぶれてしまう。だから「赤字は出ない、鹿児島テレビの名前が全国に出る」という話にもっていくという図式で話をする役をしました」
🌙なるほど。それは体験からくることだと思うんですが、阿武野さんご自身は、会社の枠にとらわれず、他社でも映画制作が広まるのが理想だと考えられているんですか?
「そうですね。2011年に映画化を始めた時、どんどん参入してほしいと思っていたし、この10年、実際にそうなりました。で、今回は他局のプロデュースまでしたわけですが、やってみて、局にとらわれず協力できるというのはとても面白い仕事でしたよね。局の壁とか、系列がどうのとか言っているのがバカバカしい。せっかくいいものが出来ているのだから、世の中に出せばいい、それだけですね。
組織とか系列とかは、かつてはいい意味で結束力がつよく、悪い意味ではシバリがきつかったんですが、テレビ局がメディアとしての力が弱まっていることもあり、個々人を拘束しなくともいいんじゃないかという方向になってきているように思います。ぼくの所属する東海テレビでは、かなり寛容でゆるやかになっていますね」
🌙それはいいことなんでしょうね。くわえて、阿武野さんの場合、一度定年退職されて会社に関わられているという事情もあると思うんですが。通常の社員だったときにも、これは出来たとお考えですか?
「出来なかったかなあ。いや、出来たかなあ……。どうだろう。
意外とコロナという契機が大きいのかもしれませんね。急に会社から「在宅」でいいからと、家でパソコンでやるようになった。そうなると、もう会社という場所に行かなくともいい。それだけで自由度は飛躍的に高まったように思います。だって出勤しなくてもいいんだから。
東海テレビは、10時になるとキンコンカンコンとチャイムが鳴るんです。夕方6時にまた鳴る。ニュースをやっている最中にもですよ。10時6時という勤務時間のシバリがあるものですから。しかも、報道の部員はニュース時間の関係で、1時間突き出た状態でいるにもかかわらず、チャイムは鳴る。その音とその場所、会社に居続けてきたことで、無意識のうちに縛られていたんですね。
ところが在宅になるとチャイムがない。ケータイ電話があればどこでも誰ともつながれる。「会社」に属するという意識から解放されてくるんですね。
おもしろいもので、ぼくは60を過ぎて、1年契約になって、何かあればいつでもやめますと言える状態になったというのは大きいですね。
会社ではいろいろ試みることも認められていて、書店に並ぶような書籍を単著で出したのは、ぼくが初めてになるのかもしれない。これまでの本は「東海テレビ取材班」編著になっていて、印税はすべて会社に入れていたんです。それも自分たちで分配しても会社は文句を言わなかったんじゃないかと思うんですが、そうしなかったのは考えもしなかったというか、会社人間だったというか、正しい組織人だったんでしょうね」
🌙では、コロナがあって、阿武野さんの中で考え方の変革があり、プロデューサーとして他局と仕事するのもしやすくなったと?
「95%はそうですね。残りの5%は、まだ何か組織的に嫌なことを言われるかもしれないというスッキリしない感じがありますね。
だから、嫌なことを回避しようと頭が回転する。たとえば(自社・東海テレビの)会長と酒を飲みに行ったときに「いま、鹿児島テレビの……」と耳に入れておくんです。それで、この件については、いちおう話しましたよと根回しをすませてしまう。
今回の『テレビで会えない芸人』の整音など音の作業は、名古屋でやることにしたんです。
東海サウンドという会社があって、優れた音響効果のスタッフなのでそこでやりましょうと。いつもぼくたちの仕事のパートナーでもある東海サウンドには、今後鹿児島テレビの仕事もできるようになるから、製作費を縮減してねと話をしておく。鹿児島テレビの社長が現場を見てみたいということだったので、ぜひおいでください。東海テレビの会長、社長ともお引き合わせするというセッティングもする……」
🌙なにやら外交官のようですね。
「まあ、そうですね」
🌙そういう根回しのようなことも、プロデューサーの仕事だということですか?
「うーん。人と人を結びつけるというのは、プロデューサーの大きな仕事ですが、一部は単なる保身ですね。ガチャガチャ言われるのを回避する方便が含まれていますから。
ただ、こういうことをしておくことで、仕事はスムーズに進むし、気分も楽になりますから」
🌙なるほど。今回のことが実績となり、今後たとえば系列局以外でも、劇場公開に関しての協力関係は可能だと?
「映画は可能だと思いますね。テレビ番組に関しては、ライバル関係にあるものですから。じつはこの作品もライバルだったんですね。
ちょうどコンクールの地区予選を東海も通っていたんです。日本民間放送連盟賞のエンターテインメント部門の九州ブロックでは「テレビで会えない芸人」。東海北陸では、私も企画に関わった東海テレビの作品が予選を通過して、中央審査で鹿児島が最優秀となりました。だから、ちょっと気持ちは微妙ですよね。
ただ、地方で頑張っているところがあって、お手伝いをするのは何も問題ないと思っています。そうそう。ずっと賞をとってなかったんですが、今年、東海テレビがグランプリをとったんですよ。「チョコレートな人々」が民間放送連盟賞グランプリをとったんです。
ドラマもドキュメンタリーもバラエティもぜんぶ含めた賞で、1月末に放送するんですが。ええ。よかったなあと。これで3年はうるさいことを言われずにすむかなあ」
🌙3年ですか。
「そう。それで、『テレビで会えない芸人』の話にもどすと、最後に松元ヒロさんが、憲法前文を読み上げる場面があるんですが、あれを聞いたときに震えたんですよね。胸があつくなった。魂をこめて読むと、こんなにひとに感動を与える文章なのかと。
これまで憲法をああいうふうに読むのは、どこかでタブーなのではないかと思っていた。しかし、これは少なくとも論議喧しい9条ではなく、前文だから。これに文句をつける人はいないだろう。
だから一緒にモニターしていた鹿児島テレビの社長に言ったの。これから憲法前文を毎日、放送のオープニングにやる局になってくださいよと。
しかも松元ヒロさんだけでなく、オープニングで読んでみたいという人を集めて、憲法前文を次々いろんな人が諳んじる。ときには自分なりの演出を加えたりしながら、一生懸命に「ここに宣言する!」とやる。そうしたら、「憲法の鹿児島テレビ」として全国に知れますよと」
🌙毎朝、目覚めにやるんですか?
「そうそう。夜は興奮して寝つけなくなるかもしれないからねえ。ハハハハ。計ってみたら、あれ1分半だったかなあ。そう。意外と長くないんですよね。君が代、日の丸でクロージングするNHKよりも意味がある」
🌙偏向しているとかいう人が出てくると、それはそれで面白いなあ。あのシーンは、テレビバージョンにあったんですか?
「これは最初入ってなかったんですね。映画版をやりはじめたときに、第3稿ぐらいかな、出てきたんです。おいおい、こんなのもあるのかと。しかも、これがあることで、前にある、君が代をアメリカ国歌の曲調で歌ってみせたりするネタがきれいに収容できる。
ヒロさんが「いまの日本はアメリカの属国ですよ」という。あれは右翼への批判として言っているわけではない。何に対して怒っているのか。そういうことがはっきりわかる。
そういう秘蔵ものが、あとからそっと出てくるんですよ。このスタッフは、どれだけ取材しているんだとびっくりしましたね」
🌙ところで以前、紀伊國屋ホールでのライブを見にいくと阿武野さんが話されていたときは、何か目的があったんですか?
「あのときはねえ、最新の舞台を映画に入れ込もうとカメラを入れたんですね。それの立ち合いと、ヒロさんからご招待されたので、席で観ていたんです。ただ、それまでに撮れたいたもののほうに勢いがあって、最終的にそちらを使ったんですが。あれは今年(インタビュー時点、2021年)の6月くらいでしたかね」
🌙映画の中で、新作の稽古場面が出てきます。立ち稽古で、自宅の書斎でワープロ打ちをし、赤字の入ったものを手に読み上げていく。これが、読んでいるという感じで、なかなか自分の言葉になっていなくて、床にうずくまるところがありますよね。いったい本番はどうなるのかなぁという。
「そうそう。稽古を重ね、だんだん形になっていくところを見せてくれるというのも、すごいなあと思いました。本当に悩んでいるんですね。ううっと頭を抱えてしゃがみこんでしまう。それも、意外とあっさり最初は切ってあったんです。ピッ、と。だから、生みの苦しみを長々と編集でつないでもらいましたね」
🌙そうだったんですか。
「ここは彼が本当に悩んでいるんだから長めに出そうよと、切らずにつなげたんですね。
ピッと切ってしまうのはテレビマンの生理なんでしょうね。もうわかりましたよね、と切ってしまう。だけど、ヒロさんは、うずくまったあとも、スローをかけたように動かなくなる。一生懸命芸に向き合っている、あそこは芸の真骨頂、生みの苦しみそのものなんだから切ってしまったらいけない、と」
🌙今回、映画を観た印象として、ライブのネタが過激だとは思えなかったんですね。テレビの枠に収まらないからテレビに映らないというのは、本当にそうなんだろうか? たしか冒頭でテレビ局側のひとのコメントとして、視聴者が求めなくなっているからのではという話があって。残念だけど、一面それはあるかなぁと思ったんですね。
「ぼくは、ブームとかムーブメントをつくるというのは、最初は誰も望まないだろうというところから発想したほうがいいだろうと思うんです。
みんなが望んでいるものを、いわゆるマーケティングのようなことを考えてやってきた果てがいまのテレビだという気がしていて。むしろ、いま望まれてはいない。けれども、これはもしかしたら大きな化学反応が起きるかもしれない。そう思って、人や番組を送りだしていくほうが何倍も面白いと思うんです」
🌙流行っているからやろう、じゃないという。
「そう。ドキュメンタリーをつくるときによく言うんですけど、「当てに行くようなバッティングはしない。三振でもいいから、振り切れ!」って。そうじゃないと、みんな同じようなものになっていく。結果的に、見る側は、どこも同じようなものしかないから見なくなる。新しさがないから。
それよりは、へえー、こういう世界もあるんだ。まず自分がものすごいものを見てしまった。だから、みんなに見せたい。これが、テレビマンの根っこの生理だと思うんですね」
🌙わたしは、転職してライターになったのが遅くて、ずっとバントをやってきたなぁというのがあるんですよね。手堅いバントを誇るというのをずっとしてきたなぁという。フルスイングしてきたかなあと。
「ハハハハ。ぼくもバントから入ったかもしれないなあ。
行政の広報番組、愛知・三重・岐阜の東海三県と名古屋市の15分から30分の番組があって、それを上手に作るということをしていましたから。
でも、それもやりようで面白いんですよね。与えられた取材現場で何を見つけるか。プッシュバントにするのか、転がらないバントにするのか。
同じバントでも、やり方ですよね。必ず面白くできる。ときにはトリッキーなことも取り入れていく。そういう工夫をしていると、「アブちゃんが来ると面白くなるよね」と喜んでいただけるようになっていく。
そうすると、もうゼヒモノ(スポンサーから是非取材してと要望された)のニュースでも、取り組み方で面白いものになるんですよね。ここはバントだけど、バントを愉しくやれる人かどうかはとても大事だと思います。そうでないと、思い切りスイングできる人になれないんじゃないでしょうか」
🌙ナイスフォローですね。いまのそれ、noteに使っていいですか。
「もちろん。1分のニュースを一生懸命やれないひとは、ドキュメンタリーはできないよと、よく言っていますから。毎年やるニュースだからと、去年の原稿を引っ張りだしてコピーする。そういうやつは絶対ダメだと」
🌙そろそろ時間なので、最後にひとつだけ。あれはヒロさんの書斎なのかなあ、壁に写真が飾ってありましたよね。チャップリン、オードリー・ヘップハーン、それにゲバラという組み合わせが面白いなあと。
「ゲバラ、ありましたか? へぇー。(東風のスタッフから、場面のカットを見せられる)ああ、ありますね。そうかあ。ぼくは、なんのこだわりもなく見ていましたね。ここはチャップリンに行くためのものというのが、僕の頭の中にはあったんですね。ゲバラとオードリー・ヘップバーンにはまったく目はいってなかった。
ぼくにとっての松元ヒロさんは、あの電車が出ても、ずっと手を振っているひとなんですよね。それも一生懸命に。
松元ヒロさんの本当の政治性は何かということには興味はあるんですけどね。事によると、ものすごいアナーキストじゃないかとか。だけど、そういうところに踏み込まない。彼は常に対権力ということは考えていて、だから権力をもった人たちは、どんな政党でも同じようにきちんと批判するんだろうなぁと。
今度、インタビューされるなら、そこはヒロさんにぜひ聞いてみてください」
🌙ええ。今度「週刊朝日」の取材で松元さんをインタビューするときに聞いてみます。ゲバラ好きなんですか?って。

注記🍚インタビュー中、阿武野さんのしゃべりの中では、四元さん、牧さんに対する呼称に「さん」はありませんでした。実際はいわゆる呼び捨てです。その分、会社の枠をこえた後輩に対する親愛の情を感じましたが、文字化にあたっては敬称を付け加えています。音源を聴きかえすと敬称なしのトーンから間違いなく、その気持ちは伝わるのですが、如何せん文字言語では、上から目線の人と誤解されるおそれがなくもなく。もし一人でもいらっしゃたら本意ではないので、ごく一般的な慣習に合わせることにしました。
『テレビで会えない芸人』(出演:松元ヒロ×監督:四元良隆、牧祐樹(鹿児島テレビ)×プロデューサー:阿武野勝彦(東海テレビ))
2022年1月公開
http://tv-aenai-geinin.jp/
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
