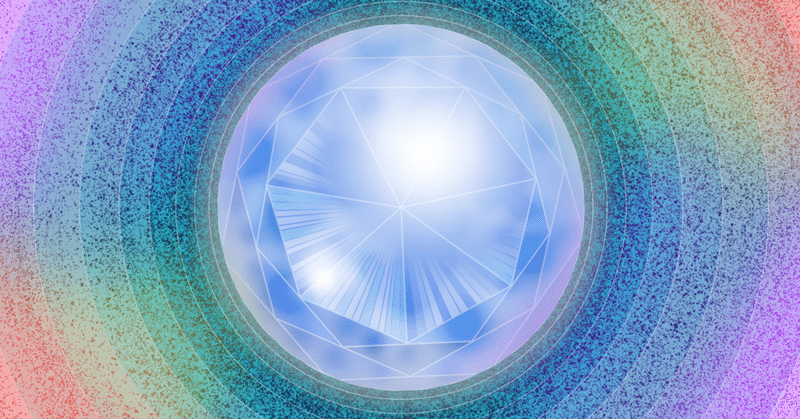
蒼月書店の奇々怪々Ⅲ ~たまゆらの宝玉~
時間がない。ないのだけど、気になって店に近付いた。
カフェ巡りが好きな俺は目の前の建物を古民家のカフェかと思ったが、本屋だった。『蒼月書店』と看板がある。
しかし、本屋の前の立て看板によると、ここは二階に飲食スペースがあるらしい。今度、利用してみようか。
気になったのは、店だけではなかった。入り口のそばに自動販売機が置かれているのだが、それは飲み物ではなく、本を売っていた。売られているのは九冊で、小説がミステリー、ファンタジー、青春、ホラー、SFの六種類。それからエッセイと自己啓発本だ。
自動販売機に張られている説明書きには、詳しい本の内容が書かれていない。
「新たな本との出会いをお楽しみ下さい」
何が出るかは、運しだいということか。
俺はカフェでよく本を読む。それ用に一冊買ってみてもいいかもしれない。
珍しさと面白さもあって、俺はファンタジー小説を一冊購入した。紙コップで売られている飲料自販機のように、自販機の小さな扉が開いた。中には四六判サイズの本が入っている。俺がその本を手に取ると、扉は自動で閉まった。
『アダマス』
それが本のタイトルだったが、この本にはカバーがなかった。
表紙をめくろうとして、視界の隅で何かが動いたのに気付いた。視線を動かすと、本屋の入り口の前にグレーの猫がいた。じっとこっちを見ている。
野良猫かなと思ったのも束の間、今はそれどころではないことを思い出した。
「あっ、やべ」
俺は腕時計で時間を確認した。中学時代の友人の俊と会う予定だが、約束の時間に遅れてしまう。
俺は買った本をリュックにしまい、駅へ急いだ。
俊と遊んだ夜、俺は帰宅するとリュックを下ろしてベッドに腰掛けた。
明日は大学の講義があるし、その後はバイトだ。酒を飲める年齢になって、たまに調子に乗って飲み過ぎてしまうことがあるが、今日も少し酒が多かったかもしれない。
風呂に入ろうとベッドから立ち上がって、そういえば、と思い出した。俺はリュックから購入した本を取り出す。パラパラとめくったが、何も書いていなかった。
小説なのに、何もないってどういうことだ?
俺はもう一度、初めのページを確認した。目次も何もない。
「なんだ、これ。小説どころか、読み物ですらないの・・・・・・か」
独り言の途中で、本の中表紙に文字が浮かび上がってきた。タイトルの『アダマス』の文字だ。
俺は驚きのあまり、それを凝視した。それから、その文字に触ってみた。特に何があるわけでもなかった。
「えっ? どういうこと?」
酔っ払っておかしく見えているんだろうか。
俺は次のページをめくってみた。何も書かれていなかったが、再び文字が現れた。
この世界には一つの伝説がある。
父なる空の神と母なる大地の女神から生まれたとされる巫女。かつて、悪さをしていた天狗を封印し、その巫女はミネアタルに結晶化して山の頂上に眠る。
その眠れる巫女が生み出した光の宝玉を龍が守護しているといわれる。それは「アダマス」と呼ばれており、この宝玉が巫女のもとへ導き、彼女を目覚めさせるという――
現れた文字はそこまでだった。
俺はどういう仕組みでこの文字が出てきてるのか不思議でならなかったが、本を調べても明確な答えは導き出せなかった。
結局、俺は諦めて栞を挟み、本を机の上に置いた。
アラームの音で目を覚ますと、俺はベッドから起き上がった。ひとまず、二日酔いは大丈夫そうだ。
机の上の本に目がいった。俺は興味をそそられて本を手にした。
「ん?」
何故か栞がなくなっていた。本をめくると、栞ではなく、一枚の写真が挟まっていた。
「こんなの、なかったよな?」
写真には龍が写っていた。龍の絵かと思ったが、それにしては顔や鱗が生々しいような・・・・・・。
裏を見ると、ここにも文字が書かれていた。
興味ある? 返事を下さい。
「はっ?」
思わず声が出ていた。
どうなってるんだ、これ。
気味悪く感じる一方で、好奇心も沸いていた。試しに、俺は写真の裏の文字の下に返事を書き込んでみた。
「この龍は本物?」
書き終わると、写真を本に挟んで閉じた。
朝の支度を終えてから、もう一度本を開いた。龍の写真はちゃんと挟まっていた。裏を確認すると、俺の文字の下にさっきはなかった文字があった。
その通り。
俺は息を呑んだ。
すると、さらに文字が現れた。
興味あるようね。あなたもこっちへ来る?
「えっ?」
突如、視界がぼやけ始め、何も見えなくなった。
声が聞こえて、俺は目を覚ました。近くで女の声がする。
俺は身体を起こすと、自分が外で倒れていたことに気付いた。周囲を見渡すと、一人の音が少し離れた場所でうずくまっている。
「さぁ、早くそれをよこすんだ!」
一人の男が女に向かっていく。俺はとっさに身体が動いた。何故か、女を助けなきゃいけないと感じた。
俺は男に体当たりした。男が倒れると、俺は女に声をかけた。
「大丈夫か!」
女はぜんそくなのか、咳き込んでいて答えられないようだった。
このままでは、まずい。
「クソッ」
男が恨めしそうに言いながら、立ち上がった。俺は女に覆い被さるようにしてかばった。
「それは、ぼくの・・・・・・」
男の言葉が途切れた。何もしてこない。
恐る恐る振り返ると、男は微動だにせず、その場で固まっていた。男の足元が円を描くようにして翠色の光を放っている。
「これは・・・・・・」
理解が追いつかないでいると、猫の鳴き声がした。
「ねぇ、あの子達・・・・・・」
いつの間にか女は咳が治まったようで、少し苦しそうに前方を指差していた。視線を向けると、こちらを見つめる二匹の猫がいた。見覚えのあるグレーの猫と、白猫だ。
「あの子達、助けてくれたのかも」
「猫が?」
「とにかく、ここを離れよう」
「あ、ああ。立てるか?」
「平気。もう大丈夫」
俺達は広い公園のようなところにいたらしい。芝生の上を歩いてそこを出た。二匹の猫がこちらを伺いながら、先行してくれている。
「とりあえず、あの猫に従ってみよう」
それにしても、ここはどこなんだ? 俺は自分の部屋にいたはずなのに。
俺は並んで歩く隣の女をチラッと見た。この女とは初めて会うはずなのに、俺は知っている。サユリ。俺の友人の妹で、ぜんそく持ちの虚弱体質だ。
ていうか、さっきの男も何なんだ? 襲っていた理由もわからないし、まるで時間が止まったかのように動かなくなったし、目の前を歩く猫も普通の猫じゃないみたいだし!
頭の中でいろんな疑問が飛び交う中、しばらく道なりに沿って歩くと、一軒の平屋が建つ敷地に二匹の猫は入っていった。俺達もそれに続く。
「あっ、よかった。二人とも無事だったんだ」
童顔の男が駆け寄ってきた。
「えっ、シュン?」
紛れもなく、俺の友人のシュンだ。昨日、一緒に遊んだ、中肉中背でスイーツが好きな乙女系男子だ。
「何で、ここに?」
「心配だから、来たんだよ。妹が従兄弟に襲われたんじゃないかって。サユリ、大丈夫?」
サユリは頷いた。
「従兄弟って・・・・・・あの男がそうだったのか」
「ジッツに会ったんだね?」
ジッツ・・・・・・あの従兄弟の名前か。
「あの猫達が助けてくれたの」
二匹の猫は玄関の扉のそばでおとなしく座っている。
「ジッツの足元に魔法陣が現れて、彼が一時的に動けなくなったみたい」
「魔法が使える猫か。すごいな」
「えっ、魔法?」
「うん。使える動物がいるっていうのは聞いたことあったけど、実際に見るのは初めてだ」
なに言ってるんだ、こいつ。魔法なんて、漫画とか、ゲームとか、小説くらいでしか聞かな・・・・・・。
俺はハッとした。本屋で買ったあのファンタジー小説。あれを開いて、写真を見つけて返事を書いたら・・・・・・。
あなたもこっちへ来る?
俺は頭を抱えた。
まさか、そんな。でも、あの本は普通の本とは違っていたし・・・・・・。
「どうしたの?」
気付けば、サユリが俺を覗き込んでいた。
「いや、何でもない」
サユリから視線を外した先で、白猫と目が合った。綺麗な翠色の瞳の猫は、コクリと頷いた。
何だ、今の反応。まるで、俺の考えを肯定しているかのような・・・・・・。
「ルチルさんや、ミラも気にしてたんだよ」
その名前を聞いて、俺は二人の女の顔が浮かんだ。これもまた知らないはずなのに、俺は何故か知っている。
バタン! と大きい音がした。玄関の扉が勢いよく開いた音だった。
「キョウヤ! サユリちゃん!」
出てきたのは姉のルチルと妹のミラだった。俺に姉妹はいないはずなんだけど。
「やっぱり! 声が聞こえたから、もしかしてって思ったの」
見た目クールビューティーだけど熱血系の姉だ。頭脳派で要領が良く、サポートが得意で家事が苦手。
「サユリさんは身体、問題ない?」
「少しぜんそくが出たけど、今は平気」
ポジティブ思考の元気娘で家事得意な妹。・・・・・・よく知ってるな、俺。
「良かった。私、サユリさんが何で危険な目に遭うのか、まだよくわかってないんだけど」
それは、俺もわからない。
「まずは、中に入って」
俺達は家の中に入った。リビングのソファに座ると、サユリが話し出した。
「この前、怪我をして困ってた男の人がいて、その人を助けたの。裏山の麓まで案内して欲しいって言われて。そのときはぜんそくも落ち着いていたし、言われた通りにしたら、これをあなたにって」
サユリはポケットから玉を取り出した。それは、透明な玉の中に黄色い光が宿っていた。
「これは何かと尋ねたら、光の宝玉だって。この山の頂に眠る巫女が生みだしたもの。それが、あなたを巫女の元へ連れていってくれるでしょう、と」
「それって、この辺りに伝わる伝説の宝玉じゃない?」
「たぶん、そう。私がこの宝玉に気をとられていたら、男の人はいつの間にかいなくなってた。強い風が吹いたから、もしかすると」
「龍になって頂上に戻ったってわけね」
ルチルの言葉に、サユリは頷いた。
伝説っていうのは、俺が買った小説に載っていたあれのことか。
「アダマス・・・・・・」
「あっ、そうそう! 宝玉の名前がアダマスっていうんだよね」
「その話を僕とキョウヤが昨日聞いたんだ。その後、ジッツが僕に会いに来た」
俺、聞いていたのか。
「サユリが持っているアダマスをわたしてくれって。どうして知っているのか教えてくれなかったけど、どうしても必要なんだって話してた」
「それでどうしたの?」
「本物かどうかわからないけど、伝説でいわれているすごいものだし、サユリがもらったものだからって断ったんだ。そうしたら、様子が変わって、サユリが持っていても意味はないって怒鳴った。それで、帰っていったんだけど」
「キョウヤは心配になって、サユリちゃんのところへ行ったのね」
なるほど。そういう流れか。
「ジッツは、私が朝早くにあの公園で散歩することを知っていたから。そのタイミングを狙ってきたのかも」
「気になるね、ジッツのこと。どうして宝玉を欲しがるのか」
俺は引っかかったことを口にした。
「龍がサユリに宝玉をわたしたってことは、巫女の元へ来て欲しいってことか?」
そう呟きながら窓を見ると、窓の向こうから白猫がこっちを見ていた。気のせいか、またコクリと頷いて口元が少し笑った気がした。驚いて隣のグレーの猫を見ると、瑠璃色の瞳を細めてツンとした表情でそっぽを向いた。
こっちは愛想がないな。
「私を? 何のために?」
サユリの問いに、俺は首を傾げた。
「天狗のことと何か関係があるのかもしれないわね」
腕を組んで考えていたルチルが言った。
「伝説では、巫女が結晶化したのは天狗との戦いの後。宝玉も眠る前に生みだしたといわれているから」
「私、行ってみる。頂上に」
宝玉を見つめながら、サユリはそう決めていた。
「待って、サユリ。ぜんそくが悪化したらどうするんだ」
シュンが不安を口にした。
「薬もあるし、大丈夫よ。それに、本当に私が来て欲しいと思っているのなら、行かなきゃ。ジッツだって諦めてないかもしれないし」
「サユリが受け取ったものだけど、無理していくこともないだろう。僕が代わりに行くよ」
「でも、サユリさんにわたしたことに何か意味があるのかもしれないよ?」
迷っているシュンの肩に、俺は手を置いた。
「俺がサユリについて行くよ。一人じゃ心配だし」
そう言うと、ルチルが手を叩き、ミラがソファから身を乗り出した。
「おっ! さすが我が弟!」
「よく言った、お兄ちゃん! ちゃんとサユリさんを守ってよ!」
特に何が出来るってわけでもないんだが。
「・・・・・・わかった。僕も行くよ。僕とキョウヤがいれば、少しは安心だろう?」
「ありがとう。兄さん、キョウヤ」
「じゃあ、私達も麓まで行くわ。この中じゃ、魔法を使えるのは私だけだからね。裏山にかかっている魔法の痕跡を調べるわね」
「私達って、ミラも行くのか?」
「もっちろん!」
「ダメって言っても、この子は聞かないからね」
裏山の麓までやってくると、さっそくルチルが山を観察し始めた。後ろを振り返ってみると、俺達の後に、二匹の猫がついてきていた。
この猫、本当に何なんだ? 助けてくれたし、悪い奴じゃないのはわかるけど。
「頂上付近とこの入り口に痕跡があるわね。簡単には入れないようにしているのよ。
まずはこれを解かなきゃ」
すると、サユリのポケットが光り出した。そこから、サユリは宝玉を取り出す。
宝玉の中の光がさらに強く光り、入り口の方へまっすぐ光の筋が伸びる。
「痕跡が消えたわ!」
ルチルが驚いた様子で声を上げた。
「それじゃあ、先に進めるのか?」
「えぇ。頂上付近の痕跡は巫女を守るためのものでしょうけど、その宝玉があれば、大丈夫じゃないかしら」
「巫女の元へ連れていってくれるっていうのは、本当なんだね」
「よし、行こうか」
歩き出そうとしたが、ルチルに呼び止められた。
「私達はここに残るわ。ジッツが来たときのために、幻術をかけておいてあげる」
「わかった」
「三人とも、気をつけてね」
ルチルとミラを残して、俺達三人と猫二匹は山の中へ足を踏み入れた。
頂上が見えてくると、サユリの持つ宝玉の光がより強くなった。サユリが宝玉を掲げると、光は頂上へ向かって伸びていく。
「これで、頂上の魔法の痕跡も消えたかもしれない」
「そうだな。サユリ、もう少しだ。行けるか?」
「大丈夫」
俺は気になっていたことをサユリに訊いた。
「龍は人間の男になっていたんだよな。どんな感じだったんだ?」
「そうね・・・・・・。穏やかで上品、柔らかい物腰の老紳士って感じ」
「意外だな。龍って荒々しいイメージだったんだけど」
「巫女の宝玉を守護していた龍だから、そのイメージとは違うのかも」
俺は、ついてくる猫を一瞥した。
今度は人じゃなくて、猫になってるか?
白猫は俺の視線に気付いて、小さく鳴いてかぶりを振った。
まただ。俺の思っていることに対して、答えているような・・・・・・。
一方、グレーの猫は視線が合ってもそっけない。どちらにしろ、謎の多い猫達だ。
歩みを進めて頂上へ近付いていくと、声が聞こえてきた。
「誰かいるのか?」
聞こえてくるのは、二人だ。
「そんな、もしかして・・・・・・!」
「おい! サユリ!」
サユリが走り出した。俺とシュンも彼女を追いかける。
頂上に着くと、巫女が眠る祠の前に二人の男がいた。
「ジッツ! どうして?」
「やっと来たね。ここに来ると思ってたんだ。待ちくたびれたよ。サユリ、その手にある宝玉、ぼくにわたして」
「いけません。他の誰にもわたしてはならない」
ジッツの近くにいた男が言った。穏やかだけどきっぱりとした口調、白いローブを着た品の良い雰囲気は、サユリが言っていた老紳士に違いなかった。
「どうしてここにいるんだ? ルチルさんが幻術をかけていたはずなのに」
「あぁ、あれか。あんなの、ぼくには通じないよ。ぼくの霊力が強いこと、シュンもサユリも知ってるでしょ」
「でも、ルチルさんの幻術だって、強力で・・・・・・!」
「ぼくには天狗のサポートもあるからね。どうってことない」
俺は耳を疑った。
「やはり、そうでしたか」
老紳士が落ち着いた声で呟いた。
「天狗にかけた封印が弱まってきていることは察知していたのですが、まだあれが自ら動くことは出来ない。誰かを差し向けて宝玉を狙ってくるのではと考えていたのですが、ずいぶん強い霊力の人間を見つけたものだ」
「天狗だなんて・・・・・・。ジッツ、宝玉を狙うのは天狗に言われたからなのか?」
「そうさ。天狗が必要としているんだよ。封印を完全に解くために」
「何でジッツがそんなことを手伝っているんだ」
「封印を解いた見返りに、ぼくの願いを叶えてくれるんだ」
「そんなこと、本気で信じているのか?」
「彼は誰も聞いてくれなかったぼくの話を聞いてくれた。霊力を持つぼくを認めてくれたんだ。そんな彼が困ってるんだよ」
そう言うと、ジッツは何かブツブツと唱えた。彼の右手に赤い光が宿り、それをサユリに向けて放った。
「サユリ!」
シュンがサユリを突き飛ばしてかばうと、赤い光を浴びて彼の身体が石化していった。
「嘘だろ?」
「兄さん!」
サユリが倒れた拍子に落ちて転がった宝玉を、ジッツは拾った。
「これがあれば!」
俺は取り返すべく、ジッツに突進していったが、かわされた。
「返して!」
サユリがジッツの右手を掴んだが、なぎ払われる。その彼女を老紳士は受け止めた。
「それはあなたが扱っていいものではない」
老紳士の瞳が青く光った。彼は白い煙に包まれ、そこから白い龍が出現した。
あれは、写真で見た龍と同じ?
「それなら・・・・・・天狗よ! 復活のときだ!」
ジッツが宝玉を掲げると、宝玉の光が増し、少し離れた場所からオレンジ色の光の柱が上空へ上がったのが見えた。
「あれは・・・・・・」
すると、こっちへ素早く向かってくる何かを視界で捉えた。それは、龍とぶつかり、どちらも空へ高く上がる。
「やった! これでぼくの願いも・・・・・・」
俺は天狗に気をとられているジッツの手から宝玉を取り返した。サユリの元へ走る。
「キョウヤ!」
サユリは俺の背後を見て叫んだのがわかった。俺が振り返ると、怒りを宿したジッツの目と合った。あいつの握り拳の赤い光が大きくなる。
やばい、石になる!
そう思ったとき、ジッツの足元が紫色に光る。ジッツはそれに気付いてすぐに避けた。
ジッツの後ろには、あの猫達がいた。
「また、お前らか!」
ジッツは猫らに向けて赤い光を放ったが、翠色のシールドのようなもので阻まれた。
「ぼくの力が・・・・・・」
グレーの猫が唸り声を上げると、猫らを守るシールドから青い光が放たれ、ジッツを包む。俺は目が眩んだ。
「これ、は・・・・・・」
光が消えると、全身凍ったジッツの姿があった。
そして、白猫の翠色の瞳がこっちを見つめていた。
行け!
脳内で誰かの声が叫んでいた。俺は一瞬、混乱した。
「キョウヤ!」
呆然としていたが、サユリの声で気がついた。俺はサユリに宝玉を届けると、彼女はそれを手にして巫女の眠る祠へ向かう。
「巫女様、どうか、お目覚め下さい」
両手で握っていた宝玉を巫女へ差し出した。宝玉は浮かんで巫女の元へ静かに移動すると、輝きだした。その光は巫女の足元から徐々に頭まで包んでいき、結晶化を解いていった。
光が消えると、宝玉は砕け散った。
巫女はゆっくりと目を開く。
「私の元まで宝玉を運んでくれて、ありがとう。お礼は後でするわ」
巫女は祠から出ると、氷付けのジッツに触れた。そこから赤い光を抽出すると、空へ浮かんでいった。
空では、白い光とオレンジの光がぶつかっている。
「目覚めたか、巫女よ」
聞いたことのない声が聞こえた。恐らく、天狗だ。
赤い面の天狗は矢の形をした無数の光を巫女へ飛ばした。龍が風を起こし、いくつかの矢が巫女から逸れる。
巫女は紫に光る結界を張った。それにより、巫女へ向かった矢は天狗へと跳ね返った。
「あなたがあの少年に与えた力を返しましょう」
天狗が戻ってきた矢を払うと、紫の光が蔦のように天狗に絡まった。
「何だと!」
巫女は天狗に向けて赤い光を放出した。光が消えると、石化した天狗の姿が見え、それは落下して粉々になった。
その途端、石化していたシュンが元通りになった。
「兄さん!」
俺とサユリがシュンへ駆け寄る。
「僕、動ける・・・・・・」
「あぁ、よかった。戻ったんだな」
「石化の呪いは解けたわ。もう大丈夫よ」
声に振り向くと、巫女と龍は地上へ戻ってきていた。
「終わったのか」
巫女は頷いた。
「麓の方でも石化の呪いを感知していたけれど、そちらも解けているはずよ」
ルチルとミラのことだとわかった。解けたなら、もう平気だな。
「私は巫女のミネア。この守護龍はオニキスよ。改めて、お礼を言うわ」
巫女はサユリへ向き直った。
「オニキスを助け、私の元までアダマスを運んでくれたお礼、させてちょうだい。あなたの望みを叶えてあげるわ。私に出来ることなら、だけど」
「望みなんて、そんな」
「それなら、体質を改善してもらうのは?」
俺が思いついたことを話すと、シュンが頷きながら言った。
「そうだよ。サユリがずっと望んでいたのはそれじゃないか」
「でも、そんなこと叶うんでしょうか?」
サユリが問うと、巫女は微笑んだ。
「これでも私は、浄化の力が強いの。あなたの体質を浄化しましょう」
巫女はサユリに近づき、額に手をかざした。その瞬間、サユリは白い光に包まれ、しだいに光は小さくなり、消えていった。
「これでもう、大丈夫。悩まされることはないわ」
そう言うと、巫女は凍ったジッツにも同じようにした。氷は溶け、ジッツは気を失ったまま、その場に横たわった。
「彼の心は孤独に支配されている。その寂しさに天狗はつけ込んだのね」
「ジッツは僕らと違って、強い霊力を持ってる。ジッツから悩みなんて詳しく聞いたことなかったけど、両親との仲があまり良くないって言っていたことがあった。その力のせいで孤立することもあったのかもしれない」
「彼の心も解けていけるよう、祈っているわ」
それから巫女は、俺の方へ向くと
「あなたも来てくれてありがとう」
と言った。
「あぁ、いや、ほっとけなかったんで」
巫女は目を細めて笑うと、龍の背に乗った。
「また、いつか会いましょう」
龍は空へ飛び立つ。その拍子に突風が吹いた。
ジッツの様子を伺うサユリとシュンを見ながら、俺は息を吐いた。
そろそろ僕らも帰ろうか。
また、脳内に声が響いた。さっきと同じ声だ。この声は誰なのか。
俺は足元から視線を感じた。目を向けると、翠色と瑠璃色の瞳がそれぞれ俺をじっと見上げていた。
もしかして・・・・・・?
白猫がニャーと鳴くと、瞳が翠色に光った。
「えっ」
突然、暗幕が下りたように、猫の姿が見えなくなった。
気がつくと、自分のベッドにいた。
「あれ?」
俺は夢を見てたのか?
ベッドから起き上がってみると、俺はスウェットではなく、服に着替えていた。
「たしか、俺は・・・・・・」
あのファンタジー小説を開いて、それから・・・・・・。
机の上を見たが、購入したあの本は見当たらなかった。
「どこにやったっけ?」
辺りを見渡して、時計が目に入った。
「あ、やべ! 本はあとで探すか」
俺は大学の講義に遅れないようにと、急いでリュックを背負って駅へ向かった。
バイトを終えた帰りに、気になっていた蒼月書店へ向かった。
しかし、本屋はそこになかった。全く何もない更地。
「どうなってんだ?」
閉店したにしても、古民家も残っていないなんて。
「雰囲気、良さそうだったのに」
ショックを受けていると、どこからか猫の鳴き声が聞こえた。周囲を確認すると、街灯の下に白猫がいた。
「お前・・・・・・」
翠色の瞳は夢で見た白猫と同じだった。何かを咥えている。
その猫は俺に近付くと、俺の足元に咥えていた何かを落とした。しゃがんで拾ってみると、それは俺が普段使っている栞だった。
これ、あの本に挟んだんじゃなかったか? 落としてたのか?
混乱していると、白猫が俺に背を向けて去っていこうとする。
「あ、おい!」
つい呼びかけると、白猫は立ち止まって顔だけ振り返った。印象的な翠の瞳が俺に向けられる。
「あ、えっと・・・・・・これ、ありがとう。もしかして、夢で会ったの、お前か?」
俺は思わず訊いてみた。答えなんて返ってくるわけないと思っていたが、
あれは夢じゃないよ。
突如、脳内で聞こえた声に愕然とした。白猫はニャーと一声鳴くと、そのまま走り去り、角を曲がった。
「待って!」
俺は追いかけたが、曲がった角の先に白猫の姿はなかった。
階段で寝転びながら伸びをし、さらにあくびをしていたら、店の奥から足音が聞こえてきた。顔を上げてレジの方へ向くと、バックヤードから翠(スイ)が出てきた。
「帰ったか」
「うん。彼に栞を返せたよ。店番、ありがとう」
「客に任せるとはな」
「客というより、もう居候になってるけど」
私はカウンターの上に置かれた本を一瞥した。
「その本は結局、何だったんだ?」
「ファンタジー小説として自動販売機に入っていたけど、これは手記だ。あの巫女が自身の体験と伝聞から書いたものだよ。彼女の力がこの手記に残ってしまったおかげで、彼は過去に起きた異世界の出来事を体験することになったわけだ」
「となると、この手記を仕込んだのは、そのなんちゃら販売機を設置した奴か?」
「うん。あの白龍さんだろうね。僕と同じように、老紳士以外の姿にも変われるはずだ」
「しかし、何のために?」
「巫女の存在を別の誰かにも知ってもらいたかったのかもね。彼女はこの間、亡くなってしまったから」
「何かあったのか?」
「いや、もうご高齢だったんだ」
「そうか。それはどうするつもりだ?」
翠は腕を組んで、うーん、と唸った。
「これは人の手には渡せないね。巫女の記録だから、彼女と縁のあった誰かに譲ることにするよ。彼女を思い出してくれるだろうし」
そう言うと、翠はその本をバックヤードに持っていった。しばらくすると、アイスコーヒーを片手に戻ってきた。
「君が彼のことを知らせてくれてなかったら、気付かないままだったかもしれない。助かったよ。やっぱり、自動販売機はやめとこうかな。いいアイデアかなと思ったんだけど」
「あれは、人間しか使えんだろう。他の客には意味がない。それこそ、お前や白龍のように人間に変われる奴でなければな」
「だからこそ、置いたんだけどな」
「相変わらず、変わり者だ」
翠はアイスコーヒーを一口飲んでカウンターに置くと、店の扉に視線を向けた。翠の瞳がわずかに光ると、扉の鍵が開く音がした。
「さて、開店だ」
今日も怪しい客達の相手をするようだ。
私は階段から椅子へ移動し、来客があるのを待った。
ー了ー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
