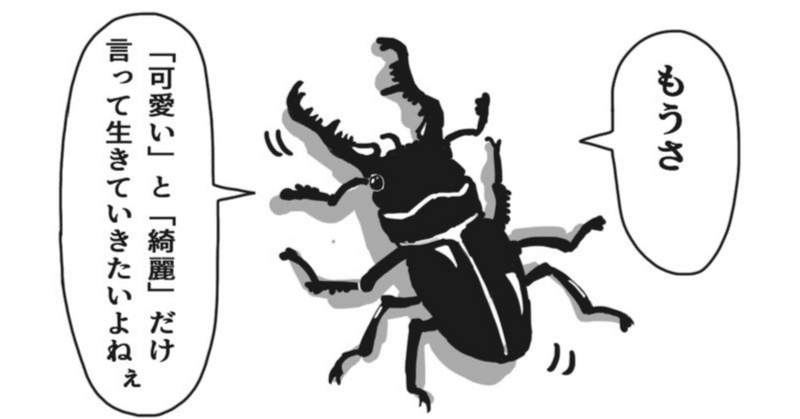
創作 晩年の味
男は長く勤めた会社から今後の選択を迫られていた。長く勤めるというだけでそれなりの地位を得ていた男は、それが時代遅れだと言われていることには耳を貸さず、仕事に於いても考える判断を放棄して、大局に流されながら個人の判断にならぬように決断をしてきた。その結果、男は仕事には無駄なプライドしか持っていなかった。
本人は、会社に必要とされている人間だと思っていたのだが、実際に会社から突き付けられた現実は現在の待遇からは想像出来ない立場と給与だった。男の会社にいる周囲の人間は、無駄にプライドが高い男がそのまま会社に残る選択をするとは考えてもいなかった。
事実、男も自分にふさわしい立場ではないと、断る気で選択を一旦保留にし、頭を整理させるために会社に所属している確固たる身分としての自由な時間を使うためだけに休暇を貰い、検討をするという長く勤めた男にこそふさわしい役目と考えるものを味わうことにした。
男は自分にふさわしい立場とは何かを考えてみることはしなかったのだが、その与えられた立場が周囲からの評価だと考えることすらもしなかった。男は世の中の時流というものには、こういうことも必要な場合が起こるのかと、結局は自分には関係ないことだろうと、他人事のように決して自分を省みることはしなかった。
この日、朝目覚めた男はベッドから下りて、いつものように深呼吸をした。男の深呼吸は人より深く、動作を大きくだった。腕を大きくあげ息を吐きながら腕をおろし、その腕を真っ直ぐにまた上に上げようとしていた時だった。
男の両胸に男の上腕部がそれぞれ少し触れた。おもむろに男は、右手で男の左胸を支えるように持ち上げた。
それは意識して自分の軀に触れた感触ではなく、掌で支えるその柔らかさは自分の意思とは無関係に、昔付き合っていた少し大きめのバストの女性を男の軀を通して思い出させた。
男は以前より肥った自分の軀に少し大きめのバストの女性が無意識に刻まれていたことを知り、少し大きめのバストの女性が男の前から居なくなったわけではないのだと少しだけ安心した。
身支度をし、玄関前の姿見で自分の後ろ姿を確認した。ふいに、控え目に強調するバストの曲線を隠すほど伸びている黒の美しさに反抗するような流行りの色に染めた髪の長い女性が、抵抗の少ない白妙の背中を確認していた姿を思い出した。
鏡越しに見えるその姿に手を伸ばして、指先だけで触れてみたい欲望に駆られていたが、鏡の世界の女がどこか他人に見え、それなのに欲望を投影する自分に他人とは思えない錯覚を覚えていた。その肌の色や髪の質感。そしてその鏡越しの姿を忘れていなかったことを思い出した男は、それが一夜の宴の出来事ではなかったのだと考え微笑んだ。
男は、会社以外に行くところなど存在しないのに外に出た。他人より少し速度が遅い歩き方は、世間からも遅れていることに自らが決して気付くことがない速さだった。
無意識に歩を進める途中に交差点にさしかかる。信号待ちでタンデムしている若い2人の男女に男は視線を合わせた。停車中の若い2人の時間はそこだけが真夜中にいるみたいに他人を寄せ付けない空気の中にいた。
少し改造してあるバイクの排気音は、本来なら会話の妨げになるはずだったのに、寧ろ2人にとっては耳元で話せる機会を与えてくれているようだった。後ろに座る女が、信号が青になるほんの少しの時間に会話を済ませ、運転している男が気付かないうちにその男のヘルメットにキスをして少し力強く腰に回していた手を結び直した。
それを信号待ちをしながら見ていた男は、かつて自分も持っていたヘルメットにも、いつかの女にその純情を奪われていたのかも知れないと思い嬉しく感じた。
しばらく歩を進めると公園に差し掛かかった。男は、どのベンチにするかも考えずにそこにあるベンチに座った。この時間は男の時間ではないと言われているような視線を向ける子供たちとその母親たちに出会った。
男は、そういう空気に気付くタイプでもなかった。男の興味はすでに違うところにあった。
全力で持てる愛情を子供に注ぐその母親の深層が表面化した眼差しは、女が自分自身に向ける厳しい視線よりも、そして忙しさから生活で忘れて置いてきた女の性分よりも、内面から見える美しさが垣間見えた。その姿や他人が入り込む余地もない眼差しを見て、男は初めて納得をした。それは、当事者のうちには見えなかったものだった。
「あなたに与える時間は、もう存在しないの。私達に存在していたはずの不確かな時間わね。私達は最初から全てが健全な関係ではないじゃない」
男は、その背徳による興奮と入り込む余地がないと感じる女の美しさを壊してみたい欲望に逆らえなかった時期があった。それは男以外の男にも訪れる衝動の一つだが、曖昧な境界線を勝手に作り出し、それを考えるだけでなく実行した男は自分本位の欲望を表に出してただ突き動いていた経験を思い出した。
そして、その関係を終わらせてくれた女を思い出して感謝した。
その反面、どうしてもう一度抱かったのかと思わずにはいられなかった。
昼になり、テラス席がある公園のなかの食事が出来るお店に入った。人がほとんどいないテラス席に案内をされ、季節を感じられる木々を見ながら男は端に座り、食べる気もなかったパスタを頼んでいた。
男の斜め前の席には若い男女がいた。若い男に向け、若い女が自分の膝に手を置き、上目遣いで話し掛けていた。話す声が聞こえる位置にいない男は上目遣いの似合う女を思い出していた。
「あなたの予定は大丈夫なのかしらね」
男は、上目遣いの似合う女には、抵抗の壁がなくなることを知っていたので自然に答えていた。
「僕は君の予定に合わせるのが最優先の仕事だ」
女は少し潤んだ目をしていた。男がその目を思い出した時、さらに1人の女のことを思い出した。
「『あなたは、目が悪いからかずっと人の目を見て話すけど、睡眠不足なのか目がずっと潤んでいるのよ、それは女子には嫌われるわね』って言われたことがあるの」
と、まどろっこしい言い方で潤んだ目で話す女に欲情を覚えていたのだが、男はこれからの人生にはやはり、潤いも必要かも知れないと考えていた。
男が考えるよりも暖かくなった午後。上着を片手で抱え、肩まで露になっている季節外れの薄着の女を見つけた。
「男の視線なんて、明日の天気くらい正確にわかるわ」
そう言って男を見ながらも、真実は知れない肩から少しだけずれた下着の紐を直す女を思い出したが、明日の天気が万が一にも外れる可能性があることも考え、男は季節外れの薄着の女を見ないわけにはいかなった。
こうして男は、1日の休日が何人もの女により何年にも感じることを忘れたくなった。男は夕方の早い時間だが仕込み最中の小さな居酒屋に入った。店主に嫌な顔をされながらもビールをもらい口に含んだ。
グラスをカウンターに置き、水滴が指に滴るのを見ながら1人の女を思い出した。女は、グラスについた口紅の痕を消すのが不自然と思わせない自然な仕草で違和感なく痕跡を拭き取った。男は、その消えた唇の痕に自分の唇を重ねる想像をしているのを悟られないようにしていた。
日が暮れはじめ、男は家に帰ることにした。少しのアルコールは男を陽気に変えるかと思ったが、男の頭は鈍く重かった。
家に帰り、重く引き摺るように玄関のドアを開けた。
「ただいま」
男は、いつも言うセリフをいつもと同じように繰り返した。
「お帰りなさい」
そう言っていた女のことを思い出そうとしたがそれは出来なかった。
「あなたは、私のことを本当に好きではないの。あなた私に興味なんてないじゃない」
そう言っていた女が妻だったことを思い出そうとしたが出来なかった。
男は、女という女のことをわからなかった。その上辺だけを知りたくて、浅い欲望にだけ従順だった。
男は、自分のなかに自分の軀を作った女を感じるのだが、それは積み上げてきたものが随分薄く感じるだけのものだった。あるべきはずの深さを求めずに、表面の上着を一枚だけ脱がし、本当に女が感じていたことを知ることもせずにやり過ごしてきたことを知っていた。
男は、会社に再雇用のお願いをしようとしたのだが、歩いている足は、会社とは違う方向だった。
会社にいない男のことを気にする男も女もいなかった。
男だけがやり直せると思っていたが、どこから何をやり直すのか。それを理解することはなかった。
読んでいただきありがとうございます。どうですかね。少しずつ書いてみようと思っています。皆さん、いつも相手していただき本当に感謝しております。
掌編、短編、ショートショートの括りがあまり分からないです。少し長くなってすみません。
最近は、アマプラのCMの女性のウィンクが忘れられないです。お久しぶりのドンピシャですとお知らせしておきます。
なんのはなしですか
自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。
